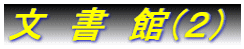
 |
「無 神」 |
|
もしも、神というものがあって、その神に向かって誰かが「神は無い」と言ったとすれば、神は、「その通りである。私は無いのである。」と言われるであろう。 そして逆に、その人に対して、「あなたによって私は生かされているのであります」といって礼拝されるのではなかろうか。 神ご自身が『私が全宇宙の生みの親である。〇年〇月〇日。』などというものを、どこかに建てておられるとは、どうしても思えない。もしも、そういうものがあれば、そんなものを、自ら建てられるようなものを神と呼ぶ訳には行かない。 神は全宇宙を創造し給うていながら その姿を消しておられるのであります。 神は、人間を礼拝し給うているので あります。 春には花を咲かせ、野山を緑でかざり 雨を降らせ、陽を明るく 風を渡らせて、何とかして人間を喜ばせて やろうとしておられるのである。 生きた花々草々をもって、神は我らを供養し給うているのであります。 しかし、依然として神はご自分を消しておられるのであります。 どこまで消しておられるか。 それは、神がお生みになった人間に「神は無い」といえるようにしておられるまでにであります。 「神は無い」という声も、神のいのちによって人間はそう言っているのであります。そこまで神ご自身で、無神になっておられるのであります。 「神など無い」と言えば言うほど、そこに、神の無神の聖なる輝きが、証明されているのではないでしょうか。 日本神道の幽の幽なる神とは、ある意味でこのことを言っているのかもしれません。宗教も、真の宗教はこの神の無神なる輝きをうつしたものであるはづである。宗教が「この教えがお前たちを救ってやるのである。この教えにふれなければ、あなたは救われない。」というようなものであれば、即、それは神ではなく、愛ではなく、聖なるものであるという訳にはいかないのである。 人前に立って「救ってやった。救ってやった。」というところには、聖なるものはないのである。 説法も、お経も、そこにもし「この説法を聴かなければ救われない」とか、「この本を、このお経を読まなければ救われませんよ」というのを、少しでも残しておれば、それは無我ではなく、愛でもないのである。 それは無神の聖なるいのちの流れとは、およそかけはなれたるものでありましょう。 |
||
おおよそ宗教は、 全能なる神を信ずるのである。 その信ずべき全能なるものの、生んだものの中に、これから救って完全にしてやらなければならないものがあると観ることほどの不信はあり得ないのであります。 それは、宗教自体の自己矛盾であるといわなければならない。そこに宗教の「我」が出てしまっているのである。 ただ、もし宗教にゆるされるべき道があるとすれば、それは神の生んだ萬物を拝むこと祝福することのみであります。それが無神なる輝きの世嗣なる宗教の姿でありましょう。 救済活動、救済活動と大声でよばわるものもあるが、おおよそ救済活動とか愛の行いとかいうものは、人前に宣伝すべきものではないのではないでしょうか。 「私はこれだけの救済活動をしました。」 「私はこれだけの愛の行いをしました。」 と、それを競っているところには、はたして愛なるものはあるのでありましょうか。 愛は夜露の如く音もなく訪れ、 萬物を潤して、 夜明けとともに消えゆくのである。 誰にも気づかれずにすべてを潤すのが愛であるとすれば、それが深ければ深いほど尊ければ尊いほど、気づかれないところの愛によって私たちはどれほど生かされていることでありましょう。 その意味において、即ち、宗教は萬物を礼拝し祝福するためにのみあるという意味においては、神道の神社には、ご神体として鏡が置かれているのでありましょう。 この鏡は、そこに来る人々の姿を写すのである。 その写った姿をまつっているのが、神社である。 その鏡の前に立った人をご神体としてまつっているのが神社なのである。 そして、その鏡の前に立って人は自分の姿に気づくのである。 自分で自分が甦がえるのである。 鏡がゆがみなく、完全に澄み切っていることが宗教の宗教たる所以なのである。 奈良に行ったとき、社寺の屋根の上に高い空があって白雲があった。空はこんなにきれいだったのかと思わされたことがある。何かお寺のいらかや、神社の建物を通してみると、山々、森々や、自然というものが、却って引き立って来ているのに気がついたことはないであろうか。神社の新造されたときに、そのような気持ちになった人は少なくないであろう。神社そのものが無我になってすべてを引き立たせているのである。神社そのものが周囲を礼拝し、讚嘆している。 それのみか、国全体が引き立って来る、ということも、自然なことであるのかも知れない。 |
||
アスファルトを突き上げて破れた所から芽を出している草の芽を見たことがある。芽というものは、先に行けば行くほど柔らかくなっている。先端は全然と言っていいほど堅さはないのにもかかわらず、なぜ突き上げ、突き破ることが出来るのか。機械でボーリングする場合は堅い岩盤と接触する部分の先端に最も堅い爪がつけられている。この芽の場合は、接触点に近づけば近づくほど、やわらかく出来ている。実は芽は全然アスファルトと接触していないのではないか。触れる寸前のところで、先に上の方で口を開けてくれているということが、あるのではなかろうか。芽には外に出ようとする意志、または願いがあるのだろうか。 いずれにしても機械の場合とは反対になっているのである。アスファルトの根源と芽の根源とは、どこかで出所を一つにしているのであろう。その一つなるところから、この事件は発しているのであろう。そこから見れば、すべてが同じであるというような何かの地点なのであろう。 仮に二十センチ下から地上に出ようと生長を開始したとき、それに合わせて地表のところに何か芽の動きに合った、働きが始まっていなければならないでありましょう。もしも、芽の動きと上の方の動きが調和していなかったならば、芽はつぶれるか横の方に曲がってしまうかするのでありましょう。石のようなものがある場合は別としても、たとえ土のようなものであっても、芽はそれよりどれだけ柔らかいか知れないでありましょう。何かが根源的なところで働いているのでありましょう。 しかし、依然としてその何かは「そんなものは無い。」と言おうと思えばいくらでも言えるようになっているのである。機械にくらべ生命の方は、何か地面に出るための知恵をそなえているのであろうか。 ある意味では、外から教えなくても自分で中から知恵を出して、生長の方法を知っているものを、生命というのかもしれない。 たとえば、新幹線はすばらしい働きをするが、電線一本切ってしまえばもう働かなくなってしまう。外からあるエネルギーを貰っているからである。ところが、完全なる例ではないかもしれないが、赤ん坊は親から出てヘソの緒を切って、母胎とどこにもつながりが無くなった時を、誕生と言うのである。 とは言っても、どこかで何かにつながっているのかも知れないが、依然としてそのようなものは姿を消しているのである。しかし、赤ん坊のことは、生命のひとつの特徴を表していることには間違いはないのではなかろうか。その何かが神であると、ただちに言うことはどうであろうか。生まれつき奇形で生まれる場合などがある。その場合は、見えない何かが完全なものを生むことが出来なかったことになるから、この見えない力が即、全能なる神であるとは言えないのであろう。 その意味でも、神は姿をさらに消してい給うのでありましょうか。 神は姿を消してい給うというのは、必ずしも五官に触れることがないというような意味だけではないのである。吾々が考えることが出来ないようになっているということ。知ることが出来ないようになっているという意味でもある。 神は見ることもさわることも出来ないから心で想う以外にない、と言われることがあるが、神は想うことが出来るのであろうか。 神は想うことが出来たとすれば、それはもう心でとらえ得るだけのものとなってしまっているのである。 吾々には心の中で、神を知ってしまいたいと言う想いもあるが、反面で、神は知ってしまえるような、そんなちゃちなものであってもらいたくないという思いもあるのではなかろうか。 そのような想いはいったい、どこから来るのであろう。 |
||
人生の意義はなんであるか。 これについても、神についてと同じではなかろうか。意義を知りつくしてしまいたい想いの反面で、人生の意義は解ってしまえるようなものであってほしくない、全部解ってしまいたくないという想いはとりされないであろう。それは、神そのものの中に、そのような性格が蔵されているからなのだろうか。 神も、妙なるものに対する無限の驚きを生きておられるのであろうか。 人間は新しさが好きである。 ロマン派が、形式を破ってたえず新しいものを求めて行くのは、つまり、驚かせることを求めているのではないか。 自分も驚きたいと同時に驚かせたいのである。 人間は父母を驚かせたいし、周囲のものに明るい驚きというものを与えたいのである。その驚かせたい最大のものは、神である。 人間は神を驚かせたいという願いを持っているのではあるまいか。 しかし全智全能なる神に、全く知らないものがあって、それを見て驚くということがあってよいものであろうか。 しかし、神には退屈というようなものは、無いのではなかろうか。 自然のめぐり、草々花々木々の、春に芽を出すその芽を見ても退屈しているようなところは少しも感じられない。生き生きとみづみづしく新鮮である。 宇宙は、永久につづくということは誰しも思っていることではなかろうか。 それは、神がたえず新しい驚きに満ちて、退屈することはないのだということを、吾々の魂は知っているからなのではなかろうか。 完全全能とは、一切の願いを満足しているもののことである。 では、吾々は今、完成していると同時に、無限の進歩生長と驚きとを、満足せるものを願わずにはいられないのではなかろうか。 神の全能の、さまざまの力のうちで、驚き感動する能力が、最初に来るのではないかと思われる。さらに、神は完全であり給いながら、全能なるが故に、無限に生長する能力をも持ち給うているのではなかろうか。 神は吾らの生きていること、たとえ一呼吸する姿と言えども、驚きを以て喜び祝福してい給うのである。何をやっても、すでに全能の神に、知られずみのものばかりであり、神も吾らも、驚くということのない生活というものには、あきあきしているのではなかろうか。 今ここにある、たとえ歩くことの一歩であっても、この宇宙のどこにもあったことない、神の驚き給う事件なのである。 神は無神なるが故に、無限の驚きをもって吾等を受けいれ給うのである。 「はなはだ善かりき」と言ったとき、神は真に、驚き感動していたまうたのではあるまいか。 神はあまりにも大きく、すべてに満ち、すべてを蔽いつくしているが故に、見えないのであろうか。 ある人が「此の世の中に神はあるか」と問うたところ、ある人は「此の世の中に神は無い」と応えた。その訳を質すと「此の世の中に神は無いが、神の中にこの世はあるよ」と応えたという話しを聴いたことがある。このような、すべてのすべてなるものを無神というのであろうか。有限なるものから見れば、無限なるものはないにちがいないのである。 全てのものをわが内に包有出来るものを無我、もしくは、無神というのであろうか。 また「神がなかなか解らない。」という。繰り返しになるが、神はご自身を消しておられるから、解らないのであり、神ご自身がみずから姿を消して解らないようにしておられるのではあるまいか。 神は知られたくないのではないか。 「私はただただ、生かすだけでよいのである。」と言っておられるのではないか。 神が解らないということこそが、神の無神の聖なる所以であると言うことが出来るのかもしれない。 神はその意味においで、解らないようにしておられるのであり、知ることが出来ないようにしておられるのである。 『古事記』の天之御中主之神が「身(みみ)を隠したまいき」とあるのはこの意味であるのかもしれない。 神は知ることが出来ない。 何が出来るか。 生かされることが出来るのみである。 神はただただ生かすのみであるから、そして姿を消しておられるのであるから、すべてにとっては、ただただ「生かされる」ということが出来るのみであり、神はただただ生かし切り、与え切るのではあるまいか。 このような意味において、知ることが出来ず、生かされることだけがあるということは、神は知る必要のないものであるということではあるまいか。 知る必要もなく、しかもそれによってあらしめられていることを「生かされている」というのでありましょう。 神は知ることが出来ない、 神は知る必要がない、 ということは、実に無神なるものの荘厳であります。 |
||
大自然の美しさ。 木々草々の美しいこと。 それらは、自分自身がそれであることを 知っているのであろうか。 ただただ、生かされており、 自分が生きていることすら、知る必要のない姿であるように見える。 ただただ自ずから然りということなのであろうか。 何か聖なるものの象徴が そこに輝き、いきづいている。 何か唱っているような言葉がそこにある。 幼児のごとき、みどり児の言葉のごときものではないだろうか。 言葉にはどうして自然の木の葉の 「葉」という文字が使われるのか。 言葉は緑なのではなかろうか。 しかも、新芽のごとき、新緑のごとき、 緑の輝きなのではあるまいか。 私たちは、松の古木にも生命を感じるが、草の芽、木の芽、その新緑。その生まれたばかりの時に、あらためて生命というものを感じさせられる。 人間の生まれたばかりの生命に、みどり児と名づけたくなるのも自然なことであるのかもしれない。 言葉がこのような緑に想える人々の生活は、どのように、みづみづしいものであることであろう。 「萬葉の世界」の人々が、やはり葉を使いたくなったその心の中に、緑々(あおあお)としたものがみづみづしく充満していたのであろうか。 「言葉は神なりき」とある。 神は、緑なのか。 そして、その神の子は、みどりごと呼ばれるのであろうか。 |
||
神はご自身を消しておられると言った時、なぜ神はご自分を消しておられるのでしょうかという問いが出て来るであろう。 我々は、なぜ「なぜ」と問いたくなるのであろうか。我々は不可解なるものに対して「なぜ?」と問うこと、そのことだけは疑わないのではあるまいか。このことに対してだけは「なぜそうなのか」と問わないのはなぜであろうか。 「なぜ、なぜと問わなければならないのだろうか」とは問わないのは、なぜであろう。 「なぜ」とは一体何であるのであろう。 「なぜ」とは神なのではあるまいか。 「なぜ」ということは、わが内なる一切の根元に近付くための、それは内なる神から放射された光なのではあるまいか。 「なぜ?」と問う場合、吾々は外に向かって問うているようであるが、よく心の方向を観察すれば、それは問うているもの自身に向かって何かを探ろうとしているのではなかろうか。自分自身の中に、納得の状態というものを探りだそうとしているのではなかろうか。 「なぜ」ということはたしかに、わが内なるより、奥なるところから出てきているようであるが、それは外に向かっているのではなく、それよりも、さらに奥にあるそれが宇宙の中心であり、神である中心に向かって問いを発しているのではなかろうか。 中心とはしかし、肉体的自己の内なる狭く微小の一点であることを、必ずしもこの場合は意味していない。それが神であるということにおいて、一点であると同時にそれは、すべてのすべてであるであろう。そのすべてのすべてである中心に向かって「なぜ」という問いが発せられている。そして何かそこから自分に、応答的にはたらきかけて来るものを感じたとたんに、われわれはもうそれに対して「それはなぜ」という問いを発しているのである。 この「なぜ」はどこどこまでも続くのであろう。どこどこまでも続くということは、どこどこまでも根源が、姿を消していることを意味しないだろうか。根源者である神は、どこどこまでもご自分を現わそうとはされたくないのではなかろうか。 今、私がこうしてわが内に湧いて来る想いを、ここに書き写していること自体が、「なぜ」の奥の奥にある根源者のいのちが「なぜ」なるものを飛びこしていまここにはたらいている姿なのである。 そのものはすべてを超えて、今ここにある、というような在り方をしているもの、それが無神という聖なるものの輝きなのであろうか。 ここでもやはり私は「なぜ私はこのようなことが綴りたくなるのか?」と問うている。ここでは「なぜ」ということが、私にとっての内なる存在に向かって、どのような意味を持っているのであろうかという思いが湧く。 「なぜ」という言葉が、この文章の種となっており、そこから言の葉が芽を出し、生長していることが私にはうなづけている。 このコトバ、という文字を使用した人は、言葉の葉を、木(みき)の中から次からつぎへと芽を吹出し生長する緑色をした葉を想ったか、また落葉のごときものを思ったであろうか。紅葉も美しければ、落葉も美しいであろう。なにかしかし、「ハジメに言葉ありき、言葉は神なりき」という場合は、生み出すはたらき、生命あるはたらきを表現しているのではなかろうか。 落葉は、ある意味では死んでおり、生み出すというよりも、生み出された結果としてそこにある。落葉は葉ではないのでなかろうか。生長しみづみづしく生命に満ち満ちてあるものを葉というのではなかろうか。 「葉」はあくまでもただただ「葉」である。落葉はあくまでも落葉であって、葉ではないであろう。古代の人には落ち葉は葉ではなかったのではあるまいか。もしそうだとすれば、ただただ生み出すこと、生きてあることだけが目的そのものである生きる姿というコトバがそこにある。 |
||
結果がなくても生きうる存在。 それ自体でそれである存在。 神は結果を求め給わない。 これを無神というのである。 神は「光りあれ」と言い給うたけれども、 その結果どのような光が生まれ、その光がどのようなものを生み出していったか という結果は求められ給わない。 神には結果というものは要らないのである。 神は神ご自身ですべてであり給い充足そのものであり給う。 神には結果というものが要らないのである。 神は神ご自身ですべてのすべてであり給い充足そのものであり給う。 「光りあれ」と言い給う前に、 先ず、神は神であった。 そして神はすべてであり給うた。 神はそれ自身で充足そのものであり給う。 「言葉は神なりき」とは、 言葉は充足そのものであり、充足でないものは言葉ではないのである。 充足は他に求めないから無我である。 神は無神である。 充足せるもののみ生み出すことが出来る。 神は生命である。 生命は緑であり、生長である。 神と生命と生長と、これだけが存在のすべてである。 それが神が言葉であるというときの言葉である。 生きているものだけが言葉である。 もし、そうであれば言葉の葉は生きた葉であり、緑の葉であったのである。 「はじめに言葉あり。言葉は神なりき。言葉は緑なりき」である。 しかして、神は無我であり、無神であり、緑であり、 神の子は無我の子であり、無神の子であり、みどり児なのである。 みどり児とは無我の子ということであり、無神の子である。 神にとっては自分はなく、子のみがあるのである。 それ故、子は神をしることが出来ないのである。 知る必要がないのである。 神は自分は生かすだけでよいと、言っておられるのである。 いつもいつも、神は消えておられるのである。 |
||
神は知る必要がないということは、信ずることがいらないということである。 なぜ生まれつき、信仰の篤い者と、信仰のうすい者とがあるのであるか。 もしも、信ずること篤きものをよりよく生かし、しからざるものをより少なく生かすということがありとすれば、これは全能なるものの姿ではあり得ないであろう。これでは、人間は神を恨まざるを得ないのではなかろうか。このような神を人間は許すことは出来ないであろう。それではたしかに創り主である神の方に、責任があるであろう。そのような神に、感謝と尊祟の心を起こすことは不可能である。可能なことは、そのような不幸等の世界しか作ることの出来ない神を軽蔑することだけである。そこには、神と神以外の不完全なるものとの対立がある。そこに美しさが欠けて来るのである。そこに、神と神以外のものとの戦いがある。 神はすべてである。いまかく神のことについて想い書かしめられているのも、そのすべてのすべてなるもののはたらきなのである。 神は斯くの如くあるべきであると被造者の方から言うべきなのであろうか。神こそが、「斯くあれ」と言う唯一者にまします。 しかし、わが内より「神は斯くあるはずである」という想いが湧きいづるのは何故であろう。そう思うこと自体が、既にすべてなるもののはたらきとしてあるというべきであろうか。それ自体がすべてである存在について何を言うことが出来るであろうか。 しかし、また何を言っても当たるのであると言ってもよいかも知れない。 「説以一物即不中」と言った宗教家がいたが、一物を以ってこれだと示せば即ち中(あた)らず、ということは、すべてのすべてである存在から一つだけを取り出せばもう、すべてをそのまま観ていないことになる。説くものと説かれるものとを認めること自体が、すべてのすべてなるものをそのまま観じていないということである。しかし、また一方、すべてなるものはすべてなるが故に、説くこと自体がすべてなるもののはたらきそのものであると観た場合には、すべてなるものが、そこにいつでも存在しつづけてあるとも言えるから、どのようなもの一物を以てしても、そこにすべてなるものがあり、すべてなるものに中(あた)っているということが出来るであろう。 釈迦が蓮華の花一輪ひねって迦葉によく単伝したということは、そのことを示しているのではないか。「説以一物即不中」と言ったこと自体が、「説以一物即不中」ということを似て説いていることではなかろうか。また、誰れかの言うように「山川草木国土悉皆成佛、有情非情同時成道。」と釈迦が言った時、釈迦は全宇宙の草木一本一本をすべて調べて見たであろうか。 釈迦は十二月八日の暁を見て悟ったと言われるが、それは宇宙の中の一物にもならないほどのものにすぎないであろう。ただただ、釈迦はそう言いたくなったのである。すべてのすべてなるものが、釈迦という一物を以て、すべてなるものが説き響いたのである。しかも、依然としてすべてなるものは、姿を現し給わないのである。 釈迦は一杯の牛乳、暁を観て感動の極みに「山川草木国土悉皆成佛、有情非情同時成道」と唱ったのである。唱ったのであるか、または、感動のあまり泣いたのかもしれない。そこに聖なる輝きを感じられたのであろう。ベートーベンなら、泣くかわりに楽曲を響かせたのかもしれない。 かれらはみな一様に無神なるもの、釈迦なら無佛を通り越して、無なる輝きにつつまれ、内なる自己を解放したのである。彼等の発見したものがそれでなければ、あれほどまでに人類の心を打ちつづけることは出来ないであろう。そしてその喜びの響きにふれて、大いなる輝く世界に生かされていることに目覚めた人々が出て来たのである。 釈迦にとっては、有情非情すなわち、目覚めるものも目覚めないものも、そのままの輝きによって聖なる姿である。有情非情とは、修行の出来ているものも、修行の出来ていないものもということである。 |
||
心臓は修行によって動いたのではないのである。 決意によって動いたのでもなければ、 説教を受けてから動いたのでもなく、お経を誦げてから動いたのでもなく、 お祈りをしてから動いたのでもないのである。 そのような一切の条件を越えて、まずこのいのちがいきていたのである。 宗教にふれてからではないのである。 宗教はそのいのちを讃えるためにあるのであって、宗教によっていのちをあらしめられるのではないのである。 赤ん坊が生まれて、その赤ん坊が可愛くて、このいのちを祝して、喜ばしい名前をつけるのである。 名前をつけてから赤ん坊が生まれるのではないのである。 宗教によって救われるのではないのである。 救われている尊いいのちが先ず先にあって、それを拝むのが宗教である。 「私は一度も救ったことはない。すでに救われ済みのすべてを拝むだけである。」という宗教家が最も美しい宗教家であると言わなければならないのである。 諸君は、このような宗教または宗教家がいるのかどうかと問うであろう。そしてそれを示して見よ、というかもしれない。しかしそれは自分で探さなければならない。神が無神である限りにおいて、宗教または宗教家はそのようなあり方でなければならないのである。 ある人が素晴しい修行の道場に居たときの話しをして呉れたことがある。その人はその道場の山門の所で作業をしていると、若い奥さんが小さな子供をつれて、門の前を通り掛かった。どういう訳か子供は泣きわめいている。多分何かお店で買ってほしいものがあって、それを買ってもらえなくてねだって泣いていたのであろう。門の中で作業をしている人達に気がついてかいなくてか、あまりなだめてもきかないのに腹を立ててしまったお母さんは、その子の首根ッ子をつかむと、山門の柱にその子の頭をこすりつけるようにして、何を言うかと思うと、「あまり言うことをきかないとここへ入れるよッ」と言ったそうである。「ここにあなたも入っていい子になるんですよ。」と言うかと思いきや、さにあらずで、鍔然としたというのである。その子供の心にとってこの道場は、どんなにか遠いところにあったことであろうか。子供と道場との距離は、はかり知れないものであるかも知れない。その人は、後になって考えさせられたというのである。というのは、その時一緒に作業をしていた人の中に、ブラジルから来た人が居たのである。時間的に言えば、門のところで頭をこすりつけられた子供よりも、ブラジルの人の方が早いのである。もしも、距離というものを所用時間で示すとすれば、子供とブラジルから来た人の場合は、ブラジルのほうが時間がかからず、近いということになるのではなかろうか。一体、ブラジルのほうをこすりつける近さよりも近くするものは何なんであろうか。ここでも吾々は姿、形のない何かを探さなければならないのであろう。 神がみずから無神であるとき、どこに人間の力というものが存在することがあるのか。というその方向に探すのであろう。探すというそのことが、もはや神のいのちの輝きとしてそうあるのであれば……………。 くりかえすが、そのような教えがこの地上にあるかどうか。それは諸君自身が自分自身で探さなければならない。それはこれこれであると私が言ったとき、すでにそれは私の示唆に従えと言ったことになってしまうからである。それは私の感じ取ったことであって、諸君になんらかの限定を加えてしまえば、この書は失敗であることになるのである。私にゆるされていることは、ただただ、そのままで諸君を礼拝することだけ、讃えることだけ、感謝することだけである。それ故、このことは外に向かって探すのではなく、それを自分の内に探すべきものではなかろうか。そして、内にとは既にあったという方向にそれは発見されるはづなのである、という意味を含んでいるのである。 |
||
さらに、わたし達は宗教を探して、説教を聞いて、お経を読んで、お祈りをして、それから心臓が動いたのではないということは、何度でも繰り返し言わなければならないことである。外からの如何なる学習もなく、心臓は動き出したのである。百万人の科学者が集まっても一滴もつくれないかも知れない血液をふんだんに作り、心臓をつくり内蔵を作り、母親からもらった栄養を適当に分配し、それを無造作にこなして来ているその神智とも言うべき知恵は、うちからはたらいているのである。しかし、これはただちに神の知恵であるということは出来ないであろう。生まれつき強い心臓もあれば生まれつき弱い心臓もあり、それらを平等に、完全に作ることが出来なかったものを神と呼ぶわけには行かないからである。これは、すでに述べたことである。しかし、うちにはたらきのもとがあるということだけは、確かであるだろう。 神は完全である。 神のつくり給うた世界も完全である。 しかし、なぜ眼に見ゆる世界には完全に近きものと、然らざるものがあるのか。それはその人その人の心のありよう次第である。そういう説明は、いちおうは認めることは出来るかもしれない。 しかし、なぜ心のありよう次第ということがあるのか。 なぜ、生まれつき心のよろしきものと、然らざるものがあるのか。 神はいったいなぜ、人間の心を迷うようにしておいたのであろうか。 何故、こころがよろしからざる状態を、許しておられるのであろうか。 それは神は、人間に自由を与え給うたからである。という説明もたしかに従来からあるであろう。 しかし、神は人間を迷えないようにした上で、無限の喜びを、味わえるように創造することは出来なかったのであろうか。自由ということは、たしかに価値の根底をなしているかも知れないが、「自由というものが価値の根底」という、神がそれに従わなければならないというものがあるのであろうか。そのような神は、神と呼ぶに値しないであろう。 吾々も、人間のこの迷う心を抱えて、神をいよいよ高くあがめまつり、自分をいよいよ低くみて、そしてこの迷う心を清め清めて高き神に至る。そのような努力をすることをもって誠実とし、神への謙虚なる道であるという道を歩んで来たのではなかったか。しかし、それは神への真の尊敬という訳にはいかないのではなかろうか。全能であるはづの、神のお創りになったものに、これから淨めなければならないものがあると認めること、たといそれが人間自分自身であっても、それを認めることは、神の全能のお働きを尊崇したことにはたしてなるであろうか。すべてのすべてである神の中にあるといわなければならない筈の人間の中に、迷いが実在するという思いほど、実は神に対する傲慢であるものはないのではなかろうか。神のお創りになったものに不完全はない、従って人間自身も完全であると認めることこそ、神をたたえる真に謙虚な道なのではないのだろうか。 もし、そうだとすれば、地獄、極楽の入口におられるという閻魔様は、何を審判されているのか、それは「神の作り給うたものに不完全がある」という神への不敬を、さばいていられるのかも知れないということになりはしないだろうか。しかも、人間にすれば神を尊敬していたつもりが、はからずも神を恨み軽蔑していたのではなかったか。 |
||
私は最初この説文を『あなたは自分を赦せるか』という題名にしようと思っていたのである。しかし、すべての根源である神を恨むことなく、神を赦せるか否かの問題があることに、ぶつかることを知ったのである。 しかし、神は完全なるとき、その創り給うた世界が完全であるとき、恨み心、軽蔑の心はどこにあり得るであろうか。それはいくらあるように見えても無いのである。恨むこころをこれから改めねばならないとすれば、それは既に不敬の心になっているのである。改めるという方向には、神への赦し、尊敬はあり得ないのである。 今私は何かを直感しているのであろう。その直感せるものに従って、それを書いている。直感の自己展開として、それに従ってであって、それに向かってではない。神に従ってである。向かってという方向には、果たして神を尊敬するということは、成立するのであろうか。 生命というものが、神に従って、神そのものの展開として生きている時、生命そのものの実感というものを取去り給うているのだろうか。心臓が最も良く働いている時は、心臓があるのが解らないようになっている。他の部分も同じである。実感がない時が一番働いている時である。胎児でも、あんなに重大なる生命のはじまりとも言える時でさえ、親は、胎児が発育をはじめたのに気がつかないのである。生命の誕生についての実感は、消されているのである。ここでも、神は自ら姿を消しておられるのである。 さて、苦痛というものは実感であろうか。しかし、神には苦痛があるとは思われないのである。苦しんでいる全能なる神というものは、思い浮かべることは出来ないであろう。むしろ、それは実なるものにあらずして虚なるものであるであろう。ここにも神は全く存在しない。ここは神の非実在である。 苦痛は神の非実在であって何も無いのである。何もないとは、あるものだけが、即ち神だけがそこにあるのである。苦痛というところにさえ、じっと心をとどめてみれば、そこには神が即ち楽がそこを満たしているのである。ここでもまた神は、自らを消してい給うのであろうか。 神に向かって「神は無い」と否定した時、神は「私は無いのです」と言われるであろう。 さらに「私は神を愛し、神をあがめます」と言うものに対しても、神は「私は無いのです。宇宙を私が創ったなんて、とんでもありません」と言われるであろう。神を肯定すること、神を否定すること。真の神にとってそれは何であるであろう。 神に対して、人間が迷惑をかけるということは出来るであろうか。人間の知恵ではなく、神の知恵で生きよと、宗教家は言うかも知れないが、ここでも神は姿を消しておられて、どこからどこまでが神の知恵なのであろうか、という問いをのこしているのではなかろうか。そのようなことは、知ることが出来ないようにされているのではなかろうか。少なくとも神の知恵というものがありとすれば、それは、人間の知恵が出て来たくらいでは、何の迷惑もかかるものではなく、それによって曇ったり、かげったりするものではない筈ではなかろうか。少なくとも神罰というものは、存在するはづはないのである。 すべてを越えて、神の生かす力は無条件である。人間の方が却って、その無条件に降りそそぐものを拒否しているということになっているということはないのであろうか。 人間は、自分の子供を無条件に愛する。そのことを通じて親の立場からの無条件の愛を経験することによって、親の気持ちを知ることによって、従って神の愛を無条件に受けることを身をもって知らされて行くということがあるのではなかろうか。 ここに書きつらねて来たことは、全くの仮説であると言ってもいいのである。仮説とは仮にある説という意味であって、説そのものが仮の存在であり、実在ではない。実在を説けるものは存在しない。 ここにいう仮説とは、説によって実在を示すことは出来ないという、説くことの限界を表現しようとして使っているのであります。神でさえ無神であるとき、この書物、この説文が仮ではなく、無でないということはあり得ないのであります。 |