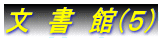『発 進 宣 言』拝 誦 <序>
『試論「波状光明化への道」―内なる神へのレポート―』より
|
(序) |
「人類光明化運動発進宣言」と云うのは、谷口雅春先生が『生長の家』第一号の冒頭の所にお書きになったものでありまして、其処には 〝発進宣言〟 とは書いてないのであります。正しくは「『生長の家』出現の精神とその事業」と云う小見出しで書いてあるのであります。この御文章は先生がお書きになった訳でありますが、拝読をはじめる前に、先ず私達は谷口先生のお書きになった御言葉と云うものは如何なるものであるか、と云うところからはじめたいと思うのであります。
谷口先生がお悟りになって、東方に面した露台にお坐りになり神想観をされた。そうして目を開くと庭の木の若葉が燦然(さんぜん)と輝いて霊光がそこに輝いていた。その樹の枝から枝には雀(すずめ)が飛び移っている。その雀も金色(こんじき)燦然と輝いて、樹も雀も金色燦然と輝いていたのであります。勿論、輝いているのは谷口先生から見ると、この樹や雀だけではないのでありまして、谷口先生のお書きになる文字も全部金色燦然と輝くところの霊光そのものであると云うことであります。これは『生命の實相』第一巻のはじめの方に、谷口先生がお書きになっておられるように、谷口雅春先生が御部屋で原稿を書いておられる御姿が埼玉県の笠原政好氏が霊眼によって見えて来たところによると、谷口先生のお姿が光明燦然たる霊人と化し、あたり一面光の海となって部屋も原稿も万年筆も全てを霊人から出た光明輝く光が占領して全面が光であった。と云うことが書かれてあります。また、『生命の實相』が、『甘露の法雨』が光明燦然と輝いて見えたと云うことはもう沢山の方々が体験しているところであります。この光りは全人類をそのまま救いとるところの神の愛の現われたものでありまして、物質を超えたところの不滅の霊光がそこに輝いているのであります。
ともかく、本当に人間をそのまま救いとるところの、人間の力ならざる神のいのちがそのまま直接現われて来て此処に輝いているのが『生命の實相』のご本である。広島の原爆にもくずれず、或いは焼津(やいづ)の方ですが三千度近い火炎の中に二回も焼いたけれども『甘露の法雨』は焼けなかったと云うこともあります。これは物質ならざるものがそこに輝いていると云うことになるのであります。ですから、もはや今日私達の前にその聖典が、尊師のお書きになったお言葉が自分の前にあると云うことは、そこに光があると云うことであって、庭の若葉が金色燦然と輝いていて、それが一様に輝いていたように、谷口先生から見れば谷口先生のいのちから出たところのお言葉は、木の葉のように『生命の實相』の全面が光明燦然と輝いていて、それを読むところの読者である私達の姿も金色燦然と輝いていて、あたかも、金色に輝くところの雀が金色に輝く樹の葉の間を燦然と輝き乍ら飛び移って喜びの声をあげている、そう云う風に、私達が『生命の實相』にふれると云うことは、光明燦然と輝く樹の葉の中を、ちようど雀が金色燦然と輝きながら飛び移っている――そう云う風な姿に、谷口先生からは見えているのであります。
私達はそれを時々、神想観をしたり、心境の澄んでいる時にチラチラと垣間(かいま)見る。そのチラチラと垣間見えたのが本当の相(すがた)であって、そのように見えない普通の姿はそれは嘘(うそ)のすがたなのであります。本当はそのように輝いて見える方こそ本当であると云うことであります。そこのところも、谷口先生の御言葉を受けとる前に、先ず、光であること、そしてそれは自分ならざる大いなる神の無限の礼拝の光である大愛の輝きであると云うことをはっきとりさせておく。それは『生命の實相』は、礼拝ですから
〝この本を読まなければ人類は救われませんよ〟 とか 〝この本によって人類を完全にしてあげるんだ〟 と云うのではないのです。神の無限の、人間を救う愛とは何かと云うと、人間の本当の完全円満なるすがたに対する礼拝と云うことです。ですから、『生命の實相』には
〝これを読まなければあなたは不完全だから完全になれませんよ〟 とは一行も書かれていないのです。其処(そこ)には、 〝私が悟って本当に神の御すがたを発見した時に、すべてを観たら人間はそのまま完全円満欠くる処なき素晴しい存在であった、と云うことが解ったんです。それで一々全人類を拝みに行くわけにはいかないから『生命の實相』と云う本によって、本当のすがた――本を読む以前から、否々私が生まれる以前からすべての人は完全円満であったと云うことを本によって私は拝ましていただいているのです〟
と云うことです。そういうすがたをしています、『生命の實相』と云う御本は。
讃嘆ということが近頃盛んに云われていますが、谷ロ雅春先生がお悟りになったときから生長の家は全人類讃嘆運動であると云うことです。そういうこととして出発しているのです。拝みの宗教なのです。ですから「天地一切のものと和解せよ」と云う言葉が冒頭に出てくるわけです。
人が生長の家の御本を一冊手にすると云うことはいかに尊いことであるか……。光なる神の子が光なる御本を手にしている。人と聖典とは光と光との関係です。光を手にしているのです。
もはや、この御本の中の文字がいかなる意味であるかと云うことの前に、「罪」という言葉も「死」という言葉も谷口先生の光なるいのちから出て来たということを拝まなければなりません。そこから拝ませていただくと「光明」という言葉が輝き、「無明」という 〝光が無い〟 という言葉が燦然と輝いているのです。全面、光の海であるわけです。
住吉本宮が建立される時、 〝御霊(みたま)はどこから貰って参りましょうか〟 とお尋ねしたら、谷口先生が 〝それは私が龍宮城から直接持ち来たす〟 とおっしやった。ここです。こういうようないのちある御言葉というものはダイレクトに
〝創造の本源世界〟 から持って来られるのです。あれは谷口先生が何処に坐っておられるか、谷口先生から出づる御言葉は何処から出てくるかと云うことを物語っていると思うのです。
|
|
|
|
|
『発 進 宣 言』拝 誦
『試論「波状光明化への道」―内なる神へのレポート―』より
|
(1) |
尊師谷口雅春先生の御書きになられた「生長の家人類光明化運動発進の宣言」冒頭にある 〝自分はいま生長の火をかざして人類の前に立つ〟 との御言葉は、「吾れ」(自分)と「今」と「生長の火」とが一つになっている絶対の愛の絶対的輝きとして鳴り響いているのである。この絶対の愛とは聖経『甘露の法雨』の「神」のところで天使(てんのつかい)によって、
真理
光明
智慧
絶対の愛
と謳われているところの絶対の愛である。この愛は、現象的、時節状況の上に成立っている相対の愛ではないのである。絶対なるが故に神が〝光あれ〟と言わざるを得なくなったように、この愛は絶対なるが故に立たざるを得ないいのちの輝きであり、広がらざるを得ない輝きなのである。
この火の点燈はそれ故に、絶対的点燈なのである。それがこの発進宣言の中で書かれている〝火だ! 自分に触れよ。自分は必ず触れる者に火を点ずる〟との御言葉の意味なのである。『完成(ななつ)の燈台』とは『絶対の燈台』と言うことである。自(みず)から輝かざるを得ない燈台なのである。生長の家は『絶対(ななつ)の燈台』を指し示すのではなく、『絶対(ななつ)の燈台』として、今、此処に立っているのである。ここにはまた絶対の調和の消息がある。この絶対の調和を大調和と言うのである。大調和とは〝一〟からすべてが発していることである。調和とは多なるものの一への総合ではない。〝一つ〟にして自ら立つ調和がある。はじめのはじめからあるハーモニーである。〝はじめに大調和ありき〟である。
一人で立つ大調和。自ら鳴っている大調和と言うことである。一人で成り立つからこそ大と言うことが出来るのである。絶対の愛即ち大調和である。
|
|
| (2) |
闇に対しては光をもって相対せよ。
非実在を滅するものは実在のほかに在らざるなり。
と『甘露の法雨』にはある。光として、実在としてわがいのちがここに立っていなければこの聖句はついにひとごとに終るのではなかろうか。自分は光なのである。自分は実在なのである。ここに光明化運動が発進するのである。
かつて雑誌『動向』に尊師谷口雅春先生が発表された「光明縁起説」において引用された 〝黒暗(やみ)淵(わだ)の面(おもて)を覆(おお)ひたりき、神光あれと言ひ給ひければ光ありき〟 のコトバの中のこの 〝光あれ〟 との宣言に相当するのが「人類光明化運動発進の宣言」の中の〝われは起たざるを得なくなったのである。……わが光にふれよ〟との天地のはじめに立ちての尊師のおコトバなのである。これは神とともなる天地創造の呼吸の消息なのである。ここのところに無明縁起説と光明縁起説とのはっきりとした分かれ目があるのである。全天地を光りの展開として拝む道である。全天地に天皇の御稜威(みいつ)を拝む道がここに開かれたのである。天皇の光りはこれから人間の力によってつくりあげられるのではない。すでに天皇一元の世界である。天皇の御いのちに生かされてわがいのちはここに輝いているのである。天皇をおまもりすると見えるはたらきそのものがすでに天皇のいのちのみたまのふゆによるのであった。親鸞の〝大信心は仏性なり、仏性即ち如来なり〟の説法は即ち〝愛国心は住吉大神なり。住吉大神即ち天照大御神なり〟ということである。
|
|
(3) |
「無門關(むもんかん)第六則 世尊拈華(せそんねんげ)
世尊(せそん)、昔、霊山會上(りょうぜんえじょう)に在って、花を拈(ねん)じて衆に示す。是(こ)の時衆皆黙然たり。唯迦葉(かしよう)尊者のみ破顔(はがん)微笑(みしょう)す。世尊曰く、吾れに正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)、涅槃(ねはん)妙心、實相無相、微妙(みみょう)の法門あり。不立(ふりゅう)文字(もんじ)、教外別傳(きょうげべつでん)、摩訶(まか)迦葉に付嘱(ふぞく)す。」
人間が生きているということ、そのことがすでに破顔微笑(はがんみしょう)なのである。神の生かすいのち花咲きて、わがいのちとして微笑し給うているのである。 〝わが生くるはわが力ならず〟 とは、わがいのちが笑っていることを示しているのである。
山川草木国土悉皆成仏(さんせんそうもくこくどしっかいじょうぶつ)、有情非情同時成道(うじょうひじょうどうじじょうどう)と釈尊が言ったときが、一切万物が破顔微笑している姿を発見したときであったのである。それ故、釈尊が拈華微笑(ねんげみしょう)されたとき、迦葉(かしょう)のみが悟ったのでもなければ、みんな他のものは仏子、如来ではないと釈尊が観ておられたのでもないのである。
実相無相、微妙の法門とは、一切衆生悉くが如来そのものであるとの悟りなのである。迦葉のみしか悟らせることが出来なかったというのでは、山川草木国土悉皆成仏、有情非情同時成道と言われた釈尊のお悟りが曇ったということになるのである。釈迦の前には一人も救われていないものはいないのである。そのことは、
『法華経』が最も尊い経典であるというのは、その事を釈迦が、「われもと誓願を建て一切の衆生をしてわが如く等しくして異ることなからしめんと欲せり、わが昔願う所の如きその願今既に満足せり、汝らは既に仏であり如来であるぞ」という風に説いているからである。「今、既に」ということが大切なのである。(『神真理を告げ給う』149頁)
と釈尊自ら説いているので明らかなことなのである。
迦葉一人が道を托されたというのは、真理というものは、たった一人に伝われば、それが全世界が悟ったことであるということをこの拈華微笑のことを通して釈尊は示しているのである。迦葉に伝えられた道は、やはり彼をとりまくすべてが仏であるという悟りである。であればやはり迦葉のみに伝わるというのは、彼一人だけが救われたということではないのである。
釈尊が拈華微笑したとき、釈尊の眼には、すべてのものが如来に観えているのである。如来と如来との雲集(うんじゆう)説法が釈尊の説法なのである。
日本神話では、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の天之岩戸(あまのいわと)がくれに際しては、高天原(たかあまはら)全体が笑いにどよめいたと伝えられている。何故、天鈿女命(あめのうずめのみこと)は、あのように笑って踊ることが出来たのであるか。それは、天照大御神は未だかつて一度も隠れ給いたることなしという生長の家の大真理を知ったからである。それはちょうど、釈尊が山川草木国土悉皆成仏、有情非情同時成道と言われたのと同じことなのである。尊師がお悟りになったときは、天地一切のものが和解し、感謝し、大調和の姿であることを発見されたのであった。
この神の側に立って、万物を祝福されたのが『生命の實相』なのである。人間神の子とは人間すべて迦葉であるということである。
われわれは、悟りを喜び迷いを嫌い、また、善を尊び悪を卑む。そして、生を喜び死をいとう。しかし、これらはどうでもよいことなのである。こんなことは全く神の子の関心をもつべきことではないのである。こんなことにいつまでも関わっていてはならないのである。神もない。仏もないのである。不思(ふし)善悪である。
観自在菩薩(かんじざいぼさつ)が照見(しょうけん)された世界は、光のみ、悟りのみの世界であった。光のみの世界であった。『般若心経』の無とは、観自在菩薩の照らし見る光の輝きなのである。無とは光りということである。先ず
〝光り〟 なる観自在菩薩がそこに立っていられるのである。無、無というひびきは光りの展開なのである。先ず光りがあるのである。光りとして観自在菩薩は立っていられるのである。
谷口雅春先生は先ず光りなのである。光りとして光りが宣言せられたのが、「人類光明化運動発進の宣言」なのである。観自在菩薩が無をつらねたように、この宣言では、世界の情況が語られているのである。悪は、暗は非存在なのであるから、そこには光りのみみちみつるのである。神つまりますのである。顕斎という時になって、より一層光りそのもので表現されたのが、雑誌『動向』で発表せられた尊師の『光明の縁起説』なのであった。無眼耳鼻舌身意で表現せられるものが、『光明縁起説』では、眼も耳も鼻も舌も身も神のいのちの光明のかがやきの展開として拝まれているのである。かつて釈迦がこの現象を否定するためにもちいられた十二因縁観が、ここでは先ず光があってその光の展開として十二因縁が拝まれているのである。
|
|
(4) |
ここに、いわゆる「人類光明化運動発進の宣言」と言われている尊師のお言葉を揚げておこう。これは『生長の家』誌創刊号に 〝『生長の家』出現の精神とその事業〟
と題されたご文章の冒頭の部分である。
自分はいま生長の火をかざして人類の前に起つ。起たざるを得なくなつたのである。友よ助けよ。同志よ吾れに投ぜよ。人類は今危機に頻してゐる。生活苦が色々の形で押し寄せて人類は将(まさ)に波にさらはれて覆没(ふくぼつ)しやうとしてゐる小舟(おぶね)の如き観はないか。自分は幾度も躊躇した。起つことを躊躇した。自分は中心者として増上慢のそしりを受けることを恐れてゐたのだつた。一求道者(ぐどうしゃ)としていつまでも謙遜でゐたかつた。併し今は謙遜でありたいと云ふことが自分にとつては安易を貪る一つの誘惑と感じられる。自分はこの誘惑に打ち克って人類を救はねばならない。自分の有(も)つてゐる限りの火で人類を救はねばならない。自分の火は小さくとも人類の行くべき道を照さずにはおかないだらう。此の火は天上から天降つた生長の火である。火だ! 自分に触れよ。自分は必ず触れる者に火を点ずる。生長の火を彼に移す。自分は今覚悟して起ち上つた。見よ! 自分の身体(からだ)が燃え尽すまで、蝋燭(ろうそく)のやうにみづからを焼きつゝ人類の行くべき道を照射する。
自分のかざす火は人類の福音(ふくいん)の火、生長の火である。自分は此の火によって人類が如何にせば幸福になり得るかを示さうとするのだ。如何にせば境遇の桎梏(しつこく)から脱(ぬ)け出し得るか、如何にせば運命を支配し得るか、如何にせば一切の病気を征服し得るか、また、如何にせば貧困の真因を絶滅し得るか、如何にせば家庭苦の悩みより脱し得るか……等々。
今人類の悩みは多い。人類は阿鼻(あび)地獄のやうに苦しみもがきあせつてゐる。あらゆる苦難を癒やす救ひと薬を求めてゐる。しかし彼らは悩みに眼がくらんでゐはしないか。方向を過つてゐはしないか。探しても見出されない方向に救ひを求めてゐはしないか。自分は今彼らの行手を照す火を有(も)つて立つ。
尊師は、この文章のはじまる前のページのとびらともいうべきページに次ぎのように書いておられる。すなわち、
吾れを伸ばすものは、
絶えず与へてゐると云ふ感じ、
絶えず人から喜ばれてゐると云ふ感じ、
与へる歓びは自己拡大の感じ、
自己の愛が次第に拡がる感じ、
この感じのうちに生命は伸びて行く。
と。ここに尊師が〝自分は幾度も躊躇した〟と言われることの意味があるのである。つまり、光を受けるものから、光りを与えるものへの位置の転換ということである。照らされる自分から、照らす自分への転換であり、幽斎(ゆうさい)から顕斎(けんさい)への転換である。この度の住吉本宮の顕斎は、全信徒の 〝照らされる者から、照らす者へ〟の自覚の転換である。信徒全員が〝発進宣言〟のいのちにたち還り、生長の火となって万物の前に起ったことを意味しているのである。
此の火は〝天上から天降った生長の火〟であって、人間の修業や過去の成績を因として因縁の流れによって生み出されるものではないのである。〝自分はいま生長の火をかざして人類の前に起つ〟といわれる。そのいまは久遠(くおん)の今である。吾れといまと此処がピタリと一つになってしまっている、実相の火である。自分といまと生長の火がピタリと一つになっているところに忽然(こつねん)とわが内から放射する火なのである。それ故繰り返せば
〝自分はいま生長の火をかざして〟 とは自分と今と生長がひとつになった久遠の火ということである。これは絶対の生長、自(おのず)からある生長である。
それ故、この火は久遠不滅の火なのである。〝自分の身体(からだ)が燃え尽すまで〟とは、完全に実相の火のかがやきによって、肉体的存在(全現象界)を否定しつくすことを意味しているのである。却ってここに久遠の実相の火の顕斎がある。光明一元の世界。神が〝光りあれ〟といいたもうた光りとしての火一元・生長一元の世界が意味されているのである。
|
|
| (5) |
それはまた、「般若心経」において、光明なる観自在菩薩が照見し給うのと同じ姿として、尊師という、いまと生長が一つになった火(光明)が照見し給うのである。観自在菩薩が無、無、と照見し給うのに相当するのが、人類の現状への想いなのである。無、無、と照見せられたとき、現象が否定されて照見される光りがそこに満ちて行くように、尊師が現状を言われるとき、そこに現象の完全否定が成就されて、尊師の輝きが満ちつくして行くのである。尊師がある書物で説かれているように〝肉体なし〟とは肉体から逃げるにあらず十方世界は吾が肉体なりと知ることである。ろうそくが燃えつきるとは、全宇宙が火であり、ろうそくであると知ることなのである。
ここで〝起つ〟と言われるのは、久遠の今なるいのちが起つこと、おのずから起つことを意味しているのである。〝今、起て!!〟との宣言は尊師には〝今なる汝よ、起て!!〟ということであった。その天徠(てんらい)のコトバが自分のうちに復活して、尊師は起たれたのであった。それ故、その今にかえったとき、内から無限創造のいのちが動きだして起たざるを得なくなったのである。表面上は世界・人類の現象を見つめて起たざるを得なくなったととることも出来るのであるが、それのみではないのである。この生長のいまなる自分は顕(あら)われずにはいないのである。それは、人間が真理を知ったならば必ず起たざるを得ないものであることを宣言されたのである。起たないのは、真理を知らないからなのであるということである。
―― 〝友よ助けよ〟 ――この場合、久遠の火なる尊師に呼びかけられる友なるものはやはり久遠の火である。久遠のいのちが久遠のいのちに呼びかけているのである。観世音菩薩が観世音菩薩に呼びかけているのである。光明が光明に呼びかけている。光明の純粋持続である。尊師と吾れとの関係は光と光りの関係である。
――〝人類は今危機に頻している。〟――何故人類は危機に頻しているのであるか。それは〝自分〟が、全人類が久遠の如来そのものであり、このまま此処が天国であることを忘却しているからである。それでは、何故、さらに光明化運動を発進するか。矛盾ではないのか。ここが一番重要な問題となって来るのである。
何故、運動が必要であるのか。何故、立たざるを得なくなるのか。また、運動は如何にして可能であるのか。何者が運動をするのであるか。これらのことが常に重大な問題となるのである。
|
|
(6) |
〝中心者として立つ〟ということは、頂点として起つということとは異っている。中心者とは宇宙の中心として起つことを意味しているのであって、神として起つこと、光りとして起っていることを意味しているのである。ここに、謙遜と増上慢とを超えた一つの道、中心を生きる道がある。上と下とを超えたところの中心なるものの生きる道である。中心を生きるに非ず、中心なるものが生きるのである。われらが火を点じていただくとは、久遠の昔より光りであり、久遠の昔より尊師の弟子であったという中心なる自覚に点睛せられることであり、われらもまた、中心者として生きることを意味しているのである。それは〝われは神の子〟の自覚から、〝われは神の親〟なる自覚への転換の時を意味しているのである。生まれるものから生むものへの転換であり、被造者から創造者への生れかわりの時である。創造とは実在の創造である。実相なるものの創造である。実相世界はわがいのちの展開である。神はわがいのちの展開である。如来はわがいのちより生れ出づるのである。すべての実在はわがいのちの展開なるが故に、われと実在との間には如何なるすき間もないのである。そして実在の創造は忽然なるが故に時間もないのである。これを日無堅間(めなしかつま)の小舟(おぶね)に乗るというのである。自分が目無堅間なのである。自分のいのちの展開として目無堅間の小舟がある故に、小舟と自分との間には如何なるすき間も存在しないのである。
釈迦の拈華微笑(ねんげみしょう)。一つの蓮華をひねって迦葉(かしょう)につたえたいのちは、実にこの中心者としてのいのちの消息であり、わがいのちの消息であり、そのいのちの展開としての実在自己の展開した姿をつたえたのである。吾らは目無堅間(めなしかつま)の小舟(おぶね)に乗ってこの世に鳴り出でるのである。
これは、天皇の絶対性と自己の絶対性の同時成道の道である。それは、時間空間、上下左右、謙遜と増上慢を超えて中心に帰った道である。中心帰一とは中心に帰って中心と一つになることであり、自分のいのちが中心者として起つことなのである。それは中心に帰る途中のプロセスを意味しているのではないのである。尊師が、中心者として起たれたのは、プロセスとしての中心帰一ではなく中心帰一の完成、完成の中心帰一、として完成者として起っておられることを意味するのである。万教帰一というのも、すべてのものが一つの中心に帰るという永遠のプロセスを意味するのではないのである。いのちはすべてすでに帰一しているのである。帰一し、その中心から発しているものをいのちというのである。万教帰一とはすべてが帰一している、完結せる帰一、即ち中心が生きることである。すべてのものが一つから発している中心に自己のいのちを発見することである。なぜ中心帰一するか。中心からすべてが発しているからである。帰一する前に一から発しているということである。
これが〝今〟を生きるということである。これが幽斎から顕斎への転換である。住吉大神の全身全霊を生きるということである。この住吉大神の全身全霊なるいのちの輝きを生きるのが、祝福するのが神の子の自覚に点睛することである。火を点ずることである。
|
|
(7) |
釈尊がお悟りになったときには山川草木国土悉皆成仏、有情非情同時成道と万物を拝まれたのである。尊師が大啓示をお受けになられた後、庭の木の若葉にいのちの光が輝き、枝から枝に飛びうつる雀が金色に輝いて見えたといわれる。この万物が輝いているのを拝せられたのである。それを
〝天地一切のものと和解せよ〟 のお言葉で歌われたのが大調和の神示である。それは、自分のいのちが天地一切のものに和解するというよりも、むしろ、自分のいのちが天地万物から拝まれ感謝され、めでられていること、生かされていることの発見であったのではなかろうか。そのことを
〝わが生くるはわが力ならず、天地を貫きて生くる祖神(みおや)の力〟 と歌われているのである。そして、その喜びの極に歌い出されたのが「大調和の神示」であったのである。
すべてのものに神のいのちの光が輝く。木だけではなく、若葉だけではなく、尊師がお書きになるペンにもインクにも原稿用紙にも机にも、お部屋にも光りが輝き満ちている。このことは『生命の實相』第一巻 〝私と生長の家〟 の中で笠原政好氏の霊感的体験が証明しているところである。
されば、尊師のお書き下さった一文字一文字には光りが輝きわたっている。 〝暗黒〟というお言葉にも〝光明〟というお言葉にも同じように尊師のいのちが輝いているのである。それ故尊師のご本にふれる人々は、尊師から輝き出でた、「聖典」という言葉の輝きの中を飛びまわる金色の雀のごとくに、喜び輝きながら光の中にうずまってとび交っているのである。
これが尊師の観られる「聖典」と「聖典」を拝受するものの姿なのである。「聖典」と読者は光と光との関係である。この光りは「聖典」を拝読してはじめて光りとなる金色ではない。「聖典」を一語も拝読しなくとも、「聖典」が輝き神の子が輝いている。光りと光りが光りしているのがそのままの神の子の姿であることへの拝みである。拝してから人間が光りとなるのではない。本来そのままで光りであったことを祝福して、拝まれて書かれたのが「聖典」であるから、「聖典」の前には本来完全円満、何ものをもつけ足すことのいらない光りが立っているのである。それ故、神の子と「聖典」とは光りと光りとの関係なのである。このことが自覚されるとき尊師のお言葉を光明一元、唯神の輝きの流れのまにまに自分の生命を托することが成就するのである。
|
|
(8) |
住吉本宮ご造営の特志奉納の記念品として贈られた高等技術印刷による尊師のご揮毫は 〝春雨来華自開〟 である。これは読んで字の如くであるが、もう一つ、 〝谷口雅春がこの世に『甘露の法雨』を持ち来すと金波羅華実相が自ら開く〟 と読んだ人も居る。この中で 〝自ら開く〟 というところが顕斎と関係をもつのである。 〝最早や人間の力では及ばない。神に直接出て来ていただく〟
ということ。神(実相)が自ら人間の力をかりずに自分で顕われて来るということなのである。しかし、 〝自ら顕われる〟 というのは実相(神)が現象化するということではないのである。生長の家では
〝現象はない〟 と完全に否定されているのである。現象に現われるか現われないかは問題ではないのである。これは実相が実相する実在の世界の消息なのである。
〝火を点ずる〟 という 〝火〟 は実相、実在のことである。何故 〝火を点ずる〟 という運動が可能であるかの問題は別に論ずるとして、何度も問題にして来た「神の子の自覚に点睛(てんせい)す」の最後の部分を引用しておこう。
彼は「事実に面しては」という。しかしその「事実」とは伺ぞや。現象のみ、本来無きもののみ。しかもこの「本来無き現象」をありと観るかぎり、彼のごとく実相一如の世界に没入する体験を得るとも、何人も「われらは弱し、われらは完からず」と嘆ぜざるをえないのである。しかし、これを「事実」というのはまちがいであるのである。知れ、事実というは実相のみであるのである。だから実相の実在のみを強調し「弱きものは無し、完からぬもの無し」と、いっさいの悪を空(くう)じ去って、しかして「一切皆善の実相的事実」のみを肯定するとき、われらは現象的事実をも征服しえて、「われらは弱し、われらは完からず」と現象的事実に征服された弱音を吐く必要がなくなるのである。
生長の家はかく「実相皆善」のみを強調して、「現象は無なり」と現象的不幸一切を空じ去る。さればこそ現実を征服する現実的威力を発揮するのである。「現象あり」と観ずれぱわれらは現象に力を認めるがゆえに現象を征服することができないのである。「現象も現象として在るのであって、かく本体界のみを主張し、本体界の完全観念を現象界にも適用せんとするのは、本体界と現象界とを混同するものである」との諸宗教家または哲学者よりの非難があるが、われらは本体界と現象界とを混同するのではない、混同とは現象界を在りと認めての立場であるが、われらは現象界無しと自覚するがゆえに、無きものは混同するの恐れなきがゆえに、われらはただ常に本体界の完全性のみを主張するのである。その結果、本体界の完全性がそのまま現象界に投影して、現象界の不幸を征服することができるのである。「現象は現象としては在るのである」といって現象界を本体界に対立せしめたり、「本体界の自叙自展が現象界であって、本体界と現象界とは一如である、そして、現象界は本体界のうちに包摂せられるものである」というような在来の見方を脱しえないような宗教では、とうていそれは現実人生を支配することができないのである。生長の家の思想が、かく素晴しい現実人生の支配力を有しているのは、主として「現象無し」とスカッと截(た)ち断り、実相独在を明快に斬然(ざんぜん)と主張しているからであるのである。
(『生命の實相』第27巻127~129ページ)
|
|
(9) |
目無堅間(めなしかつま)とは実相生命の拡がりには隙間(すきま)がないということを表現した言葉である。自分と実在との間にすき間がないということである。神の子のいのちはすき間なく実相世界をなしているという意味である。神の子のいのちは実相世界をなして堅くつまっているのである。
また、目無堅間とは、実相・実在と自分との間にすきまのないことであるということは、自分が中心であるということである。これは飛躍ではない。実在世界は一所一切所であり、一時一切時、一仏一切仏であり、自分と実在とがすきまなく一つであるときは、即ち、自分と中心との間もすき間がない。したがって飛躍というものはないのである。ここに中心帰一の現成がある。中心帰一すれば、すべてのものは中心となるのである。中心に帰一するとは自分が中心となることにほかならないのである。
中心帰一とは、中心が一に帰ることである。本来中心なるものであればこそ一なる中心に帰ることが出来るのである。中心が中心に帰るのである。一即多、多即一である。中心なるものが一に帰ること、中心なるものが中心することが光明化運動であり、神の子の生活である。
|
|
(10)
|
わが内に天国があるとは、われは天国を入れることの出来る、天国よりもなお大いなるものであるということである。
わが内に神がまします、とは、われは神を内に入れることの出来る、神よりなお大いなる存在であるということである。
すなわち、われは、全知全能の神よりなおく大いなるものであるということである。古事記で幽の幽なる天之御中主之神以前の存在とは、この意味でのわれの存在である。全知全能よりもなお大いなるものが幽の幽なる存在なのである。
それ故に、 〝われ神に全托する〟 とは、自分のいのちが力をもたないために、神に力をかりるというのではなく、われより出でたる全知全能なる神にすべてを托するということなのである。
〝住吉大神出でます〟というのは久遠の火が輝くことであり、〝住吉大神すべてを浄め終る〟とは、久遠の火一元となることであり、光明一元となることである。この光明と天照大御神の光明とは同じものである。住吉大神が何故宇宙を浄めたくなるのであるかというと、住吉大神の中なる天照大御神なるものが天照大御神を顕わしたくなってくるのである。それ故、住吉大神自身は 〝わが生くるはわが力ならず、天照大御神のいのちここにありて生くるなり〟 と言われているのである。住吉大神のはたらきそのものが天照大御神の光明の進軍の姿なのである。
|
|
(11) |
そこで、何故、光明一元なのにさらに光明化運動の必要があるのかとの問いは、 〝住吉大御神宇宙を浄め終りて、天照大御神出でましぬ〟 であるのに何故浄化のはたらき、住吉の大神がはたらく余地があるのであるかということになるのである。
住吉大神のはたらくべき、浄化されなければならない世界、迷いの世界が存在することは光明一元(天照大御神・六合照徹(りくごうしようてつ))と反するのではないかということである。
迷いはどうして存在するのであるか。
完全な神の分身であるあなたが何故迷うかと、あなたは問うであろう。〝迷いは何処から来たのか〟 というのは仏教でも重大な設問になっている。「〝迷い〟本来無し」と一刀両断に截ち切る解答は従来からある。それでも、「では、その本来無き迷いが、どうして恰(あたか)もあるかの如くあらわれて来るのか」という最後の問が残るのである。その最後の問に〝わたし〟は答えることにする。
○
あなたは仏教の「煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)」という語をたびたび聴いたこともあるし、読んだこともあるであろう。〝迷い〟がそのまま〝菩提〟の道程であるということである。〝迷い〟という「菩提とは別なもの」があるのではないのである。〝迷い〟と見えているものが、實は〝悟り〟が動き出し、現象化しつつある道程であるから、〝迷い〟本来無しといい得るのである。
あなた達が〝迷い〟だと思っているものは、実は〝わたし〟が〝神の国〟を地上に顕現するための土台又は地盤になるための精神的基礎工事を行うために授けたところのものなのである。
○
時間及び空間というものは本来ない。実相世界は超時空的存在の世界であるからである。時間の観念、空間の観念は物質的存在を心に描くための謂(い)わば〝画布(カンバス)〟として必要なので〝わたし〟が人間に与えたところの架空的観念である。それは光の波を固定して映画の光景として見せるスクリーンの役目をなさしめるために〝人間の心〟に対して〝わたし〟が与えたところの概念である。このスクリーン上に生命の波動(心の波)が放射されると、生命の波動(心の波)が固定化されて物質化して感じられるのである。この物質化として感じられる基盤がなければ、地上に天國を建設するという〝わたし〟の芸術を成就することが出来ないので、〝わたし〟は人間に時間空間の観念を与えたのである。
時間及び空間は〝わたし〟の創造である。
○
空間の観念を与えられた人間は、恰もスクリーンを与えられた人間が映写機から放射される光の波を、単に〝光の波〟として感受せずに物質界に起った具体的事象として感ずると同じ原理で、生命の波動(心の波)を単に波動として感受せずに、それを地上世界の物質的事象として感じ、その物質を具体的確固な存在として感ずるのである。地上が具体的存在だと感ずる精神的地盤が成立しなかったら、地上に天国を実現することは不可能なのだから、生命の霊的波動を物質化して感じ、地上を具象的存在だと感ずることは地上天国建設の第一歩の成就なのである。
○
しかしながら、また別の観点からするならば、生命的波動を、空間面上の〝物質〟と飜訳して誤認することは〝迷い〟の発生ということにもなるのである。そして、それが、その〝迷い〟の発生は何処から生じたかという常に投げかけられる原因になるのである。〝光〟がなければ影を投ずることもないように、〝迷い〟は地上に天国を描き出すための画布として、〝わたし〟が投げかけた影である。
(『神 真理を告げ給う』44~47頁)
と『神真理を告げ給う』の中で尊師は述べられているのである。あるのは光と光りの進軍のみなのである。神と神の進軍あるのみなのである。それ故〝迷い〟は光りが光りするはたらきであり、さらに大いなる幸福の展開を意味しているのである。
|
|
(12) |
尊師はなぜ〝われは起たざるを得なくなったのである〟と言わざるを得なかったのであるか。これは〝神はなぜ「光りあれ」と言わざるを得なくなったのであるか〟ということと同じことである。それは神は光であるからである。光がみずから光りを表現したくなったのである。それは神以外の外部的状況によって
〝光あれ〟 と言わされたもうたのではないのである。神以外には神のわざを規定づけるなにものも存在しないのである。
また尊師がなぜ、〝天地一切のものと和解せよ〟と発せざるを得なくなったのであるか。
木の葉の一つ一つがかがやき、そこに雀がとびうつる。その雀も光りである。その金色の雀が「発進宣言」で〝友よ、助けよ〟と言われる友なのである。輝く木の葉が尊師の発せられる「聖典」の言葉なのである。
歴史に発展が無いごとく光明化には発展、進歩は無い。完全の持続があるのみなのである。
愛するのではなくどっぷりと愛の海につかり切って生かされ、あまえ切っているということである。こらえ我慢し合ったりするのではない。なんともいえない、ゆたかなよろこび、勝利の喜びのひびきが鳴りだしたのだ。尊師は、 〝私は神に愛されつづけて来た〟 と言われたとのことである。このいぶきが光明化の運動方針となって輝くとき悩みや病をも癒すものとなるのである。それは山も川も木もうたいだす秘密である。
〝友よたすけよ〟の友の中には、あらゆる神々が入っているのである。だから、誰が来ても尊師は神として拝まれるのである。友よ、光なるものよ!。友は釈迦が言った成仏裡の存在なのである。
なに故、神は「光あれ」と言わざるを得なかったか。ここに「発進宣言」を発し出だされるゆえんがあった。
「発進宣言」は〝神示〟である。それは『甘露の法雨』、南無妙法蓮華経、南無阿弥陀仏というような姿をしているのである。
|
|
(13) |
あの時、尊師が『今、起て!!』という天徠の御声をお聴きになった。そのいのちの響きを開示されたのが「発進宣言」であり、それは神なるいのちの光明として発せられているのである。いのちの響きとしての光明なるが故にあの宣言のすべての文字が光明の輝きそのものなのである。
ここに立ったとき、すべてのすべての同志の片々たるように見ゆる愛行もすべてこの久遠の光の延長としてとこしなえに輝やきわたるのが拝めて来るのである。
この発進の宣言は尊師の自叙伝の中にある 〝今起て!!〟 という神の天徠の声に応じて〝今、立つ〟ということばとなったのである。あの一連の神との対話のコトバのつづきに尊師が、〝実相は完全でも現象の私はまだ貧しいのです〟ということばを発せられる。すると神の啓示は「聴け、無いものは無いのだ。あるのは実相のみだ。汝がキリストだ、釈迦だ、無尽蔵だ!!」とひびくのである。
このキリストなる、釈迦なる、無尽なる光明なるものが起ったのである。
これはいわゆる菩薩行ではない。如来そのものの行である。仏の大行である。もてる火は小さくとも大行なのである。
『生命の實相』の中に出てくる尊師と谷口恵美子先生との話。奈良の大仏をおみやげに買って帰られた恵美子先生が尊師にわたされる。すると尊師は
「これはずい分小さな大仏だね」
と言われる。すると恵美子先生は
「小さくても大仏でございます。」
とお応えになられるのである。尊師の〝かかげられる火は小さくとも〟光明一元であれば大火なのである。
先に引用した『生命の實相』第二十七巻の中の〝神の子の自覚に点睛(てんせい)す〟という章において、綱島梁川(りょうぜん)の神の子の自覚と生長の家の神の子の自覚のちがいについて述べられているところに戻るが、綱島梁川は一応神の子の自覚に達しているのであるが、〝現象は現象として在るのである〟というように現象を最後の一点において認めているのである。尊師が火を点ずるといわれるのは、この最後の一点を払い浄めて神の子の姿を拝み給うことなのであった。
|
|
(14)
|
〝わが光りにふれよ〟とは、『七つの燈台の点燈者の神示』の中の〝疑わずにわが光を受けよ〟ということにあたるのである。
そして、尊師の立たれたのと同じ〝光〟として立つことが、神の子の一人一人に出来るのであるということを宣言されたのが同じ神示の中の〝今、すべての病人は立つことが出来るのである〟という宣言となっているのである。すべての病人である。神想観が足りないという病人も、愛行が足りないという病人も、「聖典」を読むことが足りないという病人もすべてのすべての病人が立つことが出来るのである。そのままで人類の〝光〟として立っているのであるということへの尊師の祝福のコトバなのである。尊師が光りを点ずるとは、この人類の本当の姿を礼拝し祝福することにほかならないのである。たしか『美しき生活』の中で尊師は、〝人間はそのまま現象をこえて神の子である〟と『生命の實相』によってすべての人々を拝んだ、すると気がついてみると自分もすべての人々から拝まれていたのであるということをお書きになっている。
〝神の子人間〟の神とは何かにおいて、尊師は光のみの世界を発見されているのである。あとは、光りへの拝みと祝福あるのみなのである。
われわれは、宗教によって罪と病と死との三暗黒を消してから、光りとなるのではないのである。我というものを消してから光となるのではないのである。そんなものははじめから無いのである。そんなものを放っておいて、そのまま〝神の子です〟と光の中に飛び込んだときに、そのあとで、罪と病と死との三暗黒は消えるのである。
光りが近づくとき〝罪と病と死〟の三暗黒が消えるというときの、この光は、これから光となるべき、可能性をもつわれわれ人間を照して罪を浄めてそれからやっと自分が光となるというような意味での不完全な自分を照している光ではないのである。先ずわれわれが光の中に飛び込んだとき、〝光〟は自分と神との一体性から輝くところの自分の光りとなっているのである。先ず、自ら光りであると宣言し光として立つことからすべてがはじまるのである。
「人類光明化運動発進の宣言」の輝きを受ける全ての人々のために書かれているのが『七つの燈台の点燈者の神示』の中の 〝疑わずにわが光を受けよ〟 なのである。
|
|
| (15) |
そして今、人類光明化運動はやっと産ぶ声をあげたばかりである。宇宙にしてからが、いまやっと産ぶ声をあげたばかりなのである。
〝神光あれと言いたまいければ光ありき〟 これが光明化運動のはじめである。これが宇宙における「光明化運動発進の宣言」であり、〝久遠の生長の家〟から発進した光明化運動である。光の前に神があったごとく、光が生れようが生まれまいがいのちは存在するのである。そのいのちは自ら立っている生命である。それは常立(とこたち)に立っているいのちである。光をも生み出すところのいのちである。これが幽の幽なる、光の光なるいのちである。すべてを超え切ったいのちである。すべてを越えるが故にすべてのすべてなる神をも越えるのである。ここに幽の幽なる存在が忽然と顕現する。
〝神光あれと言いたまいければ光ありき〟 の神として立っておられるのが尊師のお姿なのである。しかして、〝光あれ〟と言いたもうた部分にあたるのが、発進の宣言であり、それをいよいよ詳密に説き明かされたのが、たとえば「光明縁起説」であるのである。
しかして、また、すベてを越え自分のいのちさえも超えるが故に、〝吾れ立つ〟とは却って自分がなくなることを意味するのである。
また火を点ずるとは、暗(やみ)はないということ、光明がすみずみにひろがるということである。点ずる者の前には暗はないということである。点燈者の前には死と罪と病との三暗黒はないのである。死を越えるとは死は無いということを知ることである。それは死との戦いではないのである。それ故、死を越えるということは楽行なのである。それ故火を点ずることも楽行なのである。『生命の實相』第一巻のはじめの〝七つの光明宣言〟の解説の中で「次第次第に」とか「徐々に」とかいう言葉がつかわれているのは、これは光明のゆたかなる、ゆとりある動きを現わしているのである。これは楽なるゆるやかなる光明の拡がり、しかも神の絶対のいのちの創造的展開の消息なのである。
『ああ、人生は何という喜ばしさだ! 私は諸君と共に手をたずさえて、この善き事業が大きくひろがる日のために尽したいとの念願で一杯です。』(『生命の實相』第一巻39頁)
という言葉で『生命の實相』の中での「七つの光明宣言」の解説は結ばれている。この喜びはどこから出て来ているのか。この喜びはどこからも出で来たらず。或る日、忽然として、久遠の今、今、ここに自分のいのちの中から出で来たるのである。光明化をやってからという、ある時間の後、ある空間的条件をととのえたときにという外の条件によらず、自ずから立っている喜びである。常立ちの、自ずから立っている喜びが火の正体なのである。喜びを得るために発進するのではなく、〝喜び〟なる主体が発進するのが光明化運動の発進である。
|
|
(16) |
何故に天国を建設し得るのか。それは天国なるものが動くからである。天国が天国するのが天国建設の運動である。中心が中心するのが中心帰一であると言うのも同じ意味である。
ここには天国建設の途上における犠牲ということのない道が開かれている。『生命の實相』第三巻には次のように宣言されている。
すべての人間がこの生長の家の説く真理を悟るとき、人生には、誰も人生の弾丸(たま)にあたる者がなくなる、すなわち少しも犠牲なしに地上天国になるのであります。……如何なる混乱の巷にあつても、地上天国建設途上の人生の敵弾に倒された犠牲者とはならないのであります。
(『生命の實相』第三巻95頁)
ここには尊師が犠牲的立場に立って人類光明化運動を発進せしめられたのではないことを説いておられるのである。神には対立者がなく犠牲がないからである。尊師の発見された神の光明というものをそのままに輝やかせているのが人類光明化運動であるからである。何故、犠牲ということが起らないのか、ということを明らめることは、尊師の発見された神というもの、生長の家というもの、そしてかかげられる真理というもの、そして何者が発進するのかということを明らめることと直通しているのである。
絶対不敗の光明の進軍である。
幽の幽なる吾れ。光明化運動は何ものがやるかの問題である。〝発心(ほつしん)(発進)正しからざれば万行むなしく施す〟という道元のコトバがある。
状況の上に立って運動を展開すると、光明一元論を全力的にうち揮えなくなる。〝いくら光明一元でもそれを知る人の数がこれだけという状況では〟ということになって、力を抜かれ、きばを抜かれてしまうのである。情熱が出なくなる。それはまた、尊師への堅信の喪失でもある。
|
|
| (17) |
中心帰一とは中心が一(はじめ)に帰ることなり。神想観とは神が想い観るなり。神想観をして神になるに非ず。仏行とは仏が行くことである。行をやって仏となるのではない。仏となるために行をするのではない。愛行とは愛が行くのである。行をやって愛となるのではないのである。愛(神)となるために行をするのではない。「われいま生長の火」とは神想観の〝われ今〟である。神想観の最初のわれ、今、ここである。五官の世界を去ってから久遠の今になるに非ず。われなる今なる自分が五官の世界を去るのである。五官の世界を吹き去るのである。
神はわが生みの子である。吾れは何故神を生み得るのであるか。それは吾れが神であるからである。神は神みずからを越えられる。幽の幽なる存在としての神である。吾れが〝神〟とコトバでとなえるとき、実に神を生み出しているのである。すべてのすべてなる神を生み出しているのである。一即多なるが故に、八百万(やおよろず)の神々を自分は生み出しているのである。
神はまた、自由自在なるが故に、人間の子ともなり親ともなり給うのである。
今は、吾れが神の親なるとき。今は吾れは神の子であるとき。
神は神みずからを超えたまう。常に超えるいのちが神である。神が神するのがわが生くるということである。これが光明を点ずるということである。
神を否定し、超えることが現象を否定し超えることにほかならなかったのである。これが幽の幽なることの所以である。みずからを超えるとは新生ということである。常に新たなる甦りである。甦りが神である。
すべてのすべてなる神が超えられるとき、そこに真の新生がある。神は自らを超えたまうのであった。
神というものはないのである。ただ光のみがあるのである。光というものはないのである。ただ神があるのである。しかし、前の神とこの神とは同じではないのであって、超えるという輝きそのものの永遠の新生の持続があるばかりである。
実相世界はわがいのちの展開である。実在とはわがいのちとひとつであるということである。わがいのちと一つでないものは、いくら有りと見ゆれども、それは実在ではないのである。実在(ある)とは即ち自分のいのちであるということである。自分とはなれたる存在としての天国などというものはないのである。天国とは、何よりもまず自分のいのちでなければならないのである。
否、天国などというものはないのである。自分のいのちがあるのみである。実相というものはないのである。自分のいのちがあるのみである。神というものはないのである。自分のいのちのみがあるのである。光というものはないのである。ただ自分のいのちのみがあるのである。
自分のいのちを天国といい、実相といい、神といい、光というのであった。
わがいのち光あまねしとはこのことである。うちも外もすべて暗なし。うちも外もなし、光も暗もなし、生も死もなし、わがいのちのみあり。これがあまねしということであったのである。
〝神の子〟というとき、光で〝神〟と言ったとき、それは自分のいのちの生み出した神なのである。自分のいのちの展開としての神なのである。〝神の子〟とは即ち自分の孫なのであった。その意味において、親と子は一体なるが故に、〝われは神の子〟なのであった。
|
|
| (18) |
『今、たて!』とのコトバによって、尊師は仏として、光として、たたれたのである。しかし、この光りは暗を知らない光なのである。暗と相対するところの光ではないのである。〝光は暗黒(くらき)に照る。しかして、暗黒(くらき)はこれを悟らざりき〟である。そして、〝光りもまた暗黒を知らざりき〟である。光明一元である。
『甘露の法雨』に〝暗(やみ)に対しては光りをもって相対せよ〟とある。この光りは決して暗を知らない光りなのである。
尊師が大啓示をお受けになったあとのおそらくはじめてのおコトバであると思われるのが例の詩である。「天使の声」である。
〝わたしの魂は虚空に透きとおって真理そのものと一つになった。〟
〝「お前は実在そのものだ!」〟
というおコトバを書かれたときが、そもそもの光明化のはじまりである。これが生長の火が立ったときであったのである。これこそが初発の「発進宣言」であった。
人間を見抜くという。本当に人間を見抜いたならば神の子が見えるのである。世界を本当に見抜いたら極楽が見える。尊師が宇宙を見抜かれたとき、天地一切は大調和であったのである。
暗はないとは、そこにそのまま光が充満していることである。現象なしとは、光明遍照光明充満ということである。
「世界に非道が充ちてゐると云ふことは、歴史と同じやうにそれよりも更に古い文學さへも同じやうに、否あらゆる文學中の最も古きものなる祭司の宗教と同じやうに古い嘆(なげき)である」とカントは言つてゐる。けれども生長の家は世界には何ら非道なことは存在しないと言ふのである。それは存在するものは「道」ばかりであるから、それが少くとも存在する限りはそれは「善」であり、それが「善」でない限りに於て、それは如何に存在するやうに見えようとも、それは、「非道」即ち「道の欠乏」「道の無」をあらはしてゐるに過ぎないとするのである。(…中略…)
凡て心の眼を開いて見れば「悪」なるものは存在しない。これ第一にして最後の真理である。
(『光明道中記』244頁)
|
|
| (19) |
説似一物即不中ということばがある。これが神であると一物を示せば即ちそれてしまっているのである。
これが光明化運動であると一行動をとらえて示せば、即ち中っていないのである。光明の光明たるいのちは観えなくなるのである。
自分が光明一元のいのちに帰ったときに存在するものすべてが光明化運動なのである。しかも、その光明一元の世界とは形ではないのである。
尊師が、「久遠いのちの歌」において、前半の部分で、「此の身は虹の如し……」と現象のはかなさを歌っていられるようであるが、なるほど、文字はその通りであるが、ここには悲しみが表現されているのではなく、現象を超えて久遠のいのちに還った神の子が大勝利の歓喜を輝かせておどっているのである。その意味において、全面、久遠いのちの歓喜の歌なのである。
尊師が一見、現象の危機をとらえていられるかのように見えるのは、それは、現象の不完全性を、無常性を即ち非道を、即ちそこには〝何も無い〟〝あるのは神のみ、光明のみ〟の世界を指し示されているのである。
尊師は、〝火を点ずる〟と言われるが、しかし、ある日、私の前に立ち給うた尊師は、ただただ礼拝し給うておられた。そのおすがたは、「私は、未だかつて、一度も火を点じたことはありません。私は未だかつて一人も救ったことはない。すべてのものは、火を点ずる必要のないはじめから光りであります。すベてのものは、未だかつて迷ったことなく救われる必要のない如来にまします。それをただただ拝んで祝福させていただいているのです。」と語っておられたのである。その意味では、
〝私は未だかつて一頁も『生命の實相』を書いたことはありません〟と説き給うておられるのであった。
|
|
| (20) |
尊師の開かれ給うた世界には、光明しかないのである。すべてのものの仏なる姿を祝福されて、お拝みになり給うて、その拝み
の合掌のかがやきの姿としてここに『生命の實相』は輝やいているのである。それだからこそこの『生命の實相』は、「あなたはこれを読まなければ救われませんよ。神の子になれませんよ。生長の家になれませんよ。」という姿をしていないのである。却って、
「私は、すべてのものが、はじめのはじめから、如来であることを発見したのです。この本の一行さえも、何ものをもつけくわえる必要のないいのちであることを私は発見したのです。こうして私はこの本ですべての人々を拝んでいるのです!!」
と鳴り響いているのである。ここに、〝火を点ずる〟ということのその〝点ずる〟消息があるのである。
〝み心のごとくならせ給え〟という祈りにおいて、〝み心のごとく〟とは〝神の心と同じように〟ということであり、神の心と自分の心とが一つであること、神と同じ光を発する主体に立つことである。神とともに天地創造のつづきを生きることである。〝み心のごとくならせ給え〟とは〝神と同じ心とならせ給え〟ということであったのである。
〝信〟ということは〝人が言う〟と書く。これは神と同じ心にかえった人が言葉を発すること。神と同じ光源に還った神の子は常に、今、此処において〝光あれ〟との言葉を発しているのである。〝信〟とは何らかの意味において自分以外のものにこちらのいのちを合わせてゆくことではない。
〝信〟とは却って外界の否定である。否定といえども、それはそのまま光明が言葉によって十方世界を満たすことである。〝信〟は自らここに立って、自ら光りのコトバを営むことである。外なるものを全く必要としない自発のものなのである。
〝われはいま生長の火をかざして立つ〟というときの、生長の火とはこの〝信〟の誕生を意味しているのである。
|
|