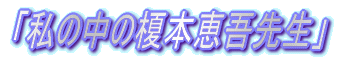

  |
合掌 ありがとうございます。 榎本恵吾先生のご遺徳を偲び、 ご縁のあった方々に執筆いただいた文章を、 お送りいただいた順(新しいものが上)に掲載しています。 左の 「もくじ」 の お名前のところをクリックすれば、 その方の投稿のところが表示されます。 |
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(97) 2007/10/15 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 榎本先生の訃報に接したのは、生長の家教修会が終わってから一週間後の火曜日の午前中だったと記憶しております。庶務の担当者より榎本先生の「謹告」を見せられました。本当にビックリしました。何故なら教修会終了後、宇治に帰られる先生とお別れの挨拶と握手をしたばかりだったからです。 上司の許可を貰いお通夜・告別式に参列させて頂きました。榎本先生の人望の厚さには驚かされました。懐かしい面々とも会うことが出来ました。 先生とご対面させて頂いたとき、まるで 「自分は死んでないよー。人間は久遠のいのちそのものだからねー」 「自分(榎本)は、はじめのはじめから無かったんだよー」 との声が聞こえてきそうです。悲しんでおられた方もおられましたが、自分は悲しみも涙も湧いてきませんでした。 「榎本先生らしいなー」と思いました。 告別式の時も 「(あの世で)先に行って待ってるからねー」 と言われている感をうけました。 一子奥様の言葉もまた素晴らしかった。さすがに榎本先生の奥様といった感じでした。 だから先生が亡くなられたということが未だ実感できません。 何故だろうと考えますと「死はナイ」ということを文字通り身をもって現象界最後の教化(きょうげ)として教えて下さったのではないかと思うしだいです。 「『そのままでよい』 のお言葉で救われました」という方もいらしゃいましたが、自分が研修生をしていて病気入院の退院後、榎本門下生のある女性からその「『そのまま』でいいんですよ」とのお言葉は自分には、どうもスッキリしませんでした。自分は『そのままでよい』 のお言葉で救われましたのではありませんでした。人間が「神の子」「仏」ならば「ただそのまま」でよいはずはない、何かしなければ、何もしないでもよいはずはないではないかとの焦りのような感覚がなかなかぬぐい去れませんでした。しかし、よくよく考えてみると救うとか救われるとか言う以前より、「はじめのはじめ」から救われ済みであったことを発見されたのが谷口雅春先生であり、そのことを直接、私に気が付かせて頂いたのが、藤原敏之先生であり、榎本恵吾先生であったのであります。その先生方もきっと口をそろえて言われることでしょう。「私は、ひとりとして救ったこともなければ、助けたこともありませんよー。みんな既に救われ済みの神の子、仏じゃもの」と。 「人類光明化運動」は、「人類救済運動」とも言われております。 實相から観たる「人類救済運動とは、人類(神の子)は、はじめのはじめから救われ済みの運動であり、神の子とは、神の子の拝みあい、感謝しあい、生かしあいの世界の運動のことではないか」と切に思うこのごろであります。 平成19年10月14日 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(96) 2007/9/9 |
|||||||
榎本先生は、まったく不思議な先生でした。 自分が榎本先生を初めて認識したのは、確か昭和60年7月の下旬頃かと思います。 ここで「認識」という言葉を使ったのは、その前年の11月の練成会の講話でお会いしているはずなのに、おぼろげな記憶しか残っていないためです。かすかに、あの「ニコニコ」マークを黒板に書かれてお話しをされた先生がいらしゃったような気がしますが、それがきっと榎本先生だったのでしょう。その時は自分にはその不思議なお話しは理解が出来なかったためだと思います。 翌年5月、宇治の職員とならせて頂きました。その頃宇治別格本山では、練成期間以外の大道場での早朝行事は、宇治の職員が持ち回りで自分の行いたい神想観を先導することになっていました。その日、職員になって初めての先導が廻ってきました。その早朝行事後のトイレで小用を足していると横から「今日の神想観は、良かったねー」と声を掛けて下さったのが、榎本先生でした。 その頃、榎本先生はいつもなら入龍宮幽斎殿での早朝行事に行かれるとのことでしたが、その日に限って何故か大道場での早朝行事に参加したくなられたことを後で知りました。その日、自分が行ったのは、ほとんど行われていなかった「神を讃える神想観」でした。職員になって間もない自分を本部講師の先生が誉めて下さったということで大変嬉しく、また一体どういう先生なのだろうと先生の著書『光のある内に』を買い求め心読しました。 それ以来、先生の限りなくなつかしくあたたかい不思議さに魅入られてしまいました。それ以前から(はじめのはじめから)先生に魅入られていたような気がします。 ある時、先生が「不思議とか不可思議ということは、人間の思う事が出来ないということだから「神」ということなんだねー」と言われたことを思い出します。 昭和62年3月、宇治から生長の家本部へ転勤となり先生から直接ご指導頂く機会は少なくなりましたが、たまに宇治へ行くと不思議と予感のままに先生にお会い出来、御文章や御揮毫を頂いたりしましたが、まるで龍宮城に行って玉手箱を頂くような不思議な雰囲気と時間でした。 平成元年、長男を授かりましたが、先生と同じ誕生日という不思議なご縁も頂きました。その子はダウン症という障害を持って生まれてきましたが、それを伝え聞かれた先生から頂いた親子3人の合掌子絵入りの『生命群像』の書は我が家の宝物であります。 今日は、先生が生きていらしゃれば満70歳のお誕生日であり、短命と言われておりました長男が満18歳の誕生日を迎えることが出来ました。これもひとえに生長の家のみ教えの賜物との感を深く致します。また、本日は谷口雅春先生に「生死の教え」の神示が天降った日でもあります。今日、本部会館の同じ階に居ながらも滅多に会わない久都間さんにトイレで引き合わせて頂き、筆無精の私の背中を押して下さったのも榎本先生の不思議なお導きを深く感じる次第です。唯々感謝合掌。 平成19年9月5日 拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(95) 2007/7/11 |
|||||||
(一) まだ、女性の練成員さんが法楽の間で寝泊まりされていた時分のことです。私も寝泊まりしていて、早朝カッコーワルツの音とともに跳ね起き、急いで廊下の脇にある長い洗面所に行き、コンタクトレンズをはめようとしました。それが、指から滑り落ち、色とりどりのタイルの貼られた洗面所に転がってしまったのです。一生懸命探してもなかなかみつかりません。側に居た年配の練成員さんが二人、愛念で一緒に探してくれましたが、やはりみつかりません。そのうち、早朝行事の時間も迫り、その練成員さん二人が、「もう無いわ。」と言って、水道の蛇口を捻り、ジャーッと水を流して手を洗われました。私は、ああこれでコンタクトも流れてしまったなあ……とガクッとしました。それでも途方にくれて探している所に、榎本先生が朗らかに歌を口ずさみながら、廊下を歩いて来られまして、「やあ、どうしたんだい。」と言われるので、この事を話しますと、すぐに一緒に濡れている洗面台に両手を這わせながら、探し始めてくださいました。先生は小声で、神様に祈ってくださいながら……。暫くして、「あった!」と先生がコンタクトをみつけ出してくださいました。それは排水口の縁にひっかかって落ちる寸前に留まっていました。今から思えば、実相の世界から、とっくに失くなっていたはずのコンタクトがひょっこり復活して出て来たのでは……と思わずにいられません。 (二) 私がまだ今の中講堂で賄係をしていた頃、夕食時になり、練成員さんも食べ終わり、賄の私達が皆で食べていました。その時は、焼いたさんまでした。一匹を二つに切ってお皿に載せてあり、私はあまりおなかがすいていなかったので尻尾の方の半分だけ食べて、その時は何故か、悪いけど捨てようと思っていました。今ではそんな事しませんが……。そのうち私達が座っているテーブルの所に榎本先生がいらっしゃいました。いつも先生は、お食事はされずに、お茶を飲まれては何か誰かとお話しされていくのでした。先生は、私のお皿を見られて、全く咎める様子はなく、むしろ喜びを持って、「あなた、それ(さんま)、もういらないの。食べないの。」と言われるので、「はい。」と言うと、「じゃあ、ちょっともらおうかね。」と食べ始められました。「藤原先生は、さんまの頭も固いのに食べられるんだよー。」とおっしゃって、やはり榎本先生も同じように、さんまを頭も全部食べてしまわれました。榎本先生の、全ての物に対する深い愛念の溢れる懐かしい思い出です。 (三) ある日の午後、いつもは車を運転されて幽斎殿の参道を降りて来られる榎本先生が、歩いて降りて来られました。私は下から登って来ていて俯いていたので全然気付かず、先生に声をかけていただいて、初めて気付きました。「やあ、楽しそうだね。あなたも杖をつくのが好きなの。」 丁度雨上がりで、私は傘でツンツン参道をつつき乍ら登って来ていたのです。 |
|||||||
| ――― 幼い頃、母の口癖は「……せられん」「……せなあかん」でした。それが私には苦しかったのです。例えばある時、小学校に通う私に、母は「傘がちびるから、ついたらあかん。」と言いました。他の友達は雨上がりに楽しそうにツンツンしながら、水たまりの道を歩いているのに。私はやったらいけないんだ……。そんなたわいもない幼い頃の心の縛りを、もういい大人なんだから、解放してもいいだろう、と思い、ある日から急に、傘を持ち歩く度に、思いきりツンツンと杖代わりにして楽しむようになりました。もう母とは別世帯だもの、傘が何本、何十本壊れてもいいじゃないか……と。幼少時、母一人娘一人の頃があったので、私にとっては母が全てだったのでしょう。 ――― |
|||||||
| そんな私の一人よがりな心の経緯など、先生は知るはずもないのですが、あの参道ですれちがった時の、先生の、全てを包み込むような、暖かな言葉と表情が、今も忘れられません。我家の玄関先には、榎本先生が自然の中を歩かれる度に、丁度よさそうな枝をみつけられては杖にされて、楽しそうに歩かれていた、その杖が二本、たてかけられています。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(94) 2007/6/8 |
|||||||
| なにか行き詰まることがあると、画家を志した私のために書かれた叔父の文章(*注)をひっぱり出して読む。書いてくれたのは私が十八歳の時だったと思う。これが私の基本となった。ギリギリの精神状態の時は、これを写したりもする。 二年半前に突然、母(叔父の姉)が他界し、その半年後、叔父が逝ってしまった。母の時は大木が、叔父の時は巨木が倒れたような気がした。どこか深いところでなにかが動いているのだなあと感じた。 叔父のことを想う事は同時に祖父母、私の母を含めた叔父の兄弟姉妹を想うことでもあり、それぞれの顔が浮かぶ。 祖父は私が二歳の時、他界したので、顔は覚えていないが、私の一番古い記憶として、その背中が残っている。祖父はなにかと問題のあった人らしいが、新宮技芸学校という洋裁を中心とした学校を始めた人で、私はその祖父が黒板に向っているところを、そおっとドアの隙間からのぞき見たのである。この光景が一体何につながるのか、わからないが、私はこの古い記憶を大切に大切に持ち続けてきた。 学校は住居とくっついていて、私の母がこの学校を継いだので、叔父の実家でもあるこの家で私も育った。今、想えばここは芸術的な雰囲気に満ちていた。絵や音楽を愛し、小さな庭には幾種類もの植物が植えられていた。祖母も情操の豊かな人だった。この家を通過したという点だけでも、叔父も私もすでに共通のなにかを持っていて響きあったのだと思う。 他に私の知っている叔父の暮らした場所を追っていくと、八王寺、麻生、鶴川、そして宇治。どこも懐しい。宇治では、ふらりと訪ねた私を一週間以上も泊めてくれた。寛大だった叔父はもとより叔母も、この自由な風来坊をいつも温かく迎えて下さった。 鶴川では、誰かが捨ててあった木の重い重いボロボロの本棚を私が欲しいと言ったため、どこかでトラックを借りて同じ鶴川に住んでいた私の下宿に運んでくれた。本当に面倒なことをお願いしてしまったなぁとつくづく思うけれど、私にとっては、叔父はこのような事を理解してくれる貴重な存在だった。今も使っているが、これが引越しの度に重く、ぐらぐら揺れ、「これも運ぶのですか?」というような顔をされる。愛すべきやっかいな本棚である。 叔父は独創的で突拍子もなくて愉快で、なによりも雰囲気を大事にしていた人だと思う。 それにしても母も叔父も同時期に逝ってしまって途方に暮れる。最後に大きく響いた叔父の声は本宮からの電話で、力強く「いつもあなたの絵を見ているよー」だった。 叔父さん、どうぞ向こう側でも楽しくやって下さい。きっと美味しいお酒もあることでしょう。あまり飲み過ぎませんように。 (*注 「文書館2」の22「ある画学生への手紙」) |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(93) 2007/5/18 |
|||||||
1700枚のハガキがあります。これは私が親元を離れ東京で一人暮らしを始めてから結婚するまでの五年間、私が帰省している間をのぞいた毎日、父が私あてに出してくれたハガキです。形式は裏面に「ニコニコ」と御聖経の一節があり表にはあて名と日付と丸で囲った父の名前、下半分にその日、本山であったこと、庭の草花のこと、家族のこと、飼っていた犬のことなど、他愛のない日常の様子が十行ほどつづられていました。父は朝ふとんの上で神想観をしたあとハガキを書き、藤原の祖父が早朝行事の前に本山のポストに投函し母がハガキを補充しておくという、今思うと夢のような連携プレーを経て、毎日私の元に届いていました。「今日はおじいちゃんと一緒にスキヤキです」「庭のもみじが色付きました」「本山の人と(自然薯)じねんじょ掘りに行きました」等、いつもそのハガキから季節を感じ、家族と触れ合い、何より父、そして神様と片時も離れていないという大安心をもらっていました。 父が亡くなり改めて父は出会った人すべてと百人百通りの付き合い方をしていたことを思います。それは家族も例外ではなく娘ひとり一人、婿ひとり一人、孫にいたるまでそれぞれ違った接し方、愛し方でした。そして二十歳から離れて暮らす私にはこの1700枚のハガキを残してくれました。父が私にあてた文章の中に「あなたがあなたらしく」ということばがよくありました。私は父にほとんど悩みを相談することはなく、おそらく「私らしく」解決していたのだと思います。けれど、キリスト教の牧師を父に持つ主人と結婚し、父の引退を前に洗礼を受けるよう勧められたとき、私は実家の父に、「生長の家の素晴らしい教えを知っているのに、キリスト教徒にはなれない」と話しました。そして私は日曜日には主人と教会の礼拝に出席し、牧師である父の説教を聞いているのに、主人は生長の家の本も読まないし父の講話も一度も聞いたことがないと不満を父に打ち明けました。すると父は「純君(主人の名前)には何も付け足すものはないし、そのままで最高ですよ! と言いました。そして講話を聞きに来てはいけないし、受洗をしないと許さないとまで言い、私に谷口雅春先生の「ヨハネ伝講義」を渡しました。その時賛美歌を幼い私達娘に教え、家族でコーラスし、私の結婚式の大きな礼拝堂で、教会員の誰よりも大きな通る声で、嬉しそうに賛美歌を歌っている父を思い出しました。主人と出会ってからキリスト教を知ったのではなく、父が「久遠の実在」から久実と名づけた私に受け継がれた、キリスト教への信仰と尊敬が、私の中にあるのを感じました。そして私はこの結婚を心から祝福してくれた、双方の両親に感謝をしつつ受洗しました。きっとこれが「私らしい信仰生活」なのだと思います。 その後、三人の子供に恵まれ、父は静岡に住む私たちの帰省を楽しみにしてくれていました。目を吊り上げ子供たちを叱っている私になぜか嬉しそうに「いいねえ。久ちゃんらしく思ったとおりやりなさい。間違いないんだから。」と言っていました。そしてなによりも主人の仕事での活躍を喜んでいました。 父の亡くなる一週間前、母の誕生日に電話をするとめずらしく父が代わり「今度はいつきてくれるかねえ。」と聞きました。八月にみんなで帰ると話すと「そうかね。みんなで来てくれるかねえ。」そのやり取りが父との最後でした。 父の告別式の次の日、主人はDVDで初めて山形教化部での父の講話を聞きました。その後主人は「真理の吟唱」を自分で買い通勤用のかばんに入れています。私は主人に父をもっとよく知って欲しいという以前のような不満ではなく、ほんの少しの淋しさを感じていましたが父は見事に、私からその淋しさをもきれいに取り去ってくれました。 父は父らしく突然昇天し、私は私らしく子供たちを叱りとばしながら父のいない今を生きています。 結婚式の前日に届いた最後の十枚のハガキを紹介させていただきます。 7月28日 ① いよいよしめくくり、いや出発のときを迎えましたね。こんなうれしいことでこの便りをしめくくれることは本当に有難いことです。今夜、犬養道子の「新約・聖書物語」お母さんと二人で買いました。 7月28日 ② 夕方、下の玄関のところの六畳の障子張りをお母さん、実代ちゃん、妙子ちゃんと私とでしました。お母さんが、どうしても張りかえて行かないと心が晴れないらしかったのです。これはまっ白い、新しい出発をする久ちゃんのためだね、と話しました。信ちゃんはお母さんの髪の手入れです。 7月28日 ③ まっ白い障子の紙を見ていますと、その中から、あなたの生まれた時のことなどから、あなたがあなたらしい表情で浮かび出て来ます。やっぱり明るいですね。 7月28日 ④ あれは、榎本組※に私が居た時、上から信ちゃんまでの三人をつれて金町の方の現場に用事があって行った時、金町の方の駅のホームで電車を待っていた時、あなたは長い三つあみを左右から上で結び合わせていました。ベンチに座って私の顔を見てくれた時、本当にきれいな子だと想いました。 ※(注) 一度本部を辞めて勤めた会社 7月28日 ⑤ そして、それから色々と有難う。あなたがこの世に生まれて来てくださったこと、あなたの存在そのものが、光であり、よろこばしさそのものです。太陽はどこに行っても其処が昼なのですね。 7月28日 ⑥ 「人間は宇宙生命の咲き出でた花である」と祝福されています。人間は一生、生まれてきた時から花なのですね。花は自分が自分であることを限りなく満足し、よろこんでいるのですね。花よめさん、花むこさんに本当によろしく。 7月28日 ⑦ 何と言っても高塚君と一緒になれたこと、今までの全てはこの出逢い、出発のためにあったのですね。純の純なるものがあなたにも輝いているからなのだと神に感謝しています。 7月28日 ⑧ そして高塚君を生んでくださったご両親に心から感謝でいっぱいです。高塚家のご先祖様にも心からのご挨拶の式でもあると出発の式のことを想っています。 7月28日 ⑨ 人間はいづこより来り、いづこに行くのであるか。あなたはやがて素晴らしい生命を宿し、生み育てる時、なおいっそう神秘に心を動かされる。生命は自分で何かを知っているのだと想います。 7月28日 ⑩ 書いているうちに十二時をとっくに過ぎてしまいました。もうこれは7月29日の分ですが、⑩として出します。それではあなたらしくニッコリ笑って、、、。心からおめでとう。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(92) 2007/5/18 |
|||||||
合掌、ありがとうございます。 私が榎本先生のご講話を初めて拝聴させていただいたのは、二年前の三月、病気で心身ともにどうしようもなく辛い時に受けた一般練成会のときでした。先生は演壇に立つなり、黒板に大きなニコニコの、太陽のような笑顔をお書きになり、眼鏡と顔の間にできた隙間から私たち参加者を眼光鋭く見渡され、力強い口調で、私たちは、はじめから、何をせずとも、そのままで神の子である、ということを、ひたすらお説きになられました。 当時の私は、先生のあまりのインパクトに、はじめは驚きましたが、どんどんと先生の話に魅了され、心の重荷が自然と雲散霧消していくのを感じながら感動に胸が打ち震えました。そして、その後一ヵ月を研修生として過ごすことになりましたが、奥様の一子先生と共に、先生には大変かわいがっていただきました。わずかな間でしたが、得る物の多き時間を過ごさせていただき、私の人生の岐路であったことは紛れもない事実でしょう。 私が先生からご指導いただいた中でもっとも印象に残っているのは、生長の家のエッセンスである『生命の實相』を、「何度も反芻し、事あるごとに、必要に応じて本を開くようにしなさい」ということでした。『生命の實相』は、人生生活の辞書とでも言ったらよいでしょうか、「これにより解決できない問題はない」と教わりました。 研修生の研修行事の一環であった聖典の輪読の時間、先生は愛深い笑顔でご指導くださり、終わりしなにご披露くださったピアノの演奏や研修生も交えた聖歌の合唱は今でも鮮明に覚えております。 先日(平成19年5月3日)行われた第五十九回青年会全国大会では、縁あって副総裁先生ご夫妻の前で体験談の発表もさせていただきましたが、それはまさに榎本先生への一番の恩返しとして、感謝の気持ちを形に表すことができました。自分の発表の間に感じていた、何ともいえない温かさには、全世界から結集した皆様のご愛念もありましたが、霊界の先生のご愛念でもあったのだと今更ながら気づかされました。 先生が今生での使命を全うされ、お亡くなりになったとき、直接お別れのご挨拶はできなかったのですが、神想観をすると、神を通して先生とお話をしている感じに浸り、いつもと変わらぬ太陽のような温かい笑顔の先生、そして幽斎殿でお祈りくださる先生のお姿が、目に浮かんで参りました。 これからは、先生にご指導いただいた通り神意を第一とする青年となるべく日々精進してまいります。常住不変の神の子の実相を拝み、おこがましくも、少しでも先生に近づければと思います。 先生と出会う機会を与えてくださった神様に、そして何より、未だ途切れることのない先生のご愛念に心より感謝し、私の今生での使命を果たさんがために祈りに徹し、人類光明化運動、国際平和信仰運動に邁進して参ります。 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(91) 2007/5/16 |
|||||||
「生まれた当時、姉妹四人の中で一番声が大きかったあなたですから、笑い声もきっと一番大きい筈であります。幸せでした。ますますお幸せに。 父 」 父のこと、そして父との思い出…あまりに大きなテーマに、一体何をどう書けばいいのだろう? と思っていた。きっかけになればと引っ張り出してきた、結婚式の朝に家族から送られた寄せ書き。最後に見たのはいつだろう…。なんとなく思い出してダンボール箱の中から出し、読んでみた。涙が溢れた。私の声が大きかったことなんてすっかり忘れていた。 物心ついた頃からずっと、私は自分が一番父に近いところにいると思い込んでいる。ひとつの部屋に家族6人が3枚の布団で寝ていた頃も、ふたりの姉、赤ちゃんだった妹と母、私と父という組み合わせだった。家族で外出する時、私と手を繋いで歩いてくれたのもいつも父だった。姉ふたりと、小さい妹の間で、不機嫌になりがちだった私を散歩に連れ出してくれたりもした。 そんなふうに父と過ごしてきたせいか、叱られても他の姉妹をかばうようにして私だけ強気で父に向かって行ったし、父を恐いと思ったこともなかった。 小学生の頃、お酒を呑む父が嫌で、押入れや下駄箱にお酒を隠したことがあった。「ダメ!」と睨みつける私に、「のぶちゃん、お酒、ちょっと出してきてよ~」と、あのにこにこでもなく、にやにやでもない何とも言えない表情で言うので、私もつい笑ってしまって固い決意もどこかへ行ってしまうのだった。 多感で悩みの多かった学生の頃は、何を相談しても「そのままで最高!素晴らしい!」と言ってくれた。しかし当時、もっと具体的なアドバイスや劇的に意識がパッとひっくり返るような宗教的な言葉も聞きたかった私は、その言葉に少し物足りなささえ感じていた。しかし父の言葉は、私が大学を卒業し社会人になってからも、そして結婚についての相談の時にも「そのままで最高!満点!」と全く変わらなかった。 寄せ書きをもらった時、父からのメッセージとそこに大きく描かれた見慣れているはずの「ニコニコ」を見て、いつも父からの具体的な言葉を求めていた私は、大きな愛とたくさんの祝福を絶えず父からもらっていたことに気付き、わんわん泣いて目をはらしたまま、義兄が運転する車で結婚式会場となる教会に向かったのを覚えている。 中学生くらいからか、だんだん性格が形成されていくとともに、私はどちらかというと小さい声の人になっていった。人の前に出て話すのが嫌いで、出来る限りそういう役回りから逃げてきた。 ところが、結婚してからはどういう訳か、町内会に始まり幼稚園、小学校の役員など人前で話さなければならない役を次々と与えられ、司会をしたり挨拶をしたりする機会がほんとに多くなった。人前に出ると極度に緊張するので、その度に「私は声が大きいんだ!」とそれだけを自分に言い聞かせていたような気がする。 でもよく考えてみると、今でも知らず知らずのうちに笑ったり、怒ったり、子供を叱ったりと感情を爆発させる時には、自分でもびっくりするほど大きな声が出る。そういえば、結婚して間もない頃、何かを父に相談した時に、「どんどんのびのび怒ったり泣いたりしなさい。実相はビクともしないんだから。」と強い口調で父に言われたことがあった。 しかし、私の性格がどうであれ父がなんと言ってくれようが、私の大きな声はどうにもならない。なぜなら、私の声の大きさは父親譲りなのだから。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(90) 2007/5/16 |
|||||||
義父が亡くなってもうすぐ2年。 今、義父の創った数々の曲の中から『日はやさしく(光を喜ぶ歌8ツ)』を編曲して手廻しオルゴール用の専用シートの5線譜に書き込みパンチで穴を開け、CD音源を作るという作業をさせていただいています。 義父が亡くなって程ない頃、義母が長浜への小旅行の折に偶然見かけて買って帰られた手廻しオルゴール。『お父さんが好きだと思って…』と義母がくるくるとハンドルを回していた姿がとても美しかった。僕はインターネットで作曲用のシートがあることを突き止めそれを相当数義母に買ってもらいました。これでいつでも義父の曲をオルゴールで演奏できるようにします、と豪語して。 最初に手がけたのは蓮華寮の義父の玄関に額装されて掛けられていた1曲。『偲ぶ会』※に間に合ったのはこの1曲のみでした。 義父が亡くなってすぐ義母より預かったメモ帳数冊、そこにびっしり義父の手によって書かれたカタカナの列を譜面にしていく作業、これはこのメモを書いたときの義父を追体験することにもなり直に義父の頭の中を覗き込んでいるような感覚にとらわれるほど僕にとって濃厚な体験となりました。しかし、『僕がやります』と請け負った当のこの僕は、到底義父の頭の中に入り込んで作品を形にしていく体力など持ち合わせず、結局やりかけたままのメモ帳が2冊と手付かずのメモ帳が数冊、今も僕の部屋の本棚の上に置いてあります。 我ながら嫌になるほど怠惰な僕を責めるどころか労わってくれ、やっと出来た物に全身全霊を込めて喜んでくれる義母と家族、そしてその声が聞こえてきそうなほど喜んでいる義父。あと4曲なんです。最後はピアノでばっちり決めますから。 ※ (編者注)平成18年7月8日、宇治別格本山で繰り上げ命日祭 の日に行わせていただいた「榎本恵吾先生を偲ぶつどい」 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(89) 2007/5/5 |
|||||||
おじいちゃんはぼくの名前をいつもいい名前だと言ってくれました。ぼくがまだお母さんのおなかの中にいた時、おじいちゃんが、「こんど生まれてくる子の名前は周(あまね)です。」とみんなに伝えてしまって、お母さんがおじいちゃんにおこったというのを聞きました。おじいちゃんはすごくうれしかったんだと思います。 おじいちゃんは、ぼくがあそびに行くと、家の中でおいかけっこをよくしてくれました。おじいちゃんがだまってゆっくりおいかけてくるのが、こわくておもしろかったです。 おじいちゃんのねているへやに入ったら、ハーモニカが三つぐらいありました。おじいちゃんがそれをふいてくれました。すごくうまかったです。おじいちゃんはとても気もちよさそうにふいていました。 おじいちゃんはいつもぼくたちが夜ごはんをたべるころにねていました。だから今でもへやでねているみたいに思うときがあります。だからいまもみんなといっしょにいるんだと思います。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(88) 2007/5/5 |
|||||||
ぼくは静岡に住んでいるので、ぼくがおじいちゃんの家に行けるのは大きな休みだけでした。でもその短い間にもいろいろな思い出があります。おじいちゃんが作ってくれるそうめんはとてもおいしかったです。あとおじいちゃんはいつもするめや魚をおいしそうに食べていました。それをぼくにも食べさせてくれました。いつもよりおいしい気がしました。おじいちゃんは食べている魚を絶対に手を使わないできれいに食べているのがすごいなと思いました。 三年生の時、ぼくは春休みの宿題をなくしてしまいました。でもその宿題がみつかりますようにと、おじいちゃんがいのってくれたので、CDプレーヤーのうしろからその宿題が見つかりました。その時ぼくは、おじいちゃんはすごい人なんだと思いました。今でもさがし物があるとおじいちゃんにおねがいします。 おじいちゃんが亡くなってしまってから、ぼくは時々おじいちゃんといた楽しい時を思い出します。おばあちゃんちに行ったら、おじいちゃんのおぶつだんにおいのりします。なんでおじいちゃんは亡くなってしまったんだろうとぼくはいつも思っています。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(87) 2007/5/5 |
|||||||
なかなか子宝に恵まれず、信仰自体が苦しく心重い日々を過ごしていた中、榎本先生にご指導を受けました。お蔭様でその2年後、結婚10年目に元気な男の子を授かりました。妊娠、出産を通して先生からいただいた深いご愛念と数々のお言葉は、待ちに待った子どもの命とともに、私の命をも新たによみがえらせてくださいました。先生に巡り会えた奇蹟に心から感謝をしつつ、最初にご指導を受けた後に送らせていただいたお礼状の一部を以下に紹介させていただきます。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 「不完全は、不完全ということにおいて存在しない。」 ――まさに私が聞きたいと心から願っていた一言でした。今までご本や講話で何百回も見聞きした言葉ではありますが、どうしてもどうしても自分に響いてこなかったのです。納得できなかったのです。でも、今回先生の発せられたお言葉は、私の固く閉まっていた心をふわっと一遍にほどいてくださいました。もう嬉しくて嬉しくてたまりません。このお言葉を思い返すたびに、嬉しくてありがたくて涙がこぼれます。 あの晩は本当に数年ぶりに、おふとんに入って微笑みながら眠りにつける嬉しさをかみしめることができました。そして翌朝、起床の時も「あー、良かった、良かった」と安心感と共に目が覚めました。何だかわからないけれど、暖かくて嬉しくて、先生にご指導いただけたことが信じられないほどに嬉しくてたまりません。 信仰が苦しいということは、どこか間違っている、しかも何が間違っているか、どうしてか、ということまでもわかっているのに、どうしてもそこから脱け出せずにいました。ご本を読んでも自分にはどこか空々しく響き、無理に納得しようとしても、自分をごまかせきれない虚しさにいたたまれませんでした。 でも今は、命は親から先祖へと過去に向かって意識を集中させていくようなものではなく、あくまでも神、先祖から親、そして私へと喜びを伝える営みであるということを実感した思いです。 先生にご指導いただいた次の日、知り合った方二人とお昼過ぎに幽斎殿まで散歩をしました。すると本当にそこは「葩さんさん」の世界でした。うぐいすをはじめとする野鳥がさえずり、桜の花びらがひらひらと舞う中を歩き、本当に信じられないほどの美しさに感動し、鳥肌が立つ思いでした。桜を見ては、こんなにもきれいだったかと思い、末一稲荷の朱塗りの橋のところでは新緑がこんなにもやさしくみずみずしかったかと感激し、本当に感動の連続でした。何百もの花びらがゆっくりひらひらと舞い降りる中、天を仰いで両手を広げて立ってみました。全身で春の命を深く呼吸している気がしました。先生のご指導前にも大講堂から見える宇治川の景色をきれいとは思いましたが、どことなくよそよそしかったものが、今や柔らかく暖かいものとして自分の中に入ってきた感じでした。 ご指導いただきましたことに、そして先生にめぐり合わせてくださった神様に、心から感謝しお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(86) 2007/5/2 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 25年前、青年会運動への情熱が無くなっていく中で、「宇治の練成会に出席したら、もう1度やる気が起きるかもしれない」と練成会に参加しました。練成中榎本先生にお声をかけていただき、研修生のお誘いを受けました。その時私は、1ヵ月も滞在するつもりもなく、「20日位でよかったら研修生になります」とお返事したのを覚えています。 それから3年半、榎本先生の暖かくて広い光の中で過ごせた事は、本当に大きな喜びでした。 研修期間中、素晴らしく輝いていく研修生の仲間を見ながら、私は自分が少しも変わっていないのが悲しく、先生に質問しました。 「先生、私は少しも変わらないのですが、どうしたらいいでしょうか」と。 先生は、「あなたは少しも代わる必要などありません。そのままでいいのですよ。宇治川は少しも変わらず流れているでしょう。宇治川の様に、そのままでいいのですよ」とおっしゃっていただきました。私のつたない小さな発見を、本当に宝物のように大切にあつかって下さいました。 「先生、私の名前の“朝”にはお日様もお月様もあるし、十字が2つもあります。まるで生長の家のようです」とお話しますと、あとから先生は 「佐田味の味という字は光明三昧の昧と同じだ」とお話しになりました。 「素晴らしいという字は、もと(素)を晴らすと書くのですね、素を晴らすことが素晴らしいことなのですね。」とお手紙をさしあげると、先生から光明のお返事をいただきました。少しだけ披露しますね。 「合掌 “素晴らしいとは素を晴らすことである”とは、まことにすばらしいことですね。なぜ“ひらがな”を三つ入れただけでこのように私の中に喜ばしい変化をもたらして呉れるのか、素晴らしい不思議さであると思いました。“カラッポ”と思わず叫んだ吉田国太郎先生は、谷口雅春先生の愛の中に、どんなに幸せであったかということですね~。 人と人とがはなれるように見えても悲しくはないと言えるのではないでしょうか。いや、のびのびと悲しみを晴らすといいますか、晴れた悲しみというようなものを人は体験するのだと想います。悲母観音などは、実に明るく晴れやかで堂々としていられるのは、素を晴らす、または素そのもののすがたなのかも知れません。」 先生はいつも対峙する人の素の中においでなので、その時の先生の言葉や雰囲気は少しも風化せず、年月に関係なく輝いています。こうして先生をあらためて振り返ると、どんなに先生から愛されていたか、先生の暖かい愛情を感じずには居られません。先生の光の中にいる自分がいます。先生も私達の光の中にいらっしゃいます。 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(85) 2007/4/30 |
|||||||
榎本恵吾先生、ありがとうございます。 私が先生の御講話を初めて聞いたのは、宇治の新講堂が落成したこけら落としの時でした。 何か奥が深くて難しくて、この話は特別な人にしか分からない――というのがその時のおもいでしたが、なぜか心が熱く嬉しくなったことを覚えています。 その魅力にとりつかれてか、自分や家族の病気の狭間の中で、幾度も宇治へ足を運ぶようになりました。 そんな練成会の中で、以前、「写経練成会」というのがありました。 参加者も少なく、先生方とも家族的に講話を聞ける練成会でしたのに、参加されている方はどんどん質問をされる中、私は積極的に先生へ質問したり出来なくて、今でもそのことが後悔されてなりません。 その魂の高さと尊厳ある先生に圧倒されていた私でした。 そんな中で一度個人指導をしていただきましたが、緊張のあまり覚えていないのが事実で、「そのままで……そのままで……」といったお言葉しか思い出せません。 その後お手紙を出しましたら、ニコニコのお葉書をいただきました。 恵吾先生はよく『人類無罪宣言』の本をテキストにお使いになり、ゆっくりと丁寧に雄弁にお話しして下さいました。同書 2 0 8~2 1 2ページの谷口雅春先生の自伝篇のくだり<実相なる道>で、「それはわかる!」と、その時は爆発するような大きな声となり、 「懺悔しないままで、救ってくれる神がいるんですよ!」…… 自分がいらない、ゼロであること、神そのものに活かされている喜び―― 「今、喜びましょう。今、喜んでいいんですよ。喜ばせてもらいましょう!」 と、何回も何回も神様の御心を伝えて下さいました。 生長の家の根本の根本の原理! 谷口雅春先生が最後に残されたお言葉 「病無し。迷い無し、罪無し」を恵吾先生はお説き下さったのですね。 自由奔放、無礙自在。そんな凄いご指導の中には、先生のなみはずれた努力探求の精進信仰生活があった事を、私達は奥様の一子先生からお聞きしました。 先生! もっともっとたくさんお話をお聞きしたかったです。 今は一子先生からいただきましたDVDを、私の宝物として、何時も聞かせていただいています。 今も恵吾先生は神界にて光明化運動にお忙しいのでしょう。 私も先生のご指導を無にしないよう、ニコニコと神様の御心を生活させて頂きます。そしてこれからもご指導下さいますようお願いします。 先生、本当にありがとうございます。 又お会いできますことを楽しみにしています。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(84) 2007/4/30 |
|||||||
|
合掌 いつもお世話頂きありがとうございます。 さて、榎本先生の文集の件ですが、実は平成14年9月29日から平成17年6月19日まで、われわれ有志で榎本先生に月1回ご指導いただく「一(はじめ)の会」が開催され、その内容を掻い摘んで記録に残した文があります。ご参考までにお送りいたしますので、可能ならばご掲載ください。再拝
<サイトの運営管理者より……お送り頂いたワードファイルを、そのままPDFファイルに変換してここにアップロードさせていただきます。下記項目をクリックして下さい。> 1.榎本恵吾先生「一(はじめ)の会」ご指導 2.『今』 榎本恵吾先生ご指導 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(83) 2007/4/30 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 ホームページにより、榎本先生の追悼文集の原稿締め切りが4月末日になったことを知り、書かせて頂きました。 私は二十代の頃大阪に住み、京都の私立高校の教員をしていました時、大阪教化部にて榎本先生・岡先生編著『光のある内に=聖歌のすすめ=』を購入して、通勤電車や喫茶店で何回も読み返していました。 その中で、榎本先生が「われらは此の身はこのまま住吉大神の全身なのである。全霊なのである。住吉大神の“分身分霊”であるとの自覚の幽斎の時代から全身全霊であるとの自覚の、創造的展開の時となったのである」(同著P118)という一文を読み、ものすごい感動した事を思い出します。著書にふれる前私と青年会で知りあった家内(その頃は婚約中の溝口裕子さん)と二人で総本山の新春練成会に参加し、谷口雅春先生の御講話を拝聴して“全身全霊” “あーおーうーえーいー”のお言葉を直接お聞きしていましたので、著書の一文を「そのとおり !! そのとおり !!」という気持ちで読まして頂きました。 その時に、榎本先生にお会いしたいなーと思いました。それが実現したのが二十数年後でした。私は高校教員から生長の家社会事業団養護施設「神の国寮」に転職、生長の家本部青年会部奉職、生長の家総本山に転勤し、盂蘭盆供養大祭実行委員として宇治別格本山に神癒祈願担当講師として奉仕させて頂いた時でした。榎本先生は満顔の笑顔で迎えて頂きました。 「先生の著書を読まして頂いて、お会いしたいと思っていました」と申し上げますと、「休憩の時に私の部屋にいらっしゃい」と言われましたので、先生のお部屋へ訪問させて頂きました。先生は共通の知人平野さんの話をしながら、ニコニコの絵、自費出版の本、ピアノのCD・楽譜等紙袋一杯に下さり、「神癒祈願の講師の秘訣は神様との媒介であり、無私になること、喜んでやることですよ!!」とやさしく力強くご指導頂きました。 その年の大祭の神癒祈願数が前年より多く、最終日の夕食時まで「アーオーウーエーイー」を唱え続けましたが、何とも言えない魂の喜びと、「神様はいらっしゃるのだ !!」という実感がこみ上げてきました。 「貴方、故郷が京都なら京都に帰っていらっしゃい」「はい」という会話が宇治での最後の会話でした。 私の家内の母(溝口君枝)も大阪に住んでいますが、榎本先生に個人指導して頂き、私に嬉しそうな声で「榎本先生に個人指導してもらった。よかった!!」と電話をしてきました。その御礼を申し上げようと、生長の家教修会の帰りの京王線の駅で先生に「母のご指導ありがとうございました」と申し上げると、「必ず良くなりますよ」とお言葉を頂いたのが、地上での最後の会話となりました、その数日後、御昇天されました。 奇しくも四月一日より総本山聖歌隊運営委員長を拝命し、天照大神様の調和のメロディーを歌い(祈り)全てを浄めてまいりますので、榎本先生、霊界からのご指導よろしくお願い申しあげます。 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(82) 2007/4/30 |
|||||||
榎本恵吾先生は、昭和五十六年の後半から数年間、練成部に所属されて研修生のお世話をご担当になった時期があった。この間、何人の人々が、先生との研修生活を経験されたのであろうか。あの時代から、もう四半世紀が過ぎようとしている。しかし、私たちが先生の元で過ごした日々は、ますます光り輝くものとなり、私たちを無限に蘇らせているのである。それは永遠に瑞々しく、神想観の座が結ばれるところ、聖典『生命の實相』が紐解かれるところ、私たちのみならず誰でも、いつでも、どこでも、その光りは、久遠の泉のように湧出して、みどり児の詩(うた)を奏でずにははおかないのである。 研修生たちに先生は、「私のお役目は、皆さんが安心して『生命の實相』を拝読し、神想観を実修していただくための座布団のようなものです」とおっしゃっていた。また、「私の原稿の言葉は、諸君が『生命の實相』のご本をますます懐かしくなり、『生命の實相』に振り向き、『生命の實相』に帰っていただくために書いているのです」とも語っておられた。先生の言われる「座布団」とは、“みどり児”なる私たちを荘厳する如意宝珠なる蓮華の宝座のことであり、先生はその研修を通して、一人ひとりが光明一元の實相の世界に座して、自性円満なる光の子として巣立っていく、ただただそのことを願い、観じ続けておられた。だから先生は、「皆さんは、宇治本山に光りを貰いにやって来たのではないのです。逆に宇治本山の方が、皆さんの内にやってきたのです。みなさんは宇治のみならず全宇宙を照らす光りなのです」とも、おっしゃっていた。 「“愛行”とは、“愛”そのものである皆さんが行ずるから“愛行”なのであり、神想観とは、はじめのはじめから“神”である皆さんが想い観ずるから“神想観”なのです。だから、これから神想観をした後に神になり、完全になるのではありません。先ず光りだ!」。先生の言葉は、私たちが慣れ親しんだ日常の言葉としての意匠を脱ぎ捨て、生きもののように実在からのメッセージを伝える。それは『生命の實相』の文字間に、實相世界の荘厳を観た者のみが発する言葉なのである。それは、同時に同書から出た光りの展開であり、その光りに触れた者はやがてそこに無限の懐かしさを抱きつつそこに帰るのである。「神想観をしてからではない」「『生命の實相』を読んでからではない」と宣言されていた先生ほど、誰よりも神想観を深く実修し、聖典の荘厳を讃え、聖経読誦や愛行を心底楽しく行じていた人はいない。それは、「先ず光り」なるものが、その自ずからなる喜びを鳴り響かせていた法爾自然のお姿だった。 そんな先生の信仰姿勢は、そのまま私たちへの實相直視となり、一切の現象を光りへと変える一転語となり、生長の家の「基礎論」の徹底となり、研修を経験した多くの人が『生命の實相』全四十巻を、ごくあたりまえのようにして読破していったのである。それは、先生が放つ“光りの香気”のようなものが『生命の實相』の行間からあふれ、それを私たちは呼吸していた。その光りは天地いっぱいに広がり、春夏秋冬を経験するように、研修生たちは『生命の實相』という言の葉の光りの中を歩み続けていた。やがてそれは気が付いてみれば、いつの間にか光りのまっただ中へと続いていたのである。 先生のご準備してくださった光りの座布団。今は、私たちが敷かせていただく番なのである。 二〇〇七年四月二十九日 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(81) 2007/4/28 |
|||||||
アインシュタインやピカソを穏やかにしたような風貌に、前かがみになってお茶を飲みながらぶつぶつ話していたかと思うと、突然大きな声で「ない!」と飛びはねてニコニコの絵を描き「毛じゃないんですよ」と真面目におっしゃる。最初から最後まで実相一元の話をされ、至って真面目なのに面白くて大笑いしながら、最後には涙がとまらなかった。魂の根源的な喜びで舞い上がり、泣きながら受けた個人指導。帰りの新幹線の窓から見た大きな夕焼けに「実相実相」と胸を詰まらせていたら「実相はあなたの中にあるんですよ!」と榎本先生の声が私の胸でどん!と鳴り響いた。 7年後、私は榎本先生のいる祈願部に奉職する事になり、先生を毎日360度拝見できるという幸運に恵まれました。先生は毎朝3時50分に幽斎殿の扉を開けられ神癒祈願の人型を書き4時半になると神想観の先導をされました。幽斎殿には入れ替わり立ち替わりいつも沢山の人が来ていました。大拝殿での早朝行事では、聖歌をひときわ大きな声で歌われていました。榎本先生は本当に嬉しさに喜びに満ちて先導されておりました。 榎本先生は神様や教えには絶対的な確信をもっておられましたが先生個人としては謙虚で、どの方にも平等に愛し接していられたように見えました。先生のところには体験の手紙がいつも沢山届き、その度に神癒の素晴らしさに両手放しで感動されていました。そして「僕にとって祈願者は観世音菩薩なんだよ」といつもおっしゃいました。 榎本部長は事務をしている私たちに「一つ一つの作業が祈りですよ」と言われ、その私たちをいつも拝んで下さるのが先生でした。私は榎本先生に少しでも自分の出来ることで先生にさせてもらうことはないかと考えていましたが、先生は何でも自分でされ部長室はどこよりも掃除が行き届いており、廊下を歩いていると米粒程のゴミでも拾われました。 「すばらしいねぇ~」榎本先生は何を見ても感心したように言われます。傷ついていたり殻に閉じこもっていたり、たまには反抗的な研修生にも先生は抱きしめるように讃えてそう言いました。私は、苦しいのに苦しくないなんて言えないし幸せじゃないのに幸せなんて思えないなどと言って、先生のお側にいながら不満ばかり並べ、いつかは「そんな風に言いたいことばかりいえる君がうらやましいよ」と怒られました。腹が立ったり悲しい時には、先生の帰ってしまった部長室に行って泣いたり先生の絵を見たり原稿を読んだりしているうちに心が鎮まってくるのでした。 奥様の一子先生の事を語る時、先生は本当にいつも嬉しそうでした。一子先生との日常の出来事を宝物のように話していました。何かお誘いすると「かあさんが行くのなら」と言われます。本山の旅行でも「かあさんはどっちのバス?」と言っていつも並んで座りました。ある日先生はつくづくというように「僕はかあさんが一番なんだよ」と言われ何を今更と思って聞いていると「すべての女性はかあさんの延長だからね」ととても嬉しそうにおっしゃいました。 榎本先生の家で食事をいただいている時など、私は先生と奥様の掛け合いが面白くて大好きでした。先生は家ではとてもくつろいでいて若い頃の話しや、結婚式の写真を見せていただいたこともありました。 喜多さんと妙子ちゃんの結婚式を熊野本宮大社であげると聞き、旅行を兼ねて立ち寄らせていただきました。本宮の長い階段を登ってこられるお二人の後から、榎本先生は始終顔をほころばせていながらも感無量という感じでした。一子先生はシャキッとしていて、その日も先生とまったく同じ雰囲気の笑みを称えておられました。榎本先生は「後で婿達だけと写真をとるんだよ」と言って心から嬉しそうににっこりされていました。後で私が結婚式で撮った写真をいろいろ先生にお見せすると、一子先生と二人だけで映っているのを指して「これが一番いいねぇ」とおっしゃいました。 私は榎本先生が亡くなった時の事をはっきりと一部始終覚えているにもかかわらず、未だに亡くなったという実感がありません。それなのに何故先生は突然亡くなってしまったのだろうかとずっと考えていました。発作的に先生を思いだして泣くこともあります。その時に私はいつも、先生が夢にでてきて一緒に船で釣りに行ったことを思い出すようにしています。目無堅間の小舟に乗り、先生とは神想観で通じあうことができるのでしょう。最初は先生のために聖経をあげたり霊牌を書くことなどできませんでした。でも今は一子先生のお話や笑顔の中に榎本先生を見いだすことができます。先生は一子先生の内に日に日に鮮やかに蘇り輝いていて私たちに語りかけているからです。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(80) 2007/4/28 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 「谷口雅春先生の音を劣化させず…」の原稿をのせてくださって、ありがとうございました。 私の演奏させていただいた曲集のCDが出来上がりましたので、お送りさせていただきます。1枚に入りきれなかったので、2枚組となりました。内容は、 [曲集1]…「日はやさしく」(1994年1月~初夏)・「A.O.U.E.I」(1995年夏~1997年8月) [曲集2]…「はじめのはじめ」第10曲まで (2001年冬~2005年7月) です。上記の( )内は、この曲を創らせて頂いた頃のだいたいの年代ですが、それを全部まとめてMDにするため、1999年12月に再び創り直しました。 シンセサイザーで曲を創って行く場合、もとになるデータさえ残っていれば、いくらでも音を増やしたり削ったりすることが可能なので、曲集1に入っているものは、後に大幅に創り直しをさせてもらいました。榎本先生は、一つの音を変えただけでも、いつもすぐに「変わりましたよね」と気付かれていました。その耳の良さにはいつも、大変驚かされていたことを、今も懐かしく思い出します。 前の原稿にも書かせて頂いたように、どの曲をお渡しした時も、榎本先生は大変喜んで下さったのですが、その中でも特に喜んで下さった曲が、何曲かあります。曲集1の「A.O.U.E.I」17番の「祈り合い」という曲を、とても気に入っていて下さったように思います。 →「祈り合い」(クリックして下さい) ある時、ふと、このようにおっしゃって下さったことがありました。 「私は毎年クリスマスには研修生の人といっしょに賛美歌を歌っていたのだけれど、この『祈り合い』の曲がどんどんひろがって発展して行くのをきいていたら、『祈り』というものは敬虔にするものだと思っていたけれど、そうではなく、もっと、どんどん喜びが広がって行くものかと思いまして……もしもイエスがおられたら、賛美歌を歌うよりも、招神歌を歌ったり、“イユーッ”と気合いを入れたり…するんじゃないかと思いましてね。だから、あえて毎年クリスマスに賛美歌を歌う必要もないかな……という気がしてきて、今年のクリスマスには歌わなかったんですよ。」 と、このようにおっしゃったことがありました。先生は、何かをお感じになられたのかと思います。 「A.O.U.E.I」の最後、23番の「父母」は、あえてメロディーの形を変化させて、3通りの曲想にしてみました。「1回目がバッハ風、2回目がモーツァルト風、3回目がショパン風……というように創らせて頂きました」と先生にお手紙を添えてテープをお渡しすると、とても喜んで下さいました。「最後の曲にふさわしい、いいのが出来ましたね」…というようなことをおっしゃってくださったように覚えています。なんでも、京都から福井県にご用がおありになって車で向かわれる間、数時間、車の中でこの曲を聴き続けて下さったらしいです。やはり、一つのメロディーが次々に変化して、どんどん形を変えて発展して行くことが、先生はとてもお好きだったのだと思います。 →「父母」(クリックして下さい) そして、「はじめのはじめ」8曲目の「うたいて生くるよ」も、手拍子やリズムがいろいろ鳴っているのが、とても楽しくてよいです、と喜んで下さいました。 →「うたいて生くるよ」(クリックして下さい) 他にも、リズムをいろいろつけて、明るく、にぎやかにアレンジすることも、先生はいつも、とても喜んで下さいました。喜んで下さる先生から、私もたくさんの喜びを頂き、自分の中でちぢこまっていたいのちを、どんどん、ぐいぐいと引っぱり出してもらったように思います。 今思い出しても、ただただありがたく、懐かしく、感謝と喜びでいっぱいの、創作の日々でした。 私が自分自身、この曲を一つずつ編曲させて頂くごとに、いのちをどんどん引き出して頂き、同時にたくさんの音楽の勉強もさせて頂き、先生からたくさんの喜びを頂いたように、ホームページでまたこの曲を聴かれた方が喜んで下さったら、本当に何よりの幸いです。 ありがとうございます。 <管理者より……お送り頂いたCDの他の曲も、今後本記念館サイト内に公開させて頂く予定です。> |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(79) 2007/4/27 |
|||||||
平成十五年の一月。榎本先生のご自宅にお伺いし、いつものようにお酒を飲んでいた。その時ひょっと 「ちょっと訊くけどね、佐谷君の家まで行くにはここからどう行けばいいのかね?」 と訊かれたので 「僕の家ですか?それは車でですか、電車ですか?」 と訊くと、先生はちょっとうつむかれたあと 「電車で行くとすればどう行けばいいのかね?」 と言われた。先生の何気ない穏やかさに浸っていた。 「そうですね……ここ(宇治)から電車で行くとすればややこしいですよ。何回も乗り換えなくてはなりませんし、とにかくややこしいんです」 と言うと、先生はちょっと声高に 「どうややこしいと言うのかね?」 と、腕を組み椅子の背もたれに背中を任せながら尋ねられた。僕は何故そんなことを訊かれるのか分からないまま 「先生、本当にややこしいのです」 と言うと、先生はほんの少し間をおかれ 「だからどうややこしいのか訊いてるんだが…」 その時もなお腕組みされたままだった。僕はダイニングテーブルに両肘を伸ばしながら 「それはですね…」 僕は宇治から家までの帰路の絵図を辿りながら、その記憶の混線をほぐすようにしゃべった。先生も僕もお酒をチョビチョビやりながらの話である。 「ここ(宇治)からでしたらまず京阪電車に乗って中書島まで行って、そこで特急に乗り換え枚方市駅で降りて、そこから各駅停車に乗って門真で降りるんです。そこから大阪モノレールに乗って南摂津で降りて、そこからバスに乗って…」 と、クドクド説明した。僕はその説明に少々疲れ気味になってきていた。お酒を飲みながらだったのでそのせいもあったかも知れない。そのクドクドをじっと聴かれていた先生は 「それじゃ、ここからどれぐらいかかるのかね?」 と、クドクドを区切るように言われた。僕のクドクドに退屈になられたのかも知れない。 「時間ですか?…だいだいたい1時間ちょっとぐらいですね」 と応えた。先生は僕のクドクドを最後まで聴き終えられたあと、両腕を「ハ」の字にされ 「それじゃ今度、佐谷君のところに遊びに行くよ」 何気なかった。僕はもうびっくりしてしまって 「え!僕の家ですか?」 僕は慌てた。 「それは困ります」 と言って首を傾け先生を見た。先生はにこりともされず 「どう困るんだ」 と訊かれたので、その声高になお慌ててしまい 「困るに決まってるじゃないですか」 と何もかもほかすように言ってしまった。先生はなお腕組みされたまま 「何が困ると言うんだね?」 と、ちょっと不思議がられた。 「先生が来られるとすれば部屋の大掃除をしなくてはなりませんし…大変なんですよ」 と言うと、先生は一直線だった。 「掃除なんかしてもらわなくてもいいよ」 と平気だった。焦った。僕は先生のように平気にはなれなかった。早くこの話を終えたかった。僕の背中はうつぶせになった。゛先生が僕の家に来られるなんてとんでもない、まして僕の家といっても十畳一間のワンルームでしかない、なんにもない殺風景なところに先生が来られるなんてとんでもない゛と心の内で繰り言しながら 「それとですね、先生が来られるとなったら座布団も用意しなくてはなりませんし……第一、僕の家には座布団などありませんので、もし先生が来られるとなったら座布団を買って来なければなりませんし…」 と言った。先生はその時はもうテーブルに両肘を立てられていた。 「別にそんなもの用意してもらわなくてもいいよ」 と、だんだん話が重なってもただ泰然とされていた。僕はもうその時、背中に言葉が失われてゆく感じがした。しかし、なにか言わなくてはと焦ってきて 「僕の部屋は十畳一間のワンルームですよ、先生が来られても何のおもてなしも出来ませんよ。なぁ~んにもないですよ、なぁ~んにも」 もうきりきり舞いだった。先生は僕のうろたえぶりに杭を打つように 「なにもなくてもいいよ」 とさりげなかった。 僕はこんなやりとりに早くフタをしたかった。そんなもたもたの中で一つの提案をした。 「僕の部屋は困りますが、先生.平塚さんの家ならどうでしょう?」 と、切羽詰まりながら言った。すると先生はするりと 「平塚さんの家か…」 やっとの思いだった。僕のワンルームに来られるこの話にピリオドが打てるのを身近に感じた。もうクラクラだった。先生は平塚さんのことはよくご存じだったが、平塚さんには何の許可も受けずその場しのぎに言ってしまった。先生はテーブルに両肘を立てられたまま 「そうか…平塚さんの家か。それで平塚さんの家はどんな家かね?」 と訊かれたので 「そうそう、三室戸(みむろど)の藤原先生のお家のような感じです」 と言い切った。先生はにっこりされながら 「じゃあ、平塚さんのところにしょうか。しかしだね佐谷君、平塚さんは゛うん゛と言ってくれるかね?」 と訊かれた。僕はウヤムヤに 「大丈夫です、先生が来られるとなったらきっと喜んでくれますよ。間違いありません。大丈夫です。あとは僕に任せて下さい」 と、一人勝手に決め込んで言ってしまった。あとは野となれ山となれであった。 そのあと゛いつにしょうか゛の話になり 「三月三十一日は僕の誕生日ですので三月にしません?」 と言うと先生は 「平塚さんに都合がなければ私はいつでもいいよ」 と言われ、もうその話は一旦そこで終わりかけていた。 ただ、一つ気になることがあって先生に尋ねた。 「先生、先生は本部講師ですし祈願部長ですし一個人の家に来られてもいいのですか?」 と言うと 「そんなこと言ってたら私は結婚式にも出られないじゃないか」 と、ぽつりだった。 「それもそうですね」 と思わず相槌を打ってしまった。 平塚久子さんが「私の中の榎本恵吾先生」に寄稿された「鳥飼う人」の誕生はこんなお酒の席で生まれた。 「榎本先生が平塚さんの家に行かれますがいいですか?」 と電話で伝えると、平塚さんはびっくりされながらも快諾して下さった。快諾されたものの、そのあとが実に大変そうだった。先生を迎えるための掃除で、もうクタクタになられていた。普段掃除してない所も掃除をされていた。大掃除である。毎日毎日が掃除掃除だったと聞かされていた。平塚さんには「掃除」がなににもましての榎本先生のご訪問に際しての最高のおもてなしと思われたに違いない。素晴らしいことである。尊いことである。 そんな掃除のことを聞く度に僕は想い出していた。「掃除」は天地一切感謝の現われであると、研修生の時先生に教えていただいたことを…… 尚、先生を迎えての平塚さんの家での食事会は平成十五年の僕の誕生月に始まり、春秋と四回開き、平成十六年九月五日の榎本先生の誕生日まで続いた。 その三回目の平成十六年三月二十八日、榎本先生の音楽の先生、福場江三子先生においでいただいて、福場先生の指先に奏でられるエレクトーンの伴奏に引き込まれながら僕達八名の合唱団は榎本先生の歌声という指揮の下に声をはずませた。それは生長の家のみ教えを伝え導いて下さる榎本先生への切なる感謝の合唱であったし、榎本先生への切なる「合掌」であった…… さて、その時の曲譜は ① きれいなきれいな川で ②すがしき ③はじめの光り ④輝く国よ ⑤堅信歌(演奏) ⑥光りのある内に ⑦光りの行進 ⑧埴生の宿 ⑨生長の家の歌(演奏) ⑩鳥飼う人 ⑪母に(演奏) ⑫いのちの流れ(演奏) ⑬いのちの流れ これら十三曲であった。容量の都合上、その内五曲を「榎本恵吾記念館」に寄せさせていただいた。(下の曲名をクリックして下さい。) ①すがしき ②輝く国よ ③光りのある内に ④鳥飼う人 ⑤いのちの流れ これら全て榎本先生が作詞作曲されたものである。どうか先生のこぼれる喜びをお聴きいただきたい。 なお末節ながらこの歌声を収録編集され、CD・MD化していただいた平塚光氏のご愛念に深く感謝する。 <なお、平塚久子様の投稿と関連がありますので、左の目次から(48)平塚さんのお名前をクリックしてごらんください。> |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(78) 2007/4/27 |
|||||||
私にとっての榎本先生は、先生の書かれるニコニコの顔の絵そのものでした。そしてニコニコの光は、生長の家が大嫌いで、生長の家=暗黒の家というイメージをいだいていた私を、照らしました。 私の母は、生長の家の集まりに行って戻ってくると、とても力ない顔をして、顔をひきつらせながら、「もう大丈夫よ」と言いました。その瞬間が、私も妹もとてもとても、イヤでした。私も妹も、子どもの頃、母が生長の家をやめてくれたら、うちは幸せになるのにと思っていました。母は行く度に暗くなって帰ってくる。そんな生長の家が大嫌いでした。母が生長の家へ行くきっかけとなった我家の問題も、とても残念な結果に終わり、生長の家とは、不幸の家のようなイメージをもっていました。 そんな私が、とにかく母親教室に行ってみようと足を運ぶようになったのは、榎本先生の講話のテープを聞いて、今まで思っていた生長の家と違う世界をかいま見たからだと思います。 その後、平成14年、大きな病をもらい、宇治の練成に参加し、榎本先生に会いました。私のなかで特に記憶に残っていますのは、幽斎殿での集まり(練成ではなくて、高速道路などを使ってまわりの方々が集まってきていました)十何人かの集まりで、恵吾先生を囲んでという感じの会でした。先生が宇治へ移動になる前に見た夢(火の柱が上から下へと、下から上へといっていた)のことなどをお話し下さるその雰囲気、その時の空気がとても心地よいものであった事が一番に思い出されます。 講話や個人指導いただいたことよりも何故か、その時のことが一番印象深く思い出されます。何か一番、榎本先生の空気を感じたように思います。先生が沢山描かれた絵もみんなに、みせて下さいました。 榎本先生と出会えて、自分にとって一番良かったのは、「感謝はわく」もので、我の力で力んで「感謝はする」ものではないということを知ることが出来たことです。 自分は病気が消えるという体験は出ませんでした。が、4年前に病気をしたので、宇治に行って榎本先生に会えて、本当によかったです。 さもなかったら、きっと今でも、「生長の家」=「暗黒の家」のようなイメージを持っていたのではないかと思います。 これからも「葩さんさん」を、わかるために読むのではなく、「葩さんさん」は読むこと自体が喜びなので、くり返し読んでゆきます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(77) 2007/4/27 |
|||||||
<平成十七年九月、榎本一子先生へのお手紙> 合掌 ありがとうございます。 朝晩は大分凌ぎ易くなってまいりました。“市民の森”が近いこの辺りでは今を盛りと蝉や虫たちが往く夏にしがみつくかのように力一杯声をふりしぼって協奏曲を奏でています。 扨、このたびは思いもがけない大変な品々をお送り下さり、本当に驚喜したりどうしよう! と困惑さえしておりますが・・・私如きが頂戴する資格があるのでしょうか! 本当に申し訳なくお礼のことばもございません。 でも実を申しますと、私が知りたかった正にピッタリと的を射たテープでした。ビデオテープの方はいゝのかなと思いながらも、すぐに何回も続けて拝見し拝聴し、その都度一子先生の御講話を胸一杯になりながら大感動の連続でございました。私の知りたかったことばかりでびっくりした位です。 恵吾先生のDVDは今再生する機械がなくて未だ拝見しておりませんが、かえって先のたのしみが出来た感じで、何にも勝るお宝を大切に温存しているようで無限の倖せを感じているところです。 榎本先生の世界こそ本物であり、そこが又憧れでもあり、毛一筋の不信もない筈なのに、実は現象面では一つの問題に悩んでしまう自分が未だいるのです。 と申しますのは、本家であるのに家督相続者が確立していないという私の責任上の問題です。 どうしたらよいのか、又今の現象に何を足せば希望する結果になるのだろう、とか又これは私の実相の観じ方が足りないせいなのか……などと知らぬ間に実相に背を向けて暗やみの研究をはじめている自分がいるのです。 でもそういう時、恵吾先生の “付け足すべきものは何もないのだよ” というお言葉が聞こえてくるような気がして、ハッとするのです。そして同時に『葩 (はなびら) さんさん』の中の文章が思い出されるのです。 “こちらの心で観じようが観じまいが、いちいち努力して実相を引っぱり出そうとしなくても絶対に自分で出てくる力を完備しているのです。……ですから実相にはこちらの力というものが要らないのです。” 何というすごい表現なのでしょうか! そう言えば、“これは中々大変だ” とか“中々むづかしくって”とか思うものは “すでに実相ではない” といつもおっしゃっていましたよね。そうなんだ、遠慮しないで完全円満の自分の実相を喜んでいればみ心が自然に自ずから顕れ給うのでした。そうなのでした、もう四つに組むのは止めよう、それがどんな形になろうと、み心を心として “唯々ありがとうございます” と受けてまいりましょう。その勉強のために、実践のために残りの私の人生があると言っても過言ではないのですね。 恵吾先生の教えて下さった世界こそ、次元の高いまことなる世界です。生長の家の縦の真理の神髄を、解りやすくより偉大にかみ砕いて教えて戴けた私達は、本当に倖せでありました。 永遠(とわ)の感謝をこめて、心から「有難うございます」を捧げます。 今までのこと、今回のこと、心から御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 九月五日 畑元 佑季子 榎本一子先生 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(76) 2007/4/24 |
|||||||
そうですね、先生とお会いしたのは昭和57年ころでしようか。 生前まで、わがままな僕を指導してくださり、本当に感謝しています。 先生が現象界から去った後も、父と一緒に月一度幽斎殿で神想観をしていますが、僕は今でも先生がみんなの前で神想観をしている姿が脳裏に焼きついて、今でも先生がいるかのように見えるのです。 「みんなと一緒に、神想観をしようね。」って、本当に今でも先生は霊界からみんなに優しく見守っているのですね。 微力でありますが、これからも幽斎殿の神想観は続けます。「安心してくださいね。先生ありがとうございます。」 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(75) 2007/4/16 |
|||||||
私が先生を想うとき、ご生前に幽斎殿の廊下や各部屋の隅々にまで流れていた、明るく温かくやわらかく喜ばしい光の流れのような空気を、その中で手を動かすと、その手の動きに添ってゆったりとその光が流れ動くような、そんな感覚をもって想い出されます。 そのような雰囲気の中で先生を部長として戴きながら奉職させて頂いた日々は、言葉に表し尽くせないほどの幸せでした。 先生は幽斎殿を霊的研究所と言われ、「おおっぴらには言えないけれど、生長の家が僕のために霊的研究所を作ってくれたと思っているんだよ」と話されたことがありました。練成部から祈願部に異動になり、先生が練成の担当から外れて行かれたのを惜しむ声もたくさん聞かれる中、そのような味わい方をもって先生は感謝し喜んでおられました。先生の物事に対する味わい方は“無条件に生かされている”という絶対の感謝の中から出てくるもので、折々の先生のお言葉をお聞きする度、私は先生を味わい方の天才だと思っていました。 先生ご夫妻がまだ菟道のご自宅に住んでおられた頃のことです。書や絵をよく描かれるので、家に帰るとすぐ二階に上がって、お好きなことに没頭され、なかなか降りてこられない。少し淋しさを感じた奥様が二階に上がって行かれ、わざわざ先生が腹を立てるようなことを言って“ちょっかい”を出すと、先生は「母さん、そんなに僕のことを想ってくれてありがとう」とおっしゃったと、そして「主人はいつもそんなふうに言ってくれて」と奥様は嬉しそうにお話し下さいましたが、本当に先生はいつもこのように味わって感謝をされていたのです。 また、「僕にとって家内は全ての全てだからね。滝さん(私の旧姓)なんか家内の延長だよ」とおっしゃって下さり、先生が奥様から受け取り味わっておられる“女性なるもの”をお側でお仕えさせて頂いている私などからも味わって、喜んでくださっていました。 こういう先生のありようは、ご自宅でも職場でも全く同じで、場所によって変化するということはありませんでした。このようなありようが、先生そのものだったのです。 先生はたいへん愉快なお方でもありました。お酒が大好きで、幽斎殿に月下美人の花がたくさん咲いた翌日、焼酎と梅酒を造るときの大きなビンを買ってこられ、その月下美人の花を焼酎に漬けて、執務室の棚に並べました。一つのビンの中に蟻が入っていたので、「先生、蟻が一匹入っていますよ」と言うと、「いいダシが出るねー」と嬉しそうにおっしゃって、大笑いをしたこと。 廊下で会うと、「やあ、どうかね?」と満面の笑顔で声をかけてくださるときの、こちらが嬉しくなるような、愉快そうな明るい雰囲気。 感謝祭の最後に楠本総務が退場されるときに、本当に嬉しそうな大きな声で一番先に「楠本先生、バンザーイ。バンザーイ」と、飛び跳ねておられた姿。まるで青年のようでした。本当に愛すべき愉快なお姿でした。そんな先生のお姿が嬉しくて、みんなで「バンザーイ。バンザーイ」の大合唱……。 幽斎殿に流れていた雰囲気は、先生の雰囲気そのものでした。先生は本当に美しいたたずまいの方でした。限りない懐かしさをもって、先生の雰囲気が想い出されます。 私の結婚が決まったとき、龍宮の本源世界からポッカリと湧いて出てきたような感じで、「実に幽斎殿的だねえ。」と喜んで下さったのが、昨日のことのようです。 青年会活動に行きづまって、悩み苦しみ、自分の魂を納得させて下さる師を求めて、さ迷っていた私が、先生の「現象は無い !!」の一言で、先生を正師と定め、長い年月お側に置いて頂きました。 今日の幸福と安らかさ、そして先生との幸せな時間を、ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(74) 2007/4/14 |
|||||||
私は、妙子ちゃんの結こん式で、くまのに行ったことがとても強く頭に残っています。妙子ちゃんの結こん式が終わって、妙子ちゃんと喜多さんが2人で旅行に出発した後、私は熱を出しました。とてもしんどかったのでねていました。目が覚めると、おじちゃんがおいのりをしながら足をさすってくれていたのです。私はしんどかったけれど、もう治ったような気持ちになりました。たまに、おじいちゃんが足をさすってくれていたということを思い出すときがあります。うれしかったです。 私は、おじいちゃんと最後の旅行を覚えています。あわじ島へ行った時のことです。私のお父さんとお母さんと妹の唯子とおじいちゃんとおばあちゃんと6人で行きました。あわじ島で私たちは、海へ行きました。わたしはびっくりしました。クラゲがどこもかしこもとってもたくさん陸にうちあげられていたからです。私は気持ちが悪いと思いましたが、おじいちゃんはそれを楽しんでいました。私はそれを見て感心しました。おじいちゃんは、クラゲをつえでつついていました。つえでつつくと、クラゲはむくむくと動いたり、全く動かなかったりしました。 おじいちゃんがなくなる前くらいから、学校でなぜかいいことが続いていました。友達となかよくなれたり、あまりしゃべったことのないような子が「バイバイ」と言って声をかけてくれたりしました。その時は、なぜかいいことが続いているなと思っただけでした。でもおじいちゃんがなくなってしまって、お母さんにこの話をしてみると「きっとおじいちゃんはもうわかっていたんだね。」と言っていました。 おじいちゃんはまだ若いのになくなってしまったけど、この短い間にふつうの人の一生分を生きていたんだなと私は思いました。もしかすると、ふつうの人の一生分以上のことをしていたのかもしれないとも思いました。 私はおじいちゃんがなくなってしまって、ただ悲しいのではなく、これから、おじいちゃんがついているから自信を持とうと思います。私は、この作文を書くことができてうれしいです。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(73) 2007/4/11 |
|||||||
ぼくのはじめという名は、おじいちゃんがつけてくれた名前です。名前の意味は、はじめからすばらしいという意味です。いとこ七人いた中でおじいちゃんに名前をつけてもらったのは、ぼくだけでした。それに、おじいちゃんは、ぼくの名前で曲を、作ってくれました。それは、なんと四十八曲ありました。 『はじめのはじめ』という楽譜になりました。ぼくは、それをきいてとてもうれしかったです。 ぼくが、おじいちゃんに、「散歩に行こう」というと、いつも「いいよ」と言って、ぼうしをかぶって来てくれました。行くところは、いつもきまって塔の島でした。いつもじっとして魚を見ていました。魚とにらめっこをしているようでした。ぼくは、となりでたにしをつかまえてあそんでいました。 ぼくがけんどうを、ならいはじめてからは、竹刀をもっていっておじいちゃんとすぶりの練習をしていました。 ぼくが、「かたぐるまをして」と、言うと、いつも「ほれ、乗れ」と言いながらしゃがんでくれました。ぼくは、かたぐるまをしてくれてるときは、心がウキウキしました。 時は平成十七年七月十二日の8時28分。おじいちゃんが亡くなった。みんなでわんわん泣いた。そして、今でも宇治川の魚をじっと見ていると自然と涙があふれてきます。 楽しかった祖父との生活。それがなくなるとちょっとさびしい。 完 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(72) 2007/4/11 |
|||||||
いつも私がおじいちゃんの家に行くと、「よく来たね。」と言って、私が大きくなってもだき上げてくれました。そんなおじいちゃんが大好きでした。 私がピアノを弾いていると、「上手だね。もう一回弾いて。」とほめてくれました。 あるときおじいちゃんといっしょに、おじいちゃんがリングスケッチブックに描いた、絵や歌を見ていると、「清(すず)ちゃんとはぁちゃん(弟)にノートあげるから描いてごらん。」と言われ、ナスの絵や風景の絵を描こうとしても、力が入ってしまって、おじいちゃんのようにうまく描けませんでした。おじいちゃんはそれを見て、笑っていました。それは一年生ぐらいの時でしたが、まだそのノートを大切に持っています。 そして、私が四年生の時、ソプラノリコーダーをなくしてしまって、おじいちゃんに「リコーダーなくしちゃったんだけど、みつかるように祈っといてくれない?」と電話をしたら、「うん、分かった。祈っとくよ。」と言って祈ってくれた。それから一週間たっても見つからなかったので、楽器屋さんに買いに行きました。でも、どの楽器屋さんもしまっていました。そして、次の日も家でリコーダーを探していましたがみつかりませんでした。それで母がおばあちゃんに、そのことで電話している時に、弟の机のあたりでリコーダーをみつけて、「あった~。」と言っていました。あとでおばあちゃんに電話をすると、「あって良かったね。おじいちゃんがずっとお祈りしてくれてたのよ。」と言ってくれました。私は「ずっと忘れずに祈ってくれてたんだ。」と思って、とてもうれしかったです。このとき、私は改めて、「お祈りの力はすごいなぁ。」と実感しました。 おととしの春行われた、たえこちゃんの結婚式でのことです。熊野本宮の階段を上ぼりながら私に、「きれいな良い所だね。清ちゃんの結婚式もこんな所で出来たらいいね。」と言ってくれました。私は今でもそのことをはっきりと覚えています。その日のお昼は、旅館で喜多さん家族といっしょに食べました。その席で、お母さん達姉妹とおじいちゃんおばあちゃんで「埴生の宿」などの曲を合唱したり、おじさんといとこでギターの弾き語りをしたり、おじいちゃんは楽しそうにお酒を飲んでいました。そして、お酒が入ったおじいちゃんは上機嫌で歌を歌っていました。その時のおじいちゃんは、とてもうれしそうでした。そしていよいよ帰る時、おじいちゃんは、私の車で帰ることになっていたので、おじいちゃんが大好きな「チェリビダッケ」が指揮するクラシックの曲を聞きながら、京都方面と神戸方面で、道が分かれるまでいっしょに乗って行きました。 この時がおじいちゃんと話した最後でした。 おじいちゃんとのなつかしい想い出は、たくさんあります。 私が物心がついたころ、おじいちゃんは、ごく普通の人だと思っていました。でも、お葬式にはあんなにたくさんの人が来られていたり、お葬式が終わっても、お墓やお仏壇におがみに来られているので、びっくりしました。それにお葬式の後、作品展みたいなのにたくさんの人が来られているのを見て、「おじいちゃんは、すごい人なんだなぁ。」と思いました。だからおじいちゃんを誇りに思います。それから私が悩んだり、不安な時でも、いつでもおじいちゃんがついていると思えるので、安心して色々なこと取り組めるようになりました。これからも「いつもおじいちゃんがついている」と思って、いろんな事にちょうせんしていきたいと思います。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(71) 2007/3/31 |
|||||||
32才まで独身だった末っ子の私は、25才で結婚していった姉達3人よりも、数年多く父と母との3人暮らしをしました。大人になってからの父母の一人占めはとても楽しく、何よりの神様からのプレゼントだったと、今感謝いっぱいです。 特に陶芸の仕事で独立してから、父が亡くなるまでの約2年間は、毎日のように工房にやって来る父と、本当に沢山の時間を過ごしました。工房立ち上げの時には2人で信楽まで原料を買いに行ったり、父が板をのこぎりで切って道具を作ってくれたり……。昼寝をしたり、時にはお酒を呑んだりもしました。 初めての窯(かま)焚きの朝には、早朝行事の前に工房に来て、窯に向かってお聖経をあげてくれました。展示会へ出品する前の作品が入ったダンボール箱にも、お聖経をあげてくれました。 私は父の温かな祈りの中で、いつも大安心で仕事をしていたように思います。 私の造った皿や花瓶に父は絵付けをしながら、「これを幸せって言うんだねー」とニコニコしながら言っていました。私に親孝行の喜びも与えてくれました。 まだまだ技術の未熟だった頃から、どんな作品を見せてもただただほめて喜んでくれる父がいたから、続けられていた陶芸でした。でも父が亡くなって、もう作品が作れないのではないかと思った時、気がつけば、そばにはどんな時も私の作品の一番のファンでいてくれる夫がいました。私は大きな夫の支えのおかげで、それまでどおり大安心で作陶を続けることができました。 結婚してもうすぐ丸2年になります。今では元気な男の赤ちゃんまで授かり、幸せな日々を送らせて頂いています。 「早く2人の赤ちゃんが見たいなぁー」と結婚が決まってから毎日のように言っていた父。我が子を見ていると、たまにふと満面の笑みで喜んでくれている父の顔が浮かびます。 私達の結婚のキューピットになってくれた父。 最後に大きな大きな幸せを残して旅立ってくれた父。 お父さん、本当に有難う。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(70) 2007/3/31 |
|||||||
「あなたはこの本があると思ってるのかねっ !! この文字があると思ってるのかねっ !! この私がいると思ってるのかねっ !! 何で幽斎殿に来る必要があるんだねっ !! 何で私に個人指導してもらう必要があるんだねっ !! あなたは神想観神想観というが、何で神想観する必要があるんだねっ !! 何で『生命の實相』やこの本を読む必要があるんだねっ !! そんなもの一切する必要ないんだよっ !! どうしてそう言い切っていいのか、次来るまでに考えてらっしゃいっ!」 この言葉は、平成15年の4月に幽斎殿の写経室の一室にて、初めて恵吾先生と個人的に話しをさせて頂いた時に、恵吾先生が私に対して最初に発せられた言葉でした。 この当時、私は臨床心理士という専門職を目指して心理カウンセラーの仕事をしていましたが、人間本来實相そのものであるのに、自分自身も含め人は社会は世界はどうしてこうまでも不完全極まりない現象に溢れ尽くしているのか!という實相と現象の対立矛盾に心身ともに押し潰されていました。 そしてその苦しみが生き地獄のようにピークに達し、「もう自分には『ただただ實相のみに超入せよ』という道以外、自分が生きる道は残されていない。實相と現象の対立矛盾・分裂の問題をはっきりさせない限り、そこをごまかしたまま何事を為したとしても、自分に待ち続けているのは永遠に暗く虚しい地獄だけだ」というところまで完全に追い込まれていました。そしてこの唯一残された道をはっきりさせる為には恵吾先生しかいない! 恵吾先生に師事するしかない!と決意しました。 平成15年3月にはじめて宇治本山にて一般練成を10日間受け、練成期間中に幽斎殿にて恵吾先生より「葩さんさん」を頂戴し、読んだ感想を言いに来るように言われました。当時の私は「葩さんさん」を読んでも、喜びや感動が生じてくる一方で、どうしても喜びきれず納得しがたい矛盾や疑問が噴出し、そんな自分自身や真理に対する怒りで充満しているような状態でした。その状態のまま、後日、先生にその思いのたけをぶちまけに行きました。私が感じた矛盾・疑問を立て続けに話し、「どうしても喜びきれない!」ことを言い終わった後、先生はスッと立ち上がるや厳しい表情で冒頭の言葉を話され、言い終わるや否やそのまま部屋を出て行かれたのでした。 私は恵吾先生から突然与えられた公案の答えが全くわからず絶望の淵に落とされました。知識としての答えならわかっている。しかし自らの魂の底から湧出する答えを全く見出すことが出来ませんでした。 その答えを見出すため、私は数日後から家を出て宇治周辺の安宿を転々としながら、幽斎殿で神想観実修と生命の實相を読むことだけを行おうと決め、毎日幽斎殿に通いだしました。そんな私を見て、先生は朝10時の神想観終了後に声をかけて下さるようになり、「あなたがここで1分1秒でも神想観してくれてることが、どれだけ神が宇宙が喜んでくれてることか。これから神想観して少しでも気がついたことがあったら遠慮せずに私に言いに来なさい」と優しく温かく話して下さいました。 それから私は10時の神想観終了後にほぼ毎日話しをさせていただくようになり、そこでは度々、私が真理に対する矛盾・疑問を先生に激しくぶつけ、こちらも真剣だったので先生が少しでもごまかすような答えをしたら「いつでも絶縁してやる!」という思いで先生に対していました。 よく先生に怒鳴り上げるようにして質問をしていましたが、そのようにすればするほど先生は満面の笑みで実に嬉しそうな表情で「だから不完全と言える一切のものは無いんです。無いものは無いんです。……あなたのような人がいるとまた研修用の原稿を書かないといけないと思わせてくれて、こちらが元気になってくるよ!」と答えられるのでした。ごまかすどころか、寸分の妥協もない久遠實相一元のいのちを生き貫くことだけに全身全霊をかけてらっしゃる先生の計り知れない底知れなさをまざまざと感じました。 そのように幽斎殿に毎日通う生活を始めて1週間程たった頃から、何か幽斎殿のお役にたちたいと思い、先生が毎日朝8時20分頃からされてる幽斎殿の廊下掃除を半ば強引に手伝わせていただくことになりました。その掃除の手伝いがきっかけで、先生は廊下掃除が終わると職員玄関側の長椅子に座って、職員朝礼の時間までの約20~30分の間、毎日「朝のミーティング」と称して私にミニ講話や討論をして下さるようになりました。さらには10時の神想観終了後の約20~30分の間、昼休みの時間まで私の相手をして下さるようになり、先生とのそのような有難すぎる時間の日々はそれからほぼ毎日約1年間続きました。 先生とのディスカッションでは私がどんな質問をしても、先生の答えは「無い無い無い!」一辺倒でした。ある時は私の質問が言い終わらないうちに、先生は顔を真っ赤にして唾を飛ばしながら「だからその質問自体無い! あなたの言葉も無い! あなたのその口も無い! あなたもわたしも無いっ! とにかく無い無い無いなんだよっ!」とまくしたてるように話されるのでした。 また私が「釈迦自身は山川草木国土悉皆成仏、有道非道同時成道と見えるからいいでしょう。また釈迦に触れられた人は救われるからいいでしょう。でも釈迦に触れられなかったそれ以外の世界中の宇宙中の大多数の人はどうなるんです !? そこはほったからしにしたまま、釈迦一人で勝手に悟りの世界が見えたところで、そんなので何が嬉しいんですかっ !? 」と先生に問いただすように質問すると、先生は静かに「それはね…あなたの…『心が !! 』…そう見えてるんですよ。…實在の世界はそうじゃないからねぇ…そしてあなたのその『心』も無いんですよ」と答えられたのでした。何か論理や矛盾を超えた絶対の喜びに触れられたような気がしました。 約1年間、先生のそばで一緒にいさせて頂き、先生のどこまでも「實相独在」に徹しきった姿、これだけは「光明」とは言い切れないと思える現象的に難題の個人指導であろうと、すべて相手の方の「光明一元」のみを礼拝感謝して説かれる姿に真近で触れさせて頂けたことで、私が勝手に暗く狭く自己限定していた「生長の家なるもの」「實相なるもの」「實相と現象の対立矛盾」に静かに大きく地殻変動が生じ始めました。 どんな不完全な現象であろうと現象は無く、一切現象を超えた「實相独在」「光明一元」のみが本当の本当の真實在なのだという驚天動地の無限奇蹟がまさか無限の当たり前さでもって今、今、實在し続けていてくれるのかもしれないという喜び・感謝の萌芽が芽生え始めていました。 幽斎殿に通い始めて、4ヵ月経った頃の7月のある日のことでした。その頃、私は幽斎殿に歩いて通える範囲にある安いアパートを借りて毎日幽斎殿に通っていました。アパートを借りてるとかその場所について先生に聞かれてもはっきりと伝えていませんでした。「絶対的に正しい道を歩んでいる」と思う一方で、仕事もせず家を出て家族に大変に迷惑をかけてまでしている生活にどこか後ろめたい気持ちもあったからでした。 その日の午後だったと思うのですが、アパートのすぐ近くを歩いていると突然前方の車からクラクションが鳴り、ふと見てみると偶然にも先生の車でした。「で、結局あなたはどこに住んでるんだねぇ?」と先生に言われ、仕方なく場所を指し示すと「なんだっ、妙子の工房の近くじゃないかね。今から一緒に工房に行こう!」と言われました。私が「えっ !? いいですいいです」と拒否しても、かまうことなく先生は「いいからいいから行くんだよ」と話され、結局一緒に工房に行ったのでした。それが恵吾先生の四女である今の私の妻との初めての出会いでした。 たんたんと作陶する彼女と工房全体から醸し出される雰囲気は何か落ち着き、くつろげるものに包まれていると同時に、どこか恵吾先生と同じ、力の抜けた温かくぬくもりのある満足に満ちた創造的なエネルギーが静かに充満していました。それからというもの、昼休みの時間に工房に通われていた先生のお供をほぼ毎日することになりました。 幽斎殿での研修がほぼ1年経とうとしている平成16年の4月のある日のことでした。現象を超えた「實相独在」の喜び・感謝が他人事ではなく自分のこととして徐々に感じられていた一方で、どうしても喜びきれない「何か」が残っていました。その「何か」が日に日に巨大になり、私が立ち上がれないほど押し潰すように重く重くのしかかっていました。 そんなある日の早朝3時頃だったかと思います。早くに目が覚め、重い気持ちで悶々ともがき苦しんでいると、不意に私の心の中に「榎本恵吾先生は無しだぁっ !!!! 」という直観ともコトバともいえないものが私の全身全霊を貫きました。その瞬間に自分の理性や意志では全く制御不能な得体の知れない衝動が強烈に湧き上がり始めました。何の理由もないのにただただ嬉しくて嬉しくて有難くて有難くて飛び上がりたくなりました。 1分でも早く幽斎殿での早朝神想観に行きたいと勝手に体が動いて幽斎殿に向かっていました。神想観をしていても幽斎殿の下方から私の全身の毛穴1つ1つを通って、何とも形容しがたい喜び感謝智慧愛礼拝調和創造すべて渾然一体の無限生命が上方に尽きることなく噴き出すように湧出し続けました。自分の体がどうにかなってしまうんじゃないかと怖くなるほどでした。神想観中に大声で叫びたいほどにどこまでも有難さが突き上げてきました。 早朝行事が終わり、いったんアパートに帰り、再び朝8時前に幽斎殿に徒歩で向かいました。尽きることない喜びと有難さに満ち満ちたまま、歩きながら天空に浮かぶ太陽を見上げると、「あの太陽は寸分の狂いもなく自分そのものだぁっ !! 」「天空はそっくりそのまま(自分なき)自分の生命の歓喜そのものだぁっ !! 」と自分の肉体が破裂して弾け飛びそうなほどに嬉しさと有難さがどこどこまでも湧出しました。 同時にその喜びは太陽や天空、さらには宇宙をも突き破って、「宇宙遍満に永遠に光り輝く宇宙を創造しめた宇宙本源なる久遠實相なるいのちそのものが自分だったっ !! 」「生長の家の前から、雅春先生の前から、そして恵吾先生の前から、あらゆるものの前の前から實在(あり)続ける『實相独在』のいのちそのものが自分であったっ !! ここに久遠の生長の家があり、ここに久遠の雅春先生も久遠の恵吾先生もいらっしゃったのだっ !! 」という絶対歓喜・感謝が尽きることなく湧き上がりました。 周りに見えるすべてのすべてが祝福歓喜の輝きを放ち切っていました。私の両親や妹にもご先祖様にも、これまで関わったすべての人々にも私の過去すべてにも、天地一切すべてにもどこどこまでも感謝の気持ちが湧き上がり続けました。 幽斎殿にて、この喜び・感謝を先生に伝えると、先生は「早朝行事が終わって(7時過ぎに)蓮華(寮)に帰ろうと、車で本山の坂を下って道に出たら、真っ青な青空が空一面に見えてねぇ。そしたら『この底の底の底の底から晴れわたった青空は喜多君だぁっ!』って感じたんだよ。不思議なものだねぇ」と静かに喜びを湧出しながら話して下さいました。そして「これで幽斎殿(での研修)は卒業だね。これからは毎日の自分の生活の中で日々新しい喜びの発見をしていきなさい」と話されたのでした。この日は夜明けから日が暮れるまで一日中、雲ひとつない青空の一日でした。 翌日も幽斎殿にいつものように行くと、先生が嬉しそうに完成したばかりのワープロ打ちされた原稿「『無の門關に座して』~“無”と言えるすべては無く、その無しも無く~」を見せて下さいました。この原稿を読ませて頂いて、よく先生が「神を見出したら、『その神も無し』としてすぐに超えないといけないよ」と話されていた言葉が甦りました。 「神は無し」…神は宇宙も人類もすべてのすべてを完全完成に創造されていながら、「私は一度も何にも為していませんよ」と無限に消えきって死にきって、すべてのすべてをただただ祝福礼拝して下さっている。真實在のいのちとは、その「無神」そのものなるいのちであることの澄み切った感謝・喜び・懐かしさに温かく包まれました。 先生は私が「恵吾先生は無し!」とする前の前から、自分は消えきり死にきって、ただただ「無神」の礼拝感謝でもって、私の内なる「無神」そのものなるいのちを拝んでいて下さったのでした。私だけでなく、すべての人々、天地一切宇宙一切の内なる「無神」なるいのちを先生はいつもいつも祝福礼拝して下さっていたのでした。 翌日の昼休みの時間に、いつものように先生とともに工房に行きました。妙子ちゃんの新作の作品の数々が並べられていました。ふとその中の一枚の小皿が目に止まりました。目に止まったどころではありませんでした。見た瞬間に私の内から尽きることなく光明歓喜なるものが湧き上がり、その小皿から湧出している光明歓喜なるものと全く同じものであると感じました。その小皿は先生の絵や書字は一切描かれていない彼女だけによる作品でしたが、そこに間違いなく「大太陽」「大ニコニコ」が無限に喜んでいました。工房を出てから、そのことを先生に伝えると「そのことを妙子に教えてやったら喜ぶよー」と満面の笑みで話されていました。 その1年後の平成17年4月2日に、恵吾先生、一子先生、3人のお姉さん達とその家族のみんな、そして私の家族の温かい支えにより、恵吾先生の故郷でもある和歌山県・熊野本宮大社で私と妙子ちゃんは結婚しました。 結婚してもうすぐちょうど2年になります。臨床心理士の資格も取得でき、さらには誰にでも満面の笑みを浮かべる元気な長男が昨年12月に誕生し、有難すぎる日々を送らせて頂いております。 先生は私が結婚して4ヵ月後に亡くなられましたが、「無神」そのものなる恵吾先生は、神界で「『無神』そのものも無し、その無しも無し」と無限無神なるいのちの聖なる澄みきった光りを全人類、全宇宙に向かってますます輝かせて、大忙しの日々を送っておられることでしょう。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(69) 2007/3/31 |
|||||||
先生が私に下さったもの。 あたたかい愛情と信頼。 人から信頼されるということが、こんなにも嬉しい、 幸せな気持になれるものなのかと思いました。 誰も何も信じられず、頑なに自分の中に閉じこもって、 家族とも暮らせなくなってしまったような、欠陥人間の私、 宇治へ導かれ研修生に残らせて頂いたものの、 自分で自分を軽蔑して、無気力で投げ遣りな日々を送っていました。 そんな私を先生は、咎めもせず、諭しもせず、軽蔑も排斥もしないで、 悪いところをひとつも認めないで、大きく、あたたかく、包んで下さいました。 どんなにうれしかったかしれません。 生まれてはじめて感じられた温かい愛情と信頼。 その信頼に応えられる人間になりたい、と想いました。 先生のあたたかさに包まれて甘えているだけの私でした。 今、先生のお側にいられなくなって、思い知らされています。 何にもわかっていなかったこと。 今の私をみられたら、先生はどんなに悲しまれるだろうか・・ 先生は私に、それでは駄目だとか、こうしなさい、 などと言われることは一度もありませんでした。 それを少し、淋しく思うこともありましたが、 常に謙虚で、思いやり深く、愛深く、真剣に、誠実に、生きてこられた先生のお姿の中に、 美しく生きることを身をもって教えて頂いた様に思います。 私はいつも先生のお姿を、深い憧れと尊敬の想いで見させて頂いていました。 先生は、私が生まれて初めて本当に信じられた方でした。 繰り返し想い出し、先生のお姿を心の中に呼び起こし、 何とか自分を正して生きて行かなければと思います。 先生、どうぞ正しく導いて下さい、 きちんと、誠実に、まっすぐに、生きられます様に、 先生が私の中に観て下さった、本当の私になれますように。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(68) 2007/3/31 |
|||||||
合掌ありがとうございます。 26年前養心を卒業し、宇治本山に奉職させて頂くことになり、はじめて神舞姫の装束を着させて頂いたときのこと。三方の上に霊牌を乗せて講堂の前にいた時、先生に「素晴らしいねぇ、ちょっとこっちに来て」と声をかけられ、講堂のとなりの部屋に案内されて入りました。マイクや色々な機械が置いてあり、窓からはきらきらと日の光がさしているのをはっきりと感じながら、いすに腰掛けました。そのとき先生は、「この空気が、この座布団が、この椅子が、あなたが来てくれてどれだけ喜んでいるかわかりますか。あの木々が、あの葉っぱの1枚1枚が、“よいかな、よいかな”ってねぇ。空が、雲が、鳥たちが、宝蔵神社の建物が、たたみが、どんなに、あなたのことを喜んでいるか、わかりますかぁ。僕にはわかるんですよねぇ。」と、やさしく、しみじみと、あじわうように、おごそかに、おだやかに……。 私の中で、ジーン……なんとも言えない喜びがあふれ出て、涙がつぎつぎととめどなく流れて……しばらくの間、そんなお言葉を、はなびらがふってくるように、話して下さっていたのです。 ただただうれしくて、うれしくて、喜びがどんどんあふれてきて、満たされてゆくのを感じていました。私は劣等感がいつもあり、人にくらべると、眼が不自由で、暗くて、出来ることより出来ないことが多く、まして喜ばれている自分なんて思ったこともなく、生まれてはじめて最高のほめ言葉をいただき、ほんとうにすくわれました。言葉でいい表すことの出来ないほどの感動――すべてが光輝きました。祝福讃嘆して下さった先生に、心から感謝の気持でいっぱいです。 先生が亡くなられ、岐阜から宇治まで行く電車の中で、その時のことが、あのお言葉が、何度も何度も、くりかえしよみがえってきて、涙がとめどもなく流れ、宇治につくころ、やっと涙がとまり、感謝の思いがあふれました。
最近よくあの時のことを思い出し、喜びがなくなることなく、続いている感じがします。 とくに太陽の光をあびて光り輝く木々の葉っぱ一枚一枚を見ている時、先生を思い出します。 今も、宇治に行けば先生にお会いできる気がしてなりません。 先生、ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(67) 2007/3/31 |
|||||||
榎本先生は、僕にとって、生長の家そのものであり、限りなく優しい父親のようであり、どこまでも不思議な宇宙人のようであり、最初に出会った十七歳のとき(昭和五十七年九月)、「そのまま生きていていいんだ」と思わせてくださった、かけがえのない師である。語弊があるかもしれないし、誤解を招く表現かもしれないが、今改めて先生がどういう存在だったのかを考えてみると、そんな思いが湧いてきた。 少年時代の僕に、先生は、「森末君、夜中でもいつでも、『先生わかりましたーっ!』って言いながら飛んでくるくらいでいいんだよ」とおっしゃったことがあった。それくらい真理の勉強に熱中しなさい、という意味だと僕は受け取った。本当に夜中に突然お邪魔したことはなかったが、頻繁にお宅を訪ねていた頃、折りにふれ、何か気づいたことや得心したことを話させていただくと、穏やかに微笑みながら、時には僕の目をじっと見据えながら「うん、うん」とうなずかれていた様子が思い起こされる。いつもいつも、温かく心地よい空気に包んでいただけることに喜びを感じ、先生とご家族にお会いするのが、本当に楽しみで仕方がなかったものである。 同時に、いつまでも先生に甘えてはいけない、僕自身がしっかりと生長しなくてはいけない、「先生に悟りを分けてもらいたい」というような甘えた意識になってはいけない、と自分を戒める気持ちにもなった。少年から大人に生長していく過程で、先生とふれあえたことは、僕の人生にとって、はかり知れないほど大きな財産になっている。 先生との思い出はいくつもある。一緒にラーメン屋さんに行ったこと。大学の入学式に保護者として出席してくださったこと。東寺の縁日に行き、僕は柱時計、先生はマントを買われたこと。先生やご家族との楽しい団欒。ファミリー合唱隊に参加して一緒に歌ったこと。僕の拙い手紙を真剣に読んでくださったこと。練成でのご講話。大祭や新年祭で先生のもとで奉仕をしたこと。研修生の方々の仲間に入れていただいたこと等々。ここでは一つひとつを詳しく述べるわけにはいかないが、今も僕の記憶の中で、先生のはつらつとした笑顔や、軽やかな身のこなしが鮮明によみがえってくる。 なかでも特に印象深いのは、先生の「声のトーン」である。僕が車を運転して先生のお宅に向かう途中、たまたま一度だけ、僕が日頃通らないルートだったことから、助手席に座られていた先生が、「そこを左に」「これを真っ直ぐ」という感じで方向を指示してくださったことがあった。このときのご指示のタイミングが、これ以上ないほど絶妙で、しかも「声のトーン」がとてもやわらかくて心地よかったため、ものすごく「運転しやすく」感じたものだった。 運転中、同乗者から方向を指示されることは時々あるが、先生以外の人の声が、あえて心地よいとまで感じたことは一度もない。大げさかもしれないが、このときの心地よさは、先生の神想観のご指導に通じるものがあったと思う。神想観をするときは、当然目を閉じているので、何も見えず、ただ先生の声だけが聞こえてくる。先生の声が、頭の上からやわらかく降り注いで、辺り一帯を包み込み、その心地よさを感じながら、どんどん集中の度合いが高まっていったのを覚えている。先生の「声のトーン」の温かい雰囲気、一種独特の空気がピンと張ったような気持ちよさは、おそらく生涯忘れることはないし、これからも僕の心の糧となり続けるだろう。 こうしたことを含めて、先生と奥様、ご家族には、これまで考えられないほどお世話になってきており、どれだけ感謝しても感謝しきれない思いでいっぱいである。まだ何一つ恩返しできていないが、そんな自分を叱咤しつつ、これからの人生において、先生から学んだこと、先生とふれあって感じたことを、何らかの形で僕らしく表現していくことが、生涯のテーマだと考えている。まだまだ勉強も修行も足りていないが、テーマの実現に向けて、一歩一歩努力していきたいと思う。そして、いつか再び先生と出会ったとき、「森末君、よくやったね」とほめていただけるような人生にしたいと思う。 平成十九年三月二十七日 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(66) 2007/3/31 |
|||||||
合掌 有り難うございます。 15年前、青年会で地元の「花の集い」を頑張り始めた頃、真理を深めたく、宇治の一般練成に参加しました。その時初めて榎本先生のご講話を拝聴し、ニコニコの絵で救われた私は、すっかり先生のファンになりました。それからは練成へ行く都度、前の方に席を取り、追っかけのように、友達と身を乗り出して拝聴してきました。 『榎本先生が昇天されたそうです』 平成17年7月、青年会仲間から聞いた突然の訃報。ただ茫然となり、夢か幻か、これが現実というものか――受け入れ難い事実に直面し、言いようのない痛惜の念にかられました。 また、あまりの早いお別れに、ご家族の方々は今どんなに哀しんでおられるだろう、まだお若いのに……。 榎本先生のあのお優しい笑顔はもう拝見できないのか。いつも安心させて頂いている御講話は、もう拝聴できないのか。先生しか描くことの出来ないニコニコのお日さまの絵はもう見ることができないのか――色々な思いが後から後から押し寄せて来て、漠然とした淋しさの渦に引き込まれていくようで、時間ばかりが経っていって、どうしようもない空間にただ身を任せるしかなかった……日々の雑務が幸いしてか、仕事の合間にふっと思い出しては、時が自分なりの答えを運んでくれました。 先生はもう肉体的にはこの世にいらっしゃらない――天空高く駆け昇っていかれた――何の前ぶれもなく、多くを語らず、お別れの言葉を信徒に告げることもなく――ああ、でも先生らしいかもしれない。人一倍この世の使命を早く果たされ、何も言われず、桜の花びらのように。時期がくれば、もうちょっと咲いていたい、こんなに神様のために捧げてきたのに…などと執着されることもなく、理屈をつけられず、もがくこともされず、風にのって自然に神様の御許へ――信仰者であると共に芸術家でもあり、自然に生きてこられた先生のお姿そのもののようにも感じました。 ご生前、歩いておられる時でもいつでも、移り変わる自然の姿――木の葉、水の流れなど――神様の創造された美と生命の喜びを心に刻まれ謳歌されていた――神様の芸術を全身で感じとられていたお姿が、印象的でした。ある時はメモ帳にスケッチされたり、直感的にピアノ曲として表され、神様を表現してこられた――芸術家のお姿でありました。 一度先生のお作りになった曲を拝聴する機会を得られましたが、その時「先生は真に心から喜んでおられる。自性円満(そのままえんまん)を喜ぶとは、表現すればこういった何ともいえない安らかさなんだ! このような例えようのない喜びいっぱいの世界なのだ」と天の音色を聴いているような気持ちにさせていただいたのを覚えています。 “そのままでいいんですよー。今、今、そのまま神様の命なんですよ~” 思えば、生長の家で説かれている雅春先生のおっしゃっていたことを心からわからせて下さったのが榎本先生でありました。 “努力して神様に近づくのではない、初めから神様の命なんですよ~” 若い頃とはいえ、まだ未熟で御教えを机上の空論でしか捉えられず、自分を審き、拘束し、こうせねば自分は偉くなれない―無価値である。またこんなにみにくい心のある自分は生長の家から離れている、なんて罪深いんだろう――と逆の方向で自分をがんじがらめにし、本当の真理を求めていた自分には、先生のお言葉一つ一つが神様の赦しの声そのものでした。喜びいっぱい、光のシャワーで浄められ、自分はこのままでよかったんだ―嬉しい嬉しい、このまま天国に来たみたいだ。宇治の光を浴びている木々を見ながら喜びの涙を流したことが、つい昨日のことのように思い出されます。このように、生長の家の御教えを魂から、体験させてくださいました。 現実界に戻ってはまたもやもやしてしまう。その度に、榎本先生のご講話を求めては解放され、本来の、ただ喜びしかない、神様の世界へと誘導して頂きました。 “『安』という字には、ウ冠(家)に女の人が座っているから安らかなんですよ” “『暗』は、本当は明るい字なんですよ。『明』は、日と月だけど、『暗』は、日が2つもあるんですから。暗い程、神様を見い出しやすいんですよ。” “わがままの反対は『素(そ)のまま』神様のおつくりになった素をそのまま受け取ることなのです。” どのおコトバも、私の中で灯となって残っています。多くの方々に光を点じてこられた榎本先生――先生の存在は自分の中で光となって輝いています。生きておられます。 ご冥福を心からお祈り申し上げます。 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(65) 2007/3/31 |
|||||||
私は平成14年9月より半年間研修生をさせて頂いた折、幽斎殿が好きで、時間があればよく幽斎殿で神想観をしたり、写経をしたりして過ごしておりました。そんな私に興味を持って下さったのか、榎本恵吾先生からお声を掛けて頂き、お話し頂いたり、御著書を戴いたりしました。そこには私が憧れ求め続けてきた「久遠の今」のことが書かれていて吃驚、大変嬉しく思いました。 食堂では遠慮深い私をわざわざ見つけて呼んで下さり、先生の前に座ってお話しすることができました。ありがたいことでした。先生を前にして座ると、胸の中を爽やかな何かが通り抜けた様な、何と表現していいのでしょう、高く温かい、何か不思議な聖なるものに触れ得た魂の喜びを感じることが出来、この御方は一体どういう御方なのだろうかと、尊敬の念が益々大きくなっていったのでした。榎本先生の前にただただ座るだけで魂の悦びがある、幸福なのだと感じられました。 幽斎殿では先生のお描きになった、幽斎殿に菩薩雲集したかのように多勢の方々が神想観されている絵がありました。その絵のことを嬉しそうにお話しなさる先生が、懐かしく想い出されます。 オリジナルなるものを尊重される先生でした。手紙を出すとお返事に、「あなた様らしい、その人らしいのが一番尊いこととあらためて想うのであります」とお手紙頂いたこともあり、今読み返しても涙が出る程ありがたいことでした。 榎本恵吾先生先生は「私は皆さんの座布団になりたい」と仰ったこともありました。自分を踏んで飛躍して欲しいとの、本当に勿体無いお言葉でした。もっともっとお話ししたかった、先生の前に座りたかった。それなのに先生は御身を隠し給われました。よく先生は仰っていました。「榎本も無いんですよ」 榎本恵吾先生との出合い。私にとって、それは恩寵。神様の祝福の微笑でした。 「久遠の今」の光のお言葉を、榎本恵吾先生の御著書を拝読しながら味わっております。神想観も、光明化運動も、久遠の今に立とうと。 ありがとうございます。 合掌 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(64) 2007/3/31 |
|||||||
「あなたが神なんですよ!」 平成三年八月の深夜、榎本先生の鋭い声が「祈りの間」の空気を揺らした。 それが先生と私の強烈な“出逢い”だった。 何度か問答した後、五度目に「“ハイ”と受け止めなさい!」と言われ、私は戸惑いながらも気迫に負け、しかし直感的に「ハイ」と素直に答えた。 途端、先生の顔が柔らかくなり「そう、それでいいのです」と。 あの瞬間、私は榎本先生によって啓かれた。 先生からいただいたものはあまりに多いのだが、先生は「もともとあなたにあったものを祝福しているだけ」といつも微笑まれた。 生命がけで求め、苦しみ、もがき、乞うたあの頃、先生の「そのままでいいんですよ。喜べばいいんですよ。」という言葉にどれだけ励まされたことだろう。 「とってもとっても取り去ることが出来ないもの、それが“ほんもの”です」 「實相は誰が観てくれなくても自分から出てこようとするんですよ。嬉しいですね。」 講話の一言一言が光りの珠となって私の中に飛び込み、私の光りを引き出してくれた。 先生にご恩をお返ししなくてはいけないのに、私は“師”の影を踏んでしまった。 そのことを謝る前に先生は天界へと旅立たれてしまった。 「榎本先生に贈る文集」という存在に私ははじめ、“書く資格がないから”と、泣く泣く背中を向けていた。 結婚し、子育て真っ最中の私は、宇治別格本山で過ごした10年間が嘘のように、「信じる」ということを忘れたかのように、ただただ、幸せで、ぼけぼけ生活を送っている。 今おもえば滑稽だが、数日前まで、そのことが申し訳なくて、パソコンに向かえなかった。 先日、結婚記念日の折、披露宴のビデオを見て、先生の祝辞にはっとした。 「安らかという字は、家の中に女がいます。そんな安らかでいて下さい。」 そして先生からいただいた『弟子像』を再びひもといた。 “神とは佛とは求める必要のないものであり、信ずる必要のないものである。 求める必要なくして、信ずる必要なくして今、ここ、この身、このままですべてを満たし、生かして下さっているのがまことの神、佛である。” 「今の感じが安らかということなんですよ。」 夜空に浮かぶまるい月を眺めていると、まろやかな声が聴こえてくる。 ああ、先生はどこどこまでも赦して下さっているのですね。 私をがんじがらめにしていた“縛り”さえも、解かれてしまった。 拝んでくださっている優しさに包まれて…… 先生の気配はあらゆる自然が観じさせてくれます。 夕焼け空に美しい雲がたなびくとき、山に登ったときに見つけた一本の杖、 桜並木を歩くうち、ふと、振り向きたくなった時…… いつもよろこびという発見とともに、先生のお導きに心が躍ります。 同時に、私も「消え切りの澄み切りの聖なるもの」でありたいと願います。 「あなたが神なんですよ!」といつ尋ねられても「はい!」と胸を張ってこたえられるように、ここに先生への誓いを記しました。 奇しくも今日は3月31日。 私の生まれた日です。 こうして先生の“弟子”と自称させていただくことが最大の贈り物です。 ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(63) 2007/3/30 |
|||||||
もう二十五年くらい前になるだろうか。榎本先生の研修生になってから、全ての現象的なことを否定していた時、というより現象的なことを受け入れられなかった時、何処かの教区が「優生保護法改正」の祈願祭を宝蔵神社で執り行ないたいとの申し込みがあった。その時僕は宇治別格本山の祭司部で神官をしていた。 「現象無し、実相独在」だけを榎本先生から受け、生きようとしていた自分にとって、先祖の供養とか流産時の供養などは現象中の現象ではないか。実相独在で神のみ完全のみしかない世界なのに、何を今さら供養とか、署名をしての改正運動だとか、現象的なものに必死になるのだろう? と思っていた。でも、宝蔵神社にお仕えする神官の身として、祈願祭をしなければならないし、現象的なことを認めたくないしで、そこのところが腑に落ちず、自分の中で整理もつかず、悶々としていた。 そして、榎本先生ならどう答えて下さるだろう――と、思い切って訊いてみた。「今回の署名運動の祈願祭って、単なる現象処理に過ぎないんじゃないんですか? 僕はあまりする気になれないんですけど。」すると先生の答えはこうだった。「咲本君、そんなことを言い出すのは君らしいね。」と。肯定も否定もされない答えで、僕は不安定な精神状態になった。先生のそばに長い間ずっと一緒にいて、そして何年も経ってから解ったことだが、質問してもそれについて答えてくださらなかったり、別の話に変えたりされる時は、どうでもいい、大したことの無い、重要でもなんでもない質問だということだった。しかし当時はそんなことを知る由もなかった。 そして祈願祭の当日を迎えた。本山内に朝早くから、優生保護法改正の署名された紙が詰められたダンボール箱が、トラックいっぱいに運ばれて来た。本山職員も運ぶのを手伝うようにと放送で連絡が入り、僕はあまり乗り気でなくいやいや運びに行った。その時、物凄い光景が目の中に入って来たのであった。 それは、榎本先生が先頭切ってその山のように積まれてあるダンボールの箱を大きな声で「ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。」と叫びながら、髪の毛を振り乱して、全身汗だくで運んでおられたのである。 僕はその先生の姿を見たとき、全身に雷が落ちたような衝撃が走った。これが現象処理であるとか、実相独在を生き切れているとかいないとか、そんなところで信仰していた自分が何処かに吹っ飛んでしまった。 「咲本君、現象無しを生きるとは、こう生きるんだよ!」と全身でもって答えて下さったような気がした。吉田國太郎先生の『常楽への道』の中での「右へ行く時は電光石火右へ行き、左へ行く時は電光石火左へ行く。」という一節が思い出された。まさに「ダンボールを運ぶ時は電光石火これを運び、祈願祭に仕えるときは電光石火祈願祭に仕える。」である。「今を生きる」とは、「今」自分に与えられていることを本当に満足して感謝して「生きる」ということ。いちいちこれが現象であるか? 実相であるか? と問うことは意味がない。否どちらでもない。「今」あるべき姿が、あるべきものがあるだけであった。 そのことがあって、優生保護法改正の祈願祭が、宝蔵神社神前で、うやうやしくそして厳かに執り行われる運びとなった。僕は何の不安もなく迷いもなく、感謝と調和に満たされて仕えることが出来た。御祭では修祓(御祭が始まって最初に神官が、関係するもの全てにお祓いをすること)をさせてもらった。お祓いをする側もなく、される側もなく、壇上の神官もなく、大拝殿の参拝者もなく、全てが神の一つの「いのち」の営みがそこに営まれているだけであった。 榎本先生は人を喜ばす名人でした。というより「喜び」そのものが先生でした。 人の光明面を観ることにかけては宇宙一の人でした。 どんな些細なことでも満面の笑顔で喜んでくれる人でした。 自分が悩んで苦しんで暗黒面を話しに行っているのに、すべてそのまま光明に変えて下さる人でした。否、「はじめからあなたは一度も曇ったことのない光そのものですよ。」と本当の自分を発見させて下さる天才でありました。 合掌 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(62) 2007/3/29 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 25年ほど前、昭和57年11月26日、榎本先生が、斑鳩(いかるが)の地、静寂のうちに凛とした法隆寺に、研修生の方々とご一緒にお見えになりました。 回廊から金堂、五重の塔、大講堂と拝観しまして、大宝蔵殿にまいりました。 長身の観音様……百済観音様がいらっしゃいました。 先生は観音様の御前で合掌され、しばし観音様とお話しをされている様に感じました。 観音様の慈愛にみち、微笑を湛えられたお顔は、榎本先生そのままに感じられました。その光景が、今でもはっきり思い出されます。 先生にお会いしたくなったら、法隆寺に参ります。 お帰りには、わが家にお立ち寄りいただき、誌友の皆さまとご懇談いただきました。 この思い出はわが家の、そして私の宝でございます。 本当にありがとうございます。 いつも、何か問題をかかえて宇治に行くのですが、榎本先生にお目にかかると、すーっと無くなって、言葉にならないのです。それでも、榎本先生はお解りなのでしょう。 「神様は、あなたがそこに居るというだけで、よろこんでいらっしゃるんですよ」とおっしゃって、「よろこびましょうね」と言ってくださいました。 これからは、主人共々に、よろこんで、よろこんで精進して行きます。 榎本先生 ありがとうございます。 福山克己・美津子 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(61) 2007/3/29 |
|||||||
(1) 實相なるもの <2005.7.29> 榎本恵吾先生の「實相なるもの」という演題の講話のビデオがある。 榎本先生の告別式の後、『谷口雅春先生18年祭』当日の、その講話のビデオが出てきた。いきなり先生の講話は「お葬式の話」から切り出される。山口悌治先生の本部葬で谷口雅春先生が『本日は、おめでとうございます。今日は、山口悌治さんの霊界への入学です!』と言われたという話であった。その時、まるで霧が晴れたような思いであったという。この御教えでよかったと心から思ったという。その感動が朗らかな明るい声で語られていた。 思えば平成14年9月。初めての10日間の練成を受けさせて頂いた時、早朝行事にて「神は渾ての渾てだった」と忽然、涙がポロポロと流れ出で世界が変わった思いを得た。今迄の二元論でとらえていた自分の世界が全て虚構であったのだ、と知った。その日の早朝行事は、他ならぬ榎本恵吾先生の先導であった。 また、特に感慨深い思い出がある。入山して26日目。入龍宮幽斎殿にて榎本先生から大切な御著書を頂いた。本を開くと「謹呈 大熊様」と揮毫されてあった。驚いたのはその経緯である。実は私を知る以前から揮毫してあったというのだ。揮毫された日をお聞きすると、「平成14年8月18日だった」と答えられた。なんと、3カ月以上も前の事だ。その日、飛田給の大隈講師への記念品としてお渡しするつもりが、なぜか「大熊様」と書いてしまった。先生は、「不思議だねぇ。だから、あなたにしかあげられないんだよ。ずっと私の部屋に置いてあったんだよ」と嬉しそうに笑われた。その笑顔が今も忘れられない。 榎本先生の講話のビデオは、不思議な事に「宗教家の死」というテーマで締め括られている。 『谷口雅春先生は、病なし! 迷いなし! 罪なし! ありがとうございます! と云われて亡くなったんですね』 『宗教家の死に出会えるという事は、本当にスバラシイ事ですよ!』 その響きの中には、久遠の「今」を生き抜かれる「証」としての遺言(コトバ)を託された人々への、更に明るい祝福を感じずにはいられない。永遠不滅の生命を「今」生きる輝きを感じずにはいられない。常に純粋な求道者であり、多くの人々に敬愛された榎本恵吾先生。本当にありがとうございました。これからも私たちを、天翔り国翔り、太陽のような笑顔でお導き下さい。合掌。 <宇治別格本山ホームページ E-VOICE 投稿原稿。以下、同じ> (2) 魂を込める生き方 <2005.8.5> ▽榎本先生について、忘れられない思い出がある。私が宇治別格本山に入山した翌年の事。本山職員の親睦会である神睦会の旅行先で、先生が大切にされているお酒を一杯下さって「これは私の血(霊)だからね !!」といわれた。楽しい席でもあり冗句かと思っていた。本山に帰って再び参道にてお会いした時、「大熊君、あのお酒はボクの血(霊)だからね !!」と本当に真面目な顔で繰り返し言われた。 ○ ▽その日は珍しく外食であった。家族(妻と5人の子供たち)と共に近所の回転寿司・カッパ寿司に行った。「これは私の血(霊)だからね !!」と言う榎本恵吾先生の言葉はどういう意味なんだろうね?ーと妻に問いかけ、はしゃいでいた。実は尊敬する榎本先生からの言葉に嬉しかったのだ。しかもその後、榎本先生にまつわる愉快なエピソードを2つ3つ、興に乗り話していた。 ○ ▽すると翌日、榎本先生がそばに来られて、「大熊君、昨日はカッパで楽しそうだったねー。実はね、ボクは大熊君の横(レーンの向かい)に居たんだよ。」(笑い)先生は嬉しそうに「あんまり楽しそうなんで、声をかけれなかったんだけどね」と付け足された。 ○ ▽榎本先生は本当に、いつも愉快で不思議な先生だった。あのお酒の一件にしたって、今思えば、ただただ、お酒一杯にしても、心から祝福したかったのだ。私のみならず、私達は皆、常に全身全霊で歩まれる榎本先生に常なる「喜びの祝福」を受け続けて居たように思う。常にすべての人に、ものに、事に、魂を込める生き方。自分を尽くす生き方、そのもの。榎本恵吾先生とは、まさにそういう先生であった。そして、研修生も奉仕員もパートさんも、職員もみんなみんなそんな先生が大好きだった。 ○ ▽今、私たちの心の中には魂を込めた生き方の持つその迫力や、魅力や、その感化力も含めて、こんなにも 榎本恵吾先生が私たちの中で大きな存在だったのだーと痛感している。 全てのものに事に魂を込める生き方、これを『久遠の今を生きる』といい、『神の子を生きる』というのかも知れない。榎本恵吾先生の後ろ姿で、じかに教えて頂いたありがたい教えの一つである。 (3) 神はすべてのすべて <2005.8.6> ▽榎本恵吾先生の告別式の折、楠本総務より「榎本恵吾さんは徳久先生を大変尊敬しておりました。」「その徳久先生は、現場を離れて1時間後になくなりました。」「そして榎本さんは仕事を果たされて5時間後なくなりました」との言葉があった。 ▽その後、当日の5時間がどのような様子であったかを知った多くの人々は、なんと榎本先生らしい、素晴らしい有様だったのだろうと涙した。 ○ ▽7月12日。3時までに神想観先導、部長会議とその日の仕事を終えられた榎本先生は、帰宅。不調を訴えられて市内にお住まいの三女・四女 を呼び寄せられた。すぐに奥様も帰宅。ご家族と居合わせた藤原職員とで、聖経を読まれたそうだ。 ○ ▽その後、駆けつけた祈願部の畑本職員に翌日の神想観先導に関する指示をし、「聖経を読んでくれるかね」と自宅に招き入れた。そこに、なんと服部仁郎先生自筆の人型が届いたというのである。実は榎本先生はお若い時に服部先生に学ばれ、先日の教修会で服部仁郎先生自筆の人型を持っているという古くからの信徒さんに、コピーさせてもらう為に送ってもらう事をお願いしたのだそうだ。しかし送られてきた日、時間はまさに偶然である。榎本先生は、「祈願に携わる者にとってこんなに喜ばしいことはないねー」と心から喜ばれていたそうである。 ○ ▽そして引き続き聖経「甘露の法雨 」を家族とともに読誦。最後に「實相を観ずる歌」を皆で音読。その直後、姿勢を正されたまま坐亡されたという。 ○ ▽昨年の末。本山にて、職員の結婚披露宴が行われた。その時に榎本先生が贈る言葉として「私は生長の家とは、家庭信仰であると思います。」といわれたことがある。まさにその言葉通りに、 家族に囲まれ、共に真理の言葉を響かせながら坐亡された先生であった。 ○ ▽思えば、最後に音読された「實相を観ずる歌」の歌詞は、『神はすべてのすべて 』で始まる。まさに「實相独在」を語り、「實相なるもの」という演題で語り続けられた先生そのものを現すような聖歌である。私もまた、かつて先生の先導する早朝行事の中で、聖経の『神はすべてのすべて 』の文言に涙した一人でもある。 ○ ▽告別式の日、多くの人々が涙した。だが、別れが悲しいのではない。生長の家の御教えは「人間神の子」永遠不滅である。榎本恵吾先生の限りない愛に、ありがたくてありがたくて、言葉なく泣くしか出来ないのである。感謝あふれて涙あふれるのである。先生、教えて頂いた家庭信仰。實相独在の信仰 を本物にする事が出来るよう精進致します。先生の太陽のような笑顔を常に胸に行じて参ります。先生のように、本物の生長の家人となれるよう。 (4) 榎本先生と宇治クリーン運動 <2005.9.7> 9月の宇治市内におけるクリーン運動の通知が商工会議所から届いた。地域のクリーン運動であるが、本山では欠かさず20~30名が参加している。前回は7月10日に実施された。早いもので、あれから約2が月がたとうとしている。 前回は曇天で、きわめて涼しくさわやかなゴミ拾いであった。30数名の本山員参加者の中でも、部長自ら参加して下さったのは、榎本恵吾祈願部長と小林健二経理部長、長田忍練成部長の三人だった。とりわけ榎本先生は上機嫌で、行事の後「イヤー今日は本当に素晴らしい宇治クリーンだったよ 」と述べて下さった。皆嬉しそうだった。榎本先生の上機嫌な姿や発言は、常に周りの人々を幸せな気分にしてくれる。榎本先生が終わりのお祈りを11時55分頃に大拝殿前で行うと、待ってくれていたかのように雨が降り出した。 ○ その翌日だったろうか、県神社の前で、散髪屋さんからにこやかに出て来られる榎本先生をお見かけした。きっと散髪屋さんともなかよしで、楽しい会話が弾んだのだろう。 ○ あれから2ヶ月がたつ。ご一緒に宇治クリーンをさせて頂き、県神社前でお見かけした翌日、先生は霊界に旅立たれた。誰だったろうか、近い方が、「こうなる前にちゃんと散髪までしてー」といわれたが、私も言いたい。 ○ 榎本先生は、旅たたれる2日まえ。散髪だけでなくて、お世話になった宇治市内を、ありがとう ありがとう と言いながら、捨てられた空き缶空き瓶を拾い掃除をして、「イヤー今日は本当に素晴らしかった 」と言って旅たたれました。 聞くところによると、先生は天ヶ瀬橋周辺がお好きで、時折早朝のドライブコースに選ばれていたーということであった。 今回9月5日の宇治クリーンは、台風14号の為雨天中止となった。延期の日程調整を私が担当しているのだが、なぜか浮かない。しかし先々月からの経緯と自分の心を見据えた時、そこに何があったのか理解出来た。 ○ そうだ。榎本先生が限りなく愛した宇治川沿いをみんなで掃除させて頂こう。先生の分まで大きな声でありがとうございますと唱えてゆこう。あの日のように「明るく朗らかに、上機嫌で!」 …… 今もあの日の上機嫌な先生の笑顔とお声が蘇る。 …… |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(60) 2007/3/29 |
|||||||
私は平成10年1月の初詣練成会で榎本恵吾先生にはじめてお会いしました。晩年の一年間は月に2回ほど、宇治に2,3泊しては先生にご指導いただけるという幸運にめぐまれました。今もなお変らず導いて下さる先生に、感謝の想いでいっぱいです。先生、ありがとうございます。 まだ寒さの残る3月のはじめごろだったと思います。宇治で定宿にしている本山に程近い民宿「ふくや」が満室で、やむを得ず宇治第一ホテルに泊ったことがありました。会話の途中で先生に、「今回はふくやが満室で、第一ホテルにとまっています」と申し上げると、「へえー、満室なんて、そんなこともあるの。珍しいね」と仰ったあと、顔を曇らせて、「第一アサヒからここまで何分くらいかかるんだ。」と尋ねられました。「25分くらいです」とお答えすると、「そんなにかかるのか……そんなにかかるのに今日まで気付かないで、すまなかった。」――明日からは自分が迎えに行く、と仰るのです。ぼくはびっくりしました。先生はただでさえぼくがいるときは気を遣われて、ご自宅での朝の貴重な時間を削って、いつもよりも15分早く3時15分ごろに来てくださっているのです。本来なら遠慮すべきだと分かっていても、嬉しくて言い出せませんでした。 翌朝、ぼくは2時50分からロビーで先生をお待ちしました。第一ホテルのロビーは階段をあがって2階にあるので、外で待っていたほうがよいのはわかる。でも寒い。ぼくはロビーでボーっと『甘露の法雨』を広げて誦んでいました。待ち合わせにはまだ間があると思っていた3時5分ころ、はあ、はあ、いいながら階段を駆け上がってくる音がすると思うと、「待った?」と先生が入り口から駆け込んでこられました。ちょっと階段を上るのでも息が切れる超高血圧の先生が、午前3時に全力疾走で階段を駆け上がって迎えに来られたのです。車に乗ってから、ぼくは恐縮して申しました。 「先生、お迎えにきていただいて……とても嬉しいんです。本当に嬉しい……でも、ちょっとやりすぎだと思うんです……普段と同じ生活をしていただきたいんです。だから、明日からはお迎えは結構ですから。」と、やっとのことで申し上げると 「そんな……ぼくだって幽斎殿に行くのに迎えにくることくらい、たいしたことはないよ。これからも第一アサヒ(ラーメンチェーン店の名前だそうだが、先生は第一ホテルをこう呼ばれる)のときは、迎えにくることにするから。」ぼくはやっぱり断らなければと思い、「でも、やっぱりまずいです。」と申しました。すると先生は、自分が服部先生の誌友会に間違えて一時間早く行ってしまったときの話をされるのです。 「襖があってね、その奥がふだん誌友会に使われる部屋で、どうも先生はそこで寝ておられたらしいんだよ。奥様が『あなた、榎本さんが来ましたよ』といわれると、ばたばたっと音がして、先生は和服に着替えられてね、いつもどおり机を出して、ぼくと向き合って、合掌されて、『お待たせいたしましたーッ』って頭を下げて礼拝されるんだ。それでね、『この間、帰るとき、玄関の電気がついていなくて暗かったでしょう。』ぼくが「はあ」っていうと『失礼いたしましたーッ』って、また……。ぼくはね、この弟子は谷口先生に同じように扱われていたんだなーって思ったよ。」勿体無くて、涙が出ました。こんなにみすぼらしい自分に、宇宙の真理を悟っておられる先生が……。先生はどんな人に対しても、こうして接せられるのだ。皆が本当に神に見えて、貴い渾べての渾べてに見えて、拝まずにはいられない、それを実感で生きていらっしゃるのだと思いました。 先生はよく私に「現象は無いとは、言葉でない!と言えるすべてのことだよ」と仰いました。先生からお教えいただいたことを約言すれば、本当に存在するものは何かということと、これを如何に実践するかということだと思います。一切の執着の根元である「自分」、「我」は不完全なるが故に実在にあらずということが、全ての出発点になるのでした。 ある日、神想観をしているとき、ふと先生のお言葉が思い出されました。 「無っていうのは、限りなく自分は無いということで、生かされているというか、自分じゃ無いということで――だけど、絶対と云うほうは、絶対に誰からも生まれる、生んでもらったものじゃないということで――その両方が味わえてくるというのが、無の門関で、無、無、無といったときに内に甦ってくるというかね。」 私は、ここがポイントだと思いました。一切のものは無い。時間空間の世界も無い。言葉で「無い」といえるものは全て無い。もちろん自分もない。外界は無い。自分は無いとき、自分の中心、内側に、ぽっかりと、澄み切りの「ありがたい」という思いが広がってきます。この思いは、空で、ないとしか言いようがないのですが、澄んだ、でも今まで感じたことがない、ありがたいような気持ちでした。このぽっかり開いた空隙のまわりを、もやもやしたものが包んでいます。 そのとき眼を上方に転じて、はるか無限遠方を思いました。絶対で、渾べての渾べてである、宇宙を包むように存在するものがあります。もやもやを越えた最遠方、最も遠い遠心、無限に大きいはずの絶対さえもまあるく包む、さらに大きい存在。それは無であるが、そこにも自分?がいるような気がします。自分とは云えないような自分です。 中心にあるからっぽの空隙のような澄んだ「ありがたさ」である自分と、無限遠方の遠心にいる自分。遠心から出発して、中心に向って、無い無い、と現象宇宙を否定し、一つ一つの物象、もやもやした想念のかたまりを否定していくと、突然それら全てが、中心にある澄んだ「ありがたさ」の空隙に向って、自分からぺシャンとつぶれてしまい、遠心の円と中心の円がひとつになったような気がしました。遠心から中心に向う「無い」という思念と、中心から遠心に向うそれ自身で萌え上るような「ありがたい」という思いが交流して一致し、澄んだ気持ちがいっぱいに広がったのです。眼のうちが明るくなって、眼から光が出るようです。以上の私の表現が正しいのか、どこまで捉えられているか、はなはだ心もとないのですが、一切のものを無いとしたとき広がってくるありがたい思いのことを生命といい、これのみが唯一の実在であるということ、このことを先生は私に伝えたかったのではないかと思います。 自分が消えるということは、神によって生かされている、一切のものが神であって、神から礼拝されている神の一人子の喜びが味わえてきて、ありがたくなって参ります。と同時に、一切のものを生み出す存在が自分であり、神さえも生んだ自分であるという視点もあるわけです。この両者、中心にあるありがたさの“自分”と、遠心にある絶対の向うにある無(自分)がぴたりと一致するのが、生長の家の久遠の今の哲学だと思います。 先生は常に、実感として久遠の今だけを見ておられたのだと思います。いつも、あらゆるものから、生かされている感謝を味わっておられました。 「物質は無いとは、これを光として生んでいる、神と言えるということなんだねえ。光として、神として生み出した側に立っているんだねえ。」――人と応対するとき、視点を転換して、この久遠の今を相手に見ておられたのだと思います。主客を転換して、自分は消えて、相手が神であって自分はあなたによって生かされているのですよ、という礼拝のお姿になられるのだと思います。いつもこの、久遠の今の主客の入れ替えを自由に行って今を味わっておられたのだと思います。出会った人をみるとき、そこに今を見て、自分は消えて礼拝しておられますが、どうも、突然感覚が変わって、通常われわれが見ている景色が消えて、礼拝される側にまわってしまわれるようなのです。先生がたくさん描かれた観音様の絵は、先生を拝みに先生のまわりに日常的に現れていたようです。いずれにせよ、生きもののように動く久遠の今の運動とともに、自由に主客に剖判し、それを逆転、展開して自在に拝み合う生活を楽しんでおられたのではないでしょうか。自由に自分と相手の 久遠の今を一体化させ、礼拝と感謝を味わっておられたのだと思います。 ぼくの久遠の今は、先生と全く関係なしに存在しているものでした。先生の説法を浴びるように聞き、求め、求めしてきましたが、いままでぼくがやってきたことは殆ど見当違いであったと思いました。先生が常々仰っていたように、ただただ、自分は無い、ということを追求することだけが、正しい方向だと思います。先生は晩年、マクドナルド・ベインという人の、キリストの霊示集についての解説を毎日記しておられましたが、「これにはキリストは『私の説法はあなたを悟らせることはないのだ』って言っていてね。ぼくはいっぺんでこの本を信用したね。」と仰っていました。指揮者のチェリビダッケの演奏に感動した人が、「あなたの指揮がすばらしかったからです」と賛辞をのべると、チェリビダッケは不愉快そうに「あなたが感動したのは、あなたが感動したのであって、私の演奏は関係がありません。」と云ったという話を聞かれて、チェリビダッケ指揮の音楽を愛聴していらっしゃいました。先生はいかに自分が消えて、その人を自分の内側のすばらしさに目覚めさせることができるかという実験をされていたのではないでしょうか? 時間空間がない、久遠の今の一点を正確に貫いたような先生は、必然強烈な霊的エネルギーを放射されていましたが、ご自分はそれを可能な限り抑圧し、おもてに出ないようにされていました。自分ひとりが神としてあがめられないこと、私たちひとりひとりが自分のうち側だけをみて、神の一人子の喜びを味わってもらいたい、それだけが先生の念願であったように思います。ぼくのこの力は「ぼくの趣味です!」とはっきり明言され、喜びはみんな平等だよと、ぼくだって、吉田先生だって、道元も釈迦も、谷口先生もみんな平等だよ、それ以上かもしれないんだよ、と仰っておられました。 ご著書『無神』は、先生のお姿そのもののように感じます。最後にそのご文章を写させていただきたいと思います。 |
|||||||
| もしも、神というものがあって、その神に向かって誰かが「神は無い」と言ったとすれば、神は、「その通りである。私は無いのである。」と言われるであろう。 そして逆に、その人に対して、「あなたによって私は生かされているのであります」といって礼拝されるのではなかろうか。 神ご自身が『私が全宇宙の生みの親である。○年○月○日。』などというものを、どこかに建てておられるとは、どうしても思えない。もしも、そういうものがあれば、そんなものを、自ら建てられるようなものを神と呼ぶ訳には行かない。 神は全宇宙を創造し給うていながら その姿を消しておられるのであります。 神は、人間を礼拝し給うているのであります。 春には花を咲かせ、野山を緑でかざり 雨を降らせ、陽を明るく 風を渡らせて、何とかして人間を喜ばせて やろうとしておられるのである。 生きた花々草々をもって、神は我らを供養し給うているのであります。 しかし、依然として神はご自分を消しておられるのであります。 どこまで消しておられるか。 それは、神がお生みになった人間に「神はない」といえるようにしておられるまでにであります。 「神はない」という声も、神のいのちによって人間はそう言っているのであります。 そこまで神ご自身で、無神になっておられるのであります。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(59) 2007/3/29 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 榎本恵吾先生が天国に旅立たれて、はや二年目近くとなりました。 先生とはじめてお会いした時の事が、まるで昨日の様に想い出されます。すでに二十年以上も前の事ですが、正に「光陰矢の如し」です。 先生との想い出は余りにも多すぎて深く、筆を取ってもまとまりません。ただただ感謝・感謝、「ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。」この言葉のみです。 先生が何時もおっしゃって下さった、「暗は無い、只々光」だったのですね。はじめから光だったんですね……この言葉を噛み締めながら、先生がいらっしゃらないのは淋しいけれど、既に天国でご活躍なさっていらっしゃるのですから、私も元気を出してこれからの日々を、有意義に過して行きたいと希って居ります。 私の心の中では、何時でも、先生がニコニコされながら見守って下さっています。 又、一子先生がお元気でご活躍なさっていらっしゃる事も、大変嬉しい事です。 榎本恵吾先生、本当に、本当に何もかもありがとうございました。 合掌再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(58) 2007/3/29 |
|||||||
先生とお別れしてから、一年半が過ぎようとしています。霊界に旅立たれたことが、今だに信じることが出来ません。 目を閉じると、先生の笑顔がよみがえります。 多くの愛を頂きました。多くの生きる喜びを与えて下さいました。 初めてお会いしてから、早いもので 二十五年が過ぎました。初めての練成会の参加…… “ありがとうございます”と合掌に慣れず、違和感を感じておりました。先生から、研修生のお話を頂きましたが、素直に受けることが出来ず、心が頑(かたく)なに閉ざされていた私でした。しかし、いつもニコニコと合掌されるお姿に、心がいつの間にか柔らかくほぐれてゆきました。 自分を責めつづけてきた私に、「そのままですばらしい神の子」の教えを云い続けて下さいました。いつも変らず、やさしさを下さいました。どんなにうれしく、ありがたかったことでしょう。又、御家族の皆様とも親しくさせて頂き、あったかい、すばらしい家庭に触れさせて頂きました。 先生御夫妻・御家族の皆様に会ってなければ、私は、結婚してなかったと思います。 「結婚って、素晴らしい」と思えたのは、先生御夫妻に出会えたからなのです。 素晴らしい神縁を頂き、いつもいつも暖かく見守って下さった先生、一子奥様、実代ちゃん、久実ちゃん、信ちゃん、妙子ちゃん、ありがとうございます。只、只、感謝の気持ちで一杯です。 又、不思議な神縁で、先生のまわりに集まってきた研修生の皆様と、今でも交流があること、ありがたく思います。 先生、今 霊界で、どのようにすごされてますか? 懐しい方々と、お会いになりましたか? どうぞ、安らかに、おすごし下さい。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(57) 2007/3/29 |
|||||||
「それぞれの指も一からだね」と ご自分の手首をおさえておられた。 「どうだい」とか「やってるかね」といって いつも声をかけてくださった。 「はじめのはじめ、もとのもとからだよ」とかいって、 「ぼくは、伝え方の研究をしているんだよ。」とおっしゃっていた。 「兄さんのように思っていてくれたらいいよ」とも。 「君も飲みなさい」となみなみついで くださった。 「光、光、光のみ」と歌っておられた。 かんぱつ入れず「ダメダ!」をいただいた。 「子供の名をつけようか」とも。 「祈っていたよ」と声をかけてくださった。 「祈っているよ」と見送ってくださった。 「味わうんだよ」とも教えて下さった。 今、私の中で 先生が光ハジケルように 復活する。 私以上に私をご存知だった。 大愛そのものだった。 先生、 天かけり、国かけり、 我れらをおおいたまえ。 合掌 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(56) 2007/3/29 |
|||||||
榎本先生の告別式。祭壇の前に立たれた楠本先生は、切にお言葉を述べられました。 楠本先生は榎本先生の遺影にさも語りかけられるように 「私の家内の告別式には榎本さんが弔辞を述べてくれました。私が死んだ時には榎本さんに弔辞を述べてもらおうと思っていたのに、私が榎本さんの弔辞を述べることになろうとは思ってもいませんでした」 と述べられたあと、榎本先生を「祈願部長として最もふさわしい人だった」と最大限のお言葉で讃嘆して下さったのでした。そのお言葉を聴いた時 「先生、良かったですネ、先生、聞こえましたか・・・? 今、楠本先生がおっしゃったでしょ……? 何も心配しなくていいんですよ。先生は永遠に幽斎殿に残れるのですよ、良かったですね」 と、先生に呼び掛けました。なみだだけが込み上げました。 先生が亡くなられる二ヵ月前、宇治橋交差点近くのファミリーレストラン・サイゼリヤで食事をしながら先生が言われたことがその時蘇っていました。 先生はテーブルに両肘を立て合掌そのまま左右の掌を擦り合わせながら 「定年になっても幽斎殿に残れるよう楠本先生にお願いしようと思ってるんだ」 と、勢いよく言われました。僕はその時 「先生、先生は永遠に幽斎殿に残れるに決まってるじゃないですか」 と夢中になって言いました。 先生は幽斎殿が谷口雅春先生との通信が出来る唯一の場所だと言われてました。幽斎殿は先生にとって「祈り」のまほろばでもあり、神界に存します谷口先生との交信の場所でありました。 定年後、幽斎殿に残ることの切なる願いは谷口先生との交信の切実さ故に想い彷彿とされていたのではないか。 先生が定年になられても楠本先生は必ず先生を幽斎殿に残されたでしょう。 あと二年後に定年を控えたまま「定年後」のことは気にも留めないで、さっさと竜宮本源に入られました。 先生は過去を振り向くのが苦手でした。「今」の喜びの味わいだけでした。それが「吾、今、此処」の現実を生活された「生長の家」の、谷口雅春先生の申し子の生活だったに違いありません。 平成十七年六月二十八日、先生の亡くなられる二週間前、竜宮参道を降りる真っ只中で、先生は運転される車のハンドルをちょっと揺らしながら言われました…… 「佐谷君とわたしはともだちだね」 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(55) 2007/3/27 |
|||||||
| 私の記憶に間違いがなければ、榎本先生を目の当たりにしたのは、1993年4月の短期練成会で御講話を拝聴した時である。肉眼で拝顔したのは、これが初めてで最後であった。当時学生であった私は、先生の講話のうちに、宗教家としての先生の天才を観た思い出がある。 永久に真実に存在するもの、すなわち実相を唯一無二の光明存在として語られる。 生滅変異し、在るが如くみえても実在しないもの、すなわち現象を、本来無し、と喝破される。 実相を「ある」「なし」の二側面から方便を究境し、縦横無尽、自由自在に語り尽くされていた先生は、今も光明説法で諸霊を御導きされているのであろう。 拝。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(53) 2007/3/25 |
|||||||
桜が咲く季節になろうとしています。唯咲いています。 榎本恵吾先生が 「みごとな満開の桜を眺めていると、何時までも眺めていたくて、その場を去りがたい気持ちになりますが、誰も知るものがいない山奥で唯咲いている桜の木があるのを思う時、安心してその場を去れる。」と言っておられたことを思い出します。 幽斎殿で、夕立か、嵐だったのか、雨がものすごく降っていたときのことです。 「すごいよね、雲は自分で雨になって落ちてくるんだからね。」 六角のお堂の屋根の勾配から滝のように落ちてくる水のかたまりを眺めつつ、楽しそうに、また真剣な顔つきで見ておられました。 その雨の落ち方は、すがすがしいほど気持ちの良いものでした。 榎本先生に戴いたものは、言葉にも何にも表現できないものです。 唯、先生のそばにいれば満たされて、充足して、安心して居る事が出来る、そんな場所でした。ただただ認めてくださり、肯定してくださっていました。それは今でも、先生のことを思うだけで、感じられます。 朝焼けが美しいと思えば、「先生が私のために用意してくれたのかしら」。夕日が美しければ、星が美しければ、青空がすがすがしい時も、吹く風が気持ちよいときも、「先生、ありがとう。」という気持ちになります。何があっても大丈夫、先生が祈っていてくださる。守ってくださる――と。 神というものを人間に一番近づけて表現してくれたものがあるとすれば、私にとっては榎本恵吾先生であり、その存在があったがゆえに、「神とはこんなにも、私のことを愛してくれて、思っていてくれて、喜んで居てくれるもの」と思えます。「先生ありがとう」が、「神様ありがとう」になっています。先生が間におられるおかげで、とても身近で、「そんなことがあっても不思議ではない」という感じになります。 小さい時から生長の家に触れ、「人間神の子、無限力。何でもできる、強い子、良い子。」――と教えられながら、どこから何処までが神の子で、何処から自分の我なのか解らなくて――どこから何処までが実相で、どこから何処までが現象なのかも解らなくて――「人間神の子・無限力」は修行の果てに得るもので、私の手の届くところのものではない――と、あきらめていました。 榎本先生がお母様を亡くされ、葬儀を終えられ仕事に戻られたときだったと思うのですが、「通夜の席で、皆さんが母のことを、“あんなにも素晴らしい人だった”“こんなにも素晴らしい方だった”と褒めてくださる、でもね、“素晴らしかった母”と、“光明燦然と輝く母”と、どっちを取るかというと、やっぱり“光明燦然として光輝いている”ほうなんだね」というようなことを言われました。 それが今でも、私の「現象と、実相」の境界線になっています。あれをしてから、これをしてから……と、「やったことの成績」で救われようとついつい自分を縛ってしまいますが、そんなもの無しに唯、光輝く「生かされっぱなしの自分」を取りもどせる基準になっています。 ただただ感謝。先生にめぐりあえた事は、私の最大の喜びであります。 思っていることの100分の1も言いあらわす事が出来ないのが歯がゆいのですが、それでも、ほんの少しでも、先生への感謝の気持ちが表せれればと思い、言葉にすることにしました。ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(52) 2007/3/24 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 榎本先生にはじめてお会いしてから、はや20年以上経ちました。 名古屋で少し青年会活動をしていただけで、訳もわからぬまま、友達の誘いで練成を受けました。練成中の先生の講話は、いつもの「ニコニコ」と「雲」のお話でした。よくわらないまま、なんとなく居心地がよかったのか、大祭のお手伝いをし、またそれが楽しくて、そのまま研修生にならせて頂きました。 それまで、何千人といる大きな会社の中で一つの歯車として仕事をするために、毎日地下鉄で通勤し、地下街で買い物をしてと、本当に今考えると機械的に唯物的に生きてきていました。それが、先生から「山川草木国土悉皆成仏、有情非情同時常道」と、ひとつひとつすべて、神の命のさきはえと感じていくことを教えていただき、宇治の自然、あの空気の感じが懐かしく感じられるようになりました。研修生の時、研修時間にみんなで興正寺や塔の島を歩いたりして、川の流れを、木の幹を、空の色を、回りの草を、花を、葉っぱの1枚1枚を、賛嘆しながら歩いてると、心の中がどんどん開放されて行き、いつも宇治川を渡るだけでも研修時間内に戻れないほどでした。先生がいつもいつも、「喜んでいいんですよ、そのままでいいんですよ」と、本当に毎日毎日体に染み渡るようにお話しくださり、わたしの体に教え込ませていただきました。 私も、1年や2年ではまだまだわからなかったでしょうが、宇治にいる時間もおかげさまで人より長く居させてもらいましたし、出たり入ったり、幾度となくさせてもらえたおかげで、こんな私でも、大安心でいられるようになりました。理屈ではわかっていないし、言葉で文章で表現することはなかなかできないけれど、何か困った時、苦しいとき、理屈でなく、もやもやの中で、上を見て晴れ渡る空があることが、信じられる自分がいることがわかるようになりました。 研修生活の中で、先生のそばの空気、先生のご家族の中にいた時の自分、その空間から何からすべてが、わたしはありがたくて、うれしくて、うれしくて……それが永遠に続くものだと思っていました。宇治に行きさえすれば、先生が「やぁー!」とか声をかけてくださって、私の中で(ほぉ~・・・)なぁ~んて深呼吸したりして、また頑張れる日常にもどれるんです。 私は宇治に行くと必ず不思議と、食堂で、龍宮参道で、あるいは大拝殿の前で、先生にお会いして、私はいそいそと車に駆け寄ったり、幽祭殿の廊下で駆け寄ったりして、満足していました。その時も、「たくさんの人を案内して来たんです」と申し上げたら、それは喜んでいただけました。前に、総連会長をしている事もお話したら、「頑張ってるねー」と言っていただきました。 私が榎本先生と最後にお会いできたのは、亡くなられる前の月、6月の月次祭に、地元三重の人10人位といっしょにはじめて参列し、その後、講習会の後だったので「ご苦労様会」として宇治の料亭へお食事をしに行きました。その時、少し立ち話ができました。 宇治に行けば、先生にお会いすれば、何かいつも、もやもやしてたものが晴れるのに、先生が亡くなってからそれができなくなって、やっぱり寂しく思います。しかし、ご著書の『原案』、『弟子像』等を読んでいると、先生がそこに、すぐそこにいらっしゃるようで、そこがそのまま宇治本山のような気持ち、先生のそばにいた時のような気持ちになれて、大安心の境地に包まれます。本当に幸せの時でした。 今は、三重で母親教室をしていますが、時折り質問されたりすると、先生と同じことを言っている自分がいます。そして、みんなが安心して喜ばれます。これを書いてるときも、傍で子供が訳のわからないことを言ってきますが、落ち着いて子供に言っている自分がいます。先生を思い出せば、やさしい、楽しかった自分を取り戻せます。本当に、榎本先生と同じ時を過ごせたことを、有難く、うれしく思います。 先生、ありがとうございました。また、宇治でお逢いできますことを楽しみにしております。 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(51) 2007/3/24 |
|||||||
| 合掌 ありがとうございます。 榎本先生とのお別れは あまりにも突然で、今でも夢を見ているような気がします。また一方、ふと心にひらめいた事を実行して、「今のは先生が教えて下さったのかしら」と思うことがあります。 先生が教えて下さったことは数限りなくあって、すぐには思い出せないほどですが、その中の一つに、先生が東京芸大を目指しておられた姪御さんに宛てて書かれたお手紙があります。どういう経緯で私がお手紙を見せていただいたのか、もう記憶にないのですが、その内容は、 「春になって アスファルトの割れ目から顔をのぞかせる小さな緑があります。アスファルトは固いのに、そしてアスファルトに真っ先にあたる緑の先端はやわらかい新芽なのに、アスファルトを割って出てくるんです。そこには、みずみずしい新芽のために アスファルトが道を譲るような、生命の不思議さがあるのではないでしょうか」 というものでした。 この文章は(もちろん、この通りではありません)ずっと私の心に、「困難とみえる事態が起こっても、喜んで進めば、すっと道が開けるんだ、大丈夫だよ」と、小さな新芽のように穏やかで でも確固たる喜びの灯を、ともし続けてくれています。 また、「先生、こんな嬉しいことがありました!」とご報告すると、「そう言って喜んでいるあなたに、僕は満足したゆったりしたものを感じますよ」と讃嘆して下さった先生。自分でも「融通のきかない、堅い人間」の自覚のあった私は、少し気恥ずかしく、でもこの私の中に? と、嬉しくてたまらなかったものです。 未熟で何かと失敗の多かった私達の姿の奥に、光輝やく実相を観(み)続けて下さった先生の愛の大きさ、ご信仰の奥深さを、年月を経て 自らがあの頃の先生と同じ年令になった今、しみじみと復た感じさせていただいています。 奥様と四人のお嬢さん達との思い出(こちらは まだまだ現在進行形!)も、暖かく楽しいものばかりで、このように豊かな心の糧を下さった先生とご家族の皆様には、感謝の言葉を尽くしても尽くしきれません。 一信徒として、主婦として、あわただしく過ぎる毎日ですが、私達が各々の場で喜んで生活し、その喜びが光となって周囲を照らし広がることを、先生は喜んで下さっているのではないかと思っています。 今回、この文を書く機会を与えて下さった奥様をはじめ ご尽力下さった皆様に、心から感謝申し上げます。 再 拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(50) 2007/3/22 |
|||||||
“音の響きに包まれて・・・” 合掌 ありがとうございます。 平成5年4月、実家の両親が広島県から宇治の一般練成を受けに来ました。 練成を受けている母から、枚方市に住む私に電話がありました。 「レッスンや家事で忙しいと思うけど、榎本恵吾先生があなたに会って話を聞きたいとおっしゃっているので、出来るだけ早く宇治まで来てくれない?」と。 何を聞かれるのかしら? と少し気にしながらも、大好きな両親に会えるのが嬉しくて、レッスンをやりくりし、両親への差し入れに、手料理をお重に詰めて、車を走らせました。当時(平成5年頃)の私が抱いていた榎本恵吾先生の印象は、黒板へ「ニコニコ」を大きく書かれる先生。講話中、演壇で飛び上がってはびっくりさせられる先生。生長の家の本部講師で偉い人。ちょっと暗いイメージでとっつきにくいなー。という印象でした。(練成での聖歌練習では、和やかに聖歌指導され楽しく愉快な一面を見せて下さいました。) お会いした時、今までの印象は覆されました。優しい雰囲気の中に、少し恐縮ぎみに私を迎え入れて下さいました。 私の生い立ち、母校の「桐朋学園」の事や、恩師であるピアニスト故安川加寿子先生の事。「桐朋学園」出身で活躍している音楽家、演奏家の事等を、時間の経つのも忘れていろいろと聞かれました。母を介してまで「会って話を聞きたい」とおっしゃった事がうなずけるほどに・・・。榎本恵吾先生が飛田給におられた頃、同じ沿線の仙川にある「桐朋学園」に通学する、楽器や楽譜を抱えた音楽学生を見ておられ、音楽を愛される先生は学校や、学生に興味をお持ちだったのでしょう。 帰り際に、大きく真っ黒にぬられた音符で埋まっている大判の楽譜本(光りのある内に)を気恥ずかしそうに渡されました。その楽譜を手にした時、不思議な衝撃を受けました。それは厳粛で崇高なものでした。今まで沢山の楽譜に接して来ましたが、手にしただけでこのような感じを受けた事はまったくありませんでした。「これってなに?」と驚きでドキッ!とした事は今でも鮮明に覚えています。その時から「実相世界」「久遠の今」に立たれ、光明を放っておられる先生に、私の魂はぐんぐん惹き込まれて行きました。 手書きの五線譜に書かれた、大きな音符をさして、「この中にすべてのすべてがある!」「音符を書いていいんだ!」等々。今までに聞いたことのない言葉を確信をもって、光輝いて、喜びいっぱいでおっしゃる先生に、私は仰天してしまいました。 音楽に関しても、家庭生活においても、順風満帆で幸せな喜びの生活をしていた私に、何かが不思議な温かさを持って、ムクムクと頭をもちあげて来ました。このムクムクの本源は何だろう!「そうだ! 榎本恵吾先生だ!」 私はこの時、榎本恵吾先生の中に飛び込んでしまいました。それからは先生の「講話」を受講しに、又先生の作品をピアノで弾かせて頂きに、家から宇治まで19キロの道程を車でせっせと通い始めました。 それには家族の協力もありました。たまたま休日で在宅の主人は、私が留守をすると不自由でしょうに「榎本恵吾先生は神様だ。ピアノを弾く事が先生のお役に立つことであれば、これほど喜ばしい事はないよ。」と嬉々として車で出かける私を見送って下さいました。12年もの間、一度も車のトラブル等もなく、恙無く過ごせたのも大いなるもののゆるしと、家族の愛念、祈りがあったればこそと思わずにはいられません。ありがとうございます。 ムクムクの本源を体得するのに時間はかかりませんでした。 「実相独在」「光一元」の世界のみを見つめ、そこに座していらっしゃる先生。すべてが「光り」であられる先生。その光りの広がりの中に本源を感じた時は飛び上がらんばかりの喜びでした。 先生のご愛念とお導きの中で曲を弾かせて頂き、私は魂の大きな喜び、自分の使命、今までの音楽人生の中では知り得なかった諸々の発見、音楽をする至福の喜びをより深めました。 子供達も成人し、レッスンの生徒さんもそれぞれ手を離れ、自由な時間が持てる年齢、環境になりました。これからの時間は、先生が「僕の専属のピアニスト」と、満面の笑顔でおっしゃるお言葉を感謝でお受けし、存分に、先生がお喜びになる音を奏でさせて頂こう! また、そのお役に恥じないよう、演奏も究めていこう! と喜び一杯で思った事でした。 長い間、先生の作品をピアノで演奏し、録音したテープを、先生とごく身近な人達だけで聴いて喜んでいましたが、周囲の皆様のご愛念で、次々作品集が出来、MD、CDへの収録と、嬉しい展開となりました。 大講堂での録音中、音の響きが、私が鍵盤に指を触れる前にもう鳴り響いているのを感じ驚愕しました。ふと横に座っていらっしゃる先生に目をやると、合掌のお姿で静かに聴いていらっしゃいました。まさにそこは実相世界、光一元の世界。私が弾くのではなく、音符の中から喜びが溢れ、光り(音)がほとばしり出、先生を通して響いているのを体感し、感動しました。神国から榎本恵吾先生を通して天下った響き。それが曲集「はじめのはじめ」「はじめの光り」等々。先生のすべての作品です。尊敬してやまない榎本恵吾先生の下(もと)、聖地での演奏は神の祝福に包まれこの上ない幸いを思い感謝で一杯です。 収録には、当時宇治別格本山で奉職されていた現本部講師・久都間繁様の多大のご尽力を頂きました。ありがとうございました。 先生も、久都間様の存在をとてもお喜びでした。 ※ 「音楽館」(2)(3)(4)をご覧(お聴き)ください。 榎本恵吾先生の中には、練習がありません。すべて完璧。もんくなし。満点――なのです。「神想観」にも、ピアノの演奏にも。「響き出るそのままが尊くてありがたくて、喜ぶのが忙しくて、批評する暇などない……」と。常にすべての物や事を拝んでいらっしゃる先生。私が演奏の感想を求めると、いつも「すばらしい! もんくなし! 満点!」のお言葉が返ってきました。先生は「喜びあじわう事の天才」でもいらっしゃいました。 先生は、あふれ出る曲をどんどん楽譜に現わされました。先生の情熱には圧倒されるものがありました。少しでも早く響かせてほしい、との思いがFAXに託され、毎週月曜日の早朝に届くようになったのは、平成13年頃からでしょうか。 幼子のように純粋に、一途に、ご自分の書かれた音符が響くのを待ち望まれる先生に、私はFAXで楽譜が届くと、すぐにピアノで弾いて、カセットテープやMDに録音し、車を走らせてお届けしたり、郵便でお送りしました。今、思うと、忙しくとも光に満ち溢れた至福の時でした。先生は、一度もお休みなくお送り下さいました。出講でお出かけの時は出講先から。どうしても送れない時には日にちをずらせてでも、お手紙と真理の言葉を添えて。ご昇天の前日頂いたのが最後のお便りになりました。大切に納められた尊いFAX便は、今では我が家の宝物です。 「僕にはやりたい事が一杯あって、100歳まで生きても、し終えない。」 「本部講師はたくさんいらっしゃるけれど、僕ほど幸せな本部講師はいないと思う……。最近つくづく、そう思うようになりました。」と、晩年の恵吾先生のお言葉です。 しみじみと、おっしゃっていました。 榎本恵吾先生は一貫して、命がけで「実相独在」を伝え続け、貫かれました。ご家庭にあっては、素晴らしい一子奥様と喜びの家庭信仰を生きられました。お父様を敬愛される四人のお嬢様ご夫妻、可愛いお孫さん達に囲まれ、幸せな時をお過ごしになりました。講師としては多くの愛弟子から尊敬され、慕われ、たくさんの信徒をお救いになりました。多くの人を驚嘆させる素晴らしい多種の作品(論文・絵画・書・音楽・本・……)も、よろこびの中で沢山制作されました。 同胞の岡正章先生のご存在も素晴らしいですね。岡先生のご尽力でHP「榎本恵吾記念館」が立ち上げられました。恵吾先生の講話、多種の作品が生き生きと生き続けられ、多くの人の救いとなっています。 「こんなにしてもらってありがたい事だねー」と、満面の笑みの恵吾先生のお姿が見えるようです。 谷口雅春大聖師のみ教えの神髄を、命がけで伝え続けられた榎本恵吾先生。 「久遠の今」を生き抜かれた榎本恵吾先生。 先生のご生涯は、「素晴らしい! もんくなし! 満点!」です。 榎本恵吾先生の在りし日を偲び、万感胸に迫り感謝の涙が頬を伝います。 先生、ありがとうございました。心からの感謝を捧げます。 今生で榎本恵吾先生にご縁を頂けた事は何と幸運であった事か・・・! 感謝しても感謝しても、し尽くせません。 感謝 合掌 (2007年 3月21日 記) |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(49) 2007/3/22 |
|||||||
私は榎本先生のお話を練成会で聞いた時、 「この喜びは一体何なんだろう? “魂の喜び”とはこのことか!」 と、感動したことを今もはっきりと覚えています。 その後も、“魂の感動”を味わいに、何度も宇治を訪れました。 当時、先生に頂いた本の冒頭に 「私は今、『八人しか生長の家を知るものがゐないとして、どうするか、を考へなさい』(注:これはかつてあつた八人委員会が尊師から戴いた御言葉)と言ふ公案を戴いて、今日まで噴火山上の舞踏を楽しみ平穏らしく日を送つてきたことを恥ぢざるを得ない。」 とご自身に対する厳しい評価が書かれていました。そしてさらに厳しく 「もし、この世に尊師も無く、聖典も無く、組織も無く、全くの一人、汝が生長の家を知つてゐる時、生長の家が汝において初発の時如何?」 とありました。 この生長の家の大真理を、たった一人自分だけが知っていたら――なんて、考えた事などありませんでした。尊師も、聖典も、組織も、皆揃っているのはあたりまえ。ここから出発している私ですから、先生のこの文章を読んだ時、身震いのようなものを感じ、また、只一人この大真理を神から授けられた尊師と、この公案を戴いた8人のお弟子さん達の真剣さは、想像を絶するものだと思いました。 それから何年か過ぎて、私は自分の白髪が増え始めて気になりかけた頃、先生からご著書『弟子像』を戴きました。その中に、大聖師が若い弟子に送られたお手紙の一節というのが紹介されていました。「君は髪の毛がうすくなっていたが、私はぬるま湯に朝少し残しておいた牛乳をとかして、頭髪にひたすようにしている。おかげで君より黒く多いように思った、君もこれを実行してはどうか」という主旨のものでした。 これはいい事を聞いた、と思い、早速私も実行に移しました.。すると白髪の進行が止まったので、「これは効いた」と思い、榎本先生にその旨お話すると、先生は私の髪をじっと見て「僕はやっていないよ」と言って、にっこりされた。 先生が亡くなられた翌月、例年通り宇治では宝蔵神社盂蘭盆供養大祭が行われました。私は交通係りで車の誘導をしていたのですが、ちょっと目が合った人に「榎本先生、亡くなられましたね」と声をかけると、その人から「榎本先生は、最後の最後まで生長の家の素晴らしさを教えて下さいましたね。」という答えが返ってきました。 この「最後の最後まで」という言葉の中には、生前あんなに魂を揺り動かす深い真理と感動を与えて下さり、その上楠本先生のご文章「榎本恵吾部長逝く」にある「つまり坐亡だったわけである。高級霊だった。」ということを指しているに違いなかった。 「坐亡」――この最後のお姿を通して、その人は 生長の家の素晴らしさをじっくりとかみしめているようだった。私は名前も知らないこの人の、「最後の最後まで」という言葉の中に、生長の家の深い深いところで繋がっている多くの人が居るのだと感じ、大変嬉しく思いました。 今は、ウェブサイト「榎本恵吾記念館」の「講話館」を訪問し、テキストを片手に持ち、私にとっては難解な 「生長の家の信仰を続けていてくれますと、この二つの心の入れかえが出来るのです。……生と死の分かれ目なのです」 というお話を、繰り返し又繰り返し、聞かせて戴いています。 「もし、この世に尊師も無く、聖典も無く、組織も無く、全くの一人、汝が生長の家を知つてゐる時、生長の家が汝において初発の時如何?」 のお言葉を胸に、この重さにつぶれることなく日々を進んで行く勇気が出てきました。 素晴らしいウェブサイトを作って下さった関係者の皆様、ありがとうございます。 ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(48) 2007/3/18 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 私は平成十三年十二月に、佐谷昇三さんが介して下さり榎本先生のご存在を知ることができました。 佐谷さんは榎本先生の愛弟子といいましょうか、あるいはそれ以上に、先生とは何か計り知れない程の深いご縁があるように思うくらいすごい人――と私は一方的に思わせていただいています。 平成十四年春頃に、幽斎殿で初めて先生にお目にかかりました。先生はにこやかな笑顔で迎えて下さり、そして真剣なまなざしで「『甘露の法雨』のね、この一番最初の招神歌(かみよびうた)がとても大切なのですよ……」と一所懸命にお話しをして下さいました。そのときの私は、少し難しくて、どのように理解してよいかわかりませんでした。 その後、佐谷さんに毎日のようにお電話で、先生のご説法を解りやすく、具体的に教えていただき、一年近くたった頃、振り返ってみると『生命の實相』全40巻を読み上げることができていました。 私をとりまく環境もいつしか、天にも昇るような嬉しい、楽しい環境に変わってゆきました。 先生は佐谷さんのお家に訪問されるご予定でしたが、ある時、いろいろなご都合により、変わって我が家へお越し下さることになりました。はじめてお迎えするときの緊張感は、今でも忘れられません。何をどのようにしてよいのかわからず、ただ来る日も、来る日も家中の掃除ばかりしていたことでした。そしていよいよお見えになる当日などは、時間が刻々とせまってくると落ち着くことができず、主人と実相額の前でひたすら聖経をあげてお待ちしておりました。 「堅信歌」から始まり、「いのちの流れ」「光のある内に」などなどの歌を、福場江三子先生が奏でられるメロディーに合わせて、皆さんとご一緒に楽しく、楽しく歌い、先生のなごやかな雰囲気にあたたかく包まれ、至福のひとときが流れてゆきました。お帰りになる時には、玄関で「きれいなきれいな川で」を歌って下さいました。先生は命懸けで歌っていらっしゃるようにも思えました。 私は大阪の摂津市鳥飼という所に住んでいるのですが、先生は「鳥飼う人」という歌を作詞、作曲して下さり、春、秋、そして次の年の春秋の頃にお越し下さって、夢のような日々を過ごさせていただきましたことは、無上の喜びでした。 |
|||||||
 |
|||||||
おかげさまで、眠っていた鳥飼相愛会が活気づいて、誌友会を新たに発足することができました。そのうえ主人は、それまで生長の家のことには特に関心を示すこともなく、私が白鳩会にいそいそと出掛けて行くのをただ見守っていてくれるだけでしたが、神想観をしたり、仏前で聖経を読誦するようになったのです。 先生に最後にお会いできましたのは平成十七年七月九日、命日祭に出席するため宇治へ行った時でした。その時は、神癒祈願をお願いしていた誌友さんと一緒でした。幽斎殿で神想観をしたあと、先生は誌友さんが持参した『葩さんさん』の御本にサインをして下さり、「ちょっと待っててね」と立ち去られ、しばらくしてから「はじめのはじめ」、「はじめの光り」の楽譜とCDを持ってきて彼女にお渡し下さいました。そして命日祭が始まるギリギリまで、いろいろお話しをして下さり、「大阪教区の人は素晴らしいねぇ」とにっこり微笑んで下さいました。また挨拶をして後姿を見送っていると、さっと振り向かれ、「ご主人によろしくね」と、そして誌友さんにも「ご主人によろしくね」と、やさしく言って下さり、お帰りになられました。そのことは私にとって、いつまでも心に残るおことば・お姿となりました。母の祥月命日の日の出来事でした。 平成十四年から三年間、先生と親しくさせていただいた時間は、あっという間に過ぎ去ってしまいましたが、生涯忘れることのできない、永遠の時となりました。また私の人生の中で一番輝いた時でもありました。 榎本先生、大空いっぱいの愛と、やさしさを、ありがとうございます。 そしてこのような素晴らしい榎本先生を知らしめて下さった佐谷さん、本当にありがとうございます。 最後になりましたが、先生にご恩返しがしたい・・・と思い、平成十八年の新年祭・八月の大祭のときから、写経の係の奉仕をさせていただいています。宇治で一子先生にお会いすると、いつもあたたかい優しいまなざしでおことばをかけて下さいます。おそばで先生が「よくきたね」と言って下さっているように思えて、とても幸福な気持ちになります。これからも、続けられる限りご奉仕をさせていただきます。 一子先生、ありがとうございます。 再拝 (平成十九年三月十二日記す) |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(47) 2007/3/16 |
|||||||
昭和56年は、私にとって最大の幸せな年になりました。 師にめぐり会えたことに、心からの感謝を申し上げたいと思います。 まさに、どん底の人間が、人生最高の幸運を授かることになったのです。この夢のようなことが、現実にあったのです。 宇治本山にて、榎本恵吾先生にめぐり会えたのです。そして師とともに、夢のような2ヵ月をすごさせていただき、このときおそらく私の魂は、師及び一子奥様の中に飛び込んでしまったように思います。 そして今、二十数年の時が過ぎ行き、この間一日も、師と奥様のことを思わぬ日はございませんでした。この間、苦しいことや、悲しいことも、たくさんありましたが、年に一度、12月31日に、師と奥様にお会いすることが喜びで、何があっても苦しみが苦しみでなく、時が過ぎ行くごとに喜びに変わっていくのでした。 12月31日という日は、私にとって最大の喜びの日でした。 そしてあの、7月12日です。 私は先頭に立って皆様を支えなければいけない立場でありましたが、私自身が私自身をどうすることも出来ず、ただ悲しみの中でオロオロするばかりでした。師とお別れして半年ほど、聖経を読むと涙があふれ出てしまいました。これではいけないと思いましたが、先生が『そのままでいいよ。ありがとうね。』と言っておられるように思われました。 師は、本山で私たち研修生の実相を観続けてくださっておられたのですね。私も師のことは一日たりとも忘れることなく、毎日毎日、「これでいいんでしょうか」と、独り言のように、いつも語りかけておりました。 先生、私は宇治を離れるとき、心に誓ったのですよ。このすばらしい先生を、一人でも多くの人に知って欲しいと思い、生きてまいりました。 又、最後に神の導きで友江さんという人に会い、「一の会」を作らせていただきました。先生、少しでもお役に立てましたか? まだまだ書きたいのですが、書くことが出来ません。これからも、この現象世界の使命が終わるまで、楽しく生きてまいります。 先生、そちらに行くことになりましたとき、必ず迎えに来てくださいね。 (宇治別格本山 元榎本研修生) |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(45) 2007/3/12 |
|||||||
| 合掌 ありがとうございます。 私は、あるご縁から、先生の創られた曲を編曲させていただく機会に恵まれました。 先生の創られたメロディーをシンセサイザーで編曲して、いつもテープをお渡ししていたのですが、はじめの頃はまだまだ未熟な編曲でした。途中、何度もひどいスランプに陥り、長い間お渡し出来ない事もあり、忘れた頃にやっと出来て、お持ちした事もありましたが、いつもいつも心から喜んで下さって、賛嘆して下さいました。 ある時、あまりにひどい出来のものがあり、どうしても自分で納得がいかずに、もう一度創り直して行った事があったのですが、その時にも先生は、「いやあ、前に創った方も、ちゃんと先にもらっといてよかったですよ。2つ創ってもらうのもまたいいですねえ。」 とおっしゃって下さった時には、私の方が逆に驚いたくらいでした。曲の出来の上手、下手にかかわらず、どんなものでも本人の個性・独創性というものを表現する事を、とても喜んで下さいました。 テープでずっと曲を創り続けてゆき、曲もある程度集まったので、ミニディスク(MD)にまとめて曲を録音し、先生にお渡しいたしました。MDというものは何度きいてもテープのように巻きついて伸びたりしないし、音が劣化しないという利点があるので、これからもずっと同じ音で先生に聴いていただける、と思っていました。 それからしばらくして練成を受けに行き、榎本先生の御講話をきかせていただいた時、御講話の最後に、先生がこのようにおっしゃいました。 「最近はMDなんていう便利なものが出来たんですね。何回聴いても音が劣化しないんですね。私は、谷口雅春先生のMDになりたい。」 私は、「ああ、そうなんだ。」と、本当にその言葉に感動しました。雅春先生の音を、そのまま劣化させないで伝えて下さっているんだ。本当に「神の子の自分を、ただただ喜べばいい」という、生長の家の神髄をお話しして下さっているんだ。これからもずっとそのMDを鳴らし続けてほしいし、ずっと聴き続けていたい――と思い、また、榎本先生の、谷口雅春先生への深い深い思いが伝わって来たような気がして、とても感動したことを覚えています。 先生の創られた曲は、「曲集」として何冊かに編集されています。その中の「はじめのはじめ」という本を先生からいただいた時、本を開けて見ると、左側が楽譜、そして右側がどのページを開けても、たくさんの観音様が合掌しあっている絵が描かれていました。どのページを開けても全部、その同じような絵が描かれています。はじめは何故そうなのか、不思議に思っていました。 それが昨年、団体参拝練成会で長崎の総本山に行って、行事の最後の「祈り合いの神想観」をした後、帰途についた時、ふと思いました――もしかしたら、本当はすべては祈り合いの神想観の続きなのではないか。これから家に帰っても、ずっとずっと祈り合いの神想観は続いている。仮に、罵倒し合うような大ゲンカをしている人同士であっても、本当は観音様がお互いに向かい合って祈り合いの神想観をしていて、人間同士だけではなく、空と海も、山と川も、草と木もすべて一切のものが祈り合いの神想観をしているんだ――という事に、忽然と気づきました。 ああ、だから、榎本先生はどのページにも、あの、観音様が祈り合っている姿しか描かれなかったのだ。もう、先生は深い深い悟りを得ていらっしゃるから、あの絵しか描きようがなかったのだ――と思いました。 すべてのページに描かれている観音様の祈り合う姿、あれがすべての世界の、宇宙の本当の姿なのだ――と、先生はあの絵を通して教えて下さっているのだ、と思いました。 何かに行きづまったり、心が迷い出した時は、いつもあの絵を見ています。 先生からいただいたものは、数え切れない程あります。曲を編曲させていただいた事も、今自分がしている音楽の勉強の大きな基礎となりました。 今も、先生への感謝の気持ちでいっぱいです。いつも、先生のおっしゃった事、お伝え下さった真理をしっかりと受けとめ、また、神の子の自分を、魂の底から喜ぶ毎日を過ごしてゆきたいです。 榎本先生、本当にありがとうございます。 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(44) 2007/3/11 |
|||||||
合掌 有難うございます。 榎本恵吾先生は生前、私のことを勿体無くも「僕の専属のピアニスト」とおっしゃって下さり、演奏をとても喜んで下さいました。私も、先生がお喜びになるのが嬉しくて、平成5年からご昇天されるまで、数えきれない数の先生の曲を演奏させて頂きました。 先生とのご縁と、光りに包まれた至福の時を頂いた事は、感謝してもし尽くせません。 このたび、「源大(もとはる)ちゃん」(四女妙子さんの長男)誕生のほとばしる喜びを機縁とし、久都間育代さんを媒介として、感動的な経緯でこの世に天下った「誕生」の曲。ピアノで弾かせて頂きました。 まぎれもなく榎本恵吾先生そのものの響きです。懐かしく、懐かしく、恵吾先生のお姿こそ見えませんが、確かな先生の存在を全身で感じ、感動の涙が止まりませんでした。先生がお喜びであろうメロディの音色。メロディを美しくハーモニーさせる和音の響き。アルペジオの流れ。曲のテンポ。美しく流れ出でるそのままを大切に大切に演奏いたました。 生前、恵吾先生は、新しい曲の演奏を聴かれたあと、私が「いかがですか?」とお尋ねしますと、決まって「素晴らしい!もんくなし!満点!」と満面の笑みでおっしゃいました。今回の「誕生」の曲にも、その様なお姿とお声が聞こえ、先生のお喜びのご様子が音の響きと共に大きくひろがります。 「僕の曲は、すべて祈りです。」と、生前の先生のお言葉。 高き霊界から常に私達を深い愛と祈りで祝福、賛嘆し、見守って下さっている尊い榎本恵吾先生のご愛念が、「誕生」の曲を通して魂に響きます。 先生、ありがとうございます。 「僕はいつもそばにいるよ。悲しむことは無いよ。『今』を喜びなさい!」 み光りの中にまします先生の合掌されているお姿とお声が、幾重にも広がります。 「誕生」の曲の響きと共に・・・・・。 「源大(もとはる)ちゃん」の健やかなご成長をお祈りいたします。 感謝 合掌 →「誕生」の曲(ピアノ演奏) |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(43) 2007/3/9 |
|||||||
平成十八年十二月十二日、私は夢の中でかつて榎本先生がお住まいになられていた宇治市三室戸(みむろど)にあるお宅を訪れました。三人の娘さんたちが、玄関先の階段を下りたところまで出て来てくださり、「男の子が生まれたよ」と知らせてくれました。 その三人の喜ばしい雰囲気を包み、周囲の家々や風景にとけ込むが如くして、榎本先生の姿は見えないのですが、在り在りとおられることを感じました。 十二月十五日午後二時過ぎ、末娘の妙子さんに「男児誕生」との知らせを受け、私も驚きました。事前の検診では女の子と聞いていましたので、ご一家の皆が驚き喜ばれたようでした。 翌十六日、輪読会の集いに参加いたしました。そして会場に向かう電車の中で『葩(はなびら)さんさん』の本を開いて読んでおりました。すると突然、あの十二日の夢の風景がそのままに浮かんできたのです。先生の在り在りとした雰囲気もそのまま残っていました。その風景の中に文字があり、文字だけがその風景の中から浮き出てきたようでした。忘れてはいけないと思い、急いで手帳に書き記しました。 「よろこび多き 光り 栄えよ よろこび多き 光り 栄えよ ここに生まれし いのちよ みたま幸え給え」 と。これが『誕生』の詞でした。 輪読会には参加された方々の清らかなよろこびの雰囲気がありました。 先導した人の左隣から輪読してくださいと言われて私が一番で読みました。読み終えると同時にさっき電車で出てきた詞が、メロディーを伴って上から鳴り響きはじめました。それは終わるところを知らず、繰り返しまた繰り返し、ずっとその会が終わるまで鳴っていました。不思議なことに会が終わって道を歩いているときも、帰りの電車に乗ってもそれは鳴っていました。 翌日、お昼すぎに横になろうと二十分ほど眠りました。そして目が覚めたのが午後二時。目覚めと同時にまた鳴りはじめました。 「今、書き留めておかないと」と思いピアノで音を拾いました。ひとつひとつを確かめるようにして、音を音符に書き記しました。 私がこの曲を通して感じたことは、先生は妙子さんの赤ちゃん誕生を共に喜んでおられる。また奥様や娘さんたちご夫婦、それからお孫さんたち、そして先生にご縁をいただいた一人一人の、「そのままの尊さ」を、深い本当に深い祈りの内に広大無辺にどこまでも観つめ、観護ってくださっている。そのことに生きておられる間、万分の一も気づいていたのだろうか。 先生の深い祈りの内に伸びやかに泳がせて頂いていたのだ。住む世界が替わろうとも変わりなく、祈り祝福してくださっている。「澄み切り」と「無我」なる眼で今も観つめてくださっている。 まるい大きな月を見ても先生を想い、多摩川の上流で紅葉を愛でながら主人と話している時もそこに先生が共に居てくださる。高き霊界に昇られた後もまるで千手観世音菩薩のようにどこどこまでも助けてくださる。お導きを折に触れ、夕焼けの美しさや雲の流れにさえ感じます。 「私は自然そのものである。自然は私そのものである。」 という祈りの言葉は「私は無いんですよ」という先生の言葉のように、語りかけてくれます。 合掌 →「誕生」の曲(歌唱) |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(42) 2007/3/8 |
|||||||
出せなかった感想文を今、未熟で恥ずかしいまま、先生のご霊前に捧げたいと思う。 生前、榎本先生は私にとって雲の上の人で、そこは別世界であり、龍宮城だった。 『親に逢いては親を殺し、師に逢いては師を殺し、神に逢いて神と共に生きる。』 榎本先生にめぐり会い、とてつもない喜びに包まれたと同時に、始めからセットで渡された言葉……。深く深く釘を刺された気がした。 その後めぐり会った心理学の師の口から、「三歩下がって師の影を踏まず」(どんなに偉大な師に出会っても、陰を踏まないぐらいの距離を保ちなさい。さもないと自分の足で歩けなくなる)という言葉を受け取ったとき、榎本先生の顔が浮かんだ。 「神様、そんなに釘を刺さないで下さい。私だってもっと甘えたい」 と思いつつ、やはり心に深く刻んだ。「自分の足で歩く。」これが私の課題なのだと思った。 20歳のころ、初めて宇治での練成会に単身参加した私は、生長の家との決別を心に決めていた。祖母の代から生長の家だったが、私にとってそれは喜びではなく、幸せになるための矯正具でしかなかった。自分の中に憎しみや汚い感情が生まれるたびに、「こんな思いを持っていては幸せになれない」と、懸命に矯正する。自分の経験ではないのに、答えを知っている人が、人を裁いたり自分を裁いたり、いつしか自分の中にもそんなものが巣食っていることに気付き、そんな冷たい信仰が苦しく、愚かでも暖かいものに憧れるようになった。 それでも、完全さや、真の幸福に対する執着があり、妥協出来ずにもがいていた。 20歳になったころ、「もうやめよう」と思った。それまでずっと矯正してきて苦しかった、でもいつまでたっても平行線で、見張られなければいけない自分――自然に一致して生きられる人は幸せだけれど、私はそうではないらしい。現にこんなに苦しいじゃないか。これからもずっとこんな矯正具をつけて生きたいのか。もう幸せになるのはあきらめよう、人から後ろ指をさされようと、不幸で同情される人生になろうと、せめて自分だけは全面的に自分を認めてあげよう、どんなに醜い自分でも本当の自分にぴったり寄り添って生きていこう。それがわたしの幸せだ――と思った。 そんな時、母に勧められるまま、10日間の練成に参加し、生まれて初めて、矯正具を外して自由になった私は、宇治の地でのんびり気ままに過ごそうと思っていた。 見たいものを見、聞きたいことだけ聞き、食べたいときに食べ、眠たいときに眠る。おかしいほど従順に本能に従う自分を楽しんでいた。そんな中で突然、榎本先生の講話がはじまった。 人生初のゆるみモードに浸っていた私は、先生の講話を一言も聞くことなく講堂の一番後ろの壁にもたれ、足を伸ばして熟睡していた。講話が終わり、拍手で目を覚ましたその瞬間、「うわー、今の話、聞きたかったあー! 眠っていたなんて一生の不覚 !!!」という感情が、お腹の底から湧いてきた。まだ先生のことも知らなかったし、実際に一言も聞いていないのに。 これまで経験したことのない、不思議な感覚だった。 あわてて予定表を見に行き、それからの10日間、すべての榎本先生の講話を、かぶりつきで受けた。当時は毎日朝、昼、晩と日に3回程も榎本先生の講話の時間があった! それもどうしても、何が何でも、今渡したい、受け取らせたいという先生の情熱が、これでもか、これでもか、と熱く熱く、降り注がれ、それを全身全霊で受けることができた。私のための特別の個人授業を受けている様な気さえしていた。“偶然”などとは言えない、黄金の時間だった。 言葉にするのは難しいけれど、永い間求め続けた唯一のものに出会い、やっと魂が入ったような気がした。それから、嬉しくて嬉しくて、本当に身体を押さえていないと、喜びがお腹の底から飛び出てしまうようで、この世にこんな喜びがあったのかと驚いた。 はじめて榎本先生にふれた練成を終える夜、長い感想文を書いた。 一点の汚れも無い、一度も傷ついたことも、憎んだこともない、完全な自分に出会えたこと。「実相円満完全」の意味を初めて感じたこと。無条件の喜びに溢れんばかりに満たされたこと。と同時に、その後の練成会が、“闇の研究”の様に思えて、辛く苦しく感じられたこと。 『罪を右顧左眄(うこさべん)すること勿れ。迷いを右顧左眄すること勿れ。病を右顧左眄すること勿れ。汝ら百尺竿頭(かんとう)より一歩飛ぶべし』――闇にとらわれて光を忘じるな、との真理の言葉そのままの生き方が可能であること。その生き方を貫いてくださることへの、言い表せない感謝。 感激のままに綴る感想文が十数枚に及んでも書ききれず、結局そのまま、出せずに持ち帰ってしまった。完成させて送ろうと思いながら、そのままになってしまい、本当に自分の不精を悔やんでいる。 このころ、よく宇治に通った。先生の、熱気に顔を真っ赤にして怒った様な姿が懐かしい。 後年、先生の講話は穏やかに、そして「私の話は聴いたらすぐに忘れてください。」なんて云われる様になったが、その言葉にしみじみと深いものを感じていた。それは、どんなにノートにメモしても書き留められない、どんなに時が経っても、言葉が消えてしまっても絶対に消えないものだった。 先生は、「自分が受け取ったと思ったものを100万倍、無限倍にしても、本当に受けたものの100万分の1、無限分の1なんだ」っていつか言われたけど、本当にそれほど尊いものだと感じている。 榎本先生にチラリと見せていただいたその片鱗に憧れて、焦がれて、及ばずながら自分もそのように生きたい、自分の足で歩いて少しでもそばに行きたい、いつか自分でその景色を見てみたいと、遠い遠い道に思えても、目指さずにはおられない。絶対にあきらめられない。そんな思いが刻印された。 そんなにも求めていながら、先生と直接お話をしたことはほとんどなかった。先生のそばに行くと、講話をうかがったり、神想観に同席させていただいたりするだけで、魂が満足してしまった。行き詰ってもがいている時でも、先生の前に出ると、祝福に満ちたその空気に満たされて、言葉を失くしてしまった。ただただ光を吸い込もうと、深呼吸するのみだった。 いつも現実に溺れていた私の束の間の息継ぎ。そこは文字通り龍宮城だった。 そんな中、私が一番榎本先生に接近できたのは、まだ娘が1歳くらいの頃、生まれつき腎臓の障害があり病状もめどが立たず暗中模索のなか、宇治での練成中に出会った大阪の講師の言葉がきっかけだった。その方は私と子供の顔を見るなり、「この子はあなたの魂を向上させる観世音菩薩。もし、この病気が治っても次々といろんな問題が起こるから覚悟しときなさい」と言われた。私は悲しくなって、「わが子を使って魂なんか向上させたくない! 私は、ぼちぼち幸せ、ぼちぼち健康がいいんです。」と無力な反論をしたが、そのショックは大きく私は深く傷つき、その恐怖心を消し去ろうともがいた。このときばかりはいつにもなく榎本先生にかじりついた。先生の「光明のみ」に完全に包まれたくて。 友人たちの計らいにより、この時一度だけ個人面談の機会を得たが、先生の前に出ると、やはり覚束ない感謝の言葉以外は見つからなかった。ただ自然に流れる温かい涙とともに榎本先生を満喫した。 引き続き参加した伝道練成。榎本先生が同行してくださった。私は榎本先生と同じ時代に生まれ、こうしてめぐり逢えた上に大切なものを伝えていただいた。先生と同じバスに乗って同じ空気を吸っていることが、ただただ幸せで涙が溢れて止まらなかった。その喜びの大きさに、いつの間にか現実の問題は遠く霞んでしまっていた。 バスが目的地に着き、2~3人のグループに分かれるとき、私は一生のお願いとばかりに「先生と一緒にまわらせてください」と榎本先生に直訴した。普段の自分からは考えられない行動で、その間も涙はぼうだと流れ続けており、先生は怪訝な顔をしながらも、一緒に連れて行って下さった。ある家の前で並んで聖経をあげ神想観をしている間、留守中に榎本先生にこうして祈ってもらえるこの家の方は、なんて幸せなんだろう。今この家の瓦一枚一枚、庭の葉っぱ一枚一枚が、喜んでキラキラしているに違いない。そして何より、私が今この場でご一緒できる幸せに涙が溢れて止らない。その時間がどれだけ私にとって尊い、得難い時であるかを全身全霊で感じていた。まるでイエスの傍にいる使徒のような気持ちだった。 道場に着くとすぐ、先生が練成部の事務所から小さな直筆の色紙を持ってきて手渡してくださった。忘れられないこの日の思い出と共に、私の大切な宝物になった。この経験を作ってくれたすべての出来事に心の底から感謝している。 先生が祈願部に行かれてからは、講話の機会も少なくなり、さびしい思いもあったが、幽斎殿での神想観に娘とともに参加させていただくことが、私の宇治訪問の目的となった。 そこでも、「先生こんにちは」と、挨拶をするだけで精一杯だった。 以前、先生の講話を浴びるほど聴かせていただいた幸運を噛みしめながら、その場の“空気がどんなに祝福に満ちてキラキラしているだろう……この空気を娘と共にパクパクできるだけで、幸せだなあ……”なんて思っていた。できの悪い母だけれど、これだけは、私が娘にしてあげることが出来たと誇りに思いつつ。そして、娘もいつか、私と同じものを、榎本先生から受け取るだろうな――と思っていた。いつかちゃんと自分で歩ける自覚が出来たら、もう少しおそばにいって、弟子入りしたい……などと夢見ていた。 ○ 宇治にいる親友、鵜飼恭子・遠藤純子、二人からの知らせで、榎本先生の突然の訃報にふれ、この夢は、はかなく砕けた。もっとずうずうしく押しかけたかった。 もうお会いできない寂しさは、まだ実感できなかった。一番大切な師とのこの世の最後のお別れをするため、娘と二人で福岡から深夜バスに乗った。 「娘に渡したい唯一のもの。私にそれを伝えることが出来るだろうか? いや、娘は既に受け取っている。」と信じつつ、生まれる前からこれまで一緒に通った榎本先生への道を辿った。告別式の日は、娘の10歳の誕生日だった。悲しいけれど、二人でそこに同席させていただけることが有難かった。告別式の席では、「これを機に弟子にしていただきます!」と心の中で宣言した。もう「神と共に生きる」の神の域に榎本先生が逝かれたから。 最後にみんなで歌った堅信歌の後、『バンザイ!』と叫びたかった。 榎本先生と出会ってしまってから15年あまり、いろんな事があった。魂の喜びを知りながらも、私は決して順風満帆にキラキラして生きてきてはいない。先生にいただいた大きな喜びと自由を胸に生きたつもりで、問題を起こしたり、人を傷つけ、自分も傷つけた。突き動かされるままに生きて、大きな挫折に叩きのめされたり、自分を信頼できなくなったり、自分の未熟さを噛みしめたり。それはまるで小さな蛙がいきなり大海に出てしまった様だった。 本当の自分を求め続け、次々に出てくる“まがい物”の自分を捨てるため、どん底を這いずり回っていたように思う。こんな自分では到底弟子入りできないと、情けなく悲しかった。 それでもやはり、同じ山に登りたいと必死で登山口を探していた。 私が身を切るようにして捨ててきたものの中には、宗教がらみ、家族がらみのものが多い。 冷たく血の通わない言葉や信仰には、はっきりと嫌悪感を感じるし、当然と思っていた概念・真理と信じていたものの底にも闇を感じ、足元がふらつくことがある。 そんな時いつも、榎本先生の姿が浮かび、温かい愛と喜びに包まれる。 その人の生きる姿、その人と接して生まれる感情からしか、私は知ることができなかった。 『その人は偉大な師であり、私は間違いなくその人の弟子である。』 告別式の後に、一子先生の御講話を聞いて、榎本先生がどんなに強い覚悟でその生き方を貫いて下さったのかを、改めて強く強く感じ、これまでの感激・感謝をちゃんと先生に伝えきれなかったことが改めて悔やまれた。 榎本先生、一子先生のお話の中にたくさん出てきた、ご夫婦の、ご家族の暖かい愛情の、惜しみない表現がとても眩しく、遠巻きに見ていた私だった。 本当はもっともっと、娘のように榎本先生に甘えたかった。いろんな疑問も直接投げかけたかった。二日酔いになるまで一緒にお酒を飲んでみたかった。美味しいお茶を淹れて差し上げたかった。先生のような人は、もういない。とてつもなく淋しい。いつも求めている。 あんな喜びをまた感じることができるだろうかと。 「師に逢いて 師を殺し……」 今となってはこの言葉と、理屈っぽい私の受け止め方が心底恨めしい。強がりとやせ我慢ばかりで悔やみきれない後悔が噴き出す。榎本先生にめぐり会えた喜びが大きすぎて、その姿が眩しすぎて、身に余るほどのものを頂き満たされ、それ以上に求めるものは何も無いなどと思っていた。幼子の如く駆け寄りたい気持ちに素直になれず、ことあるごとにブレーキをかけてしまった。本当は影を踏むほどにぴったりくっついて学びたかった。はらわれてもかじり付く程に自分をさらけ出して、門前に座り込んででも教えを請うべきだった。それなのに、自分の方から距離を置いてきた悔いは、私の中に一生残る。 唯一の最愛の師に出会いながら、何を迷っていたのか、それより大切なことなどなかったはずなのに。それは私の未熟さと、住んでいる世界のあまりの次元の違いに、自分の現実に戻れなくなる不安だったかもしれない。黄金の時間は永いようで短く、無情にも確実に自立の瞬間はやってくる。玉手箱を開けて白髪のお婆さんになったって全然構わなかった。もし今の私が浦島太郎なら、日々その幸せを噛みしめながら、龍宮城で暮らすことを選ぶだろう。 先生が亡くなってからずっと、私はこの文章を書き続けている。 何度も書き直し、感謝と喜びしかないと思っていた自分の心の深みに、こんなにも大きな悔いと貪欲な欲求があったことを、今になって思い知った。私はこれからもずっと、心の中の榎本先生に自分をさらけ出し、問いかけ、弟子としてその教えを乞い続ける――。(3月8日) ****************** 上記の投稿文を出した後すぐ、神々の島と言われている久高島(沖縄県)に行きました。その日は雲が重く太陽は見えなくてもきれいな雲が見られるかな? と榎本先生を思いながら朝日を待っていると、つかの間ですが、金色の竜が現れ、全身全霊で先生を感じ、こんなにも喜んでくださり、ここまで、そしていつも導いてくださっていることを、はっきりと自覚させて頂きました。 写真を添付させていただきます。(3月22日)   |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(41) 2007/3/7 |
|||||||
(1) 手 紙 <2000.8> 「お父さんへ お早うございます。お茶の葉、新しいの入れておきましたよ。(そば茶)お湯、入れすぎない方がいいよ。たえこ」 午前3時頃起き出す父親と、朝、顔を合わすことなどはとても無理な四女が、リビングのテーブル上に前夜、広告の裏紙に書いた、主人宛の手紙です。そして、香ばしいそば茶を午前3時頃飲んだ形跡を残して、その紙に「合掌。わかりました。父」と主人が書き加えて、私が目覚めたときは出かけていました。 私は、用は済んだものと、その手紙をくしゃくしゃにしてくずかごに捨てていましたら、「こんなうれしい大事なものを、何ということを……」と言わんばかりに、主人は丸めたその裏紙に書いた娘の手紙に、アイロンをかけてしわを伸ばし、透明な“クリヤケース”に入れて今も、テーブルの脇に置いています。 今年1月9日、その日は私が東京の本部へ本部講師補の受験に行って帰る日でした。そして、入れ替わりに主人は泊まりがけで講演に行く日になっていました。そんな訳で主人は留守でしたが、玄関に迎えてくれた娘は、「はい、お父さんの置き手紙。一人で向こうで読んで泣き……」とからかうと、向こうへ行きました。小さな紙切れに 「合掌 お母さん、ご苦労様でしたね。今日は宇治神社(二社)の正式参拝でした。ただただ祈っておりました。祈ることが幸せでした。満ち足りて欠くること無き満点を。」と書いてありました。昨日から、いえもっと前からの、そこはかとない不安と緊張で堅くなっていた心に、その小さな置き手紙は暖かく優しく染みわたり、涙に変わって、ありがたさが全身を包みました。 「欠くる事なき満点を」――行き届かないところだらけで、精進の心も浅く、足りないところだらけの私を、いつもいつも「欠くる事なき満点なもの」として拝んでもらっている有り難さを、あらためて思いました。 藤原の父と、4人の娘と、私たち夫婦と7人家族で、笑ったり、おこったりしてにぎやかだったときは過ぎ、今は家族3人。しかも3人が仕事を持っていて、顔を見ないまま、一日が始まる日もあるくらいのあわただしい日々。用件のみの私の手紙にも、少しは心を添えましょう。主人からの置き手紙も、もう4、5通になりました。 <平成12年8月 内報 『宇治』 135号より> *************** (2) 誕生月を前に <2002.7> 「僕がどうして母さんの練成会の『神想観練習』のとき聴きに行きたくなるのか解ったよ」とある日、主人が言いました。そうなのです。2年前、私が本部講師補にならせていただいて、練成会の『神想観練習』を担当させていただくことになってからずっと、主人は、私が話している大講堂の後ろのほうに座って、聴いてくれているのです。ほとんど毎回。 早朝行事が終わって、感謝行が終わって、家に一度帰るのが、7時過ぎ。それから、私の朝食につき合いながら、7時半から始まるBSの、朝の連続テレビ小説をみるのが大方の私たち夫婦の日課になっています。『神想観練習』は午前7時半から始まるので、『神想観練習』のある日は私は家に帰れないまま、担当に入っています。主人は一人でお茶を飲むのもつまらないらしく、BSで今なら『さくら』を見て、それから8時頃から会場の大講堂に現れます。話している演壇から、車が大講堂前の広場に入ってくるのがよく見えて、話しながら私は、“あ、来た来た”と、やっぱりうれしくなります。 担当のはじめの頃は、“慣れない私を応援するために心配で来てくれているのであろうか”と思って、“有り難いなあ”と感謝はしていたものの、“家でゆっくりしていてくれればいいものを……”と申し訳なく思うので、「今までは有り難かったけど、もう家でゆっくりしていてくださっていいわよ」といったものです。そんなとき、決まって「別に母さんのために行っている訳じゃない」といつも言うのでした。父兄参観付き『神想観練習』でした。 「へえー、理由がわかったの。どうして、来てくれるの?」と私。「そのうち書面で……」と夫。「もったいぶらないで、言ってよ」と私。「いやいや、いずれ……」となかなか言ってくれないのです。 最近の『神想観練習』のときでした。テキストの『詳説神想観』の間に、本からはみ出るくらいの紙がはさんであるのに気が付きました。開いてみると夫からの手紙で、 「僕自身、最近までよくわからなかったのですが、これはあなたに恋をしているからに違いない、とわかりました。」と書いてありました。一瞬、誰かがこのメモを見ないかと、恥ずかしさにドキドキして、それからじわーっと……。 結婚36年、同い年夫婦の私たち。2ヵ月お先に私、今月65歳の誕生日を迎えます。 <平成14年7月 内報 『宇治』 158号より> *************** (3) リコーダー、探して! <2005.2> 「おばあちゃん、リコーダーが見つからないんだけど、おじいちゃんに祈ってもらって!」 3学期がはじまって少し経った頃の夜9時過ぎ、長女のところの4年生になる孫娘からの電話でした。3学期になって初めての音楽の授業で、リコーダー(たて笛)を使うというので、明日の準備をしていたところ、どうしても見つからなくて、今まで探していたというのです。失くしものが見つからないと、おじいちゃんに頼んで来て、祈ってもらってそれが見つかって、何度となく助けられていることにすっかり味をしめている孫たちは、また「なくしもの110番」に頼んできたというわけでした。 声の様子で、困っていることがよく伝わって来ました。持ち物を大切にしていない反省が、自分を責めているようでした。私はつとめて明るく、「はい、わかった。今からおじいちゃんにお願いして、祈ってもらってあげるからね。おばあちゃんも祈るしね。必ず出てくるから、安心してね。」と、電話を切りました。 主人はすぐ、祈り始めてくれました。私も祈りました。少し経って電話をしてみたところ、「まだ見つからない」ということでした。 私は笛が出て来る、来ないよりも、10歳の孫娘の“祈れば神様は何でもきいてくださる”という“信じる心”をそこないたくない、という想いが切実でした。孫娘に「必ず出てくるから、安心してもう寝るように」と言って電話を切ったものの、“明日要るのに大丈夫だろうか?”と不安が頭をもたげてきました。主人は、私にも、もういいからやすむようにと言いました。私の祈りはまだまだ100パーセントではないのでした。主人は、私と孫娘と皆の全権を依頼されながら、不安そうでもなく、焦っている様子もありません。ただただ安らいで、神に祈っているだけでした。結果が気になっている私と、ただただ祈りを続けている主人と……。 結局、その日は出てきませんでした。孫は、担任の先生にお願いしてリコーダーを貸して頂いて、その日は切り抜けました。2日、3日、出てきません。3日目の夜、「今日、もうあきらめてリコーダー買いに行ったんだけど、お店が全部休みで買えなかった」と、母親である娘が電話で言いました。ああ、そうか、やっぱり……買うことにしたか……と思いながら、娘と話しているその瞬間「あったぁー、リコーダーがあった!」耳がつぶれるほどの大きな声で、娘が叫びました。泣き笑いとも聞こえる大きな声で、笑っていました。私と電話しながら目をやったところに、あったというのでした。 信じたり、あきらめたり、また信じなおしたりしていた私と違って、信じて祈り続けていた主人のおかげでした。はじめ、出てこなかった日、主人は確かに「いやいや、祈りがきかれるのはこれからだよ」と言ったのでした。“いつまでに叶えて欲しい”というのは、人間の都合を先に立てた思いで、本当の祈りではなく、信じて祈り続けるとき、必ず一番よいときに祈りはきかれることを、また生活の中で教えられたのです。 <平成17年2月 『ネットワーク宝蔵』 130号より> *************** (4) 旅立ち・感謝 <2005.8> 合掌 ありがとうございます。 宝蔵会の皆様とは、『ネットワーク宝蔵』の第1号発刊の頃よりおなじみでありました、夫・榎本恵吾本部講師(祈願部長)が、平成17年7月12日、卒然として今世の使命を終え、霊界へ旅立ちました。 その日も、午前3時に自宅を出て、いつもの通り沢山の方の祈願をし、神想観をし、何もかもいつも通り終え、午後から自宅に帰りました。家族には体調不良のことは見て取れましたので、病院で診てもらうことをすすめましたが、明るい、安らかな表情で、「病気は出たら消えるんだから……」といって、「ありがとうございます。ありがとうございます。」ととなえておりました。家族や親しい人の、声をそろえての何度目かの聖経『甘露の法雨』の読誦が終わったところで、家族のものに食事をとるように言って、横になっていた身体を起こし、正座して「ありがとうございます。」と言っていたと思ったら、後ろへ倒れました。私の腕の中に倒れ込みました。救急車が来たときは、もう心肺停止していたであろうとのことでした。何もかもが夢の中の出来事のようであり、私の心は納得のいくものではありませんでした。 平成17年に入った頃から、何故か私の心に、私の父の故 藤原敏之(元本部講師)が、言っていたことばが浮かんでいました。 「現象ありと思っていると、整った現象ほどそれを失ったとき痛手は大きいよ。仲のよい夫婦とか、豊かな生活とか、現象が思うとおりにいって喜んでいるような信仰では、足下をすくわれるときがくる。」私にとって幸せのすべてであり、存在のすべてであった主人との別れのこととハッキリはしていないながら、“今のうちに、早いうちに「現象なし」を確立しておかなければ……”とはやるような気持ちがしていました。 家族を亡くして悲しんでいらっしやるご家族に、主人は決まって「満点の卒業です。喜んであげましょう。ほめてあげましょう。」と力強く言っていました。久遠生き通しのいのちを教えられていて本当によかったと、今、感謝でいっぱいです。 生長の家総裁谷口清超先生より、『實相光明宮榎森成大居士』という解脱名を賜りましたこと、心より感謝申し上げております。 この度のことを機縁として、私は「人間は神の子であり、霊的実在である」の自覚を益々深め、み教えの中に生かされているよろこびを、一人でも多くの方に伝えていきたいと、切実に思っています。そして、それこそがご恩に報いる道と、思っております。皆様から、生前沢山頂いたご深切、ご協力に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。 <平成17年8月 『ネットワーク宝蔵』 136号より> *************** (5) 冬を迎えて <2006.1> 鮮やかな色彩を放って宇治川の河畔を染め上げ、境内を色とりどりに飾った紅葉が散り、本格的な冬の到来を迎えています。“あれは夏だったなー”と、私の身に起こった人生の一大事のことを、随分遠い日のことのように思ったりしています。 主人 榎本が、生長の家本部から出向という形で(3ヵ月の試用期間)、宇治別格本山にはじめて単身で赴任してきた日が昭和55年7月16日。宇治別格本山の中講堂で葬儀・告別式をして頂いて宇治別格本山最後の日になったのが、平成17年7月15日でした。それはきっちり、まるまる25年間が1日も欠けない年月でありました。四半世紀を宇治で過ごさせて頂き、働かせて頂いたことになりました。 子供のような単純さと、周りの人の心を傷つけることを極度に嫌った繊細なやさしいこころと、言い出したらきかない、一筋縄ではいかないやっかいな性格を併せ持ちながら、楠本総務をはじめ周りの方達に許されて、毎日を味わうことと、曲をかき、文章を綴り、新しい発見とに心をワクワクさせて、幸せに生かして頂きました。 昇天する前々日、研修生の人たちと一緒に、宇治川天ヶ瀬ラインの空き缶やごみ拾いの献労に参加し、大好きだった宇治川の景観に、お礼をしたのでしょう。蓮華寮の裏庭の掃除も、私に代わって丁寧に、きれいに2日前に仕上げてくれ、同じ日、散髪も終え、住まわせて頂いたところも、身体もきれいに浄めて終わりました。何もかも、主人の魂は知っていたのでしょうか。 二人で買いに行った夏のスーツは、昇天した日(7月12日)に出来上がることになっていました。「7月17日の練成講話のとき下ろそう」――そう楽しみに話していて、とうとう袖を通すことなく終わった最後の晴れ着(人生はじめての黒のスーツ)は、自分のための喪服のように、使命を終えた身体を包んで、天にかえっていきました。長い間、皆様、本当にありがとうございました。 合掌 <平成18年1月 内報 『宇治』 200号より> |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(40) 2007/2/22 |
|||||||
平成4年2月末、主人が医師から「肺ガンです」と宣告されました。すぐ入院して検査、そして「手術しましょう」との言葉に、一瞬私は頭が真っ白になりました。 主人は即入院いたしました。 以前、胃ガンになり医術で一応治りましたが、このたびはガンの再発でした。 私は、「魂のふるさと 宇治に行きたい。いや、行こう」と決意いたしました。そして3月の一般練成の日を、指折り数えて待ちました。背水の陣を布いて、宇治本山にまいりました。 早速、榎本恵吾先生に個人指導をお願いいたしました。先生はニコニコされて、 「『あなたは観世音菩薩だったんですね。肺を浄化させてくださったんですね。私の中に愛が、神があったことをわからせていただきました。喜ばせていただきます。うれしい自分だった! ありがたい自分だった! 尊い自分だった』と、自分の内を向いて、自分を喜びなさい」と、教えてくださいました。 「ああ!! ただ喜んで、よろこんで、よろこべばいいんや」 と、心の底から熱いものがぐっとこみ上げ、涙があふれてまいりました。 自責の念にさいなまれ、重くて暗かった私のからだが、宙に浮くような感じで、とても軽くなりました。 先生のご指導通りに、ひたすら祈り続けました。だんだん家族もよろこびと感謝の光が交叉してとても明るい波動に満たされるようになりました。 その一ヵ月後、自壊作用が起こり、肺ガンはすっかり癒やされました。 あれから十五年、八十歳を過ぎました主人は、よろこんで生かされている人生であることを一筋に、今なお現役でがんばっております。 榎本先生に御指導いただきましたお蔭でございます。 榎本恵吾先生から生長の家の根本真理を拝聴させていただきました私は、神の子として新生させていただきました。 私の家は梨を栽培しておりますので、せめて宇治の研修生の方々に梨狩りを楽しんでいただこうと、ほとんど毎年招待させていただきました。その中に榎本恵吾先生のお姿が何回もございました。 あるとき、重い病気をいくつも持って生まれた赤ちゃんの祖父母様が相談に来られました。ブルーシートの上に座られて梨を召し上がってくださっている先生に、思わず大胆にも、 「祈ってあげてくださいませんでしょうか」とお願いいたしました。 先生は笑顔でうなずかれて、研修生の人たちに「『甘露の法雨』を誦(あ)げよう」とおっしゃって先導してくださり、そのあと合掌して実相顕現を祈ってくださいました。 8月末の残暑のきびしい太陽が、色白い先生に容赦なくふりそそぎ、髪の毛が少し薄くなられた頂点が、日焼けで赤くなって行きました。暑い中、汗を流されつつも、しばしも合掌をお解きになられませんでした。 その子はすっかり癒やされ、現在は幼稚園に元気で通っています。 あの梨園での光景が、鮮明に脳裏に焼きついております。感謝一杯でございます。 最後になりました梨狩りのとき、先生は和紙を丁寧に巻かれて私にプレゼントしてくださいまして、家の座敷で拝見させていただきました。 『眞性の人間』ハ 神人にして 神そのまゝの 姿なり (ニコニコマーク入り) 謹写 恵吾 達筆な字でお書きくださっていて、瞬間、身の引き締まる思いがいたしました。次の瞬間、「掛軸にさせていただこう」と思いました。 さっそく近鉄百貨店にお願いして、約1ヵ月後、出来上がってまいりました。 すぐ、掛軸を持って幽斎殿に上がり、榎本恵吾先生に見ていただきました。 ものすごく喜んでくださいました。 その時の様子を、どのように表現させていただいたらよいやら、形容詞が見つかりません。 十日ほど経ちましたら戴きに上がりますと申しまして、再度幽斎殿にまいりました。先生のお部屋に、實相軸と並べて掛けてくださっていました。先生は 「實相の御軸がかすんで見えるね」と申されました。そして、桐の箱の蓋の裏に、「為 西本惇子様 平成十四年十一月十三日 榎本恵吾」とお書きくださいました。また別の用紙に「この掛軸にまつわるすべての人々の実相顕現と幸せを祈ります」とお書きくださっています。先生のご著書『弟子像』、『葩(はなびら)さんさん』も戴きました。 今は、世界中にただ一点のみのお掛軸をわが家の宝ものとして、大切に大切にお守りさせていただきます。 「実相独在」の核を終始お説きくださいました榎本恵吾先生。これからも、私たちをお導きください。本当にありがとうございます。 その後、榎本一子先生からDVDを頂戴いたしまして、繰り返し繰り返しお聞きさせていただき、そのたび、救われております。また、恵吾先生が天界へ旅立たれます朝、お開きになっておられました『人生の扉を開く』のご本も戴きまして、常に私の鞄に入れ、少しの時間にも読ませていただいております。 思い出は尽きません。ありがとうございます。 合掌 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(39) 2007/2/12 |
|||||||
『光のある内に』の中に、高校受験を控えられていた先生が、一本のしおれきったおしろい花に、やかんで水をどんどん注ぎ込まれたら、翌朝にはその葉っぱは、水滴をさえ付ける程にまで生き返っていた。という内容のご文章がありますが、私はそこを読むたびに、まるで自分のことの様に思われてなりません。 先生に出会うまでの私は、自分が生きていることに何の価値も見出せず、生きる目的も、希望も何もなく、時に流され、ただ何となく生きている・・・それだけの人生でありました。 そんな渇ききった私の人生に、先生はあの「おしろい花に水をやる」がごとく、毎日、毎日、真理の水をどんどん注ぎ込んで下さいました。私は、みるみるうちに自分が「神の子」であることの喜びに満たされてゆき、そのまま、ありのままの自分の尊さ、素晴らしさに歓喜いたしました。 現象の乏しさに、失望しか見出せなかった自己への価値感が、360度転回し、「神の子」として私は生まれ変わることが出来ました。不完全な現象の「私」を一切観ず、唯々「生命」を観つづけ、賛嘆しつづけて下さったのでした。 三年間という時を、宇治別格本山の研修生から職員として、なおかつ先生と同部所に席を置かせて頂くという、この上ない有難いご縁を頂いて、渇ききっていた「私」は、水滴を付けるほどの、喜び溢れる「神の子」と化し、そして結婚させて頂くことができました。 結婚してからは、可愛いい三人の子宝を次々と授かり、優しくて私の全てを受け止めてくれる夫との家庭生活は、幸福と喜びで一杯でした。 しかし、何か辛いこと悲しいことがあると、自分の信仰の足りなさを嘆き、先生から言われつづけてきた「喜んでいるだけでいいんだ」 「そのまま喜びなさい」が出来ず、喜べない自分を苛むのでした。“そのまま喜ぶ”ということの重さ、深さがひしひしと身に染み入り、その苦しみの果てには、いつも“悟りたい”があるのでした。 「悟りたい」……悟っていないから喜べないのだ。先生の立っておられる“喜び”の世界に自分も行きたい……!! 悟りは“無い”と教えられながら、頭では納得していながら、心の底では“悟り”を追いかけていました。そして、“先生”を追いかけていました。 生きているだけで素晴らしい事と、喜んでいたかつての私は、時の流れと共に変化し、現象の明暗にいつしか心乱され、やはり「生きていることは辛い・・・」と思うようになっていました。 そんな矢先の、先生の突然の“死”…… 子育てが終わり、人生に一段落ついたら、いつの日か、先生と色々と話したい。そんな日が必ず来ると、何の疑いも無く信じきっていました。それは、全く愚かなことでした。“今、今、瞬間の今”の生命の喜びを語りつづけ、そして自ら生きつづけて来られた先生であったのに……。いつか……、そのうち……は無かったのでありました。 自分の薄っぺらで、いいかげんな日常生活の信仰が露呈され、見事に粉砕されてしまった様な思いでした。 先生は全ての仕事を成し終え、さっさと霊界へ旅立って行かれました。 残された私には、先生の“死”を悲しんでいる間も許されないくらい、待っていたかの様に今迄にない現象問題が次々と押し寄せてきました。 先生と出会って以来、私は神の子と新生し、喜び悲しみも味わい、一進一退しながらも、自分の信仰は着実に積み重なり、生長していると確信し、自負さえしてきました。ところが、何年もかけ積み重ね、生長していたであろうはずの信仰が、この様々な問題で、一瞬にして根こそぎ、津波のごとくに立ちさらわれていってしまったのでした。 何だったのだろう……何をコツコツと私は積み重ねていたのだろうか……? 私の今までの全てを否定され、そして全てをかなぐり捨てられてしまった様な思いに押しやられてしまったのでした。 生まれて初めて味わう、どん底から湧き上がってくる“虚無感”というものが私の心に襲いかかってきました。 深い淵に追い込まれ、先生のビデオに救いを求めました。 繰り返し、繰り返し聞くうちに、段々答えが聞こえはじめました。 「外には何も無い!」 「内に全てがある!」 私がコツコツと積み重ねてきた信仰は、全て「外」であったのでした。 あれほど“現象の無”“実相独在”を教えられながら、私は“現象”を相手にした信仰であったのでした。 外には何も無いけれども、内には全てが在る。 内には、神が創り給うた完全な夫がいる、子供がいる、私がいる。 何も追いかけるものは無い、何も付け足すものは無い、積み重ねていく何物も無い。 今、ここに、完全な全てが在る。 私の内で、答えが鳴り響いてきました。 この完全なる“内なる世界”のほかには、“喜び”も無ければ“安住の地”も無かったのでありました。 先生はご講話の中で、青空太陽と雲の話をよくされましたが、その中で特に、 「このぐちゃぐちゃの雲(こころ)は、放っておいて!」 の所には、真底から魂の解放を得ていたにもかかわらず、自分のこの汚い雲を何とか消したい。きれいな雲を飛ばしたいという願望に、長い間とり憑かれていたのでした。 全く愚かな弟子で、よくぞこんな私を黙って長い間見守り、そして祈り続けて下さったと、今さらに先生の愛の深さ、偉大さに感謝と敬愛の思いで一杯になるのでした。 私は空を見るのが好きで、先生が亡くなってからは特に、空を見上げる回数が増えたように思います。 沈む夕焼けの空……燃えるような、真っ赤な太陽をとりまく雲は、実に美しくあらゆる色で、その太陽と雲は美しくコントラストされています。西の空は、見事な神の芸術として、そこに展開されています。 どの雲も美しく、どの色も美しく…… 太陽の輝きは、あらゆる雲を美しく照り輝かしているのでした。 そんな雄大な空を、感動と共に見上げていると、そのずーっと、ずーっと奥の方から、先生のあのいつもの笑顔が、ぽっかりと大きく浮かび上がってくるのでした……。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(38) 2007/2/8 |
|||||||
合掌 ありがとうございます。 毎朝神想観にて『私の中の榎本恵吾先生(前編)』を、涙でグショグショになりながら感動と共に読ませていただいておりましたところ、私もぜひ『弟子像』を読ませていただきたくなり、ページをめくっております。 平成16年夏、研修生の時、恵吾先生は「誰にも見せないでね!! 」と、『弟子像』を私にくださいました。当時一人で『弟子像』を開かせていただいておりました。感じたことや、納得できたことなどを書いて、恵吾先生にお渡ししたこともあります。でも、そのときはまだ私にはむづかしかったのです。 それが今、どうしても読みたくなり、ページを開いております。ぐいぐい引き寄せられ、没頭しております。 恵吾先生は、私のおそばで「とうとう、読んでくれましたね!! 」と、笑顔のやさしさ、あたたかさで私を包んでくださっている気がいたします。 「恵吾先生!! 今は書いてあることがすごく、すごく分かるんです」 と、お伝えしたい。 こんなことを書いていると、心が涙でいっぱいになるんです。先生のあたたかい雰囲気に包まれて、とても幸せになるんです。 先生、本当に、本当にありがとうございます!! そんな気持ちがこみ上げてまいります。 研修生の時は、ご本のこと「誰にもみせないでね」と言われていましたが、今は「この本で、とても救われています!」と、天国の先生にお伝えしたい。 本当に、本当にありがとうございます。 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(37) 2007/1/31 |
|||||||
生長の家のみ教えに導かれ、宇治一般練成に参加させて頂きました折、 “やあ、よくいらっしゃいました” と満面の笑みと合掌でお迎えして下さいました、慈愛に満ち溢れた榎本恵吾先生……。 時を経て今、静かに目を閉じますと、瞼にあの 満面の笑みと合掌のお姿の先生が、まばゆいまでに煌々(こうこう)たるみ光に包まれて……と言いましょうか、み光そのもののお姿と言いましょうか……言葉に表現しがたい光景が、ありありと瞼に浮かんでまいります。私たち誌友をやさしく導いて下さるお姿を拝することができました時、何とも言えない感無量の涙が頬をつたいます。 現世では、先生のお姿を拝する事がかなわない 一抹の淋しさがありましたが、それもいつしか消え去り、高き霊界より常に、いつも、どこにいても、私達を見守り導いて下さっているという確信が得られるようになりました。 昨年(平成18年)9月、なつかしい宇治一般練成に参加させて頂きました。 その時、練成の受付の玄関に一歩足を踏み入れたその瞬間――夢か、幻か――あのなつかしい榎本恵吾先生のお姿を、ほんの一瞬、拝する事が叶いました。 唯々「ありがとうございます」と合掌する自分の姿に、フト気がつきました。 ありがたく、うれしく、なつかしく、夢中で素晴しい練成を受講させて頂きました。 高き霊界よりご指導賜わります 榎本恵吾先生のみ心を、私たち誌友の心といたしまして、より精進してまいりたく決意いたします。 本当にありがとうございます。 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(36) 2006/12/31 |
|||||||
榎本恵吾先生との出会いは、平成13年9月の伝道練成会のときであった。 当時、悩みを抱えて参加した私は、榎本先生に個人指導をお願いした。そして 「なぜ、どこで私のことを知ったのか?」 と質問された時に、高校生のとき藤原敏之先生に会いたくて宇治の短期&写経練成会を受講し、その後榎本先生と藤原先生のご関係を知ったのがきっかけであったことをお話しし、 「私が子供の頃感じた、何とも懐かしい生長の家を、先生から感じました」 ということを申し上げたときに、先生が何とも嬉しそうな表情をされたのが印象的であった。 当時、悩みを抱えて練成会に参加したのであったが、その悩みも2回の伝道練成会と、その時に受けた榎本恵吾先生の個人指導により完全に解決していた。 月日は流れ、絶好調の状態も長くは続かずに問題が与えられた。こんな時、予定を立てて宇治本山に行くのが恒例であった。しかし、この時はかなり切羽詰まっていたため、いきなり榎本先生目当てに本山に電話をした。先生を電話口にお願いしたのは、この時が初めてだった。伝道練成の時に個人指導をお願いしたのは1年以上も前であったが、名前だけで先生が一瞬にして私のことを思い出して下さったのは本当に嬉しかった。そして、直接お会いしてご指導いただくことになり、翌週の週末を利用して宇治へと向かった。それ以来、宇治に伺う頻度が高くなったこともあり、より親しくご指導をいただけるようになった。 幽斎殿でお会いするたびに、独特のお元気な口調で「おう!どうだね!」と声をかけていただけるようになったのは、この時からである。 榎本先生が強調されていた言葉で大変印象的だったのは 「光明化運動をしないという罪はない!」 ということであった。 実際この部分で躓き、そして榎本先生の言葉で救われた人は多いのではないかと思う。 私は幼い頃、両親を機縁として生長の家の御教えに触れ、特に高校生の頃や大学生の前半までは青年会の組織で本格的に活動をしていた。しかし、数の運動に疑問を感じて活動そのものからは離れていったのであるが、生長の家の教えそのものは大切な糧であったので、そこから離れることは無かった。当時一緒に活動をしていた先輩や仲間たちの多くは、組織のみならず生長の家の教えそのものから去っていった。そういった人たちの大半は、私と同じ理由で、運動や強引なまでの行事への勧誘活動に嫌気がさしたのであると思う。実際、そのように話してくれた人もいた。教えからも離れていってしまった方々に、榎本先生のこの一言を聞かせてあげられたらと、今更ながらに思うことがある。 また、常におっしゃっていたのは 「喜んどればいいんだよ!」 である。 榎本先生が「喜ぶ」という言葉を発するたびに、何か心の奥底から筆舌に尽くしがたい喜びを感じたのを、今でも思い出す。先生のおっしゃる「喜び」というのは、何か特別ということではなく、当たり前に対する喜びなのである。 しかし、先生とお話していると、「当たり前に対する喜び」こそ、いかなる現象が整う喜びと比較しても、超えることのできない喜びであることを、直感的には感じてきていた。 榎本先生の個人指導は、一貫して「實相一元」であった。 ここからは私の所感になってしまうが、實相が實相に対して實相を説く。悩みを持って相談に訪れるのも實相。そしてそれを指導するのも實相。他には類を見ないほどの徹底した實相直視であった。たいてい個人指導というと講師が信者を指導する。導くものと迷えるものが存在すると考えられがちであるが、先生のご指導は他とは根本的に違った。不思議なくらい癖がない。構えなくて良い。とっても自然であった。 そんな経緯でようやく先生から親しくご指導をいただけるようになってきたが、平成17年の2月以降、先生とお会いするのにどうしても予定が合わない時期があった。何度電話して日程を相談しても、先生のご都合が悪かったり、先生のご都合は良くても、他の人が来るので一緒ならば良いが、個人相談という形では難しいというようなことが続いた。 そんな時、「これから長い付き合いなんだから」(あせることはないという意味であろう)と電話で言っていただいた。 何度か電話をしていて、「5月にみんなで集まる機会がある」との事を伺っていたので、ゆっくりとはお話ができないのは覚悟でお邪魔した。その時は、先生と個人的にはほとんどお話はできなかったが、榎本先生を慕う多くの先輩方に出会い、そして会食をして大変楽しい時間を過ごすことができた。 しかし、この時が先生との今生の別れとなるなんて私は夢にも思わなかったし、誰もがそうは思わなかったであろう。 7月に会社の夏休みを利用し、宇治に行こうと思って7月4日(月)に電話で榎本先生のご都合を聞いた。7月17日(日)~20日(水)の3泊4日の間、練成会の受講も兼ねて先生にお会いすることにした。先生もほとんどの時間帯でご都合が良いとのことで大変嬉しかった。 しかし、喜んだのも束の間であった。7月13日(水)の仕事中、携帯に電話が入った。そのときは会議中であったので出ることが出来なかったが、夜帰宅してみると石田さんからの連絡であったことがわかった。石田さんに折り返しの電話をする直前にたまたま自分の携帯を見たら、そこには東京第一教区の青年会の方から、既に訃報の連絡メールが届いていた。事の次第を理解できないまま、石田さんに電話した。そこで事実であることを改めて認識した。動揺したまま葬儀の日時と場所を聞かされる。 夜もそれなりに遅い時間ではあったが、会社に急遽私の夏休みの時期を変更してもらうように依頼し、翌朝宇治へと向かった。 榎本先生とお話したのは、7月4日の会社の昼休みに携帯電話で、7月17日にお会いする約束をしたのが最後となってしまった。 現在は勤務場所が変わったが、少し前までは電話をした場所の近くを通るたびに当時のことを思い出していた。 ご冥福を心よりお祈り申し上げます。 平成18年12月31日(日) |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(35) 2006/11/19 |
|||||||
「それではみなさん、こうありたい、こうなりたいと思う願いを心の中で強くお念じくださーい」と言われたかと思うと「この人達の罪を清めたまえ!」と先生は右腕をさっと上から振り下ろされた。 その瞬間、私の身体はモーレツな圧を受け、吹き飛ばされそうな衝撃を受けた。 それは新練成道場での榎本先生の祈りあいの神想観のときのことである。 私は前列、左端に座り祈ってもらう側にいた。 その瞬間、急に胸に圧迫を感じ普通の呼吸が出来なくなった。どうなるんだろう……。私は怖かった。私の右に座っている男性の呼吸も急に荒くなった。その向こうに座っている女性はすすり泣きを始めた。 神想観が終わり席に戻った。祈る側にいる女性の数人は涙をぽろぽろ出していた。 私はしばらく呆然としていた。緊張で両肩がこわばり重苦しい感じがあった。 私はその後、帰路についた。 時間の経過と共に、両肩のこわばりは消えていき、それと同時に私の中の邪念はきれいに消え去った。 私が生長の家にふれたのは、今から九年ほど前。 郵便受けに入っていた『白鳩』誌の中で紹介されていた『自己完成のために』と言う本を読んでみたくて、教文社から取り寄せた。そのなかの“認めたものが現れる”という一節に新鮮な感動を覚えた。そして生長の家に徐々に興味を持つようになった。 その年の十一月、私は初めて一人で宇治別格本山を訪問した。二十代の頃から一度はお寺で修行してみたいという漠然とした夢があった。そして何よりも気分転換をしたかった。その頃、子供のことで悶々としていた。 そしてそこでお会いして、強烈な印象を受けたのが榎本恵吾先生であった。 私は榎本先生の講話が大好きだった。しばらくして(数ヶ月して)先生は練成部を去り幽斎殿へ行ってしまわれた。 私は一般練成の七日目の夜に行われる先生の講義「実相なるもの」を拝聴したくて一泊二日で宇治に行った。 先生は講話の際、こちら(聞き手)の様子をよく見られていた。 私たちの反応を観ていた。 先生はぼそぼそと小声で話されているかと思うと、突然、急に大きな声で、わーっと話されるのであった。 先生は、時に天界の人でもあり…… また娑婆の人でもあった……。 あるときは、ぴょんと跳び上がり床をドーンと足でたたいた。 私はぐんぐん先生の講話に引き込まれていった。 喜びが、ふつふつと湧き出てきて やがて、私たちの喜びは先生の喜びとなり 先生の喜びは私たちのものとなり そして歓喜が、爆発した…… 歓喜は、おおきな光の輪になり 私たちは、みんな、おおきな光に包まれた。 食堂での昼食後、先生はいつも同じ場所(入り口から左奥の方)に座り、ゆったりとくつろがれていた。先生ご自身で描かれるニコニコマークのようなお顔をしていた。 一言お礼を申したいという衝動にかられる時があったが、おくつろぎのところ、じゃまをしては失礼と遠慮させて頂いた。 今にして思えば、勇気を出してお礼を申し上げるべきだったと思う。 榎本先生、本当にありがとうございます。 「皆さん、神にお返ししなければ、なんて考えるのは神を冒涜していますよ。神はそんなちっぽけなもんじゃないっ!」 「喜ぶことを遠慮してはいけません!」 「死ぬ気になって、プライドを、すべてを、捨てるのですっ!」 今も先生のお声が私の心に強くひびく。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(34) 2006/11/19 |
|||||||
合掌 榎本恵吾比古命の御霊様、貴殿が昇天された報に接し、洵に吃驚致しました。御健勝にて御活躍のことと思って居りましたので、とても信じられるものではありませんでした。御生前の御厚誼、ありがとうございました。貴殿のなごやかな笑顔を思い浮かべつつ心からお別れを申し上げます。“さようなら”。 本部時代、ご一緒に編集の仕事をした折のことなど、なつかしく思い起しました。又、八雲(目黒区八雲の本部職員寮)での楽しかった日々など……。 宇治での長きに亘っての、貴殿の貴いすばらしい御仕事、御指導、折々に伺って居りました。ありがとうございました。 御恵贈いただいた御貴著『弟子像』改めて、しみじみ拝読させていただきましょう。貴殿は、為すべきことを為し終えたのではないかと思考いたします。サッと逝かれた、まさに高級の御霊であられたのでしょう。心から御冥福をお祈り申し上げます。 御奥様、御子様たちを高き処からお守り、お導きくださいます様に。どうぞどうぞ……。 現象なし、物質なし、肉体なし。實相独在、生き通しの生命のみ。貴殿は、このことを見事に証しされたのでしょう。大聖師谷口雅春先生の御教えそのままを生き、逝かれたのでしょう。小生もそのうち、大聖師の御許に参ることでしょう。そのとき迄、しばらくお待ち願います。 御遺族皆様方の今世の御多幸を心からお祈り申し上げます。 お別れのご挨拶が遅れましたことをお赦し願い上げます。 弔歌 御佛(みほとけ)の慈悲の御ひかり浄らけく 蓮華(はす)の台(うてな)を包み給はむ 合掌 平成十七年七月二十六日 内海靖浩謹書 大兄 榎本恵吾御霊様 (思い溢れるままに。乱筆お許しあれ) |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(33) 2006/11/10 |
|||||||
何年か前の冬の夜、歌の仲間達を、榎本先生の御自宅に寄んでくださり、奥様の鍋料理や四女の妙子ちゃんの手作りのスコーンをいただいていた時のことです。誰からともなく環境問題の話題になりました。その時、榎本先生が、 「環境問題も大事だけど、あれもだめ、これもだめと、小さく縮まっていくんじゃなくて、諸君達には 創造する生活、生み出す方向に生活していってもらいたいものだね」とおっしゃいました。私にはその言葉が非常に印象に残りました。この頃あの言葉が、私の生きる指針になっています。 先生の奏でる和音が好きでした。榎本先生は、 「和音というのは、一つ一つバラバラの寄せ集めじゃなくて、“一つ”が先で、そこからさきはえて一つ一つの音になっているという感じで弾くと、なんとなくいい感じになるんですよね」という風によく言われていました。先生の弾かれる和音というのは、ガチャガチャした感じが全然しなくて、一つ一つの音が納まる所に納まったような大調和の音だなあと いつも思っていました。 私は長い間、暗い煩悶の生活の中に居たので、初めて聖歌練習に参加した時、今までの生活とのあまりのギャップからか、歌うのに苦しくてなかなか思うように声も出せませんでした。そして練習が終わった時、先生が近づいて来てくれて声をかけてくださり、肩をポンとなでていってくれました。その時、ああ、先生は、今まで私が苦しかった事も歌が好きな事も、全てわかってくださっている・・・と感じました。 いつからか、先生は私に、『アルト』を担当するように勧めて下さいました。それからは歌の度に、「アルト、アルト」と言っては私の顔を探して下さり、「こっちこっち」と、アルトの位置に促してくれました。その度、大切にしてくださってありがたい気持ちでいっぱいになりました。普段は引込み思案で恥ずかしがり屋ですが、楽しさと喜びと、自信のようなものを導き出して下さいました。先生の歌の集まりは、下手なものを上手にため直していくというような観点からは逆の極点にあり、「そのままでよい」ものの、魂の開放だからだと思います。 先生の愛念とか思いというのは、本当に神そのままに、至大無外 至小無内に、無限に大きく拡がり、又内には、接する一人一人の心の思いや傷を暖かく細やかに包んで下さいました。 先生が亡くなられる一月前、山登りの前日(六月十三日)に、我が家の玄関まで、初めて先生と奥様がわざわざ訪ねてきて下さいました。妙子ちゃんの結婚の内祝いの陶器を持って来てくれました。そして、玄関に飾ってある、先生の『自性合掌』と書かれた書を見られて、 「ははあ、飾ってくれてるねえ」 と喜んで下さいました。その頃 私は、家の近所の、引きこもりがちの青年から言いがかりをつけられて、憂鬱な気分でいた時で、先生にその青年の事を祈っていただいておりました。先生は、玄関を閉じられた後、近所一帯を祝福するように少し歩いて回って下さっているようでした。それが私への最後のあいさつとして来ていただいたんだなあと今になって思われ、本当にありがたいです。 七月十二日の夕刻、主人がいつもより一時間程遅く帰宅しました。「榎本先生が調子が悪いそうなのでお見舞に行って来た」とだけ言いました。そして、主人は、近所に住む本山員で、先生と特に親しい方達に一応知らせてくると言いました。私は、それじゃあ明日の神想観はないかなあ、ぐらいに思っていました。そして普通に夕食を食べ、二人共いつの間にかうとうととうたた寝をしていました。 夜八時頃、電話の音で、我に帰りました。同じ神癒祈願部の方から、 「榎本先生が危篤状態になった」 と知らせていただきました。私はびっくりして顔が真赤になってしまいました。 不思議だったのは、目覚めた時、何とも言えないような、神様に包まれているような、心安らかな暖かい気持ちで目覚めたことです。主人も私もそんな感じを受けました。それはきっと、榎本先生の魂が家を訪問してきてくれて、祝福していってくださったからだ……と直感しました。 榎本先生には、私が何か心配事や悩みがある度、祈っていただきました。よく主人に、 「先生に祈ってもらうようにお願いして」 と頼んだものです。本山内のため、神癒祈願も手渡ししていただいて、その封筒にはいつもニコニコの絵と、一言を書き添えてくださいました。 最後の月に書いてくださった言葉は、『自性幸福』でした。これからはこの言葉を胸に生きていきたい……。 先生がお亡くなりになり、一年以上経ちました。始めは、ショックが大きく、不意に涙が出ましたが、それから月日が経つうちに、榎本先生が、全ての人や事物を祈ってくださっているのが確信されて、日々先生とともにある、という感覚で過ごさせていただいております。 幽斎殿の神想観があった10時と1時の、特に神癒祈願の祈りがあった10時25分と1時25分頃になると、何をしていてもふと、時計に自然に目が行って、「あ、またこの時間だ」と気付くので不思議です。 また、先生がお亡くなりになり、心が塞ぎ、生活に摩擦が起きそうになったり、迷いが生じて来ましても、近くの縁のある神社でおみくじを引きますと、その度まるで先生からのメッセージと思われるような御言葉が出てきたりして、おかげで、踏み外す事もなく、喜び、祝福の日に変えていっていただいております。本当にありがたいです。榎本先生のお導きは今も続いていて、全ての人を暖かく守り導いてくださっておられるのでしょう。 ありがとうございます。 合掌 《追記》 ある時、先生は練成講話の中で、 「練成の練は『糸偏』、鍛錬の錬の金偏ではない。金属のようにたたき直されて良くなるのではなく、糸というのは始めからずっと変わらず同じ太さで、練成に来る前からも帰ってからも、ずっと同じものが続いている」と言われていました。 それを聞いて、なんだか嬉しくなりました。 以前、個人指導で榎本先生が話してくださいました。 「花は、ただ咲いているでしょう。自分から、どうです、私きれいでしょう、と花のほうからは言っていない。花はただ喜んで咲いているだけでしょう。その喜んでいる姿を見て、蝶ちょが嬉しくて飛んで来るんでしょう。」 当時、一度別れを経験し、心が淋しさでいっぱいだったあの頃、私の心を優しく諭すように……。 初めて研修生になる前には、 「本山に光をもらいに来るんじゃなくて、あなたが、本山に光を与えるということなんですよ」 とおっしゃってくださいました。 近頃は、ただ単に神癒の祈りの時間に時計に自然に目がいくというだけではなく、偶然にも、家事など何かしていて一息ついた時とか、ほっとしてお茶などを飲んでいる時とかに不思議と重なるのです。それは本当に、あくせく過ごすことからほっと自分が解放され、許された時間と重なるのです。榎本先生が、「ゆっくりしてもいいんだよ、許されきっているんだよ」と言ってくださっている気がします。 「(本当の)自分を大切にね」と……。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(32) 2006/11/10 |
|||||||
〈この体験は、平成10年の5月の伝道練成のものです。 最近家の片付けをしていた時に、みつけた感想のメモ書きをタイプしたものです。〉 初回の伝道に出かける前に、講話を聴いていたとき、少し緊張するかなという感じがあったのだけれど、バスの中で榎本先生が「交差点さん、ありがとう。みえる全てのものを祝福して行きましょう。」と仰った時、見失ったものが戻って来た感じがして、「ふわぁ~」と楽なところに行ってしまった感じがした。使命行進曲を先生の音頭で歌ったり、「私は神だぁ~。神がやって参りましたぁ。」という元気の出る澄み通った明るい掛け声をみんなで復唱したりと、行く途中から、よろこびが溢れていました。 そのせいか緊張もなくなり、平和な気持ちで、ただ祝福に行ったのだけれど、祝福に取り巻かれていた感じでした。 二日目の伝道も、とても素晴らしかった。 招神歌を歌っている時、そばを流れる小川のせせらぎが聴こえた。一瞬心の中に水の流れが観えた。その水面が光を浴びて揺らいでいる様が、喜んで笑っているように感じられた。その時、「味わう」って、こういう事かなという思いがよぎった。 訪ねたおうちの方もみんな素晴らしい人たちばかりだった。 「みんなトッテモ幸せなんだなぁ。」「おめでとう。」という感じが起こった。 そして伝道途中、先生の指示で、お地蔵さんの前で一緒に回った3人でお祈りしていた時、明るくて、あったか~く、丸まった感じがして、4人でニッコリしているような楽しさがあった。とっても豊かな祝福伝道をさせて頂けて、とってもとっても嬉しかった。 この頃の伝道練成は榎本先生が担当でした。伝道担当になった時、楠本先生から「あんたが受けるつもりでやりなさい。」と言われたそうで、初心を忘れず、先生は時間の許す限り、他の講師の講話も、一番前の左端で、練成員と一緒に聴いていらっしゃいました。 早朝行事の時も、練成員と一緒に座り、みんなの座るところまで眼を配って下さっていました。 今考えると、恵吾先生の祈りに包まれて、その中で伝道に行っていた気がしています。ひとつ家族のような温かさと、愉快な雰囲気が満ちる伝道(祝福)実践でした。 そして先生にとって祈りとは、生活そのものであり、生きていることそのものだったように思わせて頂いております。先生ご自身は特別祈っている意識は無かったと思うのですが、存在そのものが、全てが真存在(真理)の祈りだったのではと思わせて頂いております。だから先生が眼に写るだけで、心が清々しく浄まった感じがしていたのだなぁと、あらためて思わせて頂きました。先生はご自分の全存在をかけて、祝福の真のすがたを、教えて下さったのだと思うと、胸が温かいものでいっぱいになります。ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(31) 2006/11/10 |
|||||||
「現象は良くするのではなくて、ナイということをハッキリさせないといけないよ。」 宇治本山の地下食堂で、先生は静かにそうおっしゃった。そのときは練成中で、神奈川から来た失業中だという男性と同席していた。緑色の湯呑みを手に握りながら、奥のテーブルに二人で並んで先生のお話に耳を傾けていた。たしか、夕食後のひとときであったと思う。 僕は口を開いた。 「一切ごまかしのない、良心の苦しみのない生き方は・・・」 とそこまで言ったとき、先生が遮られた。 「それはできないだろうね。」 と穏やかに頬笑まれた。 「それができたら神ということだからね。」 何か温かいものが胸にひろがる。大丈夫だ、できなくても生かされているよという響きがその余韻にあったからである。 榎本先生の講話に、なぜあんなに新鮮さを感じたのだろう。それは、今までに聴いた宗教家や教師の話と根本的に方向性が違うからなのである。それらの先生方は、幸福になるための条件を説き、その条件を整えるための努力を奨めるのであった。 榎本先生は、「はじめから生かされている」と説かれた。無条件なるものを味わうように導かれる。實相をよろこびなさいと。よろこんでいいのだ。よかったのだと。大いなるゆるしの雰囲気であった。何か、解放というものを感じるのである。演壇に立たれている先生は光顔巍巍(こうげんぎぎ)たる姿であった。 先生の御姿を拝していると、人間はいのちの本源のよろこびに帰り着くだけでよいのだという気がしてくるのである。 先生には謎の部分がいまだにある。よくわからないのである。しかし、それでよいのである。底知れないのが人物の魅力なのであり、底が知れてはかえってつまらぬものである。 座談会を始めるとき、先生は、どんなに天気が良い日でもカーテンを閉めるように言われた。僕もカーテンを閉めるのを手伝ったものである。開けたままの方が、窓から自然な光が入って明るいのになぁと思ったものだ。閉めるから当然の如く部屋が暗くなる。そして、電灯を煌々とつけるのである。大講堂の隅の方で座談会をしたときも、先生ご自身の近くのカーテンだけでなく、講堂すべてのカーテンを職員の方に命じて閉めさせておられた。僕も“?”マークを頭の中にいっぱい浮かべながら手伝った。あれは何だったのだろう? とうとう御生前中にはきけずじまいであった。 先生が帰宅されるついでに車で駅まで送って下さることになったときのこと、「ちょっと遠回りをしよう。」とおっしゃった。ところが、川上の方に向かった車はどんどん宇治を離れていく。こんなに遠くまで来て大丈夫かなぁ――と思ったが、ほとんど大津に近いところまで来てしまった。綺麗な水辺で葦のような植物の生えている景色のいいところまで来たのである。 「せっかくだから、少し降りましょう。」 と言ったのであるが、 「いやぁ、めんどくさいネー」 とおっしゃり、突然ハンドルを切って踵を返すようにUターンしてしまった。あれも何だったのだろう ?? 今度、あの世で会ったらきいてみたい。 榎本先生は、時々、ドキッとさせられるようなご指導をされた。 ある座談会でのこと、ノイローゼのような女性が、か細い声で何か質問した。何を質問したのかは聞き取れなかった。先生は即座にお答えになった。 「神がわかる必要はない。わかってから生まれて来たんじゃないんだから。」 また女性がかすれた声で何かきいた。 「神を信じる必要はない。神の方でこちらを信じてくれているだけで十分だ。」 と平然としたものである。多分女性は信仰への疑念をもらしたのであろう。このとき、先生の中に巌のように堅い信仰の実体を感じた。静かな語り口だったのだが、忘れられないほど強い印象が残った。 幽斎殿の一階のテーブルのところで、僕は前から気になっていたことを先生に尋ねた。お世話になった予備校の先生が、唯物論者だったからである。様々な宗教書を読むと、唯物論者は死後地獄へ行くとか、無意識界で眠り続ける、と書いてあったからである。 「以前お世話になった予備校の先生が唯物論者で、神は無いと教壇で豪語していました。彼は死後どうなるのでしょうか。」 榎本先生がお答えになって曰く、 「神様は唯物論者を通して、“私は無いよ”と消えておられるのだよ。そこに無我なる光があると思うね。」 先生はどこにも闇を見ておられなかった。唯物論者の中にさえ、聖なる光を拝まれる先生は、まことの光一元の師であると言えるだろう。 先生とお会いした最後の日のことである。幽斎殿の祈願室のところで、「宇治の名木百選」というビデオを先生に頂いた。樹木を愛されていた先生のことだから、さもありなんという感じであった。先生は木々に顕れた神の生命をひたすらスケッチされたらしい。そして、それらをビデオ撮影されたものだそうである。その日は時間がなく、すぐに、先生と車で駅の方へ向かった。京阪宇治駅前で、車に乗られた先生と握手していただいたのが、今生の別れとなってしまった。 しかし、これで本当に最後ではないのだ。 生命は永遠である。 いつか時の輪の接するところで、 またお会いできると信ずるものである。 〈後記〉 榎本先生のご生前、僕は礼状一本書いたことがなかった。(酒は何本も持っていったのであるが・・・)それが今回少し多めに投稿しているゆえんである。先生は、気取らなかった。飾らなかった。威張らなかった。 自分は堅く信じていても、それを人に押し付けようとしなかった。 先生のようであれるか――、 と問いかけつつ 地上の歩みを続けていこう。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(30) 2006/10/25 |
|||||||
十年ほど前のことである。仕事上の悩みで苦しんでいたとき、毎週のように伊勢神宮の荒祭宮で午前中一杯祈っていた時期があった。帰途、草餅を食べさせる茶店においてあった神誌を見て、宇治に向かったのである。 榎本先生は、ある座談会のあと「いつでも来なさい。」とおっしゃって下さったので、当時働いていた大阪南港の職場から、 「明日、何時頃に幽斎殿にいきます」と先生に電話したのだった。ところが、宇治に着いて末一稲荷神社に参拝していると、背後の参道を走る車の音がする。振り返ると、ブロロ・・・と無情にも榎本先生の車が参道を下っていくではないか。完全に忘れられているのであった。日頃の行いが悪いと神の心にかなわずこうなってしまうのである。その日はしょんぼりして帰途についた。 それ以来、先生に会いたいと思ったら即電車に飛び乗ることにした。幽斎殿の一時の神想観に間に合いさえすればよいのである。三十分間の神想観後、先生と一階に降りると「ちょっとそこで待っていてください」とソファを指さされ、しばらくすると祈願用紙の束を部屋に置いて戻ってこられる。そこでテーブルの花瓶をはさんでしばしお話をしてくださった。もっとも、ソファで僕を待たせていることを忘れ、そのままご自宅に帰ってしまわれたこともあったが、今では懐かしい思い出である。 「無い、無い、無い。“無い”と言えるすべては無い。“無い、無い、無い”という連続も無い。その“無い”ということも無い。」 とまことに澄んだ雰囲気の中で話された。取り巻く空気が軽く涼しいのである。その生命的な感じは完全に言葉で言い表すことが難しい。 先生のところへ3,4か月に一度ぐらいのペースで通っているうちに、ソファでの歓談後、ご自宅にまで連れていってくださるようになった。平等院の近くであった。 ご自宅に着くと、先生はお酒かビールを必ずお召し上がりになり、僕はコーヒーかお茶でお相手をした。僕は酒が飲めないのである。先生はスルメや柿の種やピーナツを出して下さったものである。それらをポリポリと食べながら、実に様々な話をした。そのうちに先生がねむそうにされる。その頃を見計らってお暇するのが常であった。 先生がねむそうにされない日は、そのまま宇治橋のたもとにあるサイゼリヤに行くことが多かった。先生は必ず入口に背を向けて座られ、たいていはステーキとワインを注文された。僕は赤いスパゲティーを注文し、絵の具でも溶かしたような緑色のソーダ水を飲んだものである。 先生の不思議なところは、僕に神想観をしなさいとか、聖経をよみなさいとか一度も言わなかったことである。十年近くお付き合いさせて頂いたのだが、一言もない。そういえば感謝しなさいとか、拝みなさいと言われたこともなかった。先生は徹底的に恬淡であった。 ただ、「『生命の實相』は原典を読みなさい。編集してまとめたものは雰囲気が違う。」とかなり厳しい表情でおっしゃった。「もとの清らかなおさまりから切り取ってくるのは違う。」「引用された文章は元に帰りたいといっているよ。」とも。 谷口雅春先生の御文章に対する榎本先生の厳粛な崇敬の念を感じないではいられなかった。 先生との対話の内容は年々変化していった。最初のうちは、僕が日頃の悩みを打ち明け、それに対して先生が真理の話で答えてくださるという形だったのだが、先生と何度もお話するうちに、先生も全く悩みから解放されて生きておられるのではないことが感じられてきた。先生はいつもにこやかで淡々とされていたのであるが、ジッと対座していると、先生の言葉の端々や表情から、胸の内にある様々な想いが伝わってくるのであった。 僕は、先生と会っているときは自分の悩みの暗い話はやめようと思うようになった。 後年は、古本屋の話、うどん屋の話、コーヒー屋の話し、旅先の話をし、先生はおもに聞き役になってくださった。この頃になると、信仰の話もほとんどしなくなり、お会いしてもあっさりと世間話をし、近況を話し合ってしばらく散歩して駅でお別れするという風であった。宇治本山の裏の白山神社に参拝しはじめたのもこの頃である。先生はしきりに樹木の前に立ち止まって枝々の連なりを眺め、幹に手を当てておられた。木々の生命と語らっておられたのかもしれない。 先生の中には年齢を超越した何かがあった。お会いしているうちに、先生が自分の父ほどの年齢の方であることを忘れさせられた。 先生は宗教家として偉大な業績を残されたが、そうしたことを抜きにしても、人間性の素地そのものが美しかった。 大阪の北浜でコーヒーを飲んでいたとき、携帯が懐で鳴った。訃報であった。 四女の妙子さんが連絡してくださったのである。僕は呆然とした。次の瞬間、もっと先生孝行しておけば良かったという想いが痛切に湧いてきた。喫茶店を出て京阪の地下通路を歩いていると、フッと先生の気配を感じたのである。 先生だ!と思った。 しばらくそこに立ち尽くしてしまった。 僕もいつかは地上を去る日が来る。 あの世に帰ったら、今度は僕が先生にご馳走して差し上げたい。地上ではさんざん奢っていただいたのだから。 《後記》 僕は幸運であった。 仕事が学習塾であったから、夕方に帰ればよかった。平日の真昼間であっても、宇治に行けた。先生と生活時間帯が完全にズレていたのが幸いしたのである。僕は先生が起床される頃に就寝する生活であった。 榎本先生のことを想うと、もっとこうして差し上げればよかった。ああ、いらないことを言ってしまったと後悔だらけである。 これも、来世以降の宿題であろう。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(29) 2006/10/24 |
|||||||
榎本先生、ありがとうございます。 数年前 先生の著書「弟子像」を拝読した時、私も先生の良き弟子になれればと感じたことを覚えています。 私にとって生長の家の御教えは 又、榎本先生のご愛念であったように思います。 いろいろな困難に出会った時も、先生とご一緒に、むしろ喜びに変えて来たように感じます。 これからは 私の心の中に神様、榎本先生が常にご一緒に居られることを忘れず 明るく、元気に、そしてニコニコ顔で頑張っていきたいと思います。 先生、本当にありがとうございます。 合掌 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(28) 2006/10/24 「『月光』 にわが友を偲ぶ」
和歌山県新宮市 山中 照也
|
|||||||
今朝、テレビから「月光」が流れてきた。演奏者は、スティーブン・コワセビッチ、彼の弾く曲を聴くのははじめてだった。素晴らしい演奏であったことは言うまでもない。 第3楽章に曲が移ったとき、僕の遠い記憶の中の榎本恵吾が突然脳裡に現れた。いつものあの笑顔だった。 憶えているだろう、あの時のことを。僕たち高校3年の秋だった。千穂小学校講堂での山崎寿子さんのピアノリサイタルを、二人で聴きに行ったことを。2年先輩の彼女は、当時東京芸大在学中だったが、その時の演奏曲は紛れもなくベートーベンのピアノソナタ「月光」であった。僕たちは乏しい知識で批評めいたことを語り合い、楽しい青春のひとときを過ごし、彼女が新宮高校合唱部の恩師のご息女であったことが、僕たちの誇りであり、憧れでもあったことを共に喜んだことが、ふと甦ったのだった。 あれからもう50年も時は流れてしまい、君は何を急いでか逝ってしまったが、しかし君は僕の記憶の中では褪せることなどなく生きているのだ。 君との思い出は、高校の合唱部での活動、生徒会長としての君の活躍、僕の下宿での数々の出来事など、懐かしい思い出があり、卒業後の数年間、それぞれの道を歩みながらよく語り、ときには酒を酌み交わし、歌を歌ったりよくしたね。 ある時、君は焼きおにぎり7個持参、僕の下宿で1週間瞑想を続けたことがあった。すごいやつだと、そのとき思ったのだった。 君は意志を貫き、君の道を邁進し、その目的を成し遂げた。そして多くのよき人たちに惜しまれ、天に召された君を想うとき、誇らしくもあり、万感胸に迫るものがある。多くを語ることができないことを許してほしい。 「月光」に君の面影と遺徳を偲びつつ、ご冥福をお祈りします。合掌 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(27) 2006/10/22 「永 遠 に、御 霊 と 共 に」
東京都杉並区 岡 正 章
|
|||||||
(一)誓いの血書をしたためられたという榎本先生 およそ半世紀前、日本国の危機が叫ばれていた時代、昭和三十三年の十一月―榎本恵吾先生も私も学生時代でした。今の本部会館ホール(当時は「大道場」と言った)で行われた、谷口雅春先生のお誕生日をお祝いする生長の家青年会東京都支部の「文化祭」で(谷口雅春先生の御前で)、私は「街頭伝道形式による青年の主張」というテーマで演説をさせていただきました。そのとき私はまだ恵吾先生を知らなかったのですが、恵吾先生は私の演説を聞かれて、帰ってから血書をしたためられた――「自分はこれから生涯を通じてあなたと共に歩むことを誓う」ということを書き、指を切って血判を押されたそうです。(その現物は私に見せられることなく、どこかへ行ってしまったということですが……) しかしながら恵吾先生の生前には、私がまったく愚かで不敏で、そんなひたむきなお気持ちに万分の一もお応えることができませんでした。 しかし、魂は永遠です。これから永遠に、恵吾先生の高貴な魂と一つになって、「われ光なり」の自覚でお仕事をさせていただきたいと、思っているのです。 (二)伝家の宝刀、本を生み出す (一)から約二十年後。〝「命をかける」とは、「生活をかける」ことだ! 『理想世界』一〇〇万部達成のために、生活を懸けて、命がけでがんばるのだ!〟 と、〝猛烈〟 な嵐のような青年会運動、「『理想世界』百万運動」を展開していた時代。 「いや、〝『生長の家』に命をかける〟 とは、『今すでに完全』な 『久遠の今』に、『実相独在の真理』に命をかけることだ! 今、よろこぶことだ!」 との魂の叫びから、「天地(あめつち)の初発(はじめ)に立ちて―人類光明化運動の楽的(がくてき)展開論」など 〝いのちがけ〟 の文章を、その頃、 〝ガリ版刷り〟 でひたすら刻んでいた榎本恵吾青年……昭和五十三年ごろのことです。 私は当時、『理想世界』誌の編集長として「いのちがけ」の気持ちでその編集に打ち込むとともに、その二十年ほど前に存在した「理想世界合唱団」の復活、さらには「生長の家混声合唱団」から、男声の加わった新しい「聖歌隊」の結成に奔走していました。 「男こそ、歌うべし!」の呼びかけに呼応して、真っ先にその混声合唱に加わってくださったのが、当時青年の榎本恵吾先生でありました。 「この日本の危機の時に、聖歌なんか歌うよりも、軍歌をうたって、日本をまもる運動にいのちをかけるのだ」というような「『理想世界』百万運動」の嵐の中で、「聖歌隊」を結成するのにも、また「いのちがけ」の気持ちが必要なような時代でありました。 私はそうした中で、榎本先生の前記論文「天地の初発に立ちて――人類光明化運動の楽的展開論」などを見せていただき意気投合して燃え上がり、これと私の「よろこびの歌をうたおう」という講話録を合わせ共著にして自費出版しよう! と話し合いました。 しかし、当時、本部職員の給料は安くて蓄えはなく、自費出版などする費用の出所はありませんでした。 そのときわが家には、文字通りの「伝家の宝刀」がありました。祖先伝来の日本刀を、父が軍人であったから「軍刀」にしてあったものです。これを「美術品」として骨董屋に持ち込み、金に換えると、ひょっとすると百万円くらいになるのではないか。それを自費出版の費用に充てよう――。 そう考え、とらぬ狸の皮算用で「背水の陣」を布き、印刷屋さんに原稿を持ち込みました。本のタイトルは恵吾先生の提案で、『光のある内に』としました。「内なる光」を信じよろこび輝かそう、との趣意からでした。 組版・校正刷りまで出してもらった段階で、さてと新宿区の骨董屋さんを訪ね、「伝家の宝刀」を持ち込みました。「買ってほし。美術品として、いくらの値がつくでしょうか……」と。 結果は意外、全くだめでした。これは、「美術品」として売れるようなものではない。そのまま、祖先の形見として家に置いておいた方がいいですよ、と言って、買ってくれようとはしません。 困りました。が、本の方はすでに組版まで終わっています。 仕方がない。借金してでも、何とかしましょう――ということで、校正を進めました。 そして、「この中には谷口雅春先生のご文章の引用がたくさんあるから、谷口先生に、原稿のままでは読みにくいのできれいな校正刷りをお送りし、お許しをいただいてから出版するようにしなければ……」と、かねてから考えていたことを実行にうつしました。 ――雅春先生から、お返事がきました。 「拝啓 『光のある内に』の校正刷来ました。とても全部よむ時間がないので、ところどころ読んで自分の書いた本の一節を再発見し立派な本だと思ひました、何故これを自費出版に限定したのかと不思議に思ひました。 自費出版として自己縮小しなければ、これはしばらくのうちに一万部は出ると思ひました。日本教文社の中島省治さんに公けの出版に出すことを相談しなさい。……(後略)」 ――飛び上がって喜んだのは、言うまでもありません。 こうして、結果的にはわが家の「伝家の宝刀」が『光のある内に』の本を世に生み出したことになったのです。 日本教文社刊として、タイトルは『光のある内に』のあとに「聖歌のすすめ」という副題がつけられ、昭和五十四年八月二十日付けで初版三千部が刊行されました。そしてこれは約五年の間に六版まで版を重ね、谷口雅春先生が予測されたように約一万部が売れました。反響は大きいものがありました。二葉美代先生のように、三冊ボロボロにすり切れるまで読んだというような方もあらわれてくださいました。(現在は在庫無し絶版) 恵吾先生は、ここに書かれた通り、「実相独在」の真理に命をかけて、生涯を全うし貫かれました。 私は、恵吾先生と同じようには行かず、実相と現象のあいだをさまよいながらも、「教化部長」という私にはまったく不向きなお仕事を、なんとか二十年以上も続けることができたのは、この『光のある内に』があったからでした。そして、どの任地でも恵吾先生のいのちがけの応援をいただいたからでありました。榎本恵吾先生にただ感謝あるのみです。ありがとうございます。 (三)ホームページを作成して 平成十八年九月四日夜、ある方から次のようなメールを頂戴しました。 「《題名: すごいHP!》『榎本恵吾記念館』ホームページのあまりのすごさ、すばらしさに感動しています。ものすごい影響がありそうです。ありがとうございます。ひっそりとひそかにひろまっていってほしいです。」と。 ――私も、同感です。今朝も、「記念館」のホームページ(ウェブサイト)を開いて見直し、聴き直し、感動しています。 これは、私が作ったものではない。何ものかに導かれて、大いなるもののみ力を戴いて、作らせていただいたものだと思います。 具体的には、皆さまの積極的なご協力のたまものです。 まず、一子奥様のご賛同、ご協力、ご遺作書画など資料のご提供をいただくことができたからです。そのほか、多くの方々から膨大なご遺作文書・楽譜・演奏の録音などを提供していただき、あらためて恵吾先生のすごい創作意欲にも感動を新たにしています。 さらに、これらをウェブサイトにまとめて提供する技術は、主として私が山形時代、勤務時間外(夜)にパソコン教室の「ホームページクリエーターコース」に通って習得させていただいたのですが、これも何ものかのお導きによるとしか考えられないことでした。 そして今、「榎本恵吾記念館」ウェブサイト作成には、恵吾先生のお導きをいただいていることも、間違いありません。人間わざではできないような、円滑現象が次々に起こって、うまく作られて行っています。私も、それに感動しつつ。 冒頭に掲げさせていただいたメールのように、これは 「ものすごい影響がありそうです。…… ひっそりとひそかにひろまっていってほしいです。」 と、あらためて私も思います。 恵吾先生と私の魂の出会い・交流で特に輝いた時は、最初が昭和三十三年十一月。このときは、私はまだ恵吾先生を知りませんでした。 次が『光のある内に』出版の時。 そして今、ホームページ「榎本恵吾記念館」やこの「榎本恵吾先生を偲ぶ文集」の作成で、幽明境(さかい)を異にしながら、恵吾先生のお導きをいただいていると思います。 これからはますます己れを無にして、永遠に、恵吾先生の御霊と共に、「久遠の今」に立って無限によろこびの生長を遂げて行きたい、よろこびの人類光明化運動をさせていただきたいと切に願っています。 久遠の榎本恵吾先生! バンザイ! |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(26) 2006/10/18 「榎本先生、天国から応援してください!」
徳島県小松島市 村崎 孝江
|
|||||||
合掌 ありがとうございます。 私は十月二日、主人の永代供養をするために、主人の大好きだった宇治へ参りました。 いつもニコニコと太陽のような笑顔の、榎本講師(せんせい)のおられない宇治は淋しすぎます。いつも一緒に宇治へ行ってくれた主人もいない。体の中を風が吹き抜けてゆくようで、宇治別格本山全体が光を失ったような気がいたしました。 榎本講師に初めてお目にかかったのは、昭和六十三年、私にとって二度目の宇治短期練成会の時でございました。 当時私は、日赤病院の医師から「膵臓癌」と言われ、死も覚悟して自分の葬式費用まで用意しておりました。私が「最後に宇治へ行って水子さんにお詫びをしたい」と言ったので、下痢がひどく、体重も十キロも減って衰弱した私を、主人が宇治練成へ連れて行ってくれたのでした。 練成部の方の御愛念により、特別室の個室を貸して下さり、そこで榎本講師の御指導を受けました。 側にいた主人が、思わず 「ああ嬉しい、ああ有難い」 と合掌しました。 主人の合掌する姿を見たのは、この時が初めてでした。私は驚きました。 榎本講師は、 「あなたより御主人の方がもっと素晴しい、いい御主人が居て幸せですね」 と祝福して下さいました。 榎本講師が帰られた後で、主人が 「今ここへおいで下さったのは榎本講師ではない、神様がおまえの病気を治すために、おいで下さったのだ。だからきっと治る。絶体に死なないよ」 と言って励ましてくれました。 主人は、榎本講師のお姿の奥に、神様のお姿を見て合掌したのでした。 「御先祖様は全部永代供養しよう。父母にも感謝していなかった、水子さんにも、自分が父親でありながら一度の供養もしないで、本当に申し訳なかった」 と懺悔して下さり、二人で聖経『甘露の法雨』を読誦いたしました。 榎本講師のご指導と主人の愛念によって、私は地獄のような恐怖から解放され、健康体になることができました。 あれからやがて二〇年になります。二〇年の間にはいろいろ試練もございました。 姑が二度も骨折して入院し手術を受けたり、リハビリ等、大変でした。 主人も、十年ほど前よりパーキンソン病でほとんど働けなくなりました。 私は病人の世話と商売とで、外に出て「生長の家」のために活躍することもできませんでした。 榎本講師にお目にかかるたびに、 「私は生長の家のお陰で救われましたのに、何のご恩返しもできません」 と申し上げますと、 「ご恩返しはできる時にすればいいんですよ。あなたは生きているだけで、人のお役に立っているんですよ」 とニコニコと祝福して下さいました。 主人は私のために店舗の二階を造作して、流し台やトイレも付いた立派な誌友会場を作って下さいました。せめてものご恩返しと思って、十二年間誌友会をいたしております。 平成十四年に姑が九十七歳で昇天し、十八年八月には一年十ヶ月寝たきりで入院していました。主人も昇天いたしました。私は健康で、姑や主人の世話ができることがただ有難く、苦労だと思ったことは一度もありません。 もうこの世には、私を励まし、やさしく見守って下さる榎本講師も、主人もいません。私は砂ばくの中で一人ぽつんと立っているような気がします。 「榎本講師。もし天国で主人に会ったら、我がままで寂しがりやですが、仲間に入れて下さい。そして素晴しい生長の家の眞理を聞かせて下さい。お願いします。」 主人も、大好きな榎本講師と一緒なら、すべての束縛から解放されて、自由自在に天国を飛びまわっているかも知れません。 十月二日、宇治で奥様の一子講師にお目にかかり、以前より若々しくお美しく輝いておられるお姿に驚きました。 私も泣いてばかりではいけませんね。頑張ります。 「榎本講師、天国から応援して下さい。お願い致します。」 長い間、本当に有難うございました。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(25) 2006/10/15 「『光のある内に』三冊ボロボロに…」
東京都葛飾区 二葉 美代
|
|||||||
榎本恵吾先生とのご縁は、昭和54年、『光のある内に』のご本を戴いたころからと思います。 「天地の初発(あめつちのはじめ)に立ちて―人類光明化運動の楽的展開論」 この表題を見た時、私は飛び上がらんばかりに喜びました。 当時、白鳩会教区連合会長を拝命していた私は、本部目標を達成することが出来ず、悩んでおりました。 「これだ、これだ! これさえ学べばよくなる!! 」と。 しかし、読んでみると、「楽的展開」どころか、とてもむづかしいのです。 「久遠の今」「未発の中」「真空妙有」「久遠天上理想国実現の神示」等々……その当時の私には、むつかしいことばかり。 「自分の中に『生長の家』を発見し、話す相手さえも自分の生命の中に発見するのでなければ、ついに『生長の家』もよそごととなり、単なる遠くのものを指し示す説明に終ってしまう。」 「絶対の自由を得ていなければ、真の光明化運動は不可能である。」 「『教えは教え、運動は運動。そこには多少の矛盾不一致があってもいい』などということは許されない。」 「実相の展開そのものとしての運動に参加しなければならない。」 等々、むづかしいことばかり……。 ひたすら夢中で『光のある内に』のご本を、読んで、読んで、読み続けました。 ついにこの『光のある内に』のご本が3冊ボロボロになりました。 今、拝読してみると、とてもよくわかるのですが、当時の私は、若くて現象観のかたまりでした。今、思いますと、どうしてあんなに解らなかったのだろうと、不思議な気がいたします。 私は今、しみじみと、この『光のある内に』のご本に育てられたのだと、まことに有り難く思いまして、心より感謝申し上げております。 榎本先生からは、数限りなく、すばらしいご著書や、絵や音楽や…を贈呈していただきました。どれもこれも心にしみて、私たちの血となり肉となってくださったものばかりです。 今、私は、榎本先生の膨大なご著書、『弟子像』が愛読書になっております。 谷口雅春先生の、十二弟子に匹敵するすばらしい先生方のお心を、榎本先生でなければと思われるご筆致で、あざやかに浮び上がらせていただき、今は亡き先生方のお声が聞こえるようなすばらしいご本でございます。 今、わが「みすまる道場」で、この『弟子像』のご本をテキストにして、講話を毎月させていただいております。 「現象の日本なし。實相の日本のみ独在す。真の愛国心とは、この實相日本を礼拝する心にほかならないのである。實相のみを愛し、實相のみを観てゆけばよいのである。」 「敗戦前、真の日本なし。敗戦後、真の日本なし。現象裡に真の日本なし。前後際断の今、即久遠にのみ真の日本あり、真の日本を知らざる者は、日本人に非ず。」 今や世界が 唯物論の極に来て、その終焉を迎えようとしており、新時代の生命の胎動が、粛々として起こりつつあることを感じます。今や世界は、谷口雅春大聖師のお示しいただいた「實相独在」の真理、神意に一大方向転換すべき機を迎えているのではないでしょうか。 私も、尊師の教えを受けた者として、『光のある内に』のご本でまいて頂いた種子を大切に育て、花咲かせ、実を結ばせて、「みこころの天に成る世界」を地に成らせる創造の光明化運動に、いのちをかけたいと念願いたしております。 榎本恵吾先生は、まことに神であらせられ、真理そのものでございました。 「これからなるんじゃない。もうすでに、そのまま神の子です。それを喜んでいいんですよ。」 このお言葉は先生独得のもので、自己限定をしていた私たちの心の扉を開いてくださいました。「そのままで、神の子は完全円満である」と『生命の實相』のご本を貫いて教えていただいているのですが、それを榎本先生のお口からお聞きした人々が、みんなその悟りに入ることが出来るようになりました。 まことに、まことに、すばらしい御魂の先生でいらっしゃいました。この偉大な先生にご縁をいただけた私たちは、まことに日本一の幸せ者でございました。 高き神界を天翔けり、国翔けりしてご活躍されるであろう榎本先生に、又めぐり逢うことができる日の来ることをたのしみに、日々精進してまいりたいと存じます。 本当に、ありがとうございました。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(24) 2006/10/14 「人生、丸ごと輝けるかどうか?!」
京都府長岡京市 松本 久
|
|||||||
榎本先生に触れているかどうか、ということは、「人生が丸ごと輝けるかどうか」ということと同じだと思います。 私は、母がこの教えを信仰していたおかげで、小学生の頃から、少しは神誌に親しんでいました。それが、青年期、特に二十七歳頃から精神的悩みが深くなり、ねばりついて、何とか信仰で解決したいと思うようになりました。その頃の強い思いを一言でいえば、「宇宙に溶けたい!」でした。 宗教書にも熱心になり、これは! と思う人を見つければ手紙を書き、会いにも行きました。ですが、心は晴れません。 やはり、「生長の家」だけになりました。先の私の強い思いを実現しようと思えば、「感謝」の思いが湧出するようにならなければならないと、一心に思うようになりました。 その年の十二月に宇治別格本山で練成を受けました。が、まだ真理は私の魂に届きませんでした。それどころか、浄心行の後で、私はドーンと落ち込んだという珍しい人間でした。泣けなかったからです。うっすら涙さえ出ず……。 練成を終えてから、「ありがとうございます」を毎日一万回唱えることを目標にしました。何とか感謝の思いが出て来やすいよう、イメージングをしながら、ゆっくりと唱えていました。が、そうした一回一回の唱えの「質」にとらわれていたのでは、回数が稼げないのでした。「やっぱり、数だ!」 私は極端から極端に走る性格で、今度は速射砲のように「ありがとうございます。ありがとうございます。アァ、ありがとうございます」と唱え出しました。 何ヶ月やっても、何も開きません。五官の汗だけが溜ってゆきました。 二年程経って、二回目の宇治練成を二日間だけ受け、榎本先生のあの黒板に書かれた「ニッコニッコ顔」を見ました。その瞬間、天の岩戸が開きました。 「自分は完全円満だ!」 内奥の眼がしっかり観ました。不思議でした。これを、どこで観ているのだろう……。 すぐ、先生に会いに行きました。 先ず、私。 「感謝ができないんです!」 その後、先生は私にとってはもう驚天動地のようなことを言われました。 「谷口先生は感謝のできなかった人なんですよ」 勿論、「はじめは」という意味でしょう。が、これを聞いてから私の中で溶解が始まりました。 「じゃあ、なぜ、あんなに 『感謝』 だけをピックアップして強調するんですか」 の短かいやりとりの間に、「下から上へ向かって頑張る」という重い構図がフッ飛んで、「アレェ?」 何だか嬉しい感じです。もう後の細かい質問はどうでもよくなりました。 「この人だ! 自分にピッタリだ。この人について行けば自分は大丈夫だ」。 すぐ研修生になりました。 今、奈良県の教化部長をされている葛原本部講師と同期で、一ヶ月間の研修中、氏が的確な質問をして、それに先生が答えられているのを見ると、「こらぁ、置いて行かれるなぁ」とあせりながらも、私の特性で細かく細かく喜びを味わっていたのでした。 そんなある日、特に強い、「グッ、グッ、グッ」と胸を打つような喜びが何度か来たかと思うと、その胸にあったような蓋がはずれて、今度はそこにホームベースのようなものがあって、そこから約九十度の方向に、喜びの白い煙(湯気?)が、フヮーと拡がって行くように観えました。その時です。 「あぁ、貴方、今、豊かなものが流れていますねぇ。」 驚きです。「この人は、いったい何者なんだ !?」 私には、敬愛の気持ちと、一種の恐れに似たものも、つきまといました。 時が進んでも、私から先生への質問は「もっと深くなるには?(効率よく)」に帰結しました。 ある日、「今日こそは」と、ご自宅に伺って、 「『○○してからではない』 と言われても、もっと深く味えるようになるために、一秒でも先生の前に座っていること自体、修行じゃないですか」 と、伺うと、 「僕は嬉しいですよ」 と一言だけ言われて、後は奥様と一緒にニコニコしておられるのです。 <クソォ、二の矢も出されへん。今日はみっちり質問を組み立てて来とんのや……> 等々、とてつもない師を持ったことを恨みに思った時もあります。 そのうち、齢五十を過ぎて、何とか「榎本研修生」と言える自信もできて来ました。 いつも、いつも「喜び」があります。「どこから来たの」とか、「どうして在るのか」を超えて――もう消えませんね。 そして、「(“私”は)無いなぁ」 があります。 無限であるのは、とてつもない幸せです。特にこの十年、無限の能力を精一杯発揮させて頂きます。 感謝。合掌。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(23) 2006/10/14 「先生、今日も力をかして下さい!」
大阪市旭区 真田 積
|
|||||||
「自分で解決出来ない問題でも、神なら解決できる」と講師の講話で聞かされていた。「親に感謝」ということが、私の永年の課題だった。 小学校高学年時に、家庭の不和から母が家出し、祖母と叔母に育てられた。その時、父が自分の感情のいらだちから、不満を子供(私)に投げかけた。それで私はまた憎しみ、怒り、恨み、悔しさ等の悪感情がたかぶって、消すことができなかった。 家中のゴタゴタのさなかで、父の勤め先の友人から、「生長の家」の教えにふれることになった。 しかし、社会に出ても、よろこび一杯の胸中にならず、近くの道場で講師に「感謝」への方策を質問するが、満足する答が得られるものでなかった。「あくまでも、自己の内なる自覚のめざめから」――二十数年前の時点では、そういうことは考えられなかった。 解決の糸口は 「赦し」 と 「“現象無し”に徹すること」 だと、頭では理解しても、さて実行となると、悪感情が先廻りして、「赦し」は至難の業であった。 『甘露の法雨』の「『七つの灯台の点灯者』の神示」に、「汝ら天地一切のものと和解せよ」と。また「神に感謝しても父母に感謝し得ない者は神の心にかなわぬ」と教えられている。しかし、親と同居している日常生活の中では、「五感に現われるものは《心の影》で、実在するものでない。無いものは、無いのだ」と教えられても、根底からくつがえすには至らなかった。 相談相手の叔母は、家の事情はよく知っていた。自分たちの行為行動、私が叔母と楽しく会話をかわすことが、母から見れば憎らしく思われたことかも知れない。 叔母は、会うたびに、「私たちの代で業を消すように、専念するんだ」と話されていた。 毎日、迷いの連続だったことから辛抱できず、宇治練成会の門を叩いた。 そこで、本部から異動でお見えになった榎本先生との出会いが始まる。 講話後、風呂場で会話がはじまる。 先生から、「講話の内容が本当に良かったのか悪かったのか。失望させたのでは」と、謙遜された質問をされたように思う。 「誰が聞いても理解できるような、自己の体験を通した講話だったので、感動した」と返答したことが、昔のことながら今も記憶に残っている。 その後私は、盂蘭盆の大祭奉仕には休暇をとって、十数年間毎年奉仕させていただいた。「会場係」から「祭場係」と呼び名が変るが、その大祭奉仕の中で、私は先生から毎年、励ましと感謝のハガキをいただいた。 大祭中は、焼香台の種火の準備が私の役目で、炭火が飛び散るのを防ぐ濡れ雑巾をもつこともよき体験でした。 新年祭に初詣りした時に、「霊牌合祀祭奉仕員」の公募があった。私には恵まれた身体が与えられているので何かお役に立ちたいと、前々から思っていたので応募し、参加するようになった。 合祀祭で先生は、経机が並ぶ前列の右側に座っておられて、視線が合うと笑顔で迎えていただいた。あと片づけには、先生自ら両手に机を持って、経机の積み重ねを手助けいただいた。これは簡単なことのようであっても、なかなか出来ることではないと、常々感じていて、嬉しかった。 終ると、送迎バスのところまで足を運んでこられた。私は、「合祀祭に参加することが非常にたのしく、二、三日その余韻が残っています」と言った。先生との会話は「以心伝心」で十余年に及び、今年十二月で十二年間、皆勤で奉仕させていただくことになる。ただただ感謝です。 母は、他界する一ヶ月前、私たち二人の前で、「以前から随分いじわるをしていた」とわびていた。その後、危篤の状態の時もあったが、妹婿に頼んで、合祀祭には参加させていただいた。ただ無事を祈るばかりでした。 私は現役時代より息子の成長発展が何よりも嬉しく、昨年四月、三十代にして一流企業で課長職に昇格した時には、誰よりも先にそれを榎本先生に報告した。先生は即座に「本人の努力もあるが、お父さんの日頃の奉仕のたまものです」と。…… 私は「積善の家に余慶あり」の言葉が好きでした。徳久先生も、「入るところと出るところは違う」と講話の中で話されていたことを思い出しました。 最近、宇治別格本山職員の方々の異動があり、顔ぶれが変りましたが、変らないのは霊牌供養することです。ご先祖への感謝が、ここにきて出来るようになったと思います。「継続は力なり」。つづけることは大切です。 昨年七月に突然、天界へ旅立たれました先生。 私は、霊牌合祀祭に参加するたびに、 「今日も楽しく奉仕させていただきます。今日も力をかして下さい」 と、先生に声をかけています。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(22) 2006/10/14 「『輝ける万年青年』 の榎本恵吾先生」
兵庫県宝塚市 栗山 華江
|
|||||||
合掌 有難うございます。 今より三十年ばかり前のこと、昭和五十五年八月十日~二十日迄の「宇治別格本山・谷口清超先生ご指導特別練成会」に於て、私が初めてお目にかからせていただきました榎本恵吾先生は、まだ四十歳前で、学生っぽさの抜けない、青くさくて、お堅い感じでいらっしゃいました。が 開口一番、 「或る日、この大拝殿前のお庭を、竹箒で掃いていたら、手水鉢や松の木やらが、突然 黄金色の光を放って、キラキラ輝やいて観え出したんですヨ。すると、森羅万象が、『ああ、有難いなァ』と感動の渦に包まれて、心の底から『有難うございまーす!』と感謝することができたのです。」 とおっしゃいました。私は、「ああ、この先生はまだお若いのに、随分『魂』の次元のお高いお方なのねェ」と、いたく驚き、深く印象に残りました。 それ以来、この先生を慕うて、度々、「練成会」へ参加するようになりました。私が、「宇治」へ来ますと、先生は、とても喜んで下さり、講話中、壇上で、飛んだり、はねたりして、喜こびを、全身で表現して下さいました。 そしてついに、昭和五十七年八月「盂蘭盆供養大祭」に、私は研修生となり、「祭司部」のお受け所にて、霊牌書きの御奉仕をさせていただくことになりました。 その折、お初にお目にかかり、御一緒にお仕事することになったのが、榎本一子先生でした。 恵吾先生は、一子先生のことを、「初めて出会った時、何かとても懐かしいものを感じたんだ。それで、奥さんに決めたんだよ」と、おっしゃられたので、「うわぁ、とても純粋で、美しい決め方やなァ」と、大いに感激したのを、覚えております。 恵吾先生は、優美で、しなやかな体型で、男性にしては、珍らしく、清純な雰囲気の、芸術性豊かな感性をお持ちでしたので、そこが、文人的、詩人的で、ロマンチストの私と、フィーリングがよく合い、親しくさせてもらいました。 そして、青くさかった先生のお顔は、いつしか、御自身が黒板にお描きになられたニコニコマーク、そのままの円満な、福々しい笑顔に変貌してゆかれました。 又、先生は、奇しくも、私の実兄と同い歳であられましたので、私は、恵吾先生のことを「先生」というより「眞理」をお教え下さる「お兄さん」のような思いで接するようになってゆきました。 ですから、「先生、いつまでも、若々しく万年青年でいらして下さいネ」と願うようにもなっておりました。 なのに、享年六十八歳の御生涯は、余りにも短か過ぎたのではありませんか。 「宇治」へ行きましても、先生の、あの美しいお姿をもう拝見し得なくなったのは、甚だ寂しい限りです。 でも、観点を変えれば、(御家族の方々には、まことに申し訳ありませんが)、あの年齢で逝かれたればこそ、あの若々しい輝やきのある万年青年のお姿が、わが胸の中に定着し、これからも、想い出の中に、永遠に 生き続けることになり、むしろ、私にとっては幸いであったのでは・・・・・と思えるようになりました。 何故なら、恵吾先生が、もっとお歳を召されて、腰が曲がり、杖をついて、歩いてらっしゃるお姿など、到底想像できませんし、又、見たくもありませんもの。 神様は、その人と周囲の人達にとって、最も適した時期に、天に召さしめ給う、というのは、まことに「眞理」で ございますネ。 あらためて、恵吾先生の御冥福を、心より心よりお祈り申し上げます。 榎本恵吾先生、どうも有難うございました! 再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(21) 2006/10/13 「『そのままで尊い』 の自覚を新たに」
東京都小平市 早川 純子
|
|||||||
榎本恵吾先生に初めてお目にかかりましたのは、昭和62年8月、宇治別格本山での一般練成会でした。「天地一切のものが自分を祝福している」と分った時に感謝が出来た、というご講話が、今も印象に残っておりますが、当時は神罰の恐怖に依るノイローゼがひどい状態でしたので、先生の素晴らしさが分かりませんでした。 平成11年7月25日、東京第二教化部の日曜光明講演会に、榎本恵吾先生がお越し下さいました。その時のご講話の素晴らしさに心の底から感動致しまして、是非個人指導をして戴きたいと思い、お電話させて戴き、8月、盂蘭盆供養大祭に参加し、20日にご指導して戴きました。 その時、自分の思いを十分お伝え出来ませんでしたが、先生のご著書「葩(はなびら)さんさん」を戴きました。 帰宅後、早速拝読させて戴きました。 魂を解放してくれる素晴らしい内容でした。 私は「ねばならぬ」ですぐに自縄自縛いたしますので、その度に「葩さんさん」を拝読させて戴き、「そのままで尊い神の子である」と、自覚を新たにさせて戴いております。ご本を開けばいつでも先生のニコニコしたお顔が目に浮かびます。 榎本恵吾先生に限りない感謝の思いを込めて拙文を書かせて戴きました。心から感謝申し上げます。有り難うございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(20) 2006/10/13 「『本流の真理』 に導いて下さった先生」
兵庫県西宮市 友江 允有己(まさゆき)
|
|||||||
榎本恵吾先生は、私を「生長の家の本流の真理」に導いて下さった師であります。 平成17年7月12日までの4年間、毎月幽斎殿にて、榎本先生のお姿や表情を拝見しながら、先生のお言葉を通してご指導頂きました。 その榎本先生が7月12日、「僕と君とは一つの“いのち”だからね」、と言って私の“いのち”の中に飛び込んで来て下さいました。 私は榎本先生と今まで通りいつもご一緒させて頂いております。ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(19) 2006/10/13 |
|||||||
合掌 二十三年前の五月、私ははじめて「皇居勤労奉仕」に参加させていただきました。以来、今日に到るまで、この「勤労奉仕」は、私のライフワークのように、毎年続けさせていただいています。 忘れもしない、初参加のときのことです。ご奉仕の休憩時間に、芝生で一緒に参加しているみなさんといろいろなお話をしているときのことです。 西宮からご奉仕に参加されていた前波さんという方が、生長の家の方で、西宮のご自宅で「榎本恵吾先生を招いての誌友会」を定期的に開いているとおっしゃるのです。 それで、ある日の会のとき、参加していた地方講師の方が、どうしても朝、早く起きることができないので、なかなか早朝神想観ができないという悩みを、榎本先生に、相談されたそうです。 すると榎本先生は、 「何者が寝ていると思っているんですか!」 と一喝されたそうです。 この話を立って聞いていた私は、 「何者が!」 という言葉を聞いて、一瞬、考える間もなく、 「ああっ!」と大きく口と目を開いて、雷光に打たれたように、 「神の子が寝ているのだ」 と気づいて、ホウキを持ったまま、ズッこけて転んでしまいそうになりました。というより、自分のまわりの世界が、まるごとひっくり返ってしまったようでした。このときの私の驚きようは、それぐらい凄まじかったのです。 この「何者が寝ているのか!」という榎本先生のお言葉は、私にとって生涯忘れ得ぬ衝撃でした。 そしてこのお言葉は、その瞬間から、私の運命の扉を開いてくれました。 実際、私も「寝る子は、よく育つ」と自分にも言い聞かせ、また他人にも自己弁護しているくらい、朝が苦手でしたから、その私の自己肯定以上に、私を大肯定してくださる、その榎本先生という人こそ「何者ぞ?」と思いました。 「そんなおもしろいことをおっしゃる榎本先生という人に、どんなことをしてでも、どこであっても、今すぐにでも会いに行きたい」 と思い、前波さんにお願いしました。 こうして、西宮にある前波さんのご自宅で開かれる、榎本先生がいらっしゃる誌友会に、私は大喜びで行かせていただきました。 これが榎本恵吾先生との最初の出会いでした。 榎本先生と出逢えた嬉しさのあまり、東京に帰ってからも、毎日、天国にいるような気持ちでした。 たとえば、ベートーヴェンの『第九』の『喜びの歌』(第4楽章)と『運命』のレコードを連日聴いては、この悦びを噛み締めていました。 またあるときは、嬉しくて嬉しくて自分の部屋でひとりでに舞い踊っていました。道を歩くときは、ひとりでにスキップしている自分がいました。この嬉しさは、抑えようにも抑えようがないほどでした。 こうして、私の中に喜びの世界が広がりました。言葉にできないほどの歓喜の天国が、日々現われてきました。その喜びは、とどまるところを知らないほど大きいものでしたから、私の中の「天井」を吹き飛ばしてくれました。私のいのちは宇宙いっぱいに広がって行きました。 この、拍手(かしわで)を打ち鳴らしたくなるほどの大きな喜びと感動を受けたことを、前波さんにお話しましたら、前波さんは、 「その気持ちを、ご自分で先生にお手紙に書いて送られたらどうですか?」 とおっしゃったので、私は苦手を承知で、先生に手紙を書きました。手紙の中に、 「それまで合わなかった掌と掌が自然に合うようになってきました」 とも書きました。 私は、どうしても自分に嘘がつけない性分なので、ありがたくもないのに、簡単に合掌をする気持ちにはなれませんでした。それが榎本先生と出逢ってからは、いつも喜び感動していたので、嬉しくて、おのづから発するごとく、本心から合掌ができるようになってきました。 このことを手紙に書いて送ったのでした。 この手紙と一緒に、感謝の気持ちを伝えようと、プレゼントも送りました。プレゼントとは、スケッチブックや和紙でできた冊子、半紙、ポストカードブックなどでした。 先生は、書き物をされているので、書画の道具になる贈り物の方が役に立って喜ばれるのよと、前波さんに聞いていたからです。 すると驚いたことに、後日先生は、私が贈った冊子や半紙、スケッチブックやポストカードブックの全頁(丸ごと一冊)に、「真理の言葉」をいっぱい筆書きしてくださり、また(無数の合掌している御仏様やにこにこ笑顔の)画をいっぱいに描いてくださって、私に贈ってくださいました。 ある冊子には、『無限常楽』と題字が書かれていて、扉を開くと『真理の吟唱』の「有限そのままに無限を悟る祈り」が全部書写してありました。 「み光は降り給えり み光は降り給えり。大神の伝え給える み言葉は まことにぞ 光にましますのである・・・」 という、榎本先生のお好きなお言葉にはじまる一節が綿々と書かれていて、まるで筆書きの『真理の吟唱』のご本のような重厚さでした。 三十枚綴りのポストカードブックの一枚一枚のカードにも、この「み光は降り給えり・・・光にましますのである」のお言葉が、全てのカードに、似ていながらそれぞれ異なる(彩色ゆたかな)絵と一緒に、丁寧に書いてくださっていました。 このことがあってから、私の喜びはまたさらに大きくなりました。そして先生に、この自分の魂の喜びを、「こんなに喜んでいます!」と伝えたくて、私の親友と共謀して(?)数々のお便りとプレゼントを、ときおり贈るようになりました。 プレゼントとは、榎本先生に気づかせていただいた究極の喜びの世界を「形」にしたものがよいと考え、私なりに工夫したものばかりでした。 聖典に出てきた「黄金の薔薇三輪」という言葉に感激し、実際に「金色の薔薇」を三輪お贈りしたことがあります。 「桃」が永遠の生命を表すという話を何かの本で見つけて感激したので、先生に「桃」をお贈りしようと思いましたが、季節がら桃が売っていなくて、代わりに(よく似ている)リンゴをお贈りしたこともありました。そのとき神の子は神の中から生まれたというお話をもじって『桃から生まれた桃子ちゃん』と題する(自分で書いた)拙い詩(というより創作神話)を添えてお送りしたのですが、すると先生はさっそくご返事をくださり、 「『神の子』は桃だけでなく、リンゴをも自在に生み給うのだね」 と云ってよろこんでくださいました。 すると嬉しくなった私は、その後日、また『みどりご』というタイトルの創作神話(緑の木にいっぱい実っているコトノハ「言の葉っぱ」を、朝も昼も夜もいっぱい食べて大きく元気になった子供のお話です)を「緑のマジック」で書いてお贈りしました。 するとまた先生は、 「全開きに開かれ切ったスミキリの輝きを拝ませて頂きました。そしてあなた様があなた様であられる静かなるものもそこにあって、私の魂も落ちついて来るのを憶えるのでありました。 一つ一つの文字が黄金のみどりなるみづみづしさなるものなる輝きそのものであり、一つ一つの文字に三千のみ佛が坐し給ひ、全身の細胞ことごとく如意宝珠にして、いちいちの如意宝珠にまたまた三千のみ佛け坐し給うているのを想うのであります。・・・永遠に久遠に生長を続けて頂きたいものであります。・・・ 如来説法天人舞遊 浄土現前光明無碍 榎本恵吾 大川京子如如様 」 と、感激のお便りを下さって喜んでくださいました。 (お手紙の末尾には、よく私の名前の下に「如如様」と書いてくださっていました。大川は私の旧姓です) そうしますと今度は、先生のこの感激の便りを受けて、また私は、この上ない喜びでいっぱいになりました。 その心境はまさに、生意気にも「不立文字」そのものであると思いましたので、ポストカードに一文字も言葉を書かず、白紙のままで、金の色紙を、金粉のように細かく切ってはさんで、先生がこのポストカードを開かれたときに、黄金が散華するように工夫して、また実際そうなることで、先生がびっくりされるお顔を想像しながら、ドキドキ、わくわくしながら、歓喜の「不立文字カード」をお贈りしたこともありました。 またあるときは、早朝の明治神宮の参道に落ちていたドングリが、私には黄金に光輝くドングリに見えたので、先生に「秋の香り」のお便りをお届けしようと、手紙と一緒にそのまま封筒に入れてお贈りしたこともありました。 すると先生も東京にいらした時は、明治神宮を早朝散策されていたとのことで、懐かしく、感慨深く、嬉しく感じてくださいました。 またあるときは、 「先生はいつも龍宮城にいらっしゃるから、私も乙姫になって『玉手箱』をお贈りしよう」 と思いつき、ダンボール箱に、海をイメージしながら、いろいろな色を使って絵を描いて、旅行のお土産を詰めてお贈りしたこともありました。 このほか、ヘンデルの「水上の音楽/王宮の花火の音楽」や、アヴェ・マリア集、なつかしい日本の童謡、古式のオルゴール音楽・・・などの音楽テープをお贈りしたり、またキリストさまやマリアさまの聖画集や、宮内庁からの賜り物(皇居勤労奉仕)など、おりおりに各種のいろいろな贈り物を、天使風に工夫してお送りしました。 とくにヘンデルの音楽をお贈りしたときの先生のお喜びは一入(ひとしお)でした。 「何か大いなるものの祝福が、大宇宙となって私を包んで下さっていることを、あなた様のご愛念が代表して下さっているのを想うのであります。そのような時は、やっぱりヘンデルが私の周囲で鳴り響くのですね・・・そのことを、あなた様がどうしてか知って下さっているんですね。私にとって嬉しいことがもたらされる時、必ずどこからかハレルヤかとにかくヘンデルが響いて来るのです」 と喜んでくださいました。 また「アヴェ・マリア集」のテープをお送りして、その後日、聖母マリアさまの画集を見つけてお送りしたときも、先生は「音楽入りの絵を頂いたことになるのですね」と云って喜んでくださり、 「『マリア』のテープは殆ど毎日車の中で聴かせて頂いておりまして、宇治川沿いの景色が一そうなつかしくみづみづしさを増すのでございます・・・神様があなた様となって現われ給いて、私を抱き包みはぐくみ給うのを想わせて頂くのでございます」 と祝福してくださいました。ちょうど八月の大祭を迎えてご準備に忙しくされていた頃だったそうで、マリアさまの画集に対しては、 「『マリア』様の絵は、私を心ゆるやかにさせて下さるためにお現われになった」 と云って喜んで下さり、さらに「あなた様のご愛念の輝きを家族みんなで感じていた」ともおっしゃって祝福してくださいました。 ちなみに、お送りしたお手紙やプレゼントが届いた日は、不思議と(私は存じなかったのですが)先生のお誕生日であったり、先生のご結婚記念日であったりしたので、先生も、 「どうしてあなた様は、わたしのことを知っておられるのでしょうか?」 と不思議に感じておられました。 このように、お贈りしたどのプレゼントにも、先生は喜んでくださり、いつもすぐに先生から、喜びと祝福と「祈り」に満ちたお手紙が返って来ました。 「開かれゆく歓びの沃野を想いながらお手紙を拝読いたしました。あなた様の内なる歓びが輝きに輝やいてすべてのすべてとなり給う・・・」 と、私の魂の喜びに対して、喜んでくださり、祝福の祈りを授けてくださいました。そして、 「あなた様そのものが神のいのちの宣言によって存在しておられる、神様の〈いのち〉そのものでいらっしゃるのであります」 という「唯神實相」のお祈りの言葉を、いつも紙面いっぱいに書いて、にこにこ笑顔の絵と一緒に送ってくださいました。 あるときは、いのちの輝きを讃える「祝詞(のりと)」を贈ってくださったこともありました。 「大切に大切にすべてはあなた様を包んで輝いているのであります。そうです。あなた様の全細胞を貫いて天照す御親のみ光は流れ入り、輝き出でてすべてのすべてとなり給うのであります」 またあるときは、特製の「御札(おふだ)」を書いて送ってくださいました。 あるとき私は「神癒祈願」を申し込みましたが、私は自分の氏名の欄に、「生きとし生けるもの」と書きたくなったので(こんなこと書いたら叱られるかなと思いながらも)そう書いて送りました。 (私は「すべてのすべて」だから名前が無い、だとしたら、「生きとし生けるもの」ではないか、と思い浮かんだのでした) そうしたら、先生はそのまま「生きとし生けるもの」と「人形(ひとがた)」に筆書きして送ってくださいました。 このとき、(先生の)お喜びが伝わってくるかのように、先生はこの(落款入りの)「御札」を書いて下さったのでした。 つけ加えて白状しますと、榎本先生の「にこにこ笑顔」の絵を、私は「もう少し可愛い方がいい」と思い、大きく口を開けて笑っている「にこにこ笑顔」を描いたり、頭の上にリボンをつけた(女の子風の)「にこにこ笑顔」を描いたりして、さらに歓びが倍増した「にこにこ笑顔」を描いて、榎本先生にお送りしていたのでした。 今にして思えば、「何んということをするんだ!」と怒られそうですが、それほど当時の私は、嬉しくて嬉しくて、榎本先生と遊んでいたように思います。 また榎本先生も、こんな不躾な娘に、腹を立てずに、快く遊んで見せてくださったのですから、他の先生とは、一味も二味も違った先生でした。 この一連の往復書簡は、榎本先生による、ちょうど親鳥が卵の殻をつついて雛(神の子)を誕生させてくださる「卒啄」(そつたく)の「通信教育」のようなものではなかったかと思います。 こうして私は、榎本先生から、神の子として、如来として育てていただいたのでした。 もともと私は『生命の實相』を何十回も読んで真理の勉強をするようなタイプではなく、子供のような自由な感覚でものごとをとらえて、直観的に、本能的にものごとを楽しく(神遊びとして)とらえる傾向の強いタイプでした。 そのような私の個性を、榎本先生はちゃんと理解してくださり、大きな喜びと愛で包んで、受け入れてくださり、讃えてくださいました。 そして予想を超えるユニークさで、私のユニークさに応えてくださり、私の中から「神性」を引き出してくださり、大きな愛ではぐくんでくださいました。 「あなた様はどういうご使命の輝きを持ってお生れになったお方にましますのか。ただただ見護るばかりであります。神様はユニークなのですね。そのようにあなた様もユニークであられるのですが、天使的に見れば、自然な天然な薫りに満ちた崇き崇きなりわいにましますのです」 私は、この地上に生れてきて、榎本先生と出逢えて、本当によかったと思います。 この先生でないと、私は、魂の目覚めと満足と絶対の安心を得ることはできなかったと思います。 自分をゆるせて、自分を愛せて、自分に満足し、安らかな自分になれて、神の子の自分と出逢えたことは、神様からの最高のプレゼントだと思います。 あるときのお手紙に、 「いつの間に私たちはこのような祝福の真ッ只中に生れ出てきたのでしょう!」 と書いてくださいました。まさに先生がお説きくださっているのは、究極の「喜びしかない世界」であり、その真実を、先生は、毎秒、毎秒、一瞬、一瞬に全身全霊、全存在をかけて、愛と祝福と生命がはじけんばかりの躍動をもって、お伝えくださっていたのだと想います。 先生は、私が享受した爆発的な歓びに、爆発的な歓びと祝福の祈りで、応えてくださったのだと想います。 そしてそれこそが、唯神實相の世界、常楽の世界を日常に生きていらっしゃる先生のお姿であろうと思います。 榎本先生のもとに集う人はみんな、先生の愛と歓びの波動と一つになることで、いのちの本源の世界へ、悦びの宇宙へと帰らせていただけるのです。 どんな小さな歓びでも、それを認めることで、歓びはどんどん大きくなります。そこに生じた歓びの波動は、さらなる歓びを生み出し、より大きな歓びへと導いてくれます。 今、眼を閉じれば、なぜか榎本恵吾先生と谷口雅春先生が、ご一緒ににこにこと微笑まれながら、 「神の子の人生は、そのままでいいんだよ、思う存分喜び、楽しみ、味わい、経験するんだよ、そのために人は生れてくるんだよ」 と、語ってくださっているお姿が浮かびます。 それは長い間、人生の目的、生きる意味について漠然と悩んできた私に対する回答であるように思います。 神様からのギフトとして、天からの恵みとして、今回の人生を授かって生まれてきていたのだなぁ。いつの間にか私は、極楽浄土の住人になっていたのだ。あぁ、幸せだなぁ、何とありがたい、嬉しいことだろうと、しみじみと思います。そう気がついた今、これからの人生を、丁寧に大切に生きてゆき、他を思いやり、人のお役に立って生きてゆきたいと思います。 そしてあの日、あの時、私のいのちの中で鳴り響いた歓びが、今ふたたび「第九」のメロディーと一緒に鳴り響き出しました。 さらに、現在も、過去も、数々の前世も、すべてを超えて、今「はじめのはじめ」に帰り着くことができました。この歓びを、日々感じて、味わって生きて行きたいと思います。 『聖経』の中で、天使(てんのつかい)が訪れて、歌うがごとく「真理」を諭されていますが、いろいろな場面で、天の童子が現われて、み空を舞い踊ったり、ときに「生命の長老よ!」と呼びかけて質問をしたりする光景が描かれています。 これらの光景を拝見していて、 「ああ、私は、ここにでてくる羅綾(うすもの)を身にまとった天童たちの一人だ」 と直観しました。そして真理を教育してくださる「師」にして「生命の長老」である「天使(てんのつかい)」とは榎本先生だったのだと悟ったのです。 『聖経』には、天使(てんのつかい)が真理を語るとき、神光(みひかり)が花びらのごとくさんさんと降り注いでいる、と書かれていますが、まさにこの「實相の国」そのままを啓示されるために、榎本先生はこの地上に出現された天使(てんのつかい)だったのだと、今あらためて思うのです。 「實相そのまま」を現じたる世界を教えてくださっただけでなく、 「ますますあなた様に幸いが燦然と輝かれ、私の限りない祝福が光りとなって永遠に久遠にあなた様を引きつつみ幸いをもたらしつづけますことを深く祈念申し上げております」 と、手紙の最後で祝福してくださったように、先生はいまも永遠に久遠に、私たちの魂を礼拝し続けて下さっているのです。 今なおたくさんの「祝福」の花びら(光)をさんさんと降り注いで下さっている榎本恵吾先生の御魂に、そしてその奥にいらっしゃる谷口雅春先生の御魂に、限りない感謝を捧げます。 神は愛なり。 無限大(おおき)な愛を、ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(18) 2006/10/13 「伝 道 練 成 の 思 い 出」
東京都渋谷区 北島 直樹
|
|||||||
それはまるで傘地蔵のようだった。 大粒の雪がしんしんと降りしきる中、お地蔵さんのようにじっと動かずに、ひたすら『甘露の法雨』を唱えるしかない僕の頭の上で、積雪の量がふえていくのがわかった。 寒さには、ほとんど意識しなくてもすむぐらい慣れてきていた。だが同時に聖経をもつ両手が、凍ってしまったようだ。いや実際には凍っていないが、そんな錯覚に襲われるくらい、動かなくなっていた。 さすがに可哀相だと思ったのか、門前に僕が立っている家の主が、「その雑誌、買いますよ」と云って、その頃はまだB6判ほどのサイズだった「神誌」を何冊か買ってくれた。 帰りの車中、榎本恵吾先生はじつに嬉しそうだった。榎本先生も、傘地蔵になっていたからだ。 「みんな、まっ白」 それがこの伝道の成果のようだった。 「伝道練成」の出発前、どこから借りてきたのかわからないが、観光バスのような設えのバスに、伝道参加者が乗り込んだとき、榎本先生は、カラオケ用のエコーの響くマイクで、 「さあぁ~! みなさん! 光が行くんですよ、光が行くんです!」 といってバスの同乗者たちを鼓舞した。それからみんなで『使命行進曲』を唄った。 昭和六十二年の一月、僕ははじめて宇治別格本山の練成会に参加した。その前々年の晩秋、僕は結核で血を吐いた。それから一年ぐらい入院したり、退院しても療養したりの生活を余儀なくされていた。 長く療養していると、本を読むことにも飽きてくる。テレビを観てもさしておもしろいと感じられなくなる。仕方がないから、ビルの屋上によじのぼって星を見ていた。 体力が戻りつつあると実感した昭和六十二年の正月明け、僕は、母親を連れて旅にでた。 まず大阪から高野山に向かった。 高野山の厳寒は、病み上がりの骨身には辛かった。宿坊の煎餅蒲団で寝ていると、寒さのあまり、 「もうこのまま、死んでしまうかもしれない」 と本当に想った。すると夜中、若いお坊さんが「湯たんぽ」を運んできてくれた。温かい。これで僕は「生き返った」と思った。 早朝の勤行は興味深いものだった。 この寺の主は、高野山大学の教授で、偉いお坊さんだという。密教の儀式を、暗闇と静寂の中で、僕はまんじりともせずに眺めていた。 余談だが、この寺のごま豆腐は旨かった。 高野山のあと、宇治別格本山に向かった。 当時、東京の飛田給練成道場で大勢の人を指導されていた楠本加美野先生が、宇治に移られて、話題になっていたように覚えている。 楠本先生は、たしか河口湖や飛田給で、流産児供養などの霊供養や、徹底した「親孝行」の指導をされて大勢の人を救っておられると話題になり、全国津々浦々から大勢の信徒さんが押しよせていた。 その楠本先生が宇治に移られたので、今度からみんな宇治に行こう・・という雰囲気が感じられていた。 そういう風評を聞いていた僕も「一度、宇治の練成に行ってみよう」と思い立ち、母親と一緒に連れ立って一月の一般練成に参加した。 宇治につくとすぐに、 「宇治には、楠本先生以外にも『名物講師』がいっぱいいるよ」 と誰かに教えてもらった。すぐにその意味がわかった。なんといっても藤原先生が 「超大物」という感じで控えていられる。 このほか、もはや記憶が薄れて定かでないが、僕は練成中に、萩野先生、妹尾先生、竹岡先生といった講師陣からもご指導をたまわった。いずれも説得力のある、魅力的な先生方ばかりだった。 このほか、心霊研究をされている大野先生という講師もいらした。この先生は、なぜか僕に親近感をもっていらしたようで、よく話も伺った。 「幽斎殿は八大龍王で、横の池には龍がいるよ」 と先生がいうので、ならばと僕は、夜明け前にこっそり写真を撮りにいった。後日、現像してみると、確かに白く光る龍の姿が恐いぐらいクッキリと映っていたので、大野先生が「そうだろう」と悦んでくれたことを覚えている。 もちろん、評判の楠本先生にも、練成中、ご指導をたまわった。 宇治本山もやはり寒かった。 宇治の道場の窓から、しんしんと雪が降っているのを、僕は観ていた。 ひとりの講師が入ってきた。榎本恵吾先生だ。この講師、顔は笑っているが、雰囲気が鬼気迫っている。ぼそぼそと喋りはじめたと思ったら、ほどなく黒板に太陽のような、笑っている顔を描いた。そして太陽の絵を白墨でドンドン叩きながら、 「これしかないんですッ!」と叫んだ。 正直、「この人、だいじょうぶか?」と思った。 「實相の世界、神の世界しかないのだったら、世の中、警察はいらない。戦争だって起こってない」 と、率直に思った。いわゆる「横の真理」云々だっていらないだろう、と思った。 しかし、この異形の講師、榎本先生は、さらに声を大にして、 「無いものは、無いんです! これしか無い!」 と、ときおり飛び上がって訴えていた。 休憩時間に、地下道を歩いていたら、向こうから、背中を丸めて、ぼそぼそと何かつぶやきながら歩いてくる、しみったれた雰囲気の人がいる。 よく見ると、榎本先生だ。 「さっきの雰囲気とえらい違いだなぁ」 と思いながら合掌すると、先生の顔は、ほんの少しだけさっきの「キッとした表情」を取りもどした。しかし同時に人懐こい温和な顔でもある。 なぜか「いい先生だなぁ」と思った。 練成会には、いろいろな人が参加している。当然、中にはプログラムをさぼって、休憩室や自分たちの部屋で油を売っているティーンもいる。 榎本先生は、そこをめがけてやってくる。 どうしてもプログラム参加をしぶる若者には、その場で説法がはじまる。 練成参加者は、おちおち昼寝もできないのだ。 朝、カッコーの声が鳴り始めると、榎本先生はつかつかと部屋に入ってきて、寝ている人の枕元にしゃがみ込んで、 「ありがとうございまあ~す!」 と叫んでいる。それでも起きられない若者は、寝返りを打ったり、蒲団をかぶってこの攻撃から逃れようとするが、榎本先生の攻撃も執拗だ。 蒲団をはがされて拝まれた若者は、とうとうあきらめて早朝行事の部屋へしぶしぶ入っていく。 「四時五十分からの早朝行事の前に、三時からね、幽斎殿で神想観をやってるよ」 という話を聞いた。 「え? そんなに早く? なんで?」 と思ったが、行ってみた。途中、誰かから、なぜだか「行事は四時五十分からですよ」とクギをさされた。しかし「行くのは俺だ」と思って行って見た。 数名の人が神想観をしていた。もちろん楠本先生も、榎本先生も神想観をされている。 「な~んだ。みんないるじゃないか」 と嬉しくなって、僕も参加した。 うろ覚えだが、この幽斎殿での行事のあと、たしか「おみくじ」のようなものをみんなで引いた記憶がある。 そのとき、ある人が「感謝」と書いてある「おみくじ」を引いたので、照れ笑いをしながら、 「ああ、やっぱり感謝が足りないんですね。これからもっとまじめに感謝するようにしなきゃね」 と言っていると、榎本先生が横から割ってきて、 「どーして、そういう風にとるんですか! あなたの中に、すでに『感謝』がいっぱいあるから、こうして『感謝』って出てきてるんじゃないですか! あとはそれを形にするだけ! 喜んで形にするだけっていうことですよ!」 と、いつもの「捕獲説法」だ。その人は、ビックリした顔つきで、榎本先生の顔をまじまじと見つめながら「そうなんですか?」と聞き直した。 榎本先生は、嬉しそうに破顔微笑して、大きくうなづいた。 一般練成会が終わった。みんな帰り支度をしている。すると道場員の人が、 「このあと引き続いて『伝道練成』というのがあります。よかったら、参加しませんか?」 と言った。僕は、 「どうせ自分は療養中の、放浪の身。十日も十三日も変わらんから、ちょっと参加してみるか」 と思って参加することにした。 「楠本先生の伝道練成はすばらしい」 という評判を聞いたことがあった。伝道練成に参加すれば、楠本先生からさらに指導を受けられるかもしれない、という期待があった。それで楽しみにしていたら、今回から、伝道練成の指導は、楠本先生ではなく、榎本先生に変わりました、という。 これを聞いて、正直がっかりした。 「楠本先生じゃないの? なぁんだ」 と、落胆した。しかし、すでに参加の申し込みをした後だ。しぶしぶ参加してみることにした。 こうして練成がはじまり、榎本先生と一緒に、バスに乗って「伝道」に行くことになった。 「みなさんが光! 光が行くんですよ!」 榎本先生の魂が奮(ふる)えていた。 榎本先生の伝道は、一直線だった。 というよりも、あれは「伝道」ではないのかもしれない。いわゆる「伝道」ではないと思う。真理を知る者から、いまだ知らざる者への啓蒙活動というものではない。 まだ知らない誰かを拝みに行くという行為だ。 というより、伝道するもしないもない。伝道に行く僕たちも、これから伝道を受けるであろう人たちも、一様に同じ「光」である。 こちらの光が、あちらの光を拝みに行く。そうすることで、あちらの光もさらに光を増してくる。同時に、拝んでいるこちらの光も、また増してくる。ところが逆に、あちらの光も、じつはこちらを拝んでくれている。あちらの光が、こちらの光に力をくれる。 こんな繰り返しだ。「光の相互干渉(相互交歓)」のようなものではなかったか。 冬の京都は、たしかに寒かった。 しかし、光は「寒い」などと言うはずがない。 白い雪が降ってきた。 白い光の粒子が舞い降りてきた。 光の祝福だ。 ひと粒がどこまでも清(す)み切っている。 『聖経』を誦げていると、いろいろな想いがつぎつぎと湧き起ってきた。 しかしほどなくそれも、降り雪(そそ)ぐ無数の白い光の粒が、つぎつぎと、やさしく消していく。 唱える口もこごえて動きにくくなってきた。 口以外の身体は、もうお地蔵さんのように静止して動かない。 白い光の粒子が、ほほえむように降っている。 その清(す)み切った白い光の中に、今生きて在ることの充溢した幸せを、このとき僕は感じていた。 これが「榎本流の伝道」なのだろうか。 伝道する僕らが、伝道されていたのだ。 傘地蔵を想い出して、おもわず笑った。 はじめから、何も起きていなかった世界。 はじめから、すべてが起きていた世界。 はじめから、生成化育の律動のみが、ただ鳴り響くだけの世界。 はじめから、生きようとする世界。 はじめから、この歓びだけの世界。 はじめから、榎本先生は知っていたのだ。 帰りのバスで『使命行進曲』を歌っていた。 窓外の景色は、涙でぼんやりとしか見えなかった。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(17) 2006/10/13 「“太陽マーク”との出会い」
北海道旭川市 山川 貞子
|
|||||||
1982年、私は宇治の練成を受けるため、汽車に乗った。長旅のため手に持った本が 『光のある内に』 であった。<聖歌のすすめ>とそえ書きしてあったからである。 当時から私は聖歌隊の指導をさせて頂いていた。 宇治の練成が始まった。私はびっくりした。ご本の著者が講話に立たれたのである。そして黒板一杯に“太陽マーク”を書かれたのである。吸いつけられるように黒板を見つめている私の耳に「皆さん!! 何もしなくても始めっからこれ!! 」と云う力強い声がひびいて来た。 私はこれになりたくて宇治へ来たのだ。先生の一言で私は魂の底から救われた。もう帰っても良いと思った。私は“太陽マーク”を旭川へもって帰りたかった。先生に『光のある内に』 にサインをお願いして、四十部申込んだ。 以来榎本先生のご愛念は、ご昇天なさる時まで続いた。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(16) 2006/10/13 「奇しきご縁に感謝」
静岡県浜松市 江川 邦彦
|
|||||||
感謝合掌 平成8年の暮れ、学生時代以来20年ぶりに宇治別格本山練成会に参加しました。その日の夜、榎本先生は講話の後、練成員や職員の方々の合唱を指導され、私たちに聖歌を披露して下さいました。 あの時の、合唱される方々と先生との間に通い合う、なんともいえない幸せな雰囲気と、先生の嬉しげなご様子に、なにか非常に不思議な感銘を受けたものです。 その日の就寝の時、「これで救われる!ありがたい!」という強い思いが自然と湧き上がってきたことを、いまだに憶えております 。 何回かの練成会への参加の中で、宇治の方々の信仰による結びつきと、お互いへの信頼の深さと、神に守られているこの空間の、幸せに満ちた時の流れに深い安心感を覚えたものです。 榎本先生をとりまく人々、とりわけて別格本山職員の久都間繁氏は、静岡県での青年会時代の仲間であり、久都間氏と榎本先生の並々ならぬ結びつきを、氏からは色々伺っておりました。 また、はからずも学生時代、生学連の先輩だった平野孝之氏の結婚式にても、榎本先生、久都間氏と再会し、奇しきご縁だなあと感じ入ったものです。 私にとりましては、学生時代の生学連の活動と人々との結びつきが今日の自分の大きな心の支えであり、平野先輩との数年間の活動を通しての結びつきは、いまだに大切なものであります。そうした方々が、榎本先生を慕っていたことが、私にも強い影響を与えていたと思います。 それからしばらくして、何度目かの練成会終了の折、久都間氏とともに先生のお宅へ伺い、奥様の手料理をいただきながら酒を酌み交わす機会に恵まれました。 先生は実に楽しげに、信仰のこと、お義父様である藤原敏之先生のこと、ご家族のこと、久都間氏、平野氏など、信仰の仲間のことなど色々なことをお話してくださいました。持参した静岡の地酒を、実にいとおしむように幸せそうに召し上がっていたお姿が、忘れられません。 この方は、神に生かされた、愛すべき方なのだなあと、その時に強く感じさせていただきました。 あれから10年、私は静岡浜松の地において、宇治の練成会で強く願ったこと「使命あらばわが命生かさせ給え」を心の支えとして、今日まで生かさせていただいております。 その間、同じ信仰と価値観を共有する魂の半身としての伴侶を得、微力ながら地域での歩みを進めさせていただいております。 尊師谷口雅春先生によって、大いなる信仰と国の命につながることの喜び、そしてこれらを生きる多くの方々との出会いを与えられました。 谷口先生の悲願とされた「日本国実相顕現」と「人類光明化運動」への高き志をわが志として、その万分の一にても実現すべく歩みを進めさせていただきたいと念願しております。 榎本恵吾先生 ありがとうございました。 頓首再拝 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(15) 2006/10/10 「榎 本 恵 吾 先 生 へ」
京都市西京区 本多 清子
|
|||||||
二十幾年か前に 初めての短期練成会での 榎本先生のお言葉が わたしの心をよみがえらせ 喜びでいっぱいになりました 佛壇のとびらに 先生から戴いた 「(ニコニコマーク)光明實相」の半紙を 飾らせて戴いております やさしい慈顔が ほほえみかけて下さいます 常にわたしの趣味を理解して下さり 励ましのお言葉を戴きました お別れした悲しみを のり越えなければなりません 榎本先生は 現世のお仕事を終えられ いっそう高きところへ おのぼりになりました 毎朝 光明実相 光明実相と となえております 先生 ありがとうございます 合掌 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(14) 2006/10/5 「私の中の光そのものの先生」
滋賀県大津市 田中 康蔵
|
|||||||
私の中の榎本先生――それは、暗く冷えた私の心の中に、かすかに温もりを感じる希望に満ちた光そのものでした。その光に吸い寄せられるかのように、毎日、幽斎殿の神想観に通いながら、神の世界に一つになり、共に響きあえる喜びを想い、観じて、合掌させて頂きました。 半年間毎日通った幽斎殿の神想観で、唯一2回、二人だけの神想観を体験させて頂きました。それは、なんて贅沢な時間だったのだろうと、今も毎日、神想観をさせて頂くときには、その時の神想観を思い出しながら、合掌させて頂いています。 私の中の榎本先生は、今も変わらず私の中で生き続けておられる、光そのもの、師そのものとしか言いようのない存在なのです。 また、練成会での早朝神想観では、榎本先生の気合いの強さと、純粋さとを体験させて頂いて、ますます神想観の素晴らしさを実感させて頂いたと同時に、榎本先生先導の早朝神想観の時に出た光と、数多くの自壊作用は、私にとって生涯忘れられない経験になりました。 そして、日常・練成を通して、榎本先生の素晴らしいところは、全てに対する気配りと思いやりです。私にとって榎本先生との出会いは最高の人との出会いでした。 これからも霊界の榎本先生と一体となって、神想観・聖経読誦に励みたいと思います。 榎本先生、ありがとうございます。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(13) 2006/10/4 「尊い御言葉を宝物として」
京都府綴喜郡宇治田原町 山岡 富佐栄
|
|||||||
先生とお別れしてから、あんなこと、こんなこと、喜びをいっぱいいただいたことを、なつかしく思い出しております。 宇治別格本山に奉職し、宇治田原地区ではじめて白鳩会の地区連合会長を拝命! 講習会の目標が来て、「どうしても達成しなくては!」と必死になり、顔をこわばらせ、がんじがらめになり走り続けていた時、大拝殿の前で榎本先生に出会いました。 榎本先生は、むっつりしている私の顔を見て、 「山岡さん!! そんなにがむしゃらにならなくて、いいよ」 と、力強い御言葉をくださいました。 はっと我に返り、講習会の目標にこだわりがなくなって気持ちが楽になりました。ホッとして掴みを放していると、いつの間にか目標は突破!! 宇治田原町からバス2台で講習会に行けるようになったことがありました。 その後、何事にも「がむしゃらにならなくて、いいんだよ」の尊い言葉を大切に、私の宝物として、今日まで来ました。先生のおかげで、この一つの言葉を潜在意識に入れ、幸せいっぱい、喜びを一杯いただき、ただただ感謝です。 また、宇治別格本山に楠本加美野先生がいらっしゃってから伝道練成を定例の行事として組まれ、毎月20・21・22日の3日間のうち21日は宇治田原町にバスで行きます、とのことになりました。私は自分の地元で伝道するのがはずかしく、、ある方に私の気持ちを伝えると、「その伝道練成をことわるのはいけませんよ」と注意され、仕方なく参加いたしました。 榎本先生が伝道の係として、宇治田原町へ来てくださいました。 榎本先生は、私が地元での伝道練成をいやがっているのを知り、「山岡さんの言うとおり、行きたいところへ行ってあげるからね。」と愛念のある言葉をいただきまして、はじめは神社参りをしていただきました。近所の誌友さんも参加してくださいました。 その後、研修生より「昔の谷口雅春先生の古い本が置いてあった家があった」ということを知らされ、早速榎本先生にそのご家庭へ礼拝行に行っていただきました。 大きな旧家に一人奥さんが住んでおられ、 「昔、父と一緒に谷口雅春先生のお話を聞きに行ったことがあります」ということでした。そこは誰一人誌友さんのおられない未開拓地域でした。そのお家で思わず、 「お家を最寄会、誌友会会場として貸していただけませんか」と口走ると、 「どうぞ使ってください」 と言ってくださり、そのOさんのご家庭を中心に、聖使命会員さんが次から次へと出来ました。普及誌の愛行者も出ました。 また、Oさんの地域を榎本先生とご一緒に講習会の受講券を手に、推進して、一軒一軒回らせていただきました。おかげで多くの講習会参加者ができ、今は亡き榎本先生の御慈悲で光明化運動が発展し、宇治田原町は宇治の伝道練成のモデル地区となりました。町民も生長の家のすばらしさがわかってくださり、喜びあふれる伝道練成となりました。 青少年が非行に走り不良少年となり、少年院を出たり入ったりし、バイクに乗り、近所の人にも迷惑をかけているご家庭、病人で悩んでいるご家庭、数々の悩みを持っておられるご家庭にも、榎本先生が行ってくださり、次から次へと幸せになって行かれる方が出来ました。そして、何一つ組織のなかった宇治田原町にも郷ノ口支部奥野さん、切林支部上野さん、荒木支部土屋さん、南支部山岡の四つの支部で地区連が発足!! 宇治別格本山での教区大会では司会を拝命、又地方講師を拝命、対社会対策部長を拝命! 無我夢中で活動している中、「山岡さん、これどうかね?」と光明 圓相 自性 合掌、あの人もこの人も合掌している御姿の墨絵を戴きました。「相手の実相を拝みきることですよ」と語りかけて下さっているように思えます。今となっては身の震える思いで、感動、感謝の念でいっぱいです。 榎本先生の優しい誠、真心を受けさせていただきまして、光明の輪はサンサンといたる所で響いております。数々のご愛念、ご慈愛、御加護、御恩、想い出を大切に原点に戻り、下さった尊い墨絵を拝ませていただき精進しなくてはと思っております。 寒い時も、暑い時も、よくぞ伝道練成に宇治田原町へ来ていただきまして、本当にありがとうございました。今でも霊界から見守っていてくださるように思えます。 榎本恵吾先生、本当に永い間お世話になりました。 「そんなにがむしゃらにならなくてもいいんだよ」のお言葉を大切にして先生を偲ばせていただきます。 榎本恵吾先生、おつかれさまでした。“安らかに”。 |
|||||||
|
|
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(12) 2006/9/24 「『そのままでよい!』 のお言葉で救われました」
神奈川県鎌倉市 堀 浩二
|
|||||||
私は今から約九年前に、まことに不思議な縁で生長の家宇治別格本山に導かれ、そこで榎本恵吾先生にめぐり会い、それまで苦悩に満ちていた魂が救われました。 私は幼い頃より母親の影響で生長の家に触れて、高校生の時に練成会に参加し、大学生の時から生長の家青年会に入って、組織活動を始めました。そして社会人になっても青年会をやり続け、教区青年会委員長、光明実践委員会議長を拝命しました。その中で青年会の仲間が入ってきてはやめ、入ってきてはやめするのを見て、いつしか「自分ほど青年会をやり続けられる人間はいない」と思い上がっていました。 私は組織活動だけではなく、会社でも伝道し、講習会にも何人かお誘いしました。そして、癌や白血病などの重病になった知人、会社の同僚などに真剣に生長の家を伝えるなどして、自分ほど生長の家をやれている人間はいないと思っておりました。しかし、その反面、常に「自分はまだやり切れていない」という焦燥感に駆られてもいました。そんな中、今から10年前、私は完全に信仰に行き詰まり、「救わなくてはならない」「愛行しなくてはならない」という焦燥感と強迫観念みたいなものの虜になってしまい、ひどい不眠症になり、夜は一睡も出来ない状態になりました。 しかし、神様は私を導き続けて下さいました。私はまさに神縁としか考えられないご縁で宇治の生長の家道場に導かれ、そこで榎本先生にお会いすることが出来たのです。今から9年前の平成9年6月のことです。 その月の短期練成に私は参加させて頂き、そこで最初の座談会の時に、幸運にも榎本先生の班に入れて頂きました。 先生はそこでいきなり、先生特有にあの「そのままでよい」「人は行とか何とかをする事によって生かされているのではない」という奥義のお話を、班員にとうとうとお説きになりました。 私はそこで「自分が今どういう状態で何故、練成を受けに来たか」という話をさせて頂いた時、先生は「私はまさにこういう人のために生長の家の話をしている」と仰って下さいました。手前みそで恐縮ですが、私にはその時、先生が私に「君が来るのを待っていたよ。やっと来てくれたか。有り難う」と仰って下さっているように思えました。 その後、私は会社を休職して、宇治の道場の研修生となりました。そこで先生は、道場内で私を見つけるといつも「堀君、ちょっと話しよう」と、道場内の空いている部屋で、私一人のために深い尊い真理の話をして下さいました。そして、「そのままでよい。そのままでいいんだよ」と仰って下さいました。 それまでの私は、生長の家を「自分が偉くて、自分がやってやっているんだ」と思っていました。そして、完璧主義の私は、祈りも完璧に、神想観も完璧に、先祖供養も完璧に、伝道も完璧に、組織活動も完璧にと気負って、それで「自分ほど生長の家がやれている人間はいない、他のやつは駄目じゃないか」と思い上がっていたのです。これは偉いようで完璧な我(が)の信仰でした。そこに「生かされている」という神への感謝の気持ちは無かったのでした。それは自分も含め、全ての人間を、そのままでは救われていない駄目なものであるとして、それを救うために、良くするために「ああしなくちゃならん、こうしなくちゃならん」という考えでした。 先生は私のその我(が)で凝り固まった心を受け止めて下さり、 「神は、僕ら人間がああして、こうしてとしなくても、ただ我らを生かし、見守っていて下さる、僕らはそのままでいいんだよ」 と、やさしくやさしく説いて下さいました。 そして、私は今まで地獄のような心境だったのが救われ、大安心のうちにただ無条件に神に生かされ、赦されている自分を見出すことができました。 私はその年の6月から8月までの約3カ月間、先生の御愛念のもと、研修生活をさせて頂き、9月から会社に復帰して、現在に至っております。宇治から帰って来た私は健康を取り戻し、そればかりか以前の数百倍の悦びとパワーで、仕事に、生長の家の活動に、趣味にと、毎日、邁進させて頂いております。私はその悦びを多くの人達と分かち合いたくて、個人的にブログを立ち上げさせて頂きました。信仰の悦びの輪はますます拡がっております。 人生に絶望し、地獄を見た私を、先生は救って下さり、そして人生の全ての悦びを先生は私に下さいました。それは単に「感謝します」などという生やさしい言葉ではとても言い尽くせない程のものであります。 私は今でも、先生が亡くなったという実感があまりしません。いつでも天界から見守って下さっていると思っております。現在、生長の家鎌倉相愛会会長・地方講師をさせていただいており、悦びの中で「神に全託」の生き方、活動ができるようになりました。 これからも悦びの活動を、力一杯させて頂きます。ありがとうございます。 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(11) 2006/9/22 「奥さまへの書簡 (榎本先生への祈りを込めて)」
岐阜県多治見市 長山 弘
|
|||||||
合掌。奥さまへ。 突然に榎本先生が「神去られしこと」を聞いた瞬間に、身体が崩れ落ちる衝撃を受けました。同時に、強烈な感謝と悔恨の相反する思いが湧きました。 本当の信仰を、榎本先生から教えられながら、実相と現象を決然として判別できない自らの信仰への悔恨でした。 その日以来、ご著書『弟子像』に戻り、藤原先生のご著書に帰り、『生命の實相』を尋ねる日々を過ごしています。 七月十四日は「那智の火祭りの日」でした。 「那智の火祭りは熊野那智大社の例大祭。『扇祭』ともいい、熊野十二神が年に一度、大たいまつの先導で扇みこしに乗って那智の滝へ帰るという神事。同大社や滝は、昨年七月、世界遺産に登録された」 と、中日新聞は報じていました。 榎本先生は、若きときのこととして、 「那智山の秋の山々の感動。僕は滝壺に行く手前の大きな鳥居を見て驚いた。木の額縁に飛龍(ひろう)権現と書いてあった。……那智山でこの額を見た時、僕は自分の守護神は那智の“龍神”であると思ったのである。この龍は産みの底の龍宮の龍に通ずると思っている。」(『弟子像』60~61ページ) と書かれていました。 私は、生長の家の“扇の要”であられた榎本先生が、十三日に現し身は神去られ、十四日に扇みこしに乗って那智の龍神の元へ帰られたのか、と思いました。 十七日の日、遠くからでも奥様を拝し、榎本先生に感謝の思いを届けたいと、久しぶりに生長の家の道場に入りました。 奥様のお話を聞きながら、奥様を拝しておりますと、奥様の姿の周りに、ちょうど二重写しにもう一人の方が、同じ様にお話されているのです。 私は、涙で眼が曇ったのかとも思い、瞬きを何度もし、眼を擦り、眼を閉じてみましたが、眼を開けますと、やはり奥様の周りに金色とも、白でない白金ともいえる光に交互に包まれたお姿の方が、奥様と全く重なり、一緒に話されているのです。 御二方が、一つになって話されているのです。 奥様の姿も、薄くなり、光に包まれた、全く不思議な光景でした。 余りのことに、その方のお顔を拝しましたが、存じ上げない方でした。そればかりでなく、奥様が、白板に書かれた文字が、再び光に包まれたのです。 どうしたのかと、何度も思いました。 私は、霊感も、霊的なものも、余り感じたことのない人間です。 でも、お話と同時に、そのもう一人のお姿は消え、奥様が一人白板の字を消していられたのです。 今まで、そのようなことがあることは、『生命の實相』の中にも書かれてあり、信じておりましたが、まさか自分の中で体験するとは思ってもいませんでした。 『弟子像』にもう一回戻ってみました。那智山で飛龍権現の額縁を見た時のところに、 「かつて、一日五時間か六時間ほとんど続けて神想観をしていた頃、僕の心に浮かんだと云うか、光景が光ったと云うか、神想観を終って僕は、“吾は万群の龍の上に坐すものである”と、その光景を書きつけたのであった。何故か、黄金色に輝く龍の群が、四角く、やや前後に長く長方形の形に群をなしてうねっており、その上に自分が坐っているのを見たのである。」 と記されていました。 「那智の火祭り」は直接見たことはありませんが、十二本の大たいまつは、百五十段の石段を登った後、螺旋を描くように練り降りると紹介されています。大きなたくさんのたいまつは、動くことで、上からみたら長方形に見えるのではないか。それに、「群をなしてうねっており」という説明、「龍の群」というのも、たいまつの一つ一つの火が龍に見えるのではないか。そして、「十二の大たいまつの先導で、扇みこしにのって熊野十二神の神々が那智の滝へ帰る」という説明も、ぴったり符合していると思いました。 さらに、榎本先生は、 「その後、僕は京都の東本願寺に参拝した折り、正面に掛けられた額が龍によって囲まれているのを見たことがあって、フト、例の光景を思い出して感慨を新たにしたのであった。」(『弟子像』61ページ) と書き残しておられました。 私に、奥様の回りに現れられた方が、黄金色の(霊人)であったことが何故か分かりませんでした。私にこのような体験をさせてくださったのは、何であったのか。 「僕は、そのような絵や光景は見たことはなく……」(同書) という榎本先生の記述は、かつて、扇のみこしの上で神々と一緒に見られた光景のような気がしました。 十四日には、真っ直ぐに、那智の神々(龍神)と一緒になられ、十七日に奥様の更なる守護神として天降って来られたのではないかと、今、思っています。 妻が、奥様のお話の後、 「今日の奥様は今までの奥様ではなかった。直接、榎本先生のお話を聞いているようだった。凄い、迫力を感じました。」 と言っておりましたが、私は暫く自分の体験は話せませんでした。私にとっても強烈な印象でしたから。 このようなことを、お手紙にすることがいいのかどうか判りませんでしたが、祈っておりましたら、 「お伝えして、良い。」 という榎本先生の声が聞こえたような気がしました。 先生は、真っ直ぐ龍神になられ、奥様とご家族とをお守りされていると同時に、我々もまた先生が指導と導きをしてくださることを感じます。服部仁郎先生、吉田國太郎先生をはじめ多くのご高弟と共に、特に藤原敏之先生と尊師谷口雅春先生、谷口輝子先生のお側で、人類をご指導くださることを心から感じています。 私も、いつまでもぐずぐずしないで、人類のために、少しでもお役に立てるよう行動を開始いたします。 奥様、どうぞ、いつまでもお元気で、多くの人をご指導下さいますようお願い申し上げます。 妻が、くれぐれもよろしくと申しております。 改めて、榎本恵吾先生と奥様に、心からの感謝を捧げます。 「ありがとうございます。ありがとうございます。」 再拝 平成十七年八月一日 長山 弘 奥様へ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 平成十三年四月二十一日付けの榎本恵吾先生からの書簡を、先生を偲びつつ、拝読させて頂いております。 『弟子像』の本が完成し届いたことをお悦びいただいて、先生は 「すべて生長の家人類光明化運動なるものそれ自体の展開、経綸の厳かさを教えて下さっているものと拝させて頂くのであります。」 「想えば、生長の家人類光明化運動なるものをイザナギ大神のすがたと解すれば、生長の家人類光明化運動なるものそれ自身でのミソギが現成されているのではないか、という想いが湧くのであります。そして、ここにイザナミの大神が、天照大御神(女性)が復活され、甦り給うていることを想うのでありまして、いよいよ大いなる光の経綸を想うに到らせて頂けるということの光栄を、更に更に更にかみしめ、想わせて頂くのであります。」 とお書きいただいております。 先生の「一周忌」を迎え、先生を偲びつつ、一年の時の流れの速さに、深い感慨を抱いております。 「実相独在」の世界に生きつづけられ、観じ続けられた榎本先生の姿に深い安らぎと生命の栄光を感じて来ました。 私も、数々の体験をさせていただきながら、今は「内なる神の声と導き」に寸分の狂いも間違いもないことを感じています。 み教えの深淵を悟られ、生き続けられた「榎本恵吾先生」に今世で出会えた幸せを、時を経るごとに感じています。 「脳梗塞」に倒れ、心身ともに苦しみながら、「肉体が本当の自分でないこと」を心から感じております。 先生から戴いたお便りの中に、 「神想観の中で、本と長山会長とが一つとなって輝いて、ニコニコとした太陽のごときものの顔となって『私は無いのですよ!! 』と安らかなる聖い輝きとなりました。」 という一節があります。 静かに、静かに流れる涙をかみしめながら、先生の在りし日を偲んでいます。 榎本先生への限りない尊崇の思いと、心からの感謝を捧げます。 奥様も、いつまでもお健やかにお過ごし下さり、人類へのお導きを心からお願い申し上げます。 再拝 平成十八年七月九日 長山 弘 榎本 一子 先生 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(10) 2006/9/20 「わ が 内 な る『先 生』」
東京都三鷹市 大谷 敦子
|
|||||||
|
尊師 谷口雅春先生が生きられた真理の継承に、いのちをかけた、そして体現者であられた、榎本恵吾先生とめぐり逢えた事は、尊師が昇天なさった後の私たちに、大いなる恵みでした。 榎本恵吾先生は、全身全霊をもって、谷口雅春先生のお悟りの悦びを、ご自身がそこに立たれ、語って下さったのでした。「谷口雅春先生がいのちをかけた教えだったのだ。」と講話の中で語られた先生の言葉の響きが、今も、生き生きと私の中に鳴り響きます。 榎本恵吾先生の内からのお話(表現)は、谷口雅春先生をも、新しく感動させるような、驚かせるような、新しい萌芽を感じさせるものでした。 先生はそのよろこびを語る時、真理そのものとなって輝き、その悦びを、先生の目の前に現われた統べてのものに伝播していかれたように思います。光が光を呼び、光溢れる世界を、真に、創造し続けていらしたように思わせて頂いております。 もっともっと、先生の御許に行きたかった。もっともっと先生のお話を聴きたかったし、先生の眼差しに浴したかった私ではありますが、恵吾先生がなさった「尊師がなさった山口悌治先生への弔辞」のお話の如く、そして、やはり恵吾先生がなさった「尊師のご昇天の意味するところ」のお話の如く、何ものにも依存することなく、神の子として、今ある生を歓び、何ものにも悔悟することなく、完き肯定の中、光輝燦然と、ただ、進み行くことが、先生への唯一のお礼でしかないと思っております。 このようなことを、思わせて頂ける大いなる恵みに、こころより感謝を捧げます。 ありがとうございます。 ① 榎本恵吾先生との出逢い……先生の講話は華厳経 初めて先生とお目にかかったのは、平成10年1月の一般練成会でした。 その頃、特別悩みも無く、本も読み、青年会活動もしていたのですが、いまひとつ神の子という実感がわかず、何かそこのところで「宇治に行ったらいいのではないかなぁ。」と、ただその思いだけで一般練成に参加しました。初めての10日間練成を、榎本恵吾先生のいらっしゃった宇治で受講できたことは、最高の恵みでした。 先生は、私の疑問に思っていたこと全てを、まるで私のためだけに話して下さったかのようでした。体験談はまったく入っていず、ただ、先生が今立たれているところを、先生がなさったどの講話表現にもダブることなく、多種多様な、変幻自在な、選び抜かれたぴったりくる言葉で話して下さったのでした。 その頃練成部にいらした恵吾先生の講話は連続してあり、生長の家が生長の家たる實相独在のお話を聴くには、最高の場となっていました。結語も先生がなさり、「ありがとう」を言霊から説明してくださいました。結語の後の万歳三唱も、先生は悦びを全身に表現されて、ゴムまりのように丸くなって飛び跳ねるような感じでした。 私は先生の講話をひとつずつ聴くほどに、啓かれていった気がします。練成中盤頃、「向かうところ敵無し」とか「金剛不壊」とか、講話中に無い言葉が、ポツリポツリと私の中に浮かんで来るので、自分でも面白く思っていました。 9日目の朝の先生の「人類無罪宣言」の講話中、私を取り巻く全宇宙から(内から外から全てから、境目無く湧き出すといった感じ)、「罪は無いんだあ。生かされている。神なんだぁ。」という響き(という表現がもっとも近い)が起こり、包まれ、喜びのあまり、半日涙が止まりませんでした。見えている世界は変わらないのだけれど、別の次元に立ってしまったような、とてつもない祝福を味わわせていただきました。本当に物凄く幸せな体験でした。一呼吸一呼吸に感動する日々が続きました。幸せの中を歩く、幸せの中を動くといった感じでした。思いもよらず、實相独在だったんだぁと、実感させられた、大いなる出来事でした。 その年の7月、先生は祈願部に移られました。 そのはじめての大祭の奉仕を、幽斎殿でさせていただきました。その時、先生が、今日、大祭当日に思い浮かんだ曲ということで、B5判位の用紙に楽譜と縦書きの歌詞が書かれたものを、見せてくださいました。細い黒のペンで書かれたものだったのですが、その線の美しさ多様さ裕(ゆたか)さに魅了されました。線はうねるように、回るように、踊るように、全てのペン先が余すところ無く、活躍しているといった感じだったのです。 私はその楽譜を見たとたんに、大きく拡大し、布に染め(私はいちおう染色家です)、色付けした作品に仕上げたいと思いました。以前から、楽譜を染めてみたいという思いはあったのですが、具体的アイディアにはいたりませんでした。それがこんな形で訪れるとは思いもよりませんでした。先生のそのペン書きの楽譜を観た瞬間、その出来上がりがイメージでき、その作品を先生が喜んで下さることも想像でき、嬉しさがこみ上げました。作品を先生の9月の誕生日に贈り、驚かそうと考えた私は、先生にはそのことは告げず、ただ、そのコピーを頂きました。 後日、一対の額装に仕上げ、贈り物とさせて頂いたところ、いのちを震わせて喜んで下さったかのような、巻紙の礼状を頂きました。そのお手紙は、宝物になっています。ありがとうございます。 ② 原宿本部の日曜講話で それは平成10年3月の原宿本部での日曜講話でのことでした。 榎本恵吾先生の講話は、あたりを澄み切った輝きで満たしてしまいました。 その日は、その頃まだ同じ原宿に居を構えていた、東京第一教区の講習会が間近で、受講の推進のための奔走か、目に見える人は本当にまばらでした。でも先生はすべてのものに、全宇宙に向かって話すが如く、制約の無い広々としたところで、大いなるものに導かれてお話なさっているようでした。 本部会館ホールという、尊師と直にふれあった、想いの鮮明な場所でのご講話は、果てしない美しさをもっていました。尊師の立たれていた同じ場所に立たれている恵吾先生のいのちは、知らず知らず尊師とひとつになった悦びを、いのちを震わせながら味わっているかのようでした。そして自分無き自分が喋っているような感じでした。まったく自分が無く、真理そのものとなっていらっしゃいました。もともと色の白い先生でいらしたが、何か発光体のように感じられました。 お話の内容は、尊師との直の融合、服部仁郎先生、吉田國太郎先生とのことなど、練成会ではあまり話されないような、先生の歩みの指針となるような出逢いの、端的で鮮明なお話でした。 講話が終わり気づいてみると、会場にいらした方はみんな、悦びと嬉しさで、涙をこらえきれなかったことがわかりました。 演壇脇の通路に先生が下りていらした時、みながその素晴らしさに喜び、取り囲むような形になりました。 演壇から降りてらっしゃる先生は、「またこんな講話をしてしまったか」と、畏れ、大いなるもののみ前にひれ伏している感じでした。その時もまったく自分が無く、見事に透明でした。光による陰影によって先生のお顔のかたちが判断できるというよりも、陰影なしの、内からの光の強弱で先生の形を作っているといった感じでした。その透明さについて、その時はぴったりとした表現が思い浮かばなかったのですが、ある時ピッタリの表現をみつけました。先生は透明で、その時私が手を入れたら、手が突っ込めそうな感じだったのでした。 この不思議は、今も鮮明に私の中に厳然とあるのでした。このことだけでも、先生とお目にかかれた恵みの大なることを感謝せずにはいられません。ありがとうございます。 ③ 最後の握手……微妙な会話 宇治で先生の側で、もっと勉強したいと考えていた私ではありましたが、平成10年の秋に母が昇天し、その後、母の母の介護、そして家の建て替えと続き、私の未熟さ故に、先延ばしになってしまいました。 先生が亡くなる1週間前、先生ご夫妻と、石田氏と、東京でお食事をした時も、おやさしい先生は、「家が建ったらまた宇治に来てね。」と私を促して下さり、私も「必ず行きます。」と元気に即答したものでした。 そして、お別れ際に握手して頂きました。その時、手を離そうとした私の手を、先生は引き戻すようにまた握手されたのでした。いつもの先生の握手と、全然違う感じがしました。とても、なつっこい印象の握手でした。いま思うと、「頑張るんだよ」と励まして下さったのだと思われてなりません。先生……、本当にありがとう。 そしてまた、その別れ際に、先生ご夫妻で立たれている様子がなんとも言えずマロヤカで、物凄く清らかで美しかったのでした。先生昇天後、一子先生にお話したら、謙虚な奥様は、恵吾先生だけが美しさを放っていたように受け取っていらっしゃいました。でも、どう考えてもあの時の輝くようなマロヤカな美しさは、お二人で醸し出していられたように感じられて、ずっとそのことを考えていました。 日が経って思うようになりました。やっぱり恵吾先生の昇天を知っていて、でも……認めたくない、だから気づかなかったように見えるけれど、魂的には知っていて、最後の濃密な時をお二人で味わっていらしたのではと、思わせて頂きました。結婚ということのまろやかな果てしない喜びに触れさせて頂けたように思います。 ④ 「遍満」ということ……葬儀に向かう列車の中で 7月12日夜10時頃でした。電話が鳴り、宇治の祈願部に以前いらした方から、先生の訃報が告げられた。一週間前に東京にいらした時が、最期のお別れだとその時きづいた。 電話後、1時間ほど神想観をした。目を開くと、部屋が妙に明るく感じられ、悲しみも実感としてなかった。その晩はそのまま、ぐっすりと休んだ。あくる日は、関東ではお盆の入りで、父と午前中お墓参りに行くことになっていた。行く車中から悲しみが起こり、帰ってから、午後一番で宇治に向かった。 新幹線の中で『甘露の法雨』を誦げようとすると、気持ちがよくなって、なぜかボーっとしてしまう……なので窓外の飛び交う景色を眺めていると、全てのものに先生の雰囲気が感じられる。ふと列車内を観ても感じられる。それが宇治に向かうまでず~っと続いた。 なぜだろう……と、想いをめぐらした。 ……先生のいのちは遍満していたのでした。先生は潔かった。高潔であられた。先生は以前、講話のなかで、「さやけきものになりたい。」と仰っていらした。遍満ということが、こんなに強く感じられるとは思わなかった。先生が教えて下さったようにおもわれる。 ご自宅に伺ってわかったのだが、先生はすでに抜け殻だった。形を現している先生はそこに居なかった。やはり「遍満するいのち」になってしまわれたのだ、と想わせて頂いた。肉体という制約のないところで、のびのびと大らかに、そして、せいせいしているようにも感じられた。 告別式の時の先生のお顔には、赤みが射したように感じられた。おやさしい先生が、縁ある人たちに別れをされるためかのようであった。先生は最期まで全てを祝福し礼拝しつづけられた。ありがとうございます。 ⑤ 服部仁郎先生の“祈願札”
「最後の握手」のところで書いた、先生が亡くなる1週間前の7月5日の食事会のとき、母が姉を出産する時に祖母が服部仁郎先生に書いて頂いた、今でいう「人型」を先生にお見せしました。家の建て替えのため荷造りしていた時、見つけたものでした。10×30センチ位の大きさの和紙に「光明思念 生命完全円満」と、母の名前・年齢、そして服部先生の名前が書かれ、落款が押されているものでした。昭和30年に書かれたものでしたし、大きさからいっても、祈願部が出来る前のものではないか、という話になりました。 若い頃に服部先生に学ばれた先生は、とても喜ばれ、「服部先生の字だねぇ~」と感嘆するように仰り、コピーがぜひ欲しいという話になりました。食事が終わってから近くのコンビニでコピーをし、お渡ししようと思っていたのですが、先生と過ごす中にそんな時間は無く、その月の半ばに宇治に行く予定になっていた同席の石田さんに、持っていって貰うか、あるいは送るかしますと言うと、先生は、「今度来る時に持って来て。」と仰いました。 ところがその週末、どうしても早くそのカラーコピーを送りたくなり、日曜日に本局に行って郵送しようかとまで思いました。でもそこまでする必要がない気がして、とにかく、7月11日の月曜日の朝一番で出すことにしました。そしてその時、「落花弁」という題のついた、春頃に買った日本画の絵葉書に、今までのお礼を書いて送ってしまいました。 その絵葉書は、とても美しく清らかな感じで、なんとなく、先生の雰囲気があったので選んだものでしたが、あまりイイタイトルでなかったので、お手紙するとき、少し躊躇しましたが、美しいし、先生は気になさらないだろうと思ってしまいました。でも後で考えると、その絵は、美しいピンクの花弁が落ちかかって、かろうじて蕊(しべ)に引っかかっている図だったのでした。肉体を去る時の図だったのでした。 そしてその祈願札は、先生が不調を訴えられて帰宅した日の夕刻に届いたと、後日伺い、間に合ったことの不思議を思わずにはいられませんでした。 先生は、手元に届いた祈願札を示して、「祈願に携わる者にとって、こんなに喜ばしいことはないね。」と、駆けつけていた祈願部職員の畑本さんに話されたそうです。そのことの意味を、いまだに色々と考えてしまいます。 いつもと変わらない拝みと祝福をされ続けた先生は、生まれるという世界にいなかったので、この世の最期と見えた時にも、この様に常と変わらなかったのではないかと思わせて頂いております。 いつもいつも身をもって教え導いて下さる先生に感謝をささげます。きっときっと、今まで先生とお目に掛かって、気づかなかったことも、これからまた分かって導かれることになるでしょう。 先生、本当にありがと~~~! 叔父が20歳まえに亡くなり、祖父母が生長の家に触れ、父が母と結婚し、祈願札が書かれ、姉が生まれ、私が生まれ、そして時が流れ、祖父が亡くなり、母が亡くなり、祖母が亡くなり、家を建て替えることになり、服部先生の祈願の札が見つかり、榎本先生に届けられた。きっと、気づかないけれど、いつもこんな中を歩ませて貰っているのかも知れない。 ⑥ 幽斎殿でもの申す……答え これだけ先生の側に行かせて頂きながら、いつも訊こう訊こうと思って、そのままになっていた事があった。 7月13日の夕刻、もうすでに扉が閉まっている幽斎殿の前で、私はその質問の答えを教えて欲しいと、声を出して言った。先生の早すぎる昇天にも文句を言った。のびのびと文句を言えるような自分に、先生がして下さったように思う。 駅近くのホテルに戻ると、その答えははっきりとした。先生、ありがとう。神のいのち、神だとわかると、ひとついのちを実感してしまうから、霊の個別化はありえないのでは、……というのが私の質問だったのでした。でも、私は間違っていました。霊とか霊魂とかに、取り違えたイメージを持っていたのでした。先生の遍満するいのちは、雅春大聖師とオーバーラップしたところもあるし、でも、個別のいのちの波として、遍満していたのでした。霊は波長のようなものであると、自分なりに納得ができたのでした。 翌朝、ホテルで神想観をしている時、思いがけないものに会わせて頂けました。それは赤々と燃えるような、でも静かな、揺らぎのある大日輪でした。いのちが脈々としている感じでした。先生は生き生きとしていらっしゃるのが感じられました。 榎本恵吾先生が描かれる絵では、あまり見かけない赤でした。先生からは、スカイブルーとか緑の色が思い出されます。でもその赤は情熱的で、温かで裕かで、厳かな深い色合いでした。生長の家に、實相独在の教えにいのちをかけた先生のみたまを感じさせられました。そしてまた遍満する先生のいのちは、私たちの内にも外にも、細胞の一つ一つにもおわしますのでした。ありがとうございます。 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(9) 2006/9/18 「父 の こ と、夫 の こ と」
兵庫県神戸市 渡邊 実代 (榎本恵吾長女)
|
|||||||
私が今の主人を「結婚したい人がいる」と言って紹介したとき、父は一ぺんで彼を気に入ってしまい大喜びだった。 「渡邊君は一味ちがう。その一味が大きい。彼に会ったとき、実代ちゃんがお父さんのいいところを見て、そこを大事にして彼を好きになったというのが分かったから、ちっとも淋しくなかったんだよ」 という言葉を、その後何回か聞かされた。 結婚するまでの三年余り、私には色々な波があった。父が生長の家でない先に嫁ぐ人によく「『生命の實相』も、生長の家さえも置いていきなさい」と言った言葉が、現実として自分に迫ってきた。 生長の家という信仰に基づいた、世界一幸福で唯一最高と思っていた榎本家を離れて、それまで否定してきた唯物的で現実的、自己限定に支配された窮屈な生活に染まるのはいやだ、という思いから、生長の家でない彼が、本当に正しい半身なのか疑わしくなることがたびたびあった。私は包み隠すことなく、そんな悩みを全て父と主人にぶつけていた。父の彼を信じる姿勢は一貫しているどころか、いっそう堅固になり、主人はいつも変わらず飄々として柔らかく誠実だった。いくらかの不安の残る中、私はただ父の言葉だけを信じて新生活に身を投じていった。 形の上での生長の家は置いていけていたかもしれないが、結婚してますます私の父への依存心は強まった。子供を産んでからは特に、一途で極端なところがある私は、あり余る意欲で子育てに向かうため、逆に不安になることも多く、頻繁に電話して父に相談をしていた。 私は子供のころから病院に行った経験がなく、自分の子供たちを病院に連れて行くのも気が進まず、義務づけられている予防接種も殆ど受けていなかった。周りからは驚かれたり、脅かされたりして、不安がよぎることもあった。そんなとき父に相談すると、 「予防接種をしないで心配に思う気持ちを拭うために注射をするくらいなら、そんなことで揺るがないように余計に信仰を深める方をやりなさい」 と言われた。父に相談をするときは、厳しいこともあったが、いつも心の深いところから納得し、よろこびがあふれてくるような答えが返ってきた。 ことあるごとに父への緊急110番は続き、子供たちの失くしものでも心配事でも、二言目には、 「おじいちゃんに電話しなさい」 で解決していた。 ところが、父が亡くなる半年前くらいから、父への110番が自然になくなり始めた。自分でも父は元気だし、少なくともあと20年は生きていてくれるだろうと信じ込んでいた。それなのにふと、「これからはもう父には頼れない」というような思いが湧いてくるのが、不思議にも不吉にも感じられていた。 7月12日夕刻。何の前ぶれもなく突然末妹から、父が心肺停止状態で倒れたという電話があった。 「やっぱり……、来るときが来た」 というあきらめのような決心のようなものに、一瞬にして全身をガードされたような感覚に包まれた。「これなら、案外潔く父の霊界への誕生を祝福できて、切り替えも早く、さらなる明るい人生に進めるのかもしれない!」と思った。 とんでもなかった。 このまま死ぬまで涙が乾くことはないのでは、と思うほど、父のいない世界に生き延びていく気になれなかった。亡くなってもなお、「お父さん、お父さん」とすがりついている私の傍らで、主人は、相変わらず常に安らかに私をいたわり、見守っていてくれた。 父が「自分と似ている」と言った主人……。「一体どこが?」と、ずっと答えを求めてきた。父の影響は何より甚大で強烈だったはずなのに、その存在はいつも静かで無味無臭、無色透明で、どこにも濃いものがなかった。さわやかな風に乗って、父はいなくなってしまった。そこに残ったのは膨大な空虚さ。ある日、ハッと気がついた。父と主人が一番似ているのは、私をつつんでくれるこの空気の色、主張のない自然で透明な空気だったのだと。 数時間前、母が携帯電話の待受画面に、父の書いたニコニコの下に「光明実相」という字がある写真を使っているのを見た主人が、とてもうれしそうに「この画像、自分(私)の携帯に送ってもらったら?」と言った。(本当に計り知れない人だ)と思った瞬間、父の顔が浮かんだ。 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(8) 2006/9/14 「風となり雲となりて」 東京都青梅市 久都間 育代 |
|||||||
「先生」。心の中で語りかけると、 「どうかね」。と、懐かしい声とともに温かな笑顔を想い起こします。 はじめてお会いしたのは、昭和五十九年四月。十九の春でした。養心女子学園で、決まっていた総本山への内定を急きょ取り下げ、宇治別格本山に奉職することを願い出た私は、なぜどうして宇治へ魂が引かれるのか、自分でも理由が分かりませんでした。しかし先生にお会いしてはっきり分かりました。私の魂は間違えていなかったと。先生、奥様、ご家族、先生の研修生。この方たちと会うために私は此処に来たのだ、そう思いました。 奉職後、受付係をしていた私は、ある初夏の朝、先生からの電話を受けました。 「奈良線の奈良行きは何時があるかね」 それに応答した後、すぐに公衆電話へと急ぎました。 「先生、私今日お休みなのです。誌友会に連れて行ってください」 自分でも思いがけない大胆な行動でした。 こうして初めて、先生と一緒に奈良の王寺で開催される誌友会へと喜んで宇治駅に着くと、そこにはもう一人来ておられました。久都間さんでした。彼も先生と二人で行けると思って来たら、もう一人いたと少し残念に思ったようです。奈良行きの電車が到着し、車両に彼と私が同時に乗った時、先生は〝この二人は結婚する〟と直感されたと、もう結婚してしばらく経った頃にお話くださいました。 先生に付いて二十から二十一歳の頃は、西宮の前波邸で毎月一回開催される誌友会に通いました。いつの間にか久都間さんも通うようになり、これも先生が自然に敷いた縁であったのですね。ある日の朝、食堂でお会いした先生に、 「久都間さんが自分で書いた原稿用紙を束にして持って来られました」 と言いますと、先生は実に嬉しそうな、これ以上の悦びはないとばかりに喜ばれ、 「そうかね。彼はもってきたかね。そうかね」 と満面の笑みでした。 先生と奥様が私たちの結婚祝賀会で「埴生の宿」を歌ってくださいました。その歌声を聞きながら、この結婚をご縁として何らかの形で生長の家のお役に立ちたいと希(ねが)ったものでした。 後に先生は、研修生出身のある方が宇治本山を退職されることになった時、こうおっしゃいました。 「私はねぇ、研修生の一人ひとりにアコヤ貝の真珠の核のように、一人一人のお腹にしっかりと神の子の教えを植え付けたんだよ。それは本人が外そうと思っても、ジタバタしても、もがいても決して外れない。だからね、彼は本山を辞めても、どこに行こうが、大丈夫なんだよ」と。 私が十九から三十五まで宇治で過ごした十六年、あの先生の元で送った日々は、全て神様から与えられていた。 コンクリートの固い裂け目から、草花が咲く。その土台となるやわらかな土を先生が用意してくださっていた、自然に咲いたと感じられるように。 先生がお好きだった『まあだだよ』(黒澤明監督)の映画。あの中で教え子たちが「先生は金無垢だ」と話していましたが、先生もそうでした。そして純粋無垢でありました。来年は先生と奥様の古希のお祝いをと、あの映画での場面のように思い描いておりました。 最近読み終えた本で、『博士の愛した数式』というのがあります。その博士は八十分経つと、記憶が消えてしまう。八十分にすべてが凝縮される。そして次の八十分が始まる時は、また新たな驚きから始まるという話です。その数学博士は、自然数の中の素数をとても大切に思っています。他の整数では割り切れない、そのままで成り立っている3、5、7、11…こんなに美しい数、素数と。 主人がこの小説に出てくる博士が、先生とそこはかとなく似ているね、と言っておりました。先生がお話されるとき、書をかくとき、雲や風景の絵を描かれるとき、作曲をされるとき、素数のごとく、本当にひとつのものを愛おしむが如く、大切に大切に紡ぎ出していかれました。 昨年秋の慰霊祭で、谷口雅宣先生が「たとえ肉体は滅したように見えようとも、ご家族やご縁ある人々を、小石となり草木となり風となり雲となって見護ってくださる」と話されました。そのお言葉を今、深く感じています。 ゆく雲に 流れる水のささやきに ともに歩みし山の辺おもいて 青き空 風の流れに響く歌 師と口ずさむ〝きれいなきれいな〟 山は緑 空に映えたる夕雲に 〝きれいなきれいな〟 歌は風となり |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(7) 2006/9/13 「雲の上で寝ているようでした」 石川県金沢市 小塚 弘子 |
|||||||
第600回神性開発宇治一般練成会に参加したときのことです。夜、最後の恵吾先生の御講話のときでした。先生は、はじめに「今日は皆さんに実相世界の雰囲気を味わっていただきたいと思って話します」と言われました。 先生のトレードマークであります“ニコニコ笑顔”が、黒板からはみ出して大きく書かれ、色々と笑わせながら話して下さいました。私はその先生の言われます“実相世界の雰囲気”とはどんなものなのか、とてもとても興味一杯で聞いておりました。 そのうち、“ぴょこん”と 何だか霊のコンベアベルトに乗ったように感じ、とてもふわふわした世界へ連れて行かれました。そんな感じのまま、講話も終り就寝の時間となりましたが、その晩は一晩中、これまで経験したことのない、無限にふわふわした雲の上で寝ているようでした。 あまりにも感慨が深く、翌日一子先生に話しました。研修生として残った私は、後日、大祭のときに、恵吾先生と直接話す機会があり、その話を再度させていただきました。恵吾先生は、すごく興味を持たれ、「どの話をしたときにそうなったの?」とか、「どういう風に話しているときでしたか?」と、細かくお聞きになりました。そして、恵吾先生自費出版の『裸I・II』という本をいただいたのもそのときでした。大祭が無事終了した晩のお食事会のときも、私の経験を「新鮮だ!!」と言って下さり、本当に本当に嬉しい思い出となりました。 現在は、一子先生から頂戴いたしました、恵吾先生のDVDを何回も何回も聞き直して、私の魂は救われました。 今でも時々、恵吾先生の雰囲気を感じ、お導きをいただいております。 恵吾先生、本当に本当に、ありがとうございます。 去年七月、命日祭のため、宇治へ出かけました。恵吾先生の大好きなお茶を買い、お会い出来ることを楽しみに出発しました。宇治に着きますと、所々に『故榎本恵吾…』という立看板があり、意味が分かりませんでした。練成道場の中で尋ねてみて、はじめて突然に先生のお亡くなりになったのを知りました。 一子先生は、恵吾先生の“お相(すがた)”に会わせて下さいました。静かな美しい“お相”でした。まるで生存そのままの恵吾先生に会わせて下さった自然さで対して下さいました。今思うと、まるで神の国そのままの光景でした。 今になって考えてみますと、榎本恵吾先生は、神界へ旅立たれるギリギリのところで私をお救いくださったのだと思えて、ただただありがたく、感謝ばかりです。 榎本恵吾先生に出会えましたことに、神を思います。先生にお会いできてからの私の世界は、一変いたしました。先生の遺されたDVDで何回も学び、はじめて尊師の教えにはいれたと思います。 生かされている自分の生命がこんなに嬉しいこと、ありがたいことを、はじめてわからせていただきました。私も本当の幸せにはいれたと確信いたします。 榎本先生!! 本当に本当にありがとうございます。先生が私たちに伝えてくださいました真理を、今度は、お救いいただいた私たちが、生命がけで一切の人たちにお伝えさせていただく番です。 先生、やります。先生の後に続きます。どうぞ、天界で見ていてくださいね!! ありがとうございます。 合掌 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(6) 2006/9/12 「夢の中の榎本恵吾先生」
東京都青梅市 久都間 繁 |
|||||||
(友人宛の書簡より) 合掌、ありがとうございます。 畑本さんのお父様の訃報をお知らせくださり、ありがとうございました。 九月九日の明け方、榎本恵吾先生が私の夢の中に出てきました。 このようなことは初めてだったので、夢から覚めた後も、そして今も、先生の懐かしい魂の響きが、私の心の奥底でこだましています。 夢をみている最中、ふと気がつくと榎本先生がありありと目の前にいることに、私はとても驚いていました。そして周りにいた知人の何人かに、ことの重大さを呼びかけてみましたが、皆さんは「ごく当たり前のこと」といった様子で、さして驚いているようではありませんでした。 私は懐かしさのあまり「今のうちに何か大切な話をしておかなければ」と、生前にしていたように先生に呼びかけてみましたが、いざお話ししようとしても、具体的な言葉が見つかりません。 それでも、私を見つめてくださっている先生に、このまま進んでいいのでしょうか、というような意味のことをお訊ねすると、先生は私の「いのち」そのものを、慈愛に満ちた魂の眼で真っ直ぐに見据えて、「そのままでいい、そのまま光りだよ」と、私の実相のみを相手にして見つめてくださっていることが伝わってきました。先生はすべてを察していらっしゃる、と感じた瞬間、限りない懐かしさがこみ上げてきたのです。 そのほかにも、いろいろな話をしたようですが、もう覚えていません。 今朝の出勤の際、電車の中でこのときの情景をずっと想起していたのですが、夢の中で私がしたことは、先生に向かって、ただコンコンと戸を叩いたことだけだったことに気がつきました。 イエスは聖書のなかで、「求めよ、されば与えられん。叩けよ、されば扉は開かれん」と説いていたことを思い出します。 夢の中で生前も、今でも先生は、ただただご縁のあった渾ての人々の実相を拝んでいらっしゃったのだと思います。 「忘れないうちに」と思い、書き留めさせていただきました。 (2006年9月12日) |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(5) 2006/8/29 「“脳内清掃”をしていただきました」
宮城県仙台市 川島 郁子 |
|||||||
定年退職を期に、伊勢神宮を参拝した友人二人を宇治別格本山に案内し一泊。翌日 大阪の友人を交えて四人で幽斎殿に参拝しました。 神殿の前に座っていると、突然、榎本恵吾先生がいらっしゃり、神想観の座につかれました。 「今は神想観の時間ではないけど、緊急に祈らなければならないことがあって――。あなた方も何か祈ることはありませんか?」とおっしゃった。突然のことで、何も頭に思い浮かばなかったので、四人は黙って先生の前に正座し、先生の神想観に合わせて祈りを始めたのです。 すると、静寂な神想観の中にあって、私の頭上に突如、ハエかハチがビュンビュン音を鳴らして飛び交っているようでした。目を開いて手で追い払おうと思ったのですが、榎本先生に失礼と思い、そのまま神想観を続けました。 やがて私の頭上にハエかハチが止まったと思うやいなや、頭から脳の中、鼻の奥の中心まで、グルグルと逆円錐の形に振動を続け、榎本先生の神想観終了と共に、その不思議な振動もピタリと止まったのです。 榎本先生と一緒にお祈りをして、脳内清掃とお浄めをしていただいたことに感謝合掌。老眼鏡なしに読書を続けられるのも、きっと先生のお陰であると、感謝申し上げます。 それは忘れもしない、2000年5月19日、午前のことでした。 感謝合掌 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(4) 2006/8/24 「鮮やかに蘇る 榎本恵吾先生の思い出」
大阪市城東区 村上 拓夫
|
|||||||
誰も手を挙げない。初めての座談会でのこと。僕は質問した。「なぜ、あんな強欲な人に出会ってしまったのですか? 悪い業があるのでしょうか?」と。今考えてみれば、あるから出会うのであって、なんと馬鹿な質問であろう。榎本先生は「君は善業の方を考えなさい。善い業がなければ、宇治へは来れないんだから」とお答えになった。 先生には、苦悩を乗り越えた人特有の静けさがあった。深い苦しみ、大きな悦び、両方を知っておられる方だと直観した。 僕は榎本先生の座談会に毎日通い詰めた。朝飛び起きると京阪に乗り、宇治に着くと、受付で千五百円払ってから先生の班にもぐりこんだ。また、先生の講話の日時だけを問い合わせておいて、それだけ出席した。実は、先生のお話は、当時の自分の悩みに直接関係あるわけではなかった。しかし、引きつけられて仕方がなかったのである。 そんな座談会でのこと、「質問はありませんか?」と先生が何度おっしゃっても、一座の人々はシーンとしたままであった。僕は思い切って手を挙げた。「神想観中は霊的悦びを感じるが、日常生活では良心の呵責に苛まれるのですが」先生は本当に丁寧に回答してくださった。 「ないほうがいいという不完全は無いのだ。どの不完全がではない。不完全なるものそのものがないのだ。人間は罪を犯せてないのだ。神である自由しかないのだ」そういう意味の話を諄々としてくださった。胸に沁み込むような感動を覚えた。 ところが、話がなかなか終わらない。回答し始めてほぼ一時間が経っても、話はまだ終わらなかった。僕はハラハラしだした。他の人に悪いと思った。僕への回答はそのぐらいでいいから、次の人に質問がないかきいて下さいとも言い出せず、ようやく話が終わったときに、修験者風の男が怒り出した。先生に対して怒れないから、僕に対して怒ったのである。飛び入りで来ておいて質問するとは何事だ、というわけである。 先生と僕とでなんとかその場を丸く収めた後に、老夫婦が質問したのだが、これがいけなかった。質問の仕方が悪かったのだろう。今度は、榎本先生が烈火の如く怒りだした。後にも先にも先生がお怒りになったのを見たのは、この一度切りであった。相当スッタモンダしたのであるが、先生ご自身が何とかその場を収められ、座談会はやっと終わった。 散々なことになってしまったと、悄然として廊下を歩いていると、榎本先生が追っ掛けてこられた。予想外に明るい声であった。 「君の質問はいいネー。話が引き出される。いつでも幽斎殿に来てください」 話が引き出され過ぎてトラブルになったのであるが、先生、全く無頓着。カラリとしたものであった。 あるとき、幽斎殿のソファのところで、旅先で買った酒をお土産として先生に手渡すと、僕の目の前でグビグビと全部ラッパ飲みしてしまい、空瓶をガチャンとごみ箱に入れてしまった。「あーーーっ!」と僕は思った。これで先生は帰りに運転できなくなったのである。自動的に僕が運転してお送りすることになった。僕は身を固くした。事故でも起こしたらエライことである。慎重にやるのだ。 車内で先生が「白山神社へいこう!」とおっしゃる。僕は黙々と運転した。 だが、一本筋の違う変な林道へ迷い込んでしまったのである。狭い道でUターンもできない。農家の軽トラックが対向車として来るかもしれない。これはしまったと思い、戦々恐々として運転していたのだが、先生は隣の席で「ほーーきれいだなぁー」と木々の緑を楽しんでおられた。道に迷っていることなどどうでもよいようであった。今思い返すと、同じ車内で冷や汗をかいている僕と、悠々と景色を楽しんでいる先生とのコントラストが、なんとも滑稽でもあった。 それでもなんとか白山神社に着くと、先生は、農家の人が焚き火の跡に積んだ木の枝の束の中から、適当なやつを一本引き抜き、ステッキ代わりにして地面をコツコツ叩きながら歩かれた。気に入った樹木の前に来られると、しみじみと見上げて感嘆された。先生は感性のとても美しい方である。 参道の石段を登らず、横にまわりこみ、川のせせらぎを眺めていたときのこと。 「ここから登ろう!」 と先生がおっしゃった。そこは木の生えている土肌の急な斜面であった。先生といっしょに木につかまり、足元の落ち葉にズルズル滑りながら、汗だくになって上まで登っていった。なぜ、あんな危ないことをしたのだろう。そのとき僕はなんとサンダル履きだったのである。 でも、僕は榎本先生というと、あのときの木の枝の手応えや、落ち葉の感触が今も鮮やかに蘇るのである。 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(3) 2006/8/20 「あたたかい榎本先生のお導き」 京都府宇治市 畑本 宏実 |
|||||||
|
合掌 ありがとうございます。 榎本先生には、数えきれないほどの御愛念をいただき、この数日、次々よみがえってまいりまして、メモに書き留めております。 私は、研修生(※注)を四回もしまして、あるとき、家に帰ってしまっていたけれど、もう一度本山でお世話になるため、母と本山に戻った際、榎本先生が母と私に休憩室でお会いしてくださいました。そのとき母が、「この子は榎本先生が大好きで、先生に良くしてもらった話ばっかり、家でもするんですよ」と言いました。すると先生は、 「(宗教は)人情ではないんですよ。人情の世界ではない。神様に生かされているということです」 というように言われました。 先生は、ちっとも自分が世話をしたというような態度はされません。本山に来るまでの私は、誰も自分のことをわかってくれる人は居ないと思い、愛情に飢え、ひねくれてしまっておりました。榎本先生を通して、神様のあたたかい無限の愛を感じ、今ではこうして結婚までして本山に居られることは夢のようです。思えば何も知らないまま、年末の大浄心のための練成会を受け、偶然、個人指導をしていただいたのも榎本先生でした。心を開くきっかけになったのは、研修行事の榎本先生の聖歌練習でした。音楽の大好きな私は、歌のたびに心があったかくなり、ありがたくて涙が出ました。魂が開放される喜びを味わわせていただきました。 私が、賄係として前の中講堂で奉仕をしていました頃、ある日の午後の休憩時間に、二階のピアノで、『エリーゼのために』を弾いておりました。すると、榎本先生が戸を開けて入ってこられて、「誰が弾いているのかと思ったよ。ピアノの音が聞こえて、あなたは僕の音の出し方と似ているねえ」と言われたのを思い出します。あのときはとても嬉しかったです。 榎本先生の幽斎殿の神想観に毎日通うのが、何よりの楽しみであり、日々の心の拠り所でした。先生が出張か何かで、神想観の無い日には、家から一歩も出ないで引きこもって、先生の神想観のある日は心弾んで通いました。神想観後は、身も心も軽くなりました。私は、幽斎殿の、マイクのコンセントをセットしたり抜いたり、電気のスイッチのつけたり消したり、クーラーの設定など、その都度させてもらっておりました。神想観後、先生は、いつもそこに居る私に、一言二言話しかけてくださいました。話をするのがあまり上手でない私に、いつも先生の方からやさしくニコニコと話かけてくださいました。 最後の山登りになった伊吹山のことも、その何日か前、神想観後に、「14日(山登り)は、台風でも嵐でも行くからね」と、笑いながら言われました。伊吹山は、その日、時間も早かったせいか、私達のほかに一、二組いるだけで、ほとんど貸し切り状態でした。頂上で少しビールを飲み、少し降りた所で、皆で奥様の作ってくれたおにぎりとおかずをいただきました。先生は、ニコニコされながら、奥様がおにぎりを作り出したら、「楽しくておもしろくて止まらないらしくて、次々にいっぱい作ったんだよ」と、何度も言われていました。本当に楽しそうに何度も言われました。 榎本先生がお亡くなりになられる前は、出張などが続いて、先生が本山に居られないことが多くなりました。私は先生が居ないということについて、自然に考えるようになっていました。ある日、インスピレーションのように、「肉体の榎本先生に頼っていてはいけない」と出てきました。毎日先生の神想観に通っているのに、ちょっと先生が居ないだけで調子を崩したりしていたのでは、毎日通っている意味がない、榎本先生に申し訳ない、と思いました。これからは、榎本先生の愛念を通して、神様の無限の愛を信じるようにしていこう、と思いました。 今から思えば、榎本先生がお亡くなりになっても、私が戸惑わないでいられるように、先生が導いてくださったのだと思います。不思議なことですが、先生がまだお元気なのに、この何ヶ月か、時々こうして奥様にお手紙を書いている自分が浮かんできていました。榎本先生がお元気なのに、どうしてこんなことを考えるのかと思っておりました。 榎本先生に、本当に良くしていただいて、沢山の楽しい思い出を、これからもメモに残していこうと思っております。本当にありがとうございます。 (※研修生:生長の家宇治別格本山の道場に、長期間住み込んで奉仕をしながら研修を受ける受講生のこと。榎本先生はその研修生の指導を担当しておられました) |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(2) 2006/8/8 「救いの原点をお話くださった先生」
京都府城陽市 山岡 紀子 |
|||||||
一年祭に際し、DVDで榎本恵吾先生のご講話を聴かせていただき、懐しく、改めて大感動いたしました。入信以来、私と娘の運命を変えてくださった生長の家。特に、藤原先生と榎本恵吾先生の「現象ナシ、実相独在、既に救われ済みの神の子である、そのままの自分を無条件に今よろこびなさい」という生長の家の根本真理によって、本当のよろこびをいただきました。 そしてまた、これを聴かせていただくのを楽しみに、よく宇治に行かせていただきました。自分を喜べなかった暗い娘が、よろこびいっぱいで輝いて帰ってくるようになり、家族のよろこびとなりました。 恵吾先生は、谷口雅春先生を心から尊敬され、先生のお説きくださった真理をわずかでも劣化させる事なくお伝えしたい、という強い志をお持ちになっているのが解りました。いつも、はじめのはじめの救いの原点に引き戻してくださるのがうれしかったです。いつもご指導いただいた帰りには、心が解放されて笑える自分に戻り、うれしさいっぱいで帰ります。 あるとき急に7キロも痩せて、甲状腺ガンと判り、手術の方向に話が進んで、ご指導をいただきました。「先生エライものが出ました」と甲状腺ガンを告げますと、「大丈夫ですよ。今笑いながら入って来たでしょう。体験になりますよ」と言い切ってくださいました。深いお悟りがなければ言えない言葉だと思いました。 その日は「山川草木国土悉皆成仏、有情非情同時成道」をお説きくださり、先生のトレードマークのニコニコ顔をお書きくださり、周囲に「現象即実相、○○即○○……」と、いくつも書いてくださいました。一切の現れを善ととり、ただ感謝し、そのままの自分をただよろこび、心晴れやかに笑いながら帰りました。 一子先生からは、「大丈夫ですよ。出たものを何とかしなくとも影なんですから、私だったら手術しませんよ。神様は常に護ってくださっていますよ」との力強いお言葉をいただいて、大安心の境地に入りました。そうしてガンを放すことが出来、大好きな愛行と行に没頭する事が出来ました。それから3カ月後、主人に言われて検査をした結果、プラス反応が出なくて、両方にあったかたまりも後に消えてしまい、今改めて感謝の気持いっぱいで、自分の使命を深く感じています。 雅春先生が、「私は一人も救った事は有りません。はじめから救われているのです。それを拝ませていただいていたら、気がつくと自分が拝まれていたのです」とお話された事を知ったとき、「正に恵吾先生は救いの原点をいつもお話してくださっていた」と気付かせていただきました。 生長の家の真理は、どの方がお話しされても素晴らしいのですが、恵吾先生独特の楽しい表情や、お一人お一人を菩薩様と礼拝してくださっているお心がにじみ出た、深いお悟りのお話は格別のものでした。その陰には一子先生の、常に神と共に生きていらっしゃる力強い信念と、愛深さと、直感力のすぐれた妻であり母でいらっしゃったことが、大きく影響されていた様に思わせていただいています。 榎本恵吾先生は、最高のご家族に恵まれたお幸せな先生だったと思います。改めて、生前お世話になりましたことを心よりお礼申し上げますと共に、ご家族の方々の益々の御健康とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。 再拝 |
|||||||
「私の中の榎本恵吾先生」(1) 2006/8/6 「鼻血を出しながら一喝され…練成会にて」
東京都杉並区 増田 義彦
|
|||||||
今から18年前、宇治一般練成会に初めて参加した時、確か3日目か4日目でしたか、知り合った友人2、3人と(講話中)別室にて話をしていると、(榎本先生が)音を立てることなく静かに入ってこられました。これはサボッていておこられるかな、と思いましたが、物静かな口調で、行事には予定されていない特別なお話をして下さいました。 とても短かいお話でしたが、「皆さんは、始めの始めから“光”そのものであったのですよ―― !!! 」と、ニコニコの絵を描き大声で力説された。その時のことです。私はわけもわからずワァーとむせび泣きそうになりました。ドッと泣いてはいけないと一瞬こらえましたが、その言葉を頂いた時、心の底から頭のてっぺんまで、一瞬に喜びが“ウッ”とこみあげてしまい、こらえたものの涙がにじんでおりました。 その大声の一喝をされた時、私のムセカエル喜びが一瞬こみあげたその時、先生のお顔がまっ青になり、鼻血が片方の鼻から流れ出したではありませんか。私はふとアブない、と思いましたが、先生は指でそっと血にふれて血の指を見られたあと、何事もなかったように静かに出ていかれたのです。 私は、自分の中からこみ上げる温かな喜びを感じながら、先生の鼻血を出されて決死の思いで話された数分のお話の感動やらで、身動きできずにしばらく座ったままでした。その後、残りの練成が、十日目の最後までとても楽になりました。その予定だにしていなかった数分のお話で、心のくもりがふき飛んでしまったのです。 先日18年ぶりに、先生にDVDの中でお会いでき、おまけにそのDVDを頂けて、先生と共に一生いられます恩恵に浴せましたことを、感謝をいくらしても感謝しきれぬ思いでいます。 今回(偲ぶ会で)先生の描いたスケッチ、絵などにも触れられ幸せでした。練成後に、仕事で短期間、ニュージーランドに行くことになり、先生にお便りした時、覚えていて下さり、期限の書かれていない“人形(ヒトガタ)”を送って下さり、身につけておくといいと言って下さいました。 先生にお返しできたことは、練成後半、たまたま二人だけのお風呂で背中を流させていただいたことです。背中を流して洗っていると、「ありがとうございます」と言いながら、先生は合掌されていました。そのお姿に気づいた時、私も「ありがとうございます」と言っていました。多くの宝物を大切にしていきます。皆様お元気でお過ごし下さい。ありがとうございます。 合掌 再拝 |
|||||||